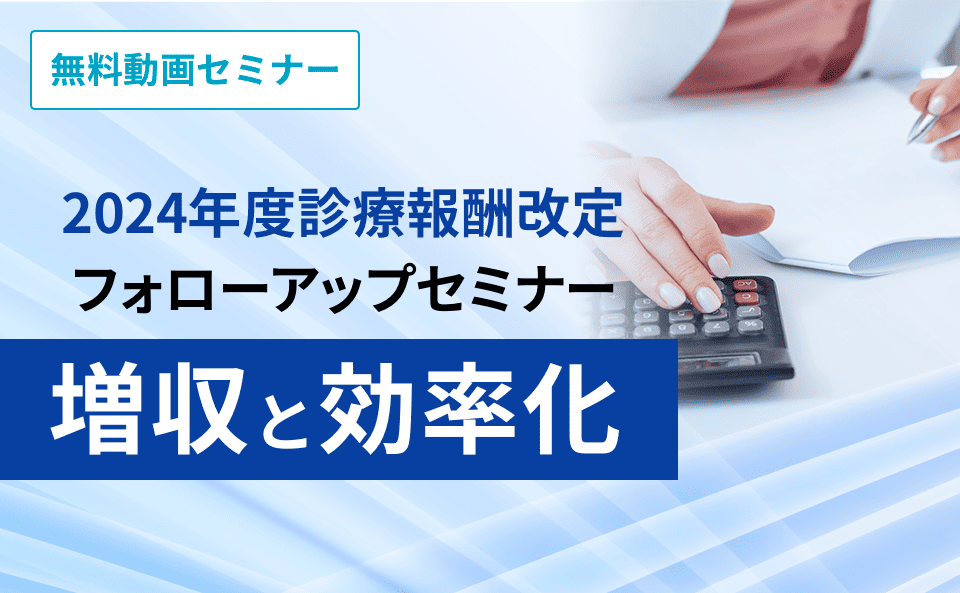#レセプトの悩み #開業直後の悩み #業務効率化 #マネジメント
目次
診療情報提供料の仕組み
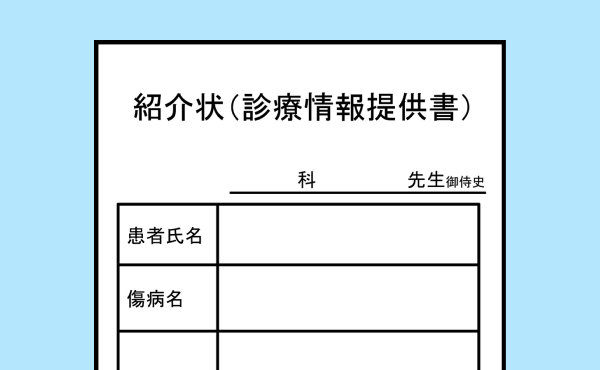
診療情報提供料とは、他の医療機関に患者さんを紹介する際に、紹介状とともに診療情報を提供した場合に算定できる診療報酬です。
基本的な仕組みとして、紹介状を受け取った医療機関側では算定できません。しかし、地域医療連携ネットワークが構築されている地域では2024年度改定で追加された「電子的診療情報評価料」が算定できます。
地域包括ケアシステムのもと、地域連携強化は今後重要性を増していきます。診療情報提供料に関する適正な理解を深め、自院の算定ルールを整理しましょう。
診療情報提供料の算定要件
診療情報提供料は、Ⅰ・Ⅱ・連携強化診療情報提供料に加え、電子カルテ情報共有サービスを評価する電子的診療情報評価料の4項目に分けられます(2025年6月時点)。
各算定要件について、実際の運用に生かせる形で解説します。
診療情報提供料Ⅰ
診療情報評価料Ⅰは、別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者さんの同意を得て、自院での診療状況を診療情報提供書に記載して紹介した場合に算定できます。算定に際しては紹介先の医療機関名の記載が必須です。可能であれば、特定の医師名まで記載があると、紹介先の対応がよりスムーズです。
なお、患者さんに渡した診療情報提供書は、自院のカルテで写しを添付しないと査定対象になる可能性があります。
患者さん1人につき月1回まで、点数は250点です(2024年度改定における)。
なお、保健福祉のサービスの有効かつ適切な実施につなげる目的で情報提供した場合に限り、保険医療機関以外の市町村または指定居宅介護支援事業者等でも算定できます。
具体的な情報提供先は、以下のとおりです。
- 患者さんの居住地を管轄する市町村
- 保健所
- 精神保健福祉センター
- 児童相談所
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 地域包括支援センター
- 指定特定相談支援事業者
- 指定障害児相談支援事業者
診療情報提供料Ⅱ
診療情報提供料Ⅱは、患者さんまたは家族からの申し出に基づき、セカンドオピニオンを求めるための情報提供を行った場合に算定できます。
治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報など、他院の医師が患者さんの診療方針について助言するために必要な情報を添付した診療情報提供書を記載し、患者さん本人か家族に提供するまでが算定に必要な一連の流れです。
必ずしも転院や治療の変更を前提とはしておらず、あくまで助言を目的としています。もし、紹介先で診療を伴う場合は診療情報提供料Ⅰとなり、査定対象となるため、注意が必要です。
算定にあたっては、時系列や自院での状況を整理する意味でも、患者さんや家族から希望があった旨をカルテに記載し、助言を受けた後の治療計画に反映させるよう、院内での情報共有が重要といえるでしょう。
点数は500点です(2024年度改定における)。
連携強化診療情報提供料
紹介元に患者さんの診療状況を報告する文書を提供した場合に、紹介先である自院が算定できる項目です。紹介した場合ではなく、紹介を受けた場合に算定できる点が他の点数とは異なります。
なお、紹介元からの求めに応じること、患者さんの同意が必要になる点には注意が必要です。
算定できる患者さんは、以下7つに分類されます。
- かかりつけ医機能に係る施設基準を届けている医療機関から紹介された患者さん
- 200床未満の病院又は診療所から紹介受診重点医療機関へ紹介された患者さん
- かかりつけ医機能に係る施設基準を届けている医療機関に紹介された患者さん
- 難病診療連携拠点病院・難病診療分野別拠点病院・てんかん支援拠点病院へ紹介された指定難病の患者さん、またはてんかんの患者さん(疑いも含む)
- 妊娠中の患者さん(3か月に1回の算定)
- 産科・産婦人科標榜医療機関から紹介された妊娠中の患者さん(自院の診療体制が整備されている場合)
- 産科・産婦人科標榜医療機関で、他の医療機関から紹介された妊娠中の患者さん
点数は150点です(2024年度改定における)
電子的診療情報評価料
電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関から診療情報提供書を持参した患者さんに対して算定できます。ただし、以下の情報のうち主要なものを電子的に確認したのち、自院の電子カルテに反映したうえで診療した場合に限る点に注意が必要です。
- 検査結果
- 画像情報
- 画像診断の所見
- 投薬内容
- 注射内容
- 退院時要約等
点数は30点に設定されています(2024年度改定における)。
算定できるのは、医療情報連携ネットワークを構築できている地域の医療機関です。ただし、自院が依頼して情報を提供してもらった場合は算定できません。
医療情報連携ネットワークについては、厚生労働省のページにまとめられています。事例や構築手順も掲載されているため、取り組みの参考にできます。
算定できないパターンを解説
診療情報提供料の算定は厳格なルールが設けられており、適切な要件を満たさない場合は算定できません。
診療情報提供料は、あくまで患者さんを他の医療機関に紹介する際に算定できるものであり、紹介元への単なる返事など、受診行動を伴わない情報提供は算定できません。また、情報提供先も原則保険医療機関(医科・歯科)が対象となっている点に注意が必要です。
誤算定を防ぐチェックリスト
診療情報提供料の適正な算定を確保するには、日々の運用においてチェック体制を構築する必要があります。以下のチェックリストを参考に、算定漏れや誤算定を防ぎ、適正な算定を推進しましょう。
別の医療機関に紹介した患者さんに算定できているか
他の保険医療機関での診療の必要を認め、患者さんの同意を得て診療情報提供書を作成した場合、診療情報提供料Ⅰ(250点)を算定できます。
以下、算定するうえでのポイントです。
- 紹介先の医療機関名が明記されているか
- 患者さんの同意が得られているか
- 同月内で同じ医療機関に同じ患者さんを紹介していないか
- 診療録に提供した文書の写しが添付されているか
セカンドオピニオンを求める患者さんに算定できているか
治療法の選択等に関して他院の医師の意見を求める患者さんからの要望を受けて診療情報提供書を作成した場合、診療情報提供料Ⅱ(500点)を算定します。
以下、算定するうえでのポイントです。
- 患者さんの病名は確定病名で登録されているか
- 自院で検査や画像診断を行い、紹介先では助言のみを求める形になっているか
- 同じ患者さんの場合月2回以上算定していないか
紹介された患者さんの紹介元に情報提供を返したか
かかりつけ医機能をもつ医療機関や難病拠点病院などから紹介された患者さんについて、紹介元の医療機関からの求めに応じて診療状況を示す文書を提供した場合、連携強化診療情報提供料(150点)を算定します。
以下、算定するうえでのポイントです。
- 算定には届出が必要
- 自院が施設基準を満たしているか
- 患者さんが算定要件に該当するか
医療連携ネットワークから取得した診療情報を自院のカルテに反映したか
別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者さんについて、検査結果や画像情報などを電子的方法により閲覧または受信し、診療に活用した場合、電子的診療情報評価料(30点)を算定します。
以下、算定するうえでのポイントです。
- 検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載しているか
- 当該保険医療機関の依頼に基づく情報ではないか
- 施設基準の届出はしてあるか
正しく漏れなく算定するにはシステムが重要
診療情報提供料を継続的に正しく算定するには、医師や事務スタッフの知識だけでなく、算定支援機能を備えた電子カルテシステムの導入が有効です。複雑な算定要件や月1回の制限、加算項目の判定など手作業でのチェックだけではどうしても限界がきてしまいます。
そこでウィーメックス株式会社では、メディコムシリーズとしてクラウド型電子カルテシステム「Medicom クラウドカルテ」と、ハイブリッド型電子カルテシステム「Medicom-HRf Hybrid Cloud」で適切な算定を支援しています。
どちらも、50年以上にわたる医事システム開発で培った算定ロジックが組み込まれています。改定の都度見直される診療情報提供料でも、確実な算定支援の提供が可能です。
クラウド型電子カルテの詳細はこちらから:クリニック向けクラウド型電子カルテシステム Medicom クラウドカルテ
ハイブリッド型電子カルテの詳細はこちらから:クラウド活用型電子カルテシステム(医事一体型)Medicom-HRf Hybrid Cloud
診療情報提供料についてよくある質問
診療情報提供料を算定する際、細かな要件や記載方法について迷いが生じるケースは少なくありません。ここでは、現場で起こりうる疑問について、具体的な対応方法をQ&A形式で解説します。
カルテ記載はどうすればいい?
カルテには、紹介先の医療機関名や提供した診療情報の内容を明記し、規定の様式に準拠した書式で記載を残す必要があります。
重要なのは、患者さんに渡した診療情報提供書と同じ内容が閲覧できる形で保存されていることです。なぜなら、診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に添付することと、算定要件に定められているためです。
コピーや電子データとして保存し、後日の査定時にも対応できるよう整備しておくと良いでしょう。
紹介先から追加でデータ提供を求められた場合は算定して良い?
紹介先の医療機関から追加の検査データや画像情報の提供を求められた場合は、診療情報提供料は算定できません。
診療情報提供料は、あくまで医療機関が診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めて患者さんを紹介する場合に算定できるものです。相手方医療機関からの依頼に基づく追加情報の提供は、療養担当規則第2条の2の範囲であり、算定対象から外れます。
まとめ
診療情報提供料は、地域包括ケアシステムの推進において重要な役割を果たす診療報酬です。適正な算定を実現するには、紹介元への返事のみでは算定できないなどの制限事項を理解し、チェックリストを活用した確認体制の構築が重要です。
まずは自院の現在の算定状況を確認し、誤算定防止のためのチェック体制を整備する作業から始めてみてはいかがでしょうか。
著者情報
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
- クリニック・
病院 - 薬局
-

医療政策(医科) 医師 事務長
第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー
-

医療政策(医科) 医師 事務長
2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」
-

医療政策(医科) 医師 事務長
第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー
-
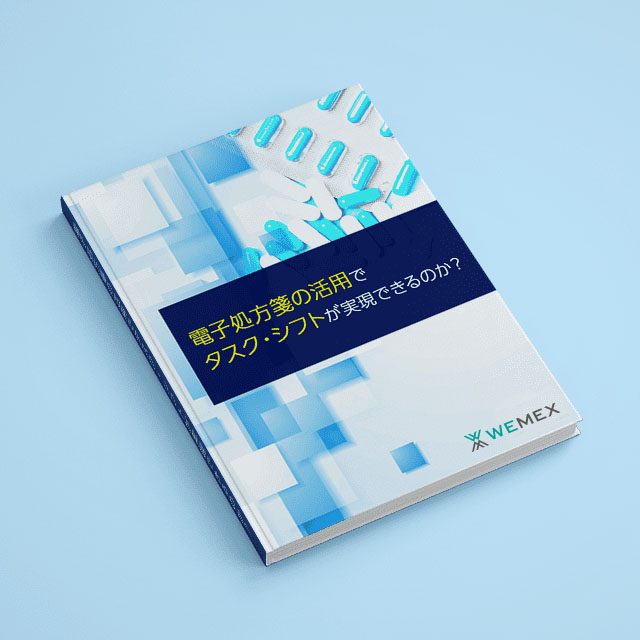
医療政策(医科) 医師 事務長
電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?
-

医療政策(医科) 医師 事務長
第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー
-

医療政策(医科) 医師 事務長
オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える
-

医療政策(医科) 医師 事務長
地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?
-
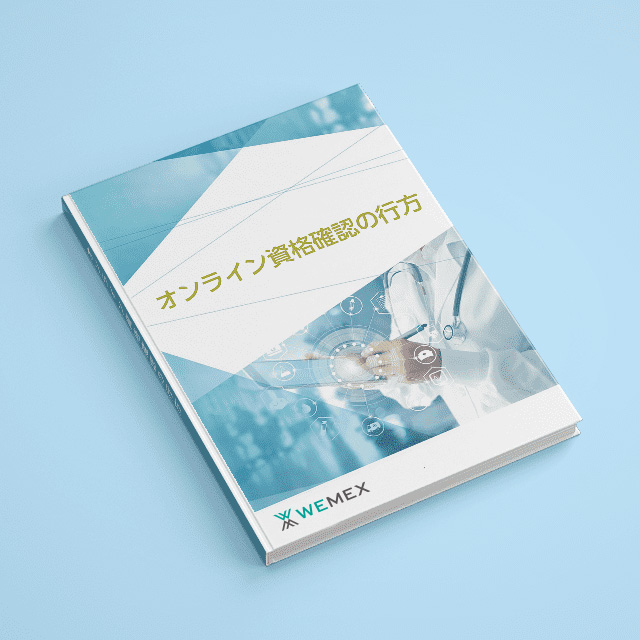
医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者
オンライン資格確認の行方