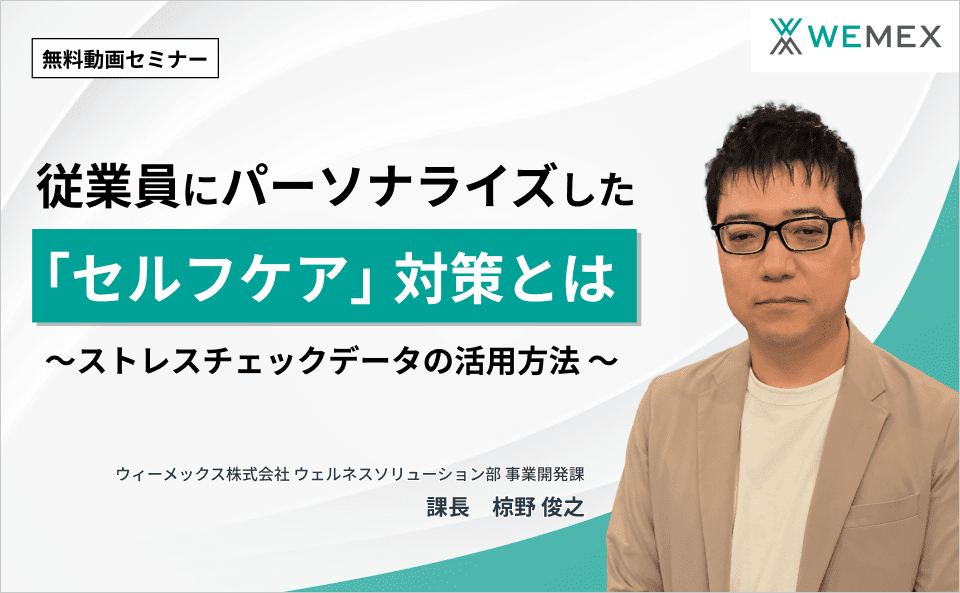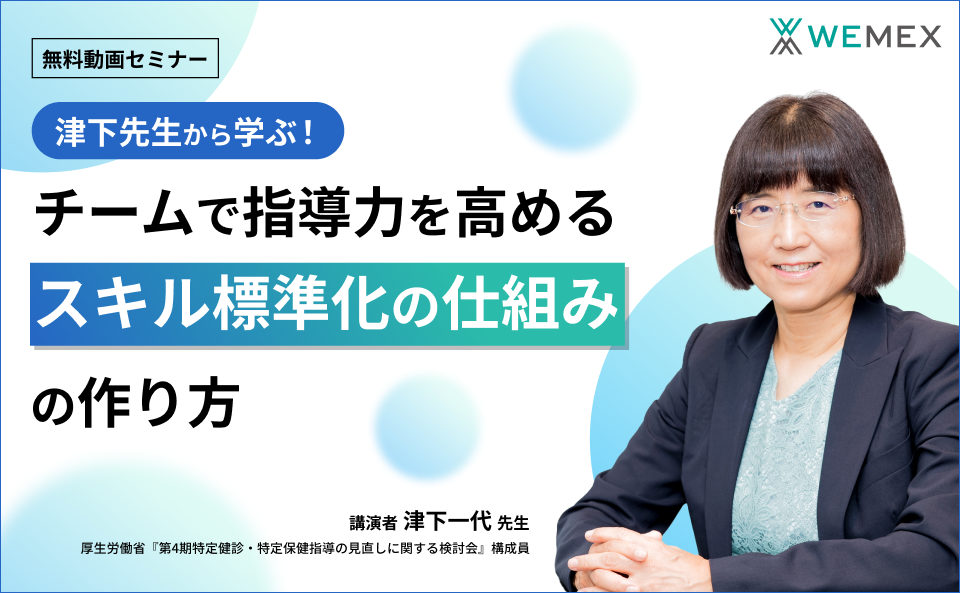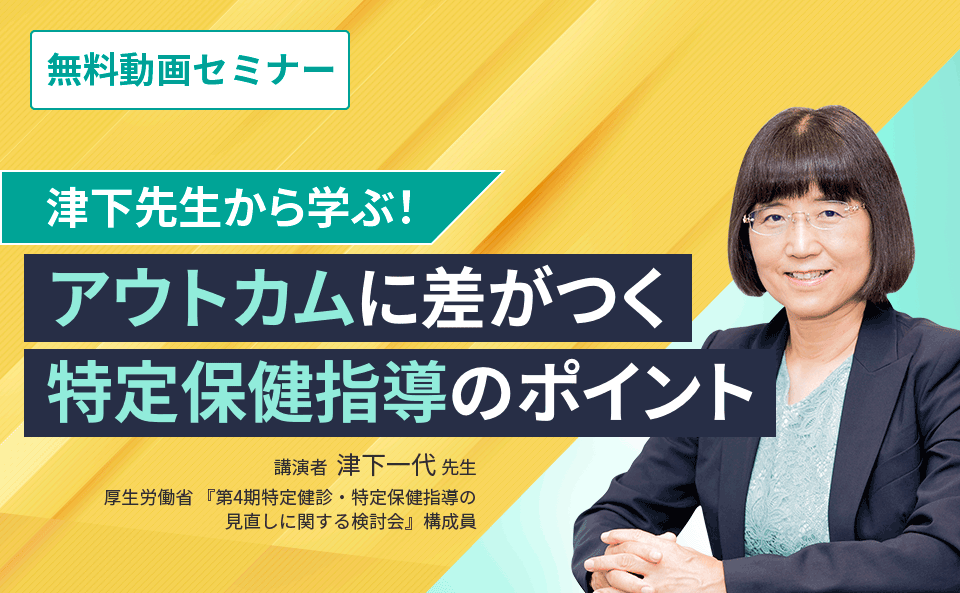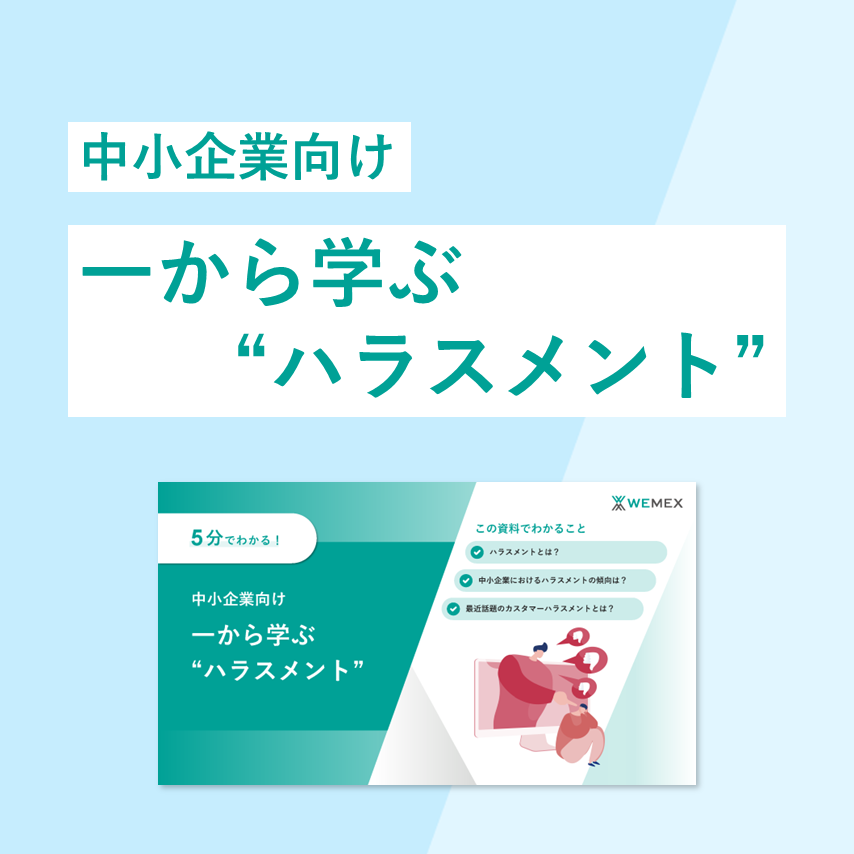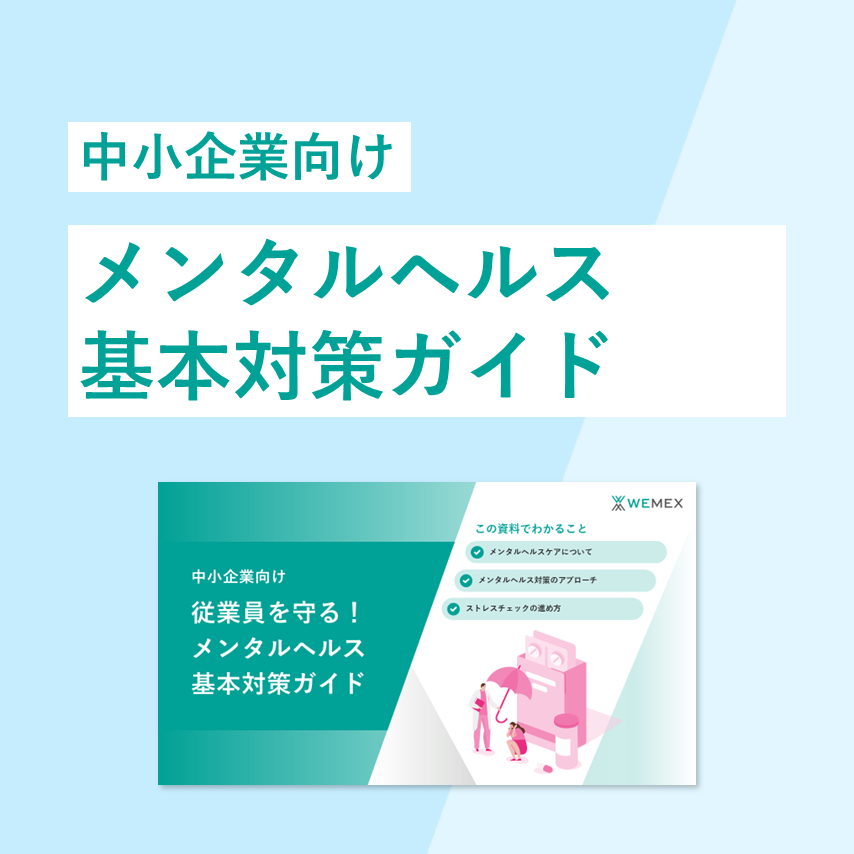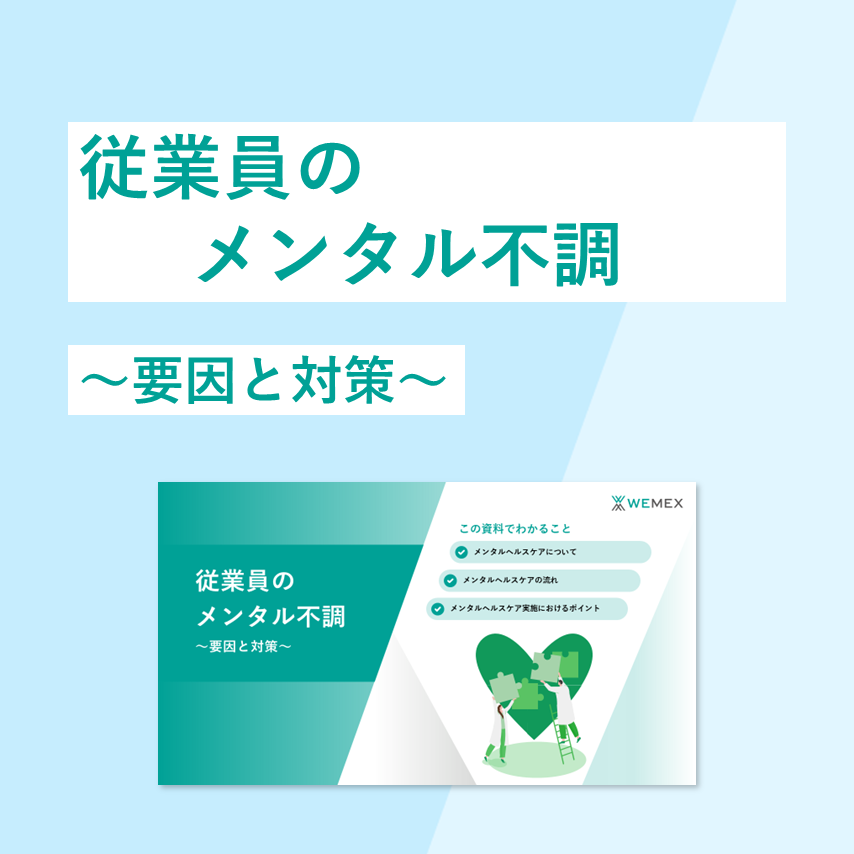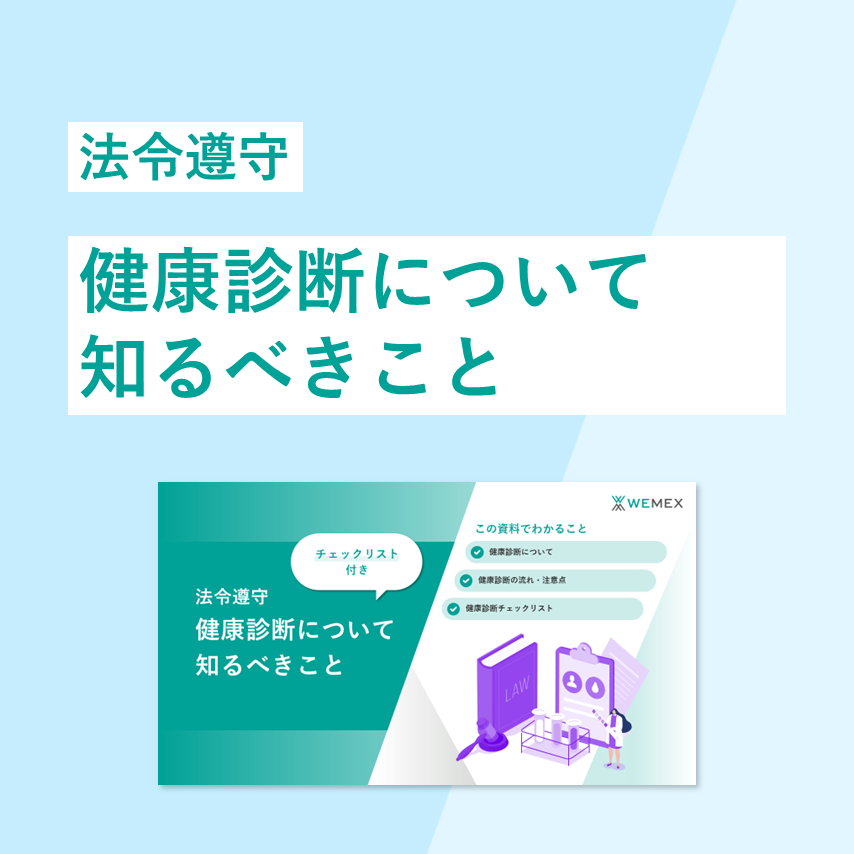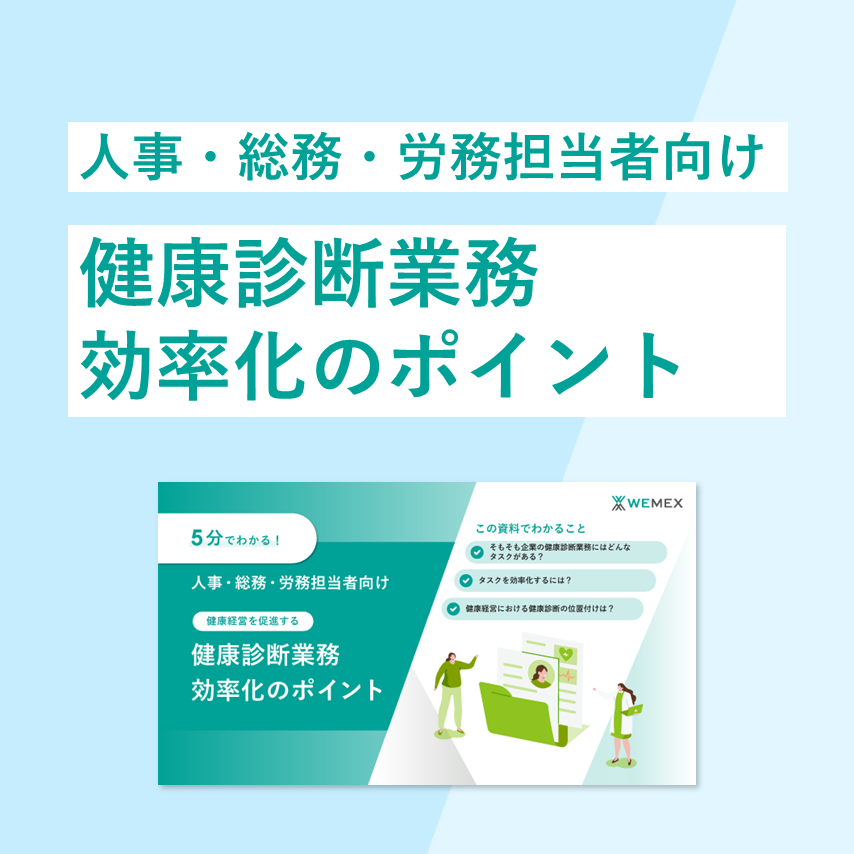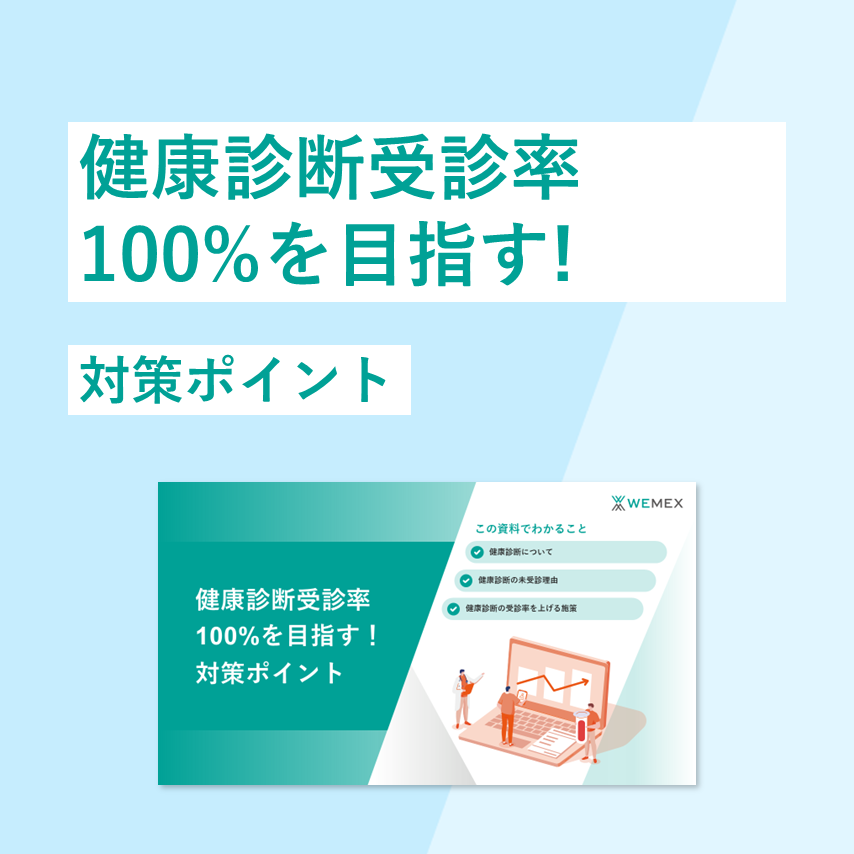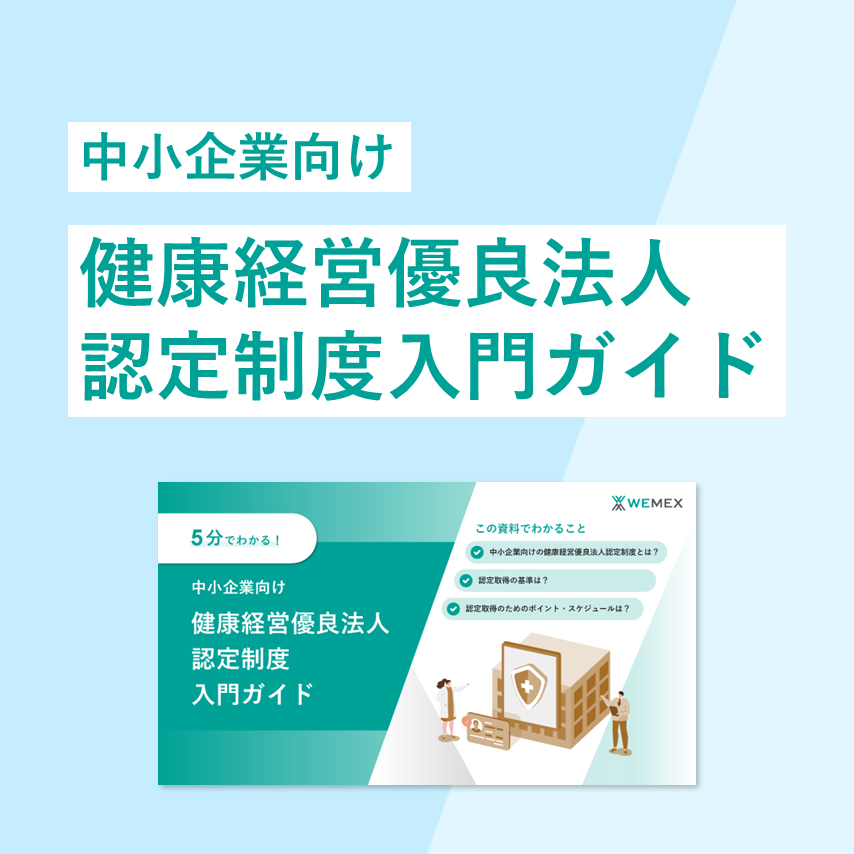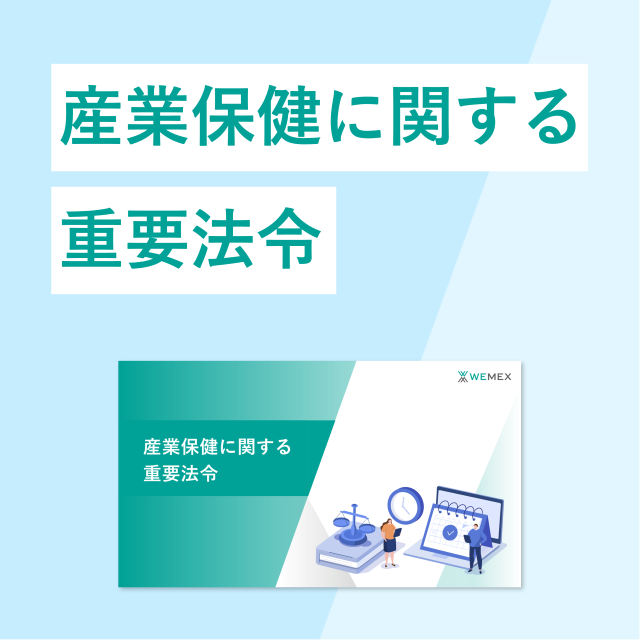目次
健康診断は会社の義務

企業は、従業員の健康を守るために、法律で定められた健康診断を実施する責任があります。労働安全衛生法第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。
さらに、従業員自身も会社が実施する健康診断を受ける義務があり、これを拒否することは認められていません。健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条に基づき、企業には50万円以下の罰金が科される可能性があります。
健康診断の対象者
健康診断の受診対象は、労働時間や雇用形態によって異なります。「常時使用する労働者」つまり正社員に対して、健康診断が義務づけられています。
正社員以外の場合について詳しく見ていきましょう。
アルバイト・パート
アルバイト・パートは、以下2つに該当する場合、受診対象となります。
- 雇用期間に定めがない(定めがある場合には1年以上使用されることが予定されている)
- 週の労働時間が正社員の4分の3以上
また、週の労働時間が正社員の2分の1以上であれば、実施することが望ましいとされています。
派遣社員・出向社員
派遣社員については、派遣元企業が健康診断を実施する義務を負い、派遣先企業にはその義務はありません。ただし、特殊健康診断*については派遣先企業が実施する義務を負う必要があります。
出向社員は、労働安全衛生法上では出向先に事業者責任があるとされるため、出向先企業で実施義務を負います。
*特殊健康診断:有害業務(高気圧業務、放射線業務、石綿業務など)に従事する労働者を対象に法令で義務づけられた健康診断
役員
役員の健康診断受診の可否は、その役職の労働者性の有無によって判断されます。工場長や支店長など、労働者としての業務が強く求められる役職に就いている場合は、健康診断の対象になります。
しかし、代表取締役や社長といった経営に専念する立場の者は、法的な受診義務の対象外となります。ただし、職場全体の健康管理を考えた場合、役員自身も健康診断を受けることが望ましいといえるでしょう。
従業員の配偶者・家族
企業が実施する健康診断は従業員を対象とした者であり、従業員の配偶者や家族は「常時使用する者」に該当しないため対象外です。しかし、健康保険組合によっては、被扶養者向けに健康診断を提供しているケースもあるため、加入している保険組合の制度を確認するとよいでしょう。
健康診断の種類

健康診断には下記の種類があります。
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
それぞれ、対象者や実施時期などについて詳しく見ていきましょう。
雇入時の健康診断
企業が新たに従業員を雇い入れる際、労働安全衛生規則に基づき健康診断を実施することが義務づけられています。これは、従業員の健康状態を事前に把握し、適切な就業環境を整えるために必要な措置です。
ただし、入社前3ヶ月以内に必要な健康診断を受け、結果を提出できる場合は、雇い入れ時健康診断を省略することが可能です。加えて、健康診断の結果を採用の可否の判断基準として使用することは禁止されています。
定期健康診断
企業は、上述で対象となる従業員に対し年1回の定期健康診断を実施する義務があります。これは、従業員の健康状態を継続的に把握し、健康リスクを未然に防ぐためです。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断は、危険業務に従事する従業員を対象に実施されます。過酷な労働環境や有害物質を扱う業務による健康への影響を定期的に評価し、必要な対策を講じることを目的としています。特定業務への配置替えの際に1回、その後は6ヶ月以内ごとに1回の頻度で継続的に行います。
特定業務従事者の健康診断の対象者は下記のとおりです。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断は、海外に6ヶ月以上派遣される従業員に対し、派遣前と帰国後に行います。目的は、長期の海外勤務が従業員の健康に及ぼす影響を事前に評価し、適切な予防措置を講じることです。海外では、気候や衛生環境、感染症リスク、食生活の変化など、日本国内とは異なる要因が健康状態に影響を与える可能性があるため、企業は派遣前と帰国後に健康診断を行うことが義務づけられています。
給食従業員の検便
給食業務に従事する従業員に対する検便は、食中毒の発生を未然に防ぎ、安全な食事を提供するために行います。給食業務に従事する人が細菌やウイルスを保有している場合、それが食材や調理器具を介して広がり、食中毒を引き起こす可能性があるためです。
そのため、企業は労働安全衛生規則に基づき、給食従業員に対して定期的な検便を実施する義務を負います。検便の対象者は、事業所に附属する食堂や炊事場で給食業務を行う従業員で、新たに雇い入れられた際と、他の業務から給食業務へ配置転換される際に行います。
健康診断の会社の費用負担
企業が従業員に対して実施する健康診断の費用は、一般的に一人あたり10,000円~15,000円程度とされています。ただし、企業の規模や健康診断の受診形態、検査内容によって変動します。
たとえば、企業が医療機関と契約を結び、事業所に巡回健診用の特殊車両を派遣してもらう場合と、各従業員が指定の医療機関で個別に受診する場合では、かかるコストが異なります。巡回健診は、一度に多くの従業員が受診できるため効率的ですが、車両手配費用が加算されるケースもあります。一方、各自で受診する方式では、診療所の選択肢が広がる反面、従業員の移動費や受診時間の管理が必要です。
健康診断の費用を企業が負担する際には、福利厚生費として計上することが一般的です。しかし、税務上、福利厚生費として認められるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 従業員全員が健康診断を受診できる体制が整えられている
- 従業員の健康管理を目的とした支出である
- 企業が直接医療機関へ費用を支払う
健康診断後に会社に求められる取り組み
健康診断後は、下記のように取り組む必要があります。
- 健康診断個人票の作成と保存
- 医師等からの意見を聞く
- 必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮などを行う
- 必要に応じて保健指導を行う
- 従業員への通知・所轄労働基準監督署長への報告
それぞれ詳しく見ていきましょう。
健康診断個人票の作成と保存
企業は、健康診断の結果を適切に記録し、従業員ごとに「健康診断個人票」を作成する義務があります。目的は、健康診断の記録を長期的に管理し、従業員の健康維持と適切な職場環境の整備を図ることです。
健康診断個人票には、受診者の基本情報(氏名、生年月日、職種など)のほか、診断結果や医師の所見、必要な措置などが記載されます。
医師等からの意見を聞く
企業は、健康診断の結果に異常が見つかった従業員に対し、適切な健康管理を実施するために、医師の意見を聞くことが義務づけられています。目的は、従業員の健康リスクを最小限に抑えることです。
また、企業は医師の意見をもとにした措置内容を従業員に適切に説明し、必要に応じて産業医や保健師とも連携を取りながら、健康管理をサポートする必要があります。
必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮などを行う
企業は、健康診断の結果や医師の意見を踏まえ、必要に応じて作業内容の変更や労働時間の短縮などの適切な措置を講じる必要があります。目的は、従業員の健康を守りながら、業務の安全性を確保することです。
必要に応じて保健指導を行う
健康診断の結果、とくに生活習慣の改善が必要とされる従業員に対しては、医師や保健師による保健指導を行うことが努力義務とされています。目的は、従業員の疾病予防や健康維持の促進です。
従業員への通知・所轄労働基準監督署長への報告
企業は、健康診断の結果を受診した従業員に通知するとともに、所轄の労働基準監督署長へ健康診断の結果を報告する義務があります。健康診断の種類によって、対象の事業者が異なります。
| 健康診断の種類 | 対象の事業者 |
|---|---|
|
定期健康診断 特定業務従事者の健康診断 歯科医師による健康診断* |
常時50人以上の従業員を使用する事業者 |
| 特殊健診 | 健診を行った全ての事業者 |
*歯科医師による健康診断:メッキ工場など、歯への影響が懸念される業務を行う従業員が対象
まとめ
健康診断は、企業が従業員の健康を守り、安全な労働環境を維持するために不可欠な取り組みです。健康診断後のフォローアップや適切な保健指導を行うことで、従業員の健康維持・向上につながり、ひいては業務の生産性向上や企業の成長にも寄与します。
健康診断の運営には、受診対象者の管理、予約手配、結果の回収、データ管理など、多くの業務が発生します。そうした課題を解決するために、健康診断の事務作業を専門業者に委託するのも選択肢の1つです。
「Wemex 健診代行」では、全国3,000以上の健診機関と提携し、契約手続きから結果の回収までを一括で代行するため、煩雑な業務を効率化できます。健康診断の事務作業をアウトソーシングし、健康管理体制を構築されたい場合はお気軽にご相談ください。
Wemex 健診代行
出典:e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)
e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_4-At_13-Pr_1-It_3)