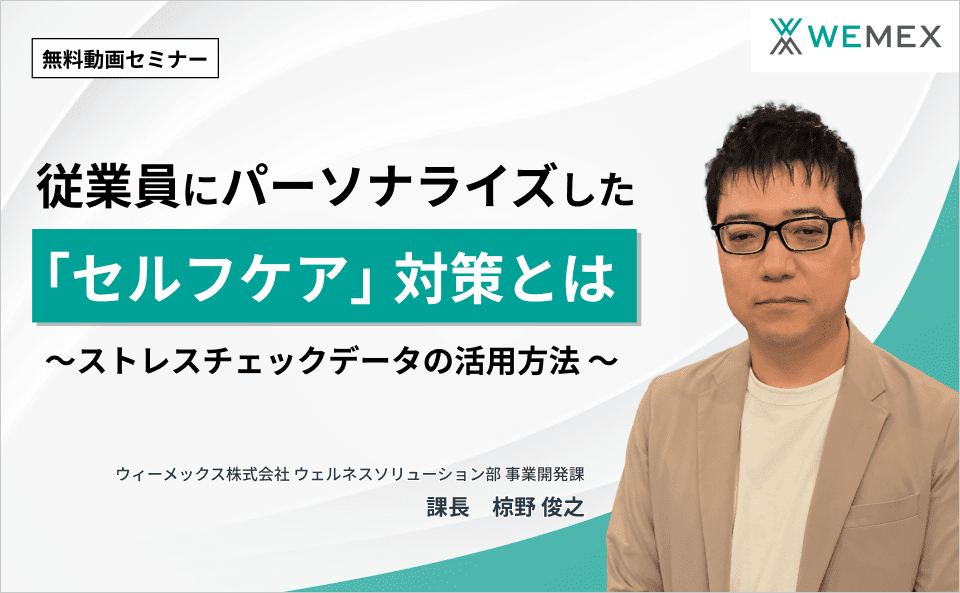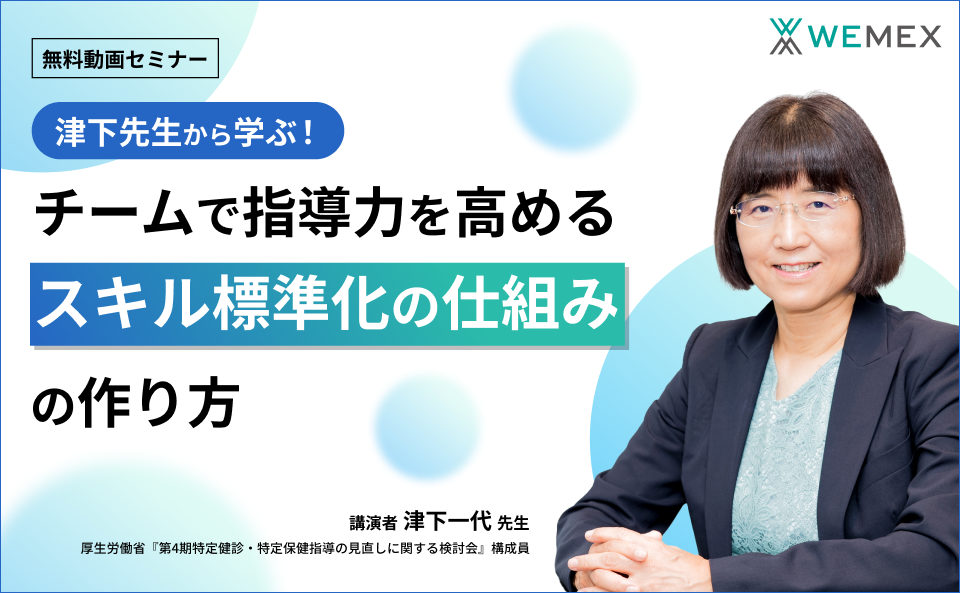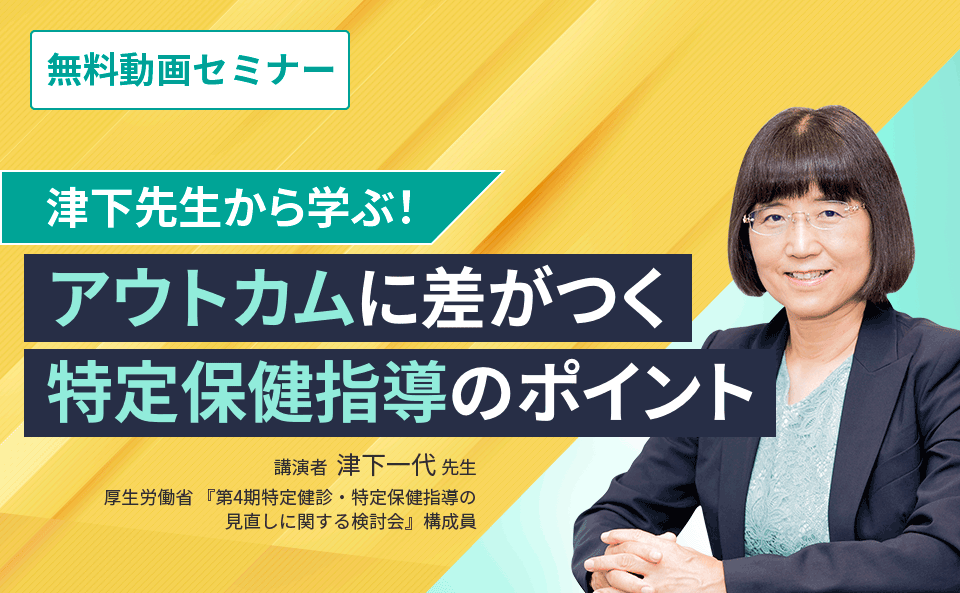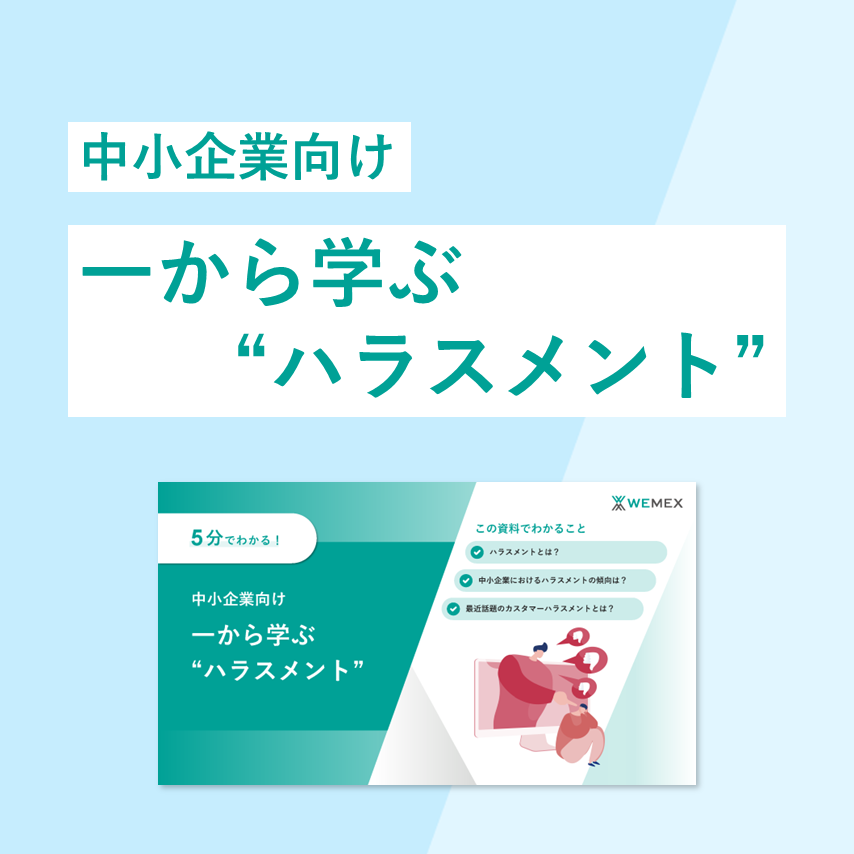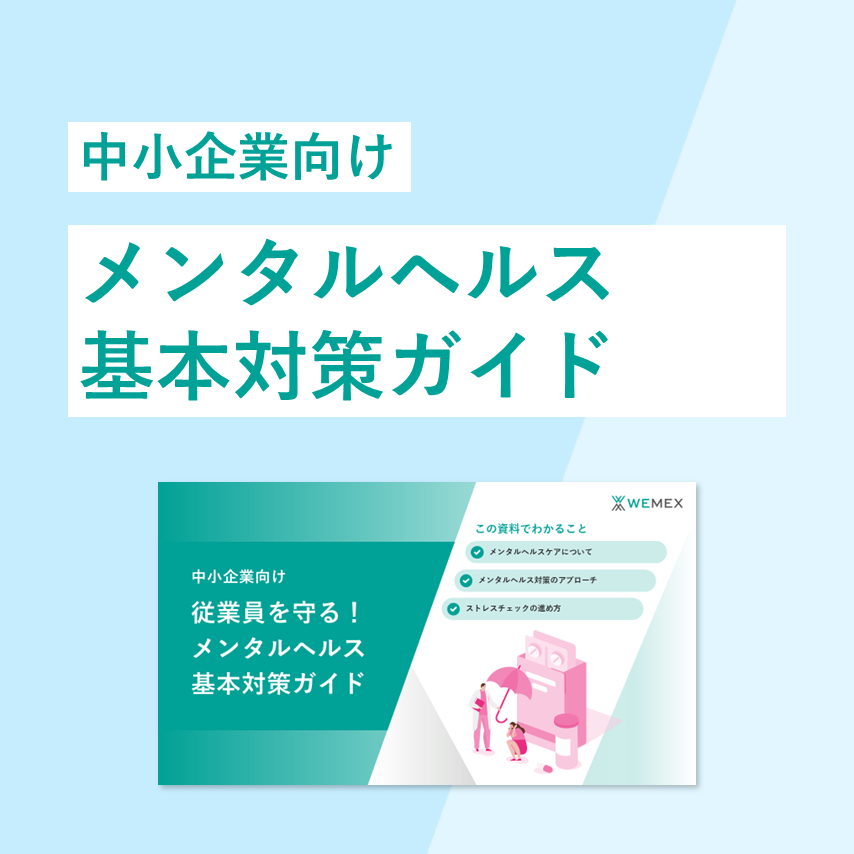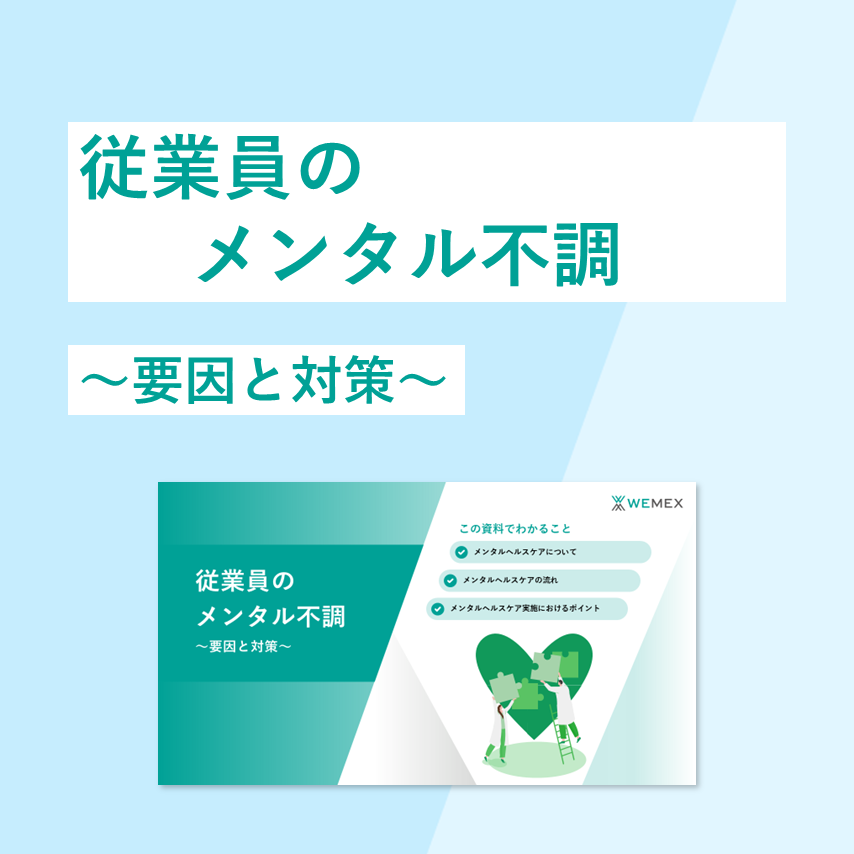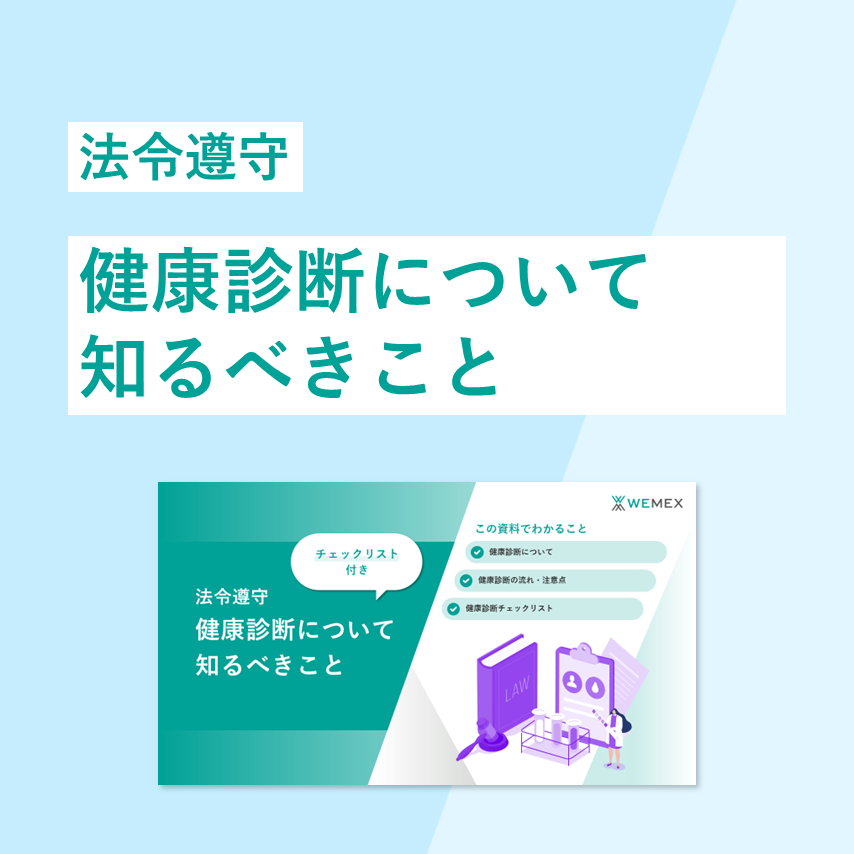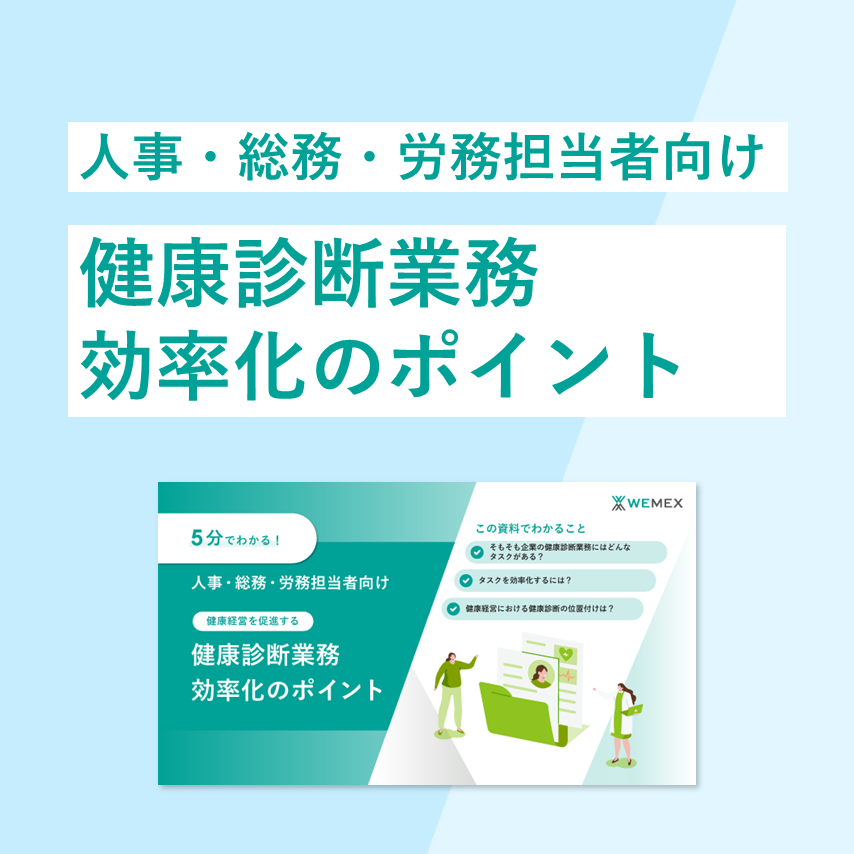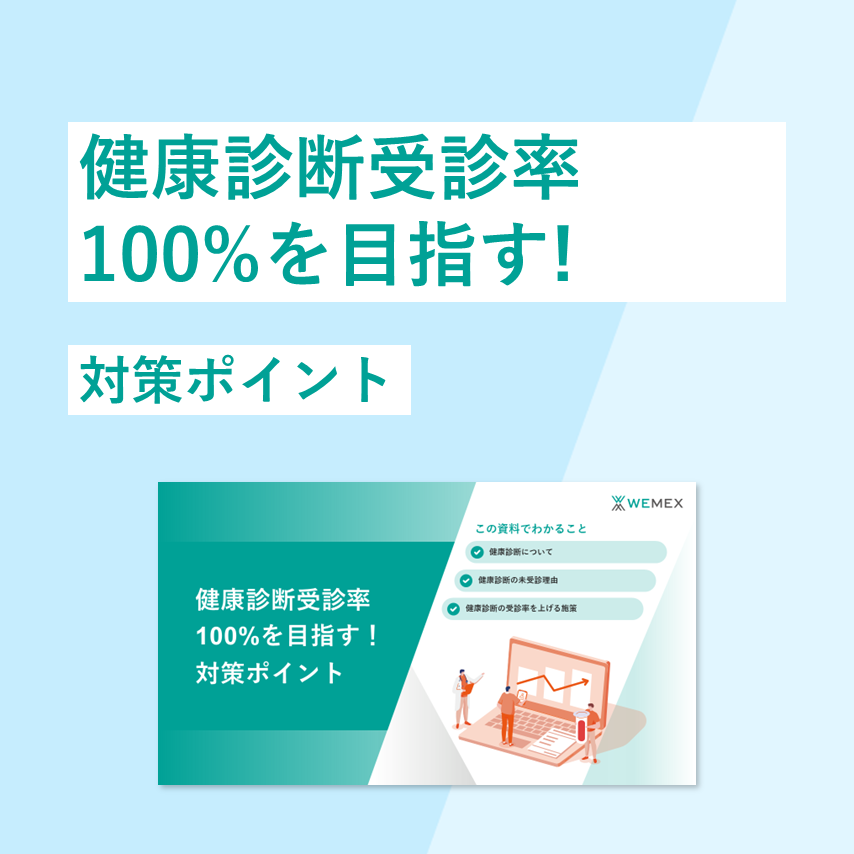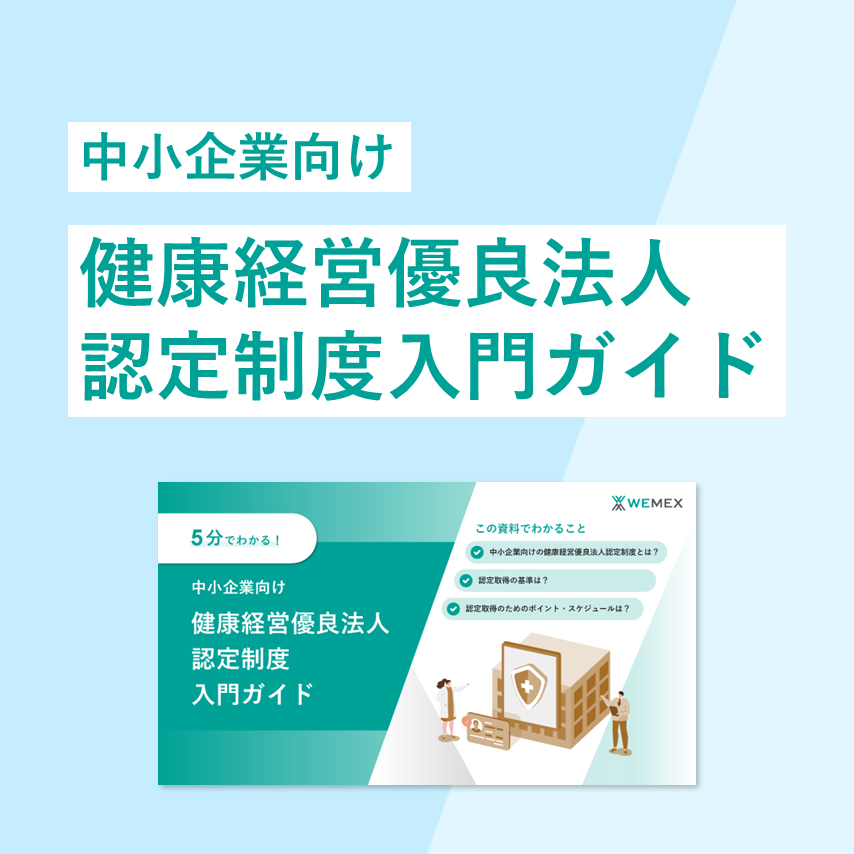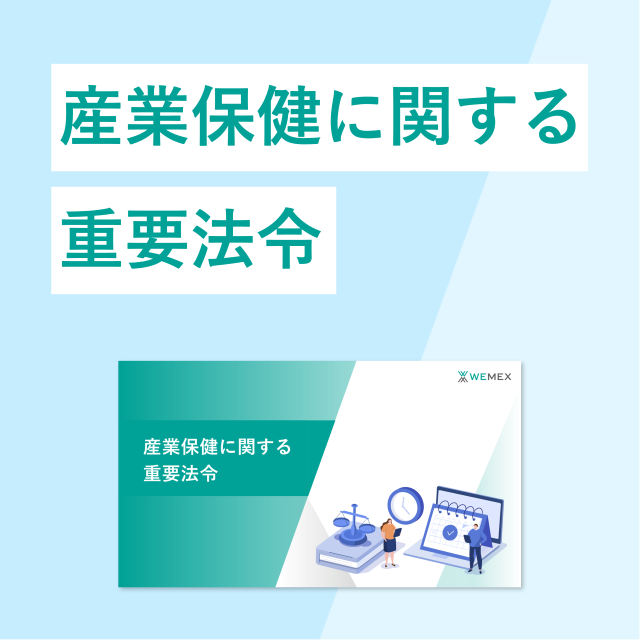目次
メンタルブレイクとは

メンタルブレイクは「mental」と「break」を組み合わせた言葉です。強いストレスを抱えたり、精神的に追い詰められたりして、心のバランスが崩れた状態を指します。
この状態が続くと、心身に不調が現れ、業務に支障をきたすことも少なくありません。また、従業員のメンタルブレイクに気づかず放置すると、うつ病や不安障害などの精神疾患に発展する恐れもあります。
メンタルブレイクが注目されている背景
「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事でストレスを感じている労働者は全体の82.7%にのぼります。この結果から、多くの人が精神的な負担を抱えて働いていることが分かります。
こうした状況の背景には、働き方の変化や長時間労働、人手不足、生活不安などの重なりなどが考えられます。またメンタルヘルスへの意識の高まりも、ストレスの自覚を後押しており、メンタルブレイクは、すべての労働者に関わる重要な課題といえるでしょう。
従業員のメンタルブレイクが企業に及ぼす影響
組織の中にメンタルブレイク状態の従業員が1人でも発生すると、全体へ影響が及ぶ可能性があります。例えばメンタルブレイク状態に対処せずに働き続けると、業務遂行能力が低下し、生産性や業績の悪化につながります。
また、メンタルブレイクによる不調で従業員が欠勤や休職をすると、他の従業員の負担が増加します。メンタルブレイクになった本人だけでなく、業務量が増えた従業員も疲弊し、離職を考える可能性が高まります。
離職者が増えると、新たな人材の採用や育成に時間とコストがかかり、組織の成長も鈍化するため、メンタルブレイクは企業にとって無視できない課題です。
従業員がメンタルブレイクに陥るストレス要因
ここでは、従業員がメンタルブレイクに陥る3つの主なストレス要因について解説します。
- 職場のストレス
- 人間関係のストレス
- プライベートのストレス
順番に見ていきましょう。
職場のストレス
メンタルブレイクの要因のひとつが、職場で感じるストレスです。過重労働や役割分担の不明確さ、サポート体制の不足などが従業員の心身に負担をかけます。
このような環境では、自分の業務範囲が分かりづらく、困ったときに相談できる相手も少ないため、ミスが起こりやすくなります。ミスを指摘されると、気持ちが落ち込み、失敗へのプレッシャーも強まります。
さらに、努力が正当に評価されない職場環境も、従業員のストレスの原因となります。「どれだけ頑張っても認められない」という思いが、キャリアへの不安やモチベーションの低下につながるでしょう。
また近年では、リモートワークやフレックス制度の普及により対面のコミュニケーション量が低下したことで、スムーズな意思疎通ができないことも、ストレスの要因となっています。
人間関係のストレス
人間関係も、従業員がメンタルブレイクに陥る大きなストレス要因です。職場では上司や部下、同僚、取引先など、さまざまな人と関わる必要があります。時には、ハラスメントや相性の合わない相手との関係がストレスの原因になることもあります。
また、職場以外でも、パートナーや友人とのすれ違いなどで、自分の気持ちをうまく伝えられず孤独を感じる場合もあります。こうした人間関係のストレスが積み重なると心が限界に達し、メンタルブレイクを引き起こすことがあります。
プライベートのストレス
プライベートでの出来事も、メンタルブレイクに影響します。たとえば、身近な人の病気や死、離婚、失業などが挙げられます。これらは深い悲しみや孤独感をもたらし、心身に大きな負担をかけます。
ネガティブな出来事だけでなく、結婚や出産、進学や就職による転居など、一見ポジティブなイベントも、緊張や不安の原因となります。「早く新しい環境に慣れなければ」と無意識に自分を追い込み、ストレスを感じてしまうこともあるのです。
メンタルブレイクに陥りやすい人の7つの特徴
メンタルブレイクに陥りやすい人には、7つの特徴があります。ストレスを感じやすい人や、自分の気持ちを内に溜め込みやすい性格の人は特に注意が必要です。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 心配性 | 取り越し苦労が多く、過度にストレスを抱えやすい 最悪の事態を想定して不安を感じやすい |
| 完璧主義 | 小さなミスも気になりストレスを感じやすい 理想が高く、他人にも完璧を求めることがある |
| 負けず嫌い | 競争心が強く、人から認められたい気持ちがある |
| 融通がきかない | 他人を頭ごなしに叱ったり、自分の考えに固執する頑固さがある |
| 周囲を気にし過ぎる | 他人の目が気になり、後で悩んだり落ち込んだりしやすい |
| 真面目な優等生タイプ | 責任感が強く、仕事でも妥協しない 他のタイプに比べてストレスを感じやすい傾向がある |
| 他人をコントロールしたがる | 周囲に自分の思い通りに動いてほしいと考え、物事が思い通りに進まないと気がすまない |
メンタルブレイクのサイン
メンタルブレイクには、精神面・身体面・行動面のサインがあります。従業員の様子に変化がないか日ごろから観察し、兆候を見逃さないことが大切です。ここからは、それぞれのサインについて説明します。
精神面のサイン
メンタルブレイクが近いとき、精神面では次のようなサインが見られます。
- 憂うつな気分になる
- 集中力が続かない
- 怒りっぽくなる
- マイナス思考が強まる
- ささいなことで落ち込みやすくなる
従業員がメンタルブレイクしかけている場合、業務への意欲や集中力が低下し、感情が不安定になることが多くなります。
身体面のサイン
メンタルブレイクのサインは、身体にも現れます。
- 頭痛
- 腹痛
- 動悸
- 不眠
- 倦怠感
- 息苦しさ
- 食欲の変化(減退・増進)
普段元気な従業員がこうした不調を訴えた場合、メンタルブレイクの可能性を考えましょう。自分から体調不良を言い出せない人もいるため、表情や動きにも注意が必要です。
行動面のサイン
行動面にもメンタルブレイクのサインが現れます。従業員が次のような行動をとる場合は注意しましょう。
- 遅刻や欠勤が増える
- 独り言が多くなる
- ぼんやりしている
- 人との関わりを避ける
- 上司や同僚とのトラブルが増える
行動の変化は周囲が気づきやすいサインです。従業員の変化を早めに察知し、適切なサポートをおこないましょう。
従業員のメンタルブレイクを予防する方法
企業が従業員のメンタルブレイクを予防するには、次の5つの方法があります。
- 職場環境を改善する
- 研修や啓発活動をおこなう
- 心の不調の早期発見に努める
- ストレスチェックを実施する
- 従業員同士のコミュニケーションを活発化する
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
職場環境を改善する
従業員のメンタルブレイクを防ぐには、職場環境の見直しが重要です。労働時間を適正に管理し、業務量を調整することで、従業員の過労を防ぐ取り組みが求められます。
快適な作業スペースを整えることも、ストレス軽減に効果的です。業務に支障が出ないよう適度な広さを確保すれば、従業員の効率が上がり、ストレスも感じにくくなります。
また、リモートワークやフレックスタイム制の導入時は、従業員同士のコミュニケーション環境やルール整備などを配慮した、安全・衛生管理の徹底も大切です。従業員が安心して働ける環境づくりが、ストレスの予防につながります。
研修や啓発活動をおこなう
メンタルヘルスに関する研修や啓発活動も、従業員のメンタルブレイク予防に有効です。従業員がメンタルヘルスについて理解を深め、自分の心の状態に気づき、ストレスに対処する力を身につけることができます。
ストレスコーピング(対処法)*1の例として、下記が挙げられます。
- 信頼できる人に話す
- 気分転換に散歩する
- 深呼吸で気持ちを整えるなど
ストレスマネジメントやリラクゼーション法の研修を通じて、自分の思考のくせやストレス反応を知ることで、感情をコントロールする力が養われます。
*1 ストレスコーピング:ストレスに意図的に対処する行動や方法のこと
心の不調の早期発見に努める
従業員の心の不調に早く気づき、ケアできる体制を整えることも重要です。職場内に、従業員が気軽に相談できる場を設けるとよいでしょう。カウンセラーや産業医による相談窓口を設置すれば、ストレスを抱える従業員が専門的なサポートを受けやすくなります。
また、日ごろから上司が従業員の表情や言動に注意を払い、小さな変化も見逃さないよう心がけることも大切です。何気ない会話や日常の業務の中で従業員のサインに気づければ、メンタルブレイクを未然に防げる可能性が高まります。
ストレスチェックを実施する
ストレスチェックも、メンタルブレイク予防に効果的な方法です。ストレスチェックは、従業員が質問票に回答し、その結果を分析してストレスの状態を把握します。
労働安全衛生法では、従業員が50人以上いる事業所に対し、年1回のストレスチェックを義務付けています(2025年4月時点)。ストレスチェックは、従業員のメンタルブレイクを防ぎ、適切なサポートをおこなうために有効な手段です。
従業員同士のコミュニケーションを活発化する
従業員のメンタルブレイクを防ぐには、職場内でのコミュニケーションを活発にすることも重要です。
人とのつながりが希薄になると、孤独感や疎外感が強まり、メンタル不調を招きやすくなります。そのため、チームで協力して業務に取り組む体制を整えたり、リモートワーク中でも定期的にオンラインミーティングをおこなうなどの工夫が効果的です。
仕事の悩みを共有できる場があれば、1人で抱え込まずに済み、ストレスの軽減につながります。日常の声かけや雑談も、従業員同士の信頼関係を築くきっかけとなるでしょう。
従業員のメンタルヘルスケアにおけるポイント

メンタルヘルスケアは、従業員が心身ともに健康で働くために欠かせない取り組みです。適切なケアや予防策をおこなうことで、ストレスによるメンタルブレイクを未然に防ぐことができます。
ここからは、メンタルヘルスケアの4つのケアと3つの予防について簡単にご紹介します。関連記事にも詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
メンタルヘルスの4つのケア
メンタルヘルスケアには、次の4つのケアがあります。
| ケアの種類 | 内容 |
|---|---|
| セルフケア | 従業員が自分でストレスに対処し、心身の健康を管理する |
| ラインによるケア | 上司や管理職が従業員の不調に気づき、対応や支援を行う |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医やカウンセラーなど社内の専門家が支援する |
| 事業場外資源によるケア | 医療機関や外部相談窓口など、社外の専門機関が支援する |
メンタルヘルスケアの3つの予防
続いて、メンタルヘルスケアの3つの予防についてもご紹介します。
| 予防の種類 | 内容(目的) |
|---|---|
| 一次予防 | 心の不調を未然に防ぐため、職場環境の改善やストレス対策を行う |
| 二次予防 | 早期発見と迅速な対応で、メンタル不調の深刻化を防ぐ |
| 三次予防 | 不調から回復した従業員がスムーズに職場復帰できるよう支援する |
まとめ
メンタルブレイクは、過度なストレスが原因で起こる心身の不調です。職場での業務や人間関係、プライベートでのストレスが主な原因となります。従業員からのサインを見逃して放置すると、生産性の低下や離職の増加など、企業にも大きな影響を与えます。
従業員の心を守り、健全な企業運営を続けるには、メンタルヘルスケアの体制づくりが欠かせません。しかし、限られた担当者だけですべての従業員のメンタル不調に対応するのは難しいのが現実です。
「Wemex ストレスチェック」は、メンタルヘルス担当者の負担を軽減し、効率的なストレスチェックを実現します。従業員がセルフケアを学ぶeラーニングや、従業員向け相談窓口の設置も可能です。
従業員の心身の健康を守るために、ぜひ一度お問い合わせください。
Wemex ストレスチェック
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo02.pdf)