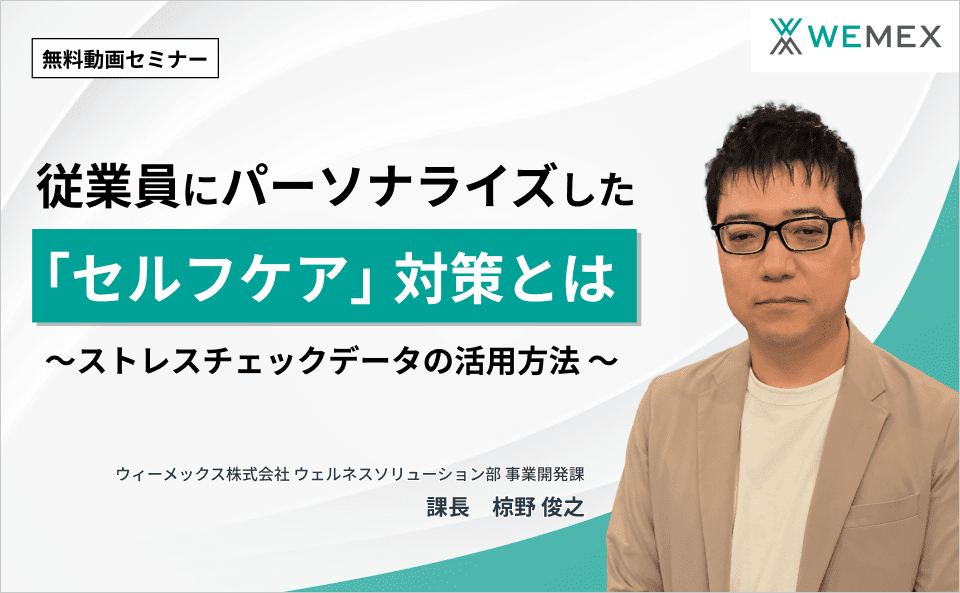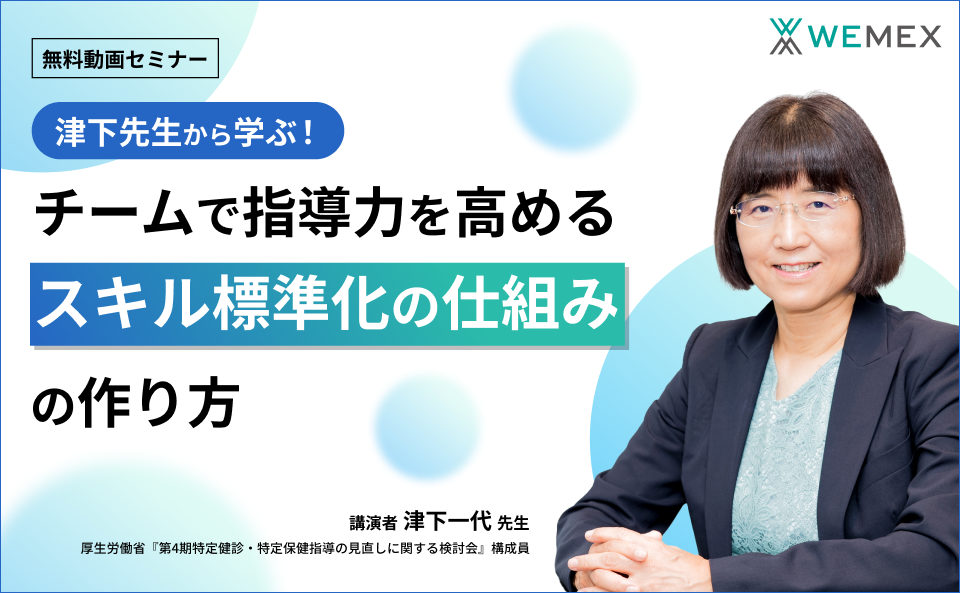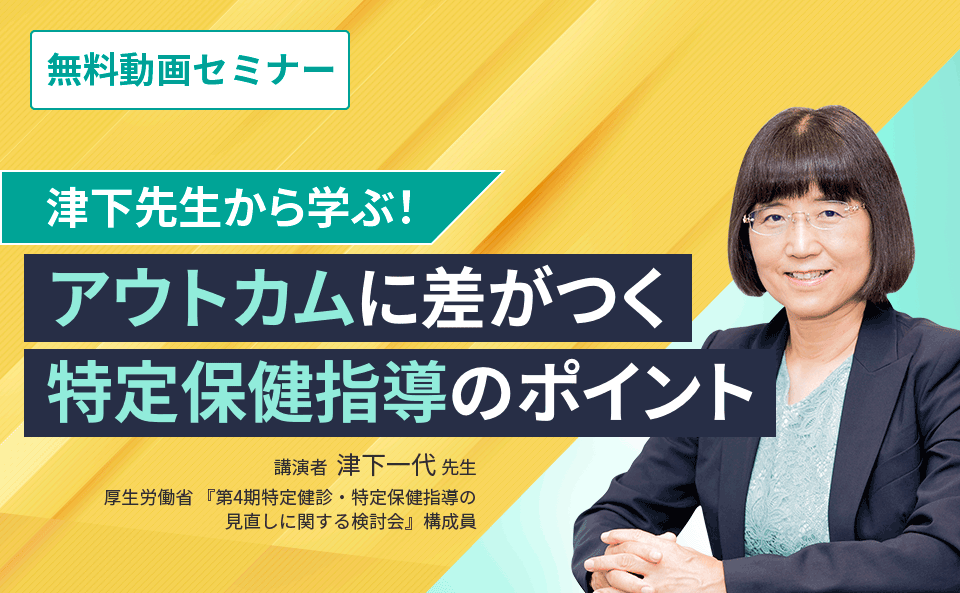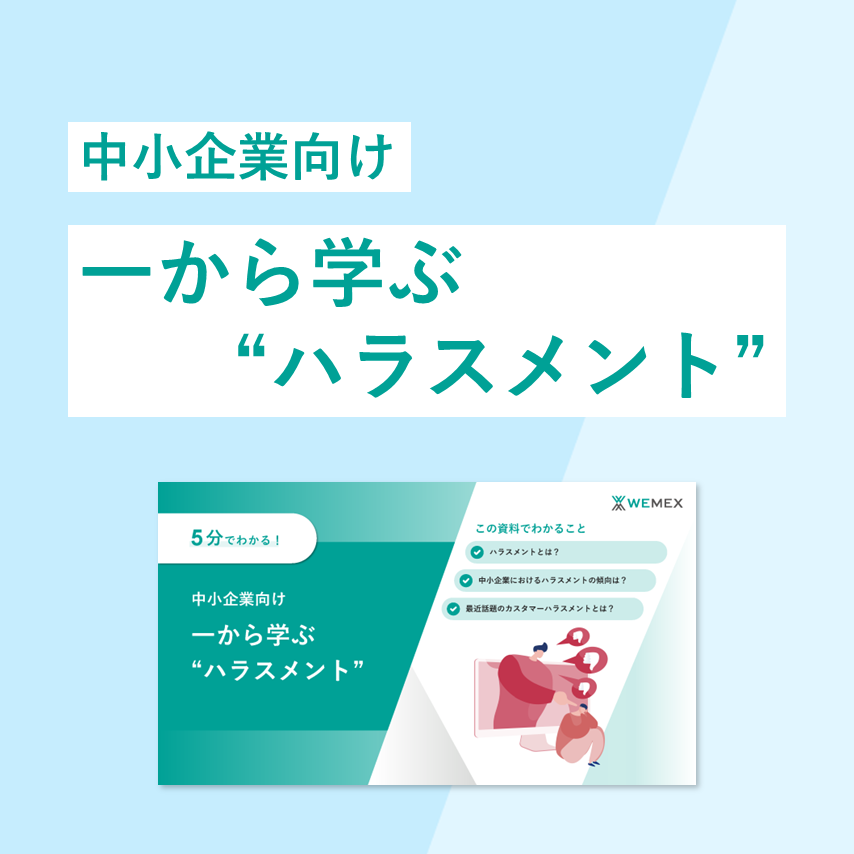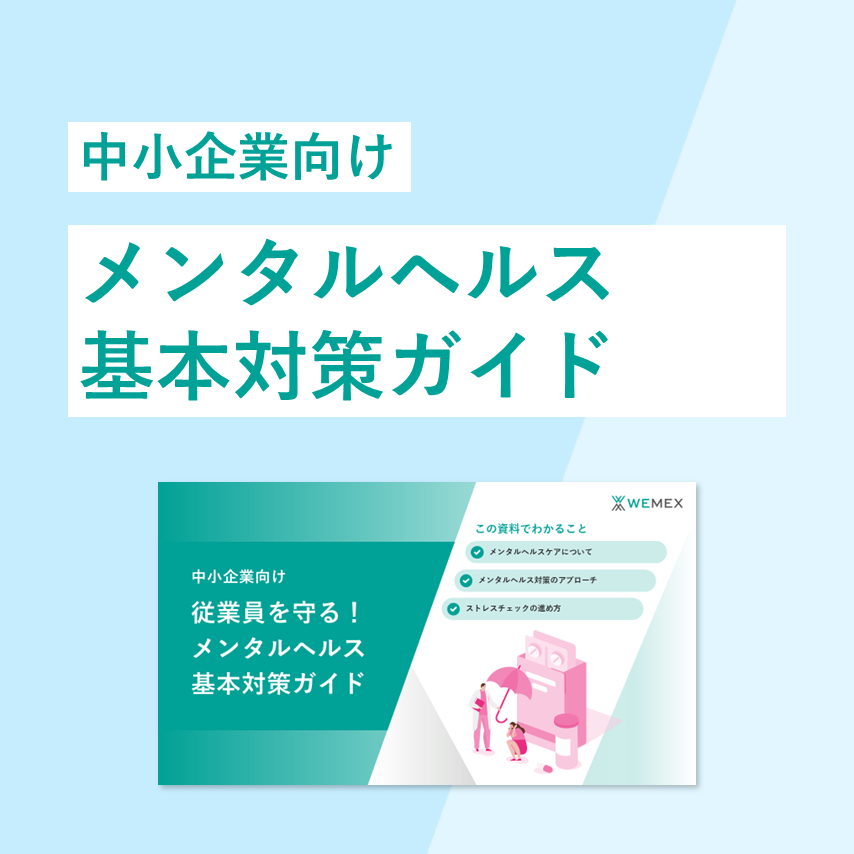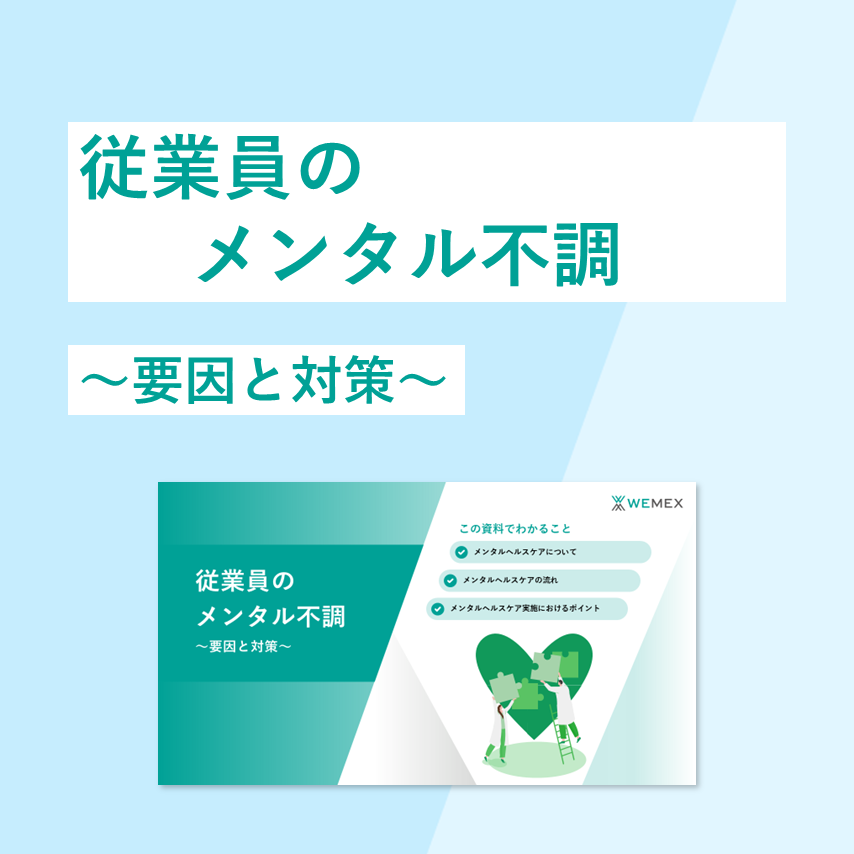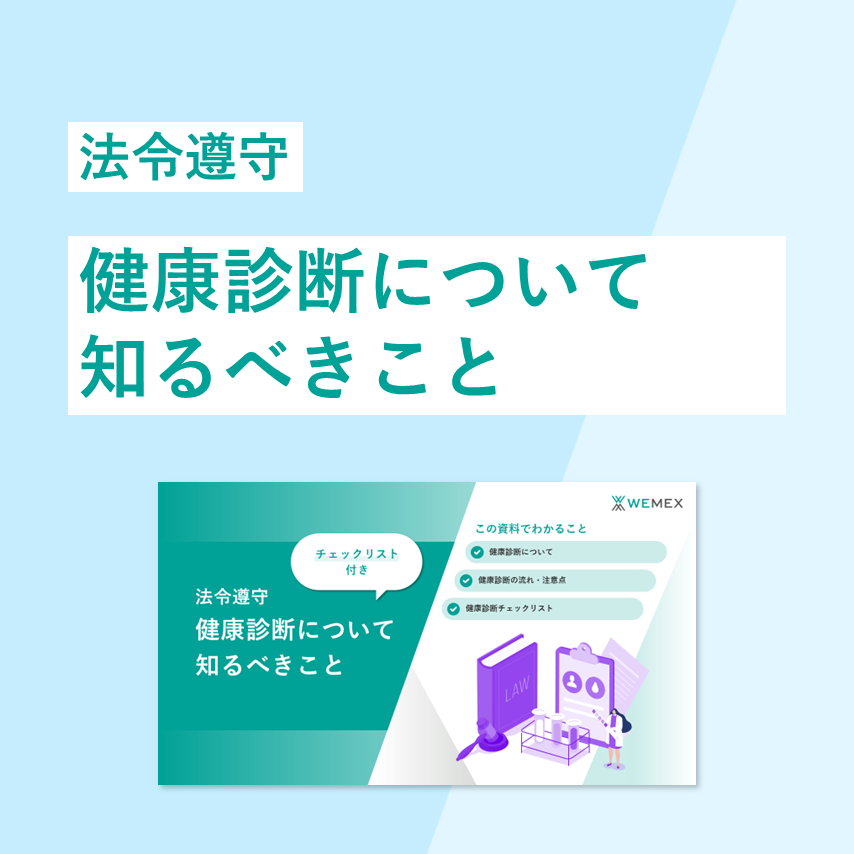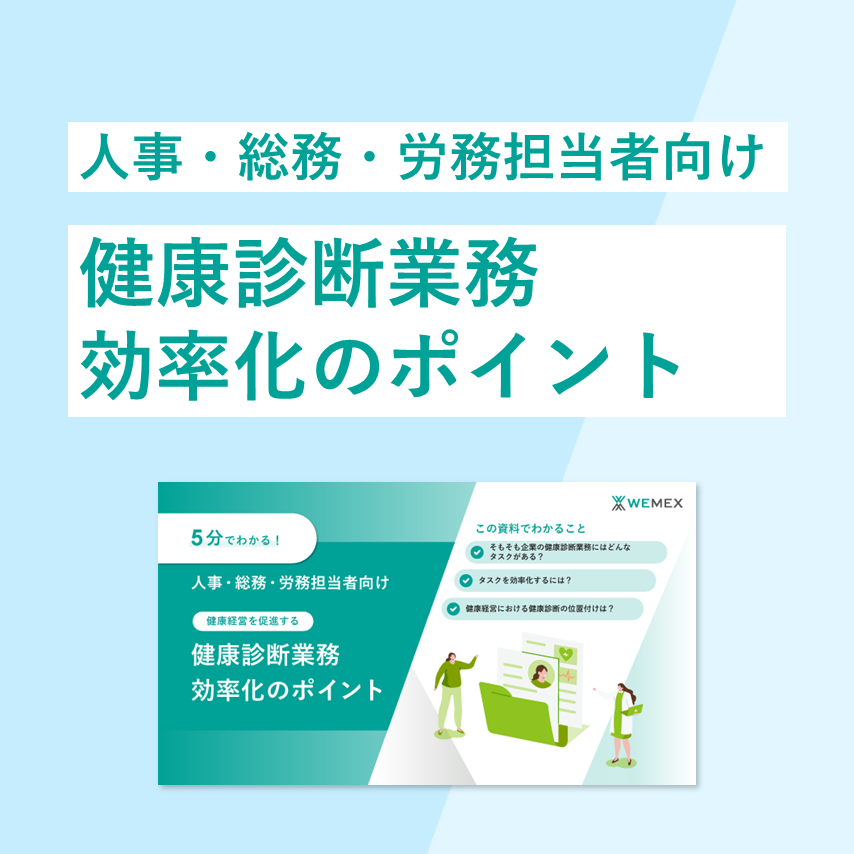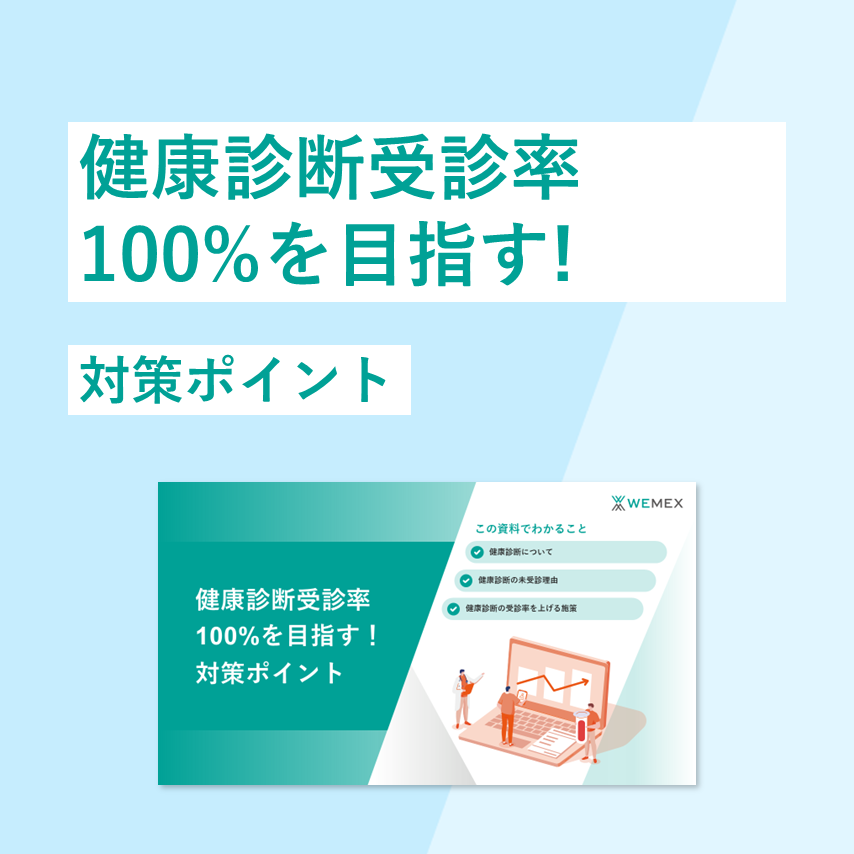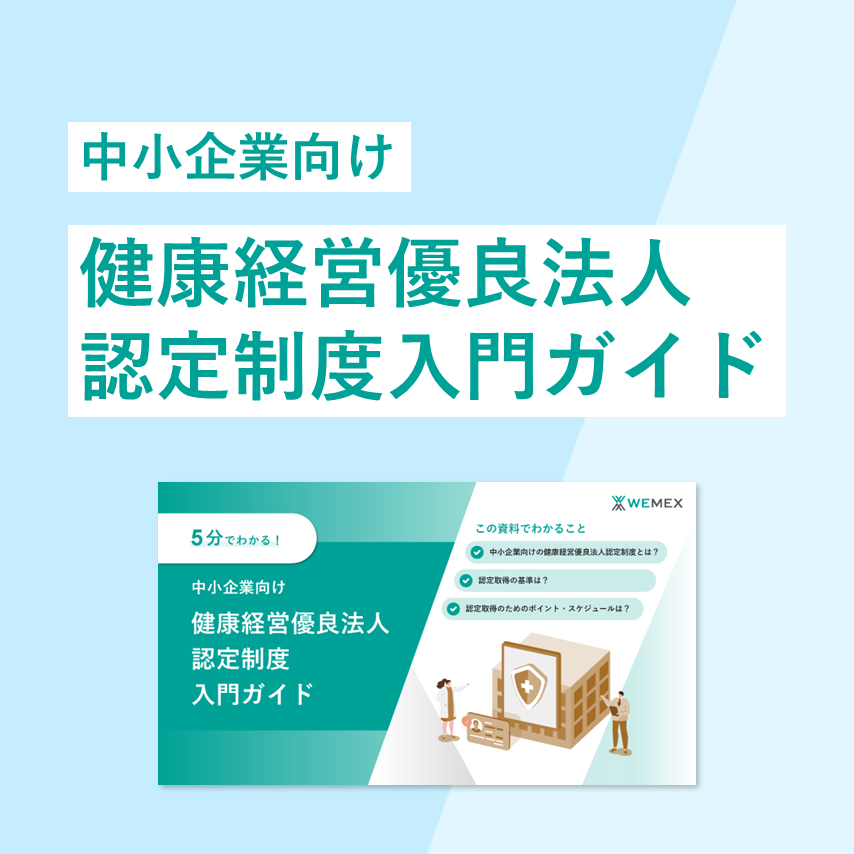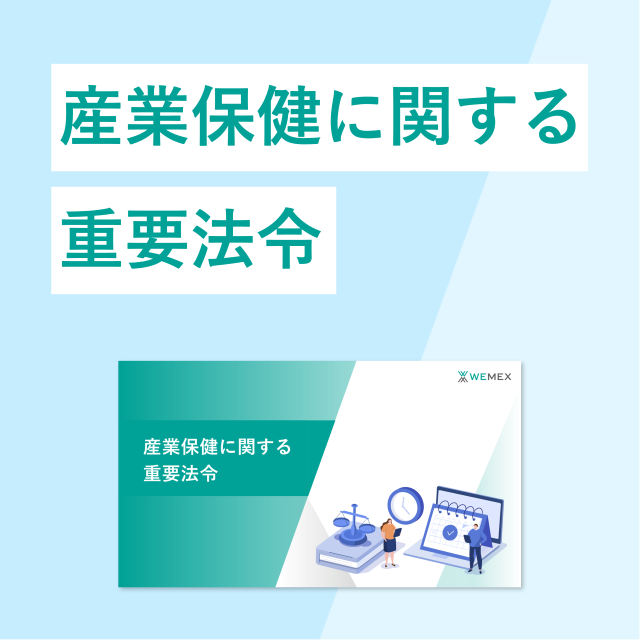目次
ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために設けられた制度です。労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員50人以上の事業場には実施が義務付けられました。制度の主な目的は、メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)、および職場環境の改善です。高ストレスと判定された従業員は、必要に応じて産業医による面接指導を受けることができます。
これまで従業員50人未満の事業場ではストレスチェックの実施は努力義務とされてきました。しかし2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、2028年頃までには50人未満の事業場でも義務化される予定です。今後さらに、従業員の健康保持や生産性の向上に寄与することが期待されています。
ストレスチェックの「実施者」は、労働安全衛生法で定められた医師、保健師、さらに厚生労働省の定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が該当します。
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
ストレスチェックにおける産業医の役割
産業医は、ストレスチェック制度において中心的な役割を担っています。医学的な専門知識を活かして、労働者の心の健康維持や職場環境の改善に取り組みます。
高ストレス者との面接指導
ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員には、産業医による面接指導が実施されます。面接指導は、従業員の心身の状況やストレス要因をより詳細に把握することを目的としています。
従業員から面接指導の希望があった場合、事業者は1か月以内に実施する必要があります。面接指導では、産業医が従業員の状況を丁寧に聴き取り、必要に応じて医療機関の受診を勧めたり、業務内容や勤務時間など就業上の配慮についても助言します。メンタルヘルス不調の予防や早期回復をサポートすることが、ストレスチェックにおける産業医の重要な役割です。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
職場環境の改善のための助言
産業医は、職場環境の改善にも積極的に関与します。ストレスチェック結果を部署やチーム単位で集計・分析し、職場に潜むストレス要因を明らかにします。
【主なストレス要因の例】
・作業環境
・業務量の多さ
・上司や同僚との人間関係
・仕事の将来への不安
産業医は分析結果に基づき、経営層や管理職に対して業務量の見直しや人員配置、ハラスメント防止、コミュニケーション活性化といった職場改善策を助言します。産業医の専門的な意見と具体的な提案は、従業員が安心して働ける職場づくりに欠かせません。
産業医によるストレスチェックのメリット
産業医が関与するストレスチェックは、企業・従業員の双方に多くのメリットがあります。
【主なメリット例】
・業務効率がアップする
・従業員のメンタルヘルスを守れる
・離職率の低下や休職・退職が減る
・企業のイメージアップにつながる
これらのメリットについて順に解説します。
業務効率がアップする
ストレスチェックを通じて産業医の専門的なサポートを受けることで、人事担当者や労務部門の負担が大きく軽減されます。
ストレスチェックの運用には専門的な知識や多くの手間・時間が求められます。たとえば、計画の立案や実施管理、結果の集計・分析、高ストレス者への面接指導対応やフォローアップまで、多岐にわたる業務が発生します。これらすべてを人事担当者だけで担うのは現実的に困難な場合も少なくありません。
産業医が業務全体をリードしサポートを行うことで、人事担当者は本来の業務に注力でき、結果的に組織全体の生産性や業務効率が大きく向上します。
従業員のメンタルヘルスを守れる
産業医が関与する大きな意義は、従業員のメンタルヘルスを医学的専門知見をもって守る点にあります。
産業医は医学的な観点から、ストレスチェックのデータや個々の状況を総合的に判断し、一時的なストレス反応と重度の心身不調とを的確に見極めることが可能です。メンタルヘルス不調の兆候を早期に把握し、重症化を未然に防ぐサポート体制を構築できます。また、従業員が産業医に気軽に健康相談できる体制は、企業に対する信頼感や安心感の醸成にもつながります。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
従業員の休職・退職が減る
産業医によるストレスチェックは、従業員の不調や障害を早期に発見し、適切な支援につなげる役割を果たします。
たとえば、業務量の多さや人間関係の問題など、従業員が抱える課題を明確化した上で、業務調整や配置転換などを行うことができます。こうしたきめ細やかな対応は、「会社が従業員を大切にする」文化や安心感の醸成に寄与し、結果として長期に安定した人材確保、離職防止や休職者減少につながります。
関連記事:適応障害による従業員の休職―企業が取るべき対応・フォローと再発防止策を解説
企業のイメージアップにつながる
産業医と連携しながら従業員のメンタルヘルス対策を重視する企業姿勢は、企業イメージや社会的な信頼向上にダイレクトに結びつきます。
定期的なストレスチェックの実施と産業医による専門的支援体制の確立は、対外的にも「従業員を大切にする企業」として積極的なアピールポイントとなります。従業員のエンゲージメント・定着率向上だけでなく、採用活動やブランド価値の向上、幅広いステークホルダーからの信頼獲得にも効果が期待できます。
ストレスチェック後の面接指導の流れ
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員が面接指導を希望した場合、産業医による面接指導が行われます。
面接指導では、産業医が従業員に対して「勤務の状況」「心理的な負担」「その他の心身の状況」などを丁寧に確認します。ヒアリング内容をもとに、産業医は事業者へ提出する「面接指導結果報告書」や「医師の意見書」などを作成します。
産業医の面接指導における注意点

産業医による面接指導を実施する際には、以下の点に注意が必要です。
- 面接指導を強要できない
- 申し出から速やかに面接指導を行う
- 面接指導の記録は5年間保存する
- オンラインの実施には条件がある
それぞれ詳しく解説します。
面接指導を強要できない
産業医による面接指導は従業員の健康を守るために重要ですが、従業員本人からの申し出があった場合に限り実施されます。企業や産業医が、従業員に面接指導を強要することはできません。
また、面接指導を受けないことを理由に、従業員に不利益な取り扱い(降格・解雇など)をすることは労働安全衛生法で禁じられています。従業員のプライバシー保護も重視し、安心して申し出できる環境づくりが企業には求められます。
申し出から速やかに面接指導を行う
従業員が高ストレスと判定された後、面接指導を申し出た場合、事業者は「遅滞なく、概ね1か月以内」に実施しなければなりません。対応が遅れると従業員の健康悪化リスクが上がります。
面接指導後は、産業医の意見を踏まえ、必要に応じて就業上の措置(勤務時間短縮、配置転換など)を講じることも重要です。
面接指導の記録は5年間保存する
面接指導を実施した際は、日時、産業医名、指導内容、就業上の措置に関する意見などの記録を作成し、5年間保存することが労働安全衛生規則で義務付けられています。
これらの記録は、万が一の労災対応や訴訟時に適切な健康管理を証明する根拠にもなります。保存時は個人情報保護に万全を期し、厳重な管理が必要です。
オンラインの実施には条件がある
近年、オンラインによる面接指導の実施が増えています。オンライン面接指導を実施する場合は、事前に衛生委員会等でその方法や運用について十分に審議し、従業員に内容をわかりやすく周知しておく必要があります。
また、従業員のプライバシーを確保し、安定した通信環境を用意した上で、なりすましの防止などの具体的な要件を満たすことが求められます。これらの条件をクリアすることで、利便性の高いオンライン面接指導も安全かつ効果的に活用できます。
詳細については「厚生労働省|ストレスチェック制度等における面接指導等のオンライン実施に関する留意事項」を参照ください。
まとめ
産業医と連携したストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につながる重要な取り組みです。産業医が専門的な立場から高ストレス者に面接指導を行い、ストレス要因の特定や具体的な職場対応を提案することで、従業員が安心して働ける環境づくりが可能となります。
また、産業医と連携することで人事・労務担当者の業務負担の軽減や、従業員の健康維持にもつながります。ストレスチェック制度の運用や面接指導の流れについては、産業医と協力しながら進めることが、企業の持続的な成長に不可欠です。
ウィーメックスでは、産業医と連携したオンライン面接や意見書作成など、企業向けストレスチェックサービスを提供しています。ぜひご検討ください。
出典:e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240201_505M60000100033)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf)