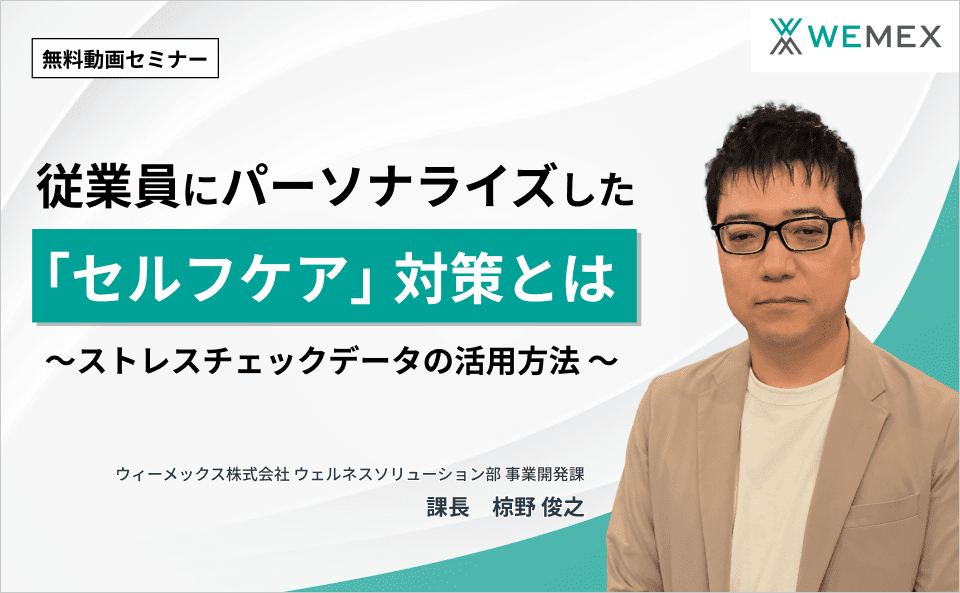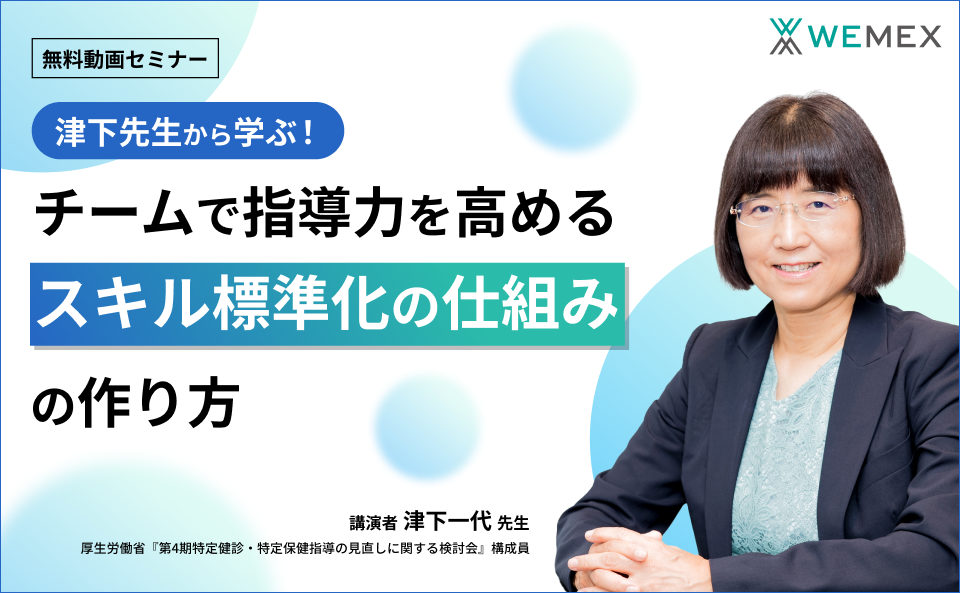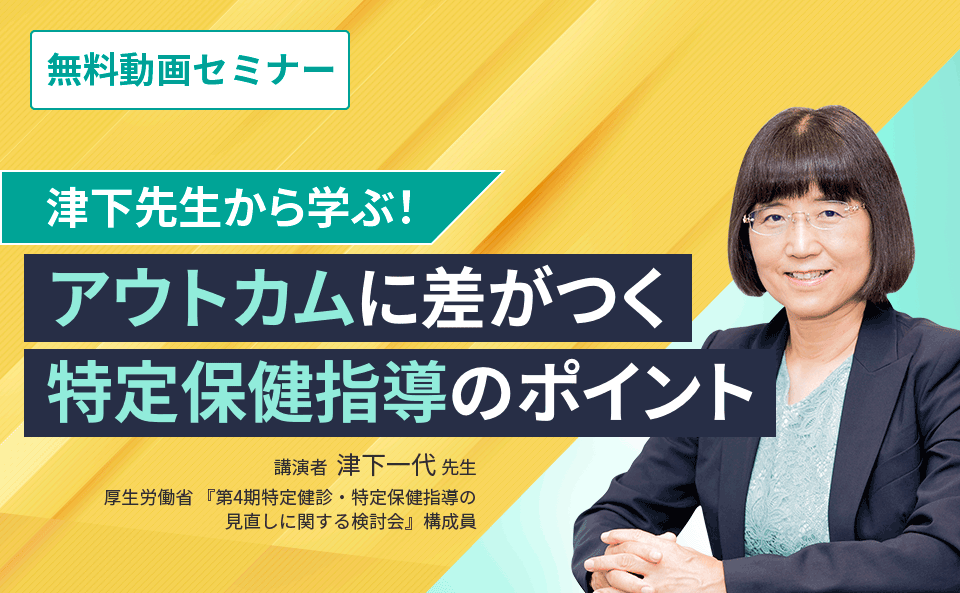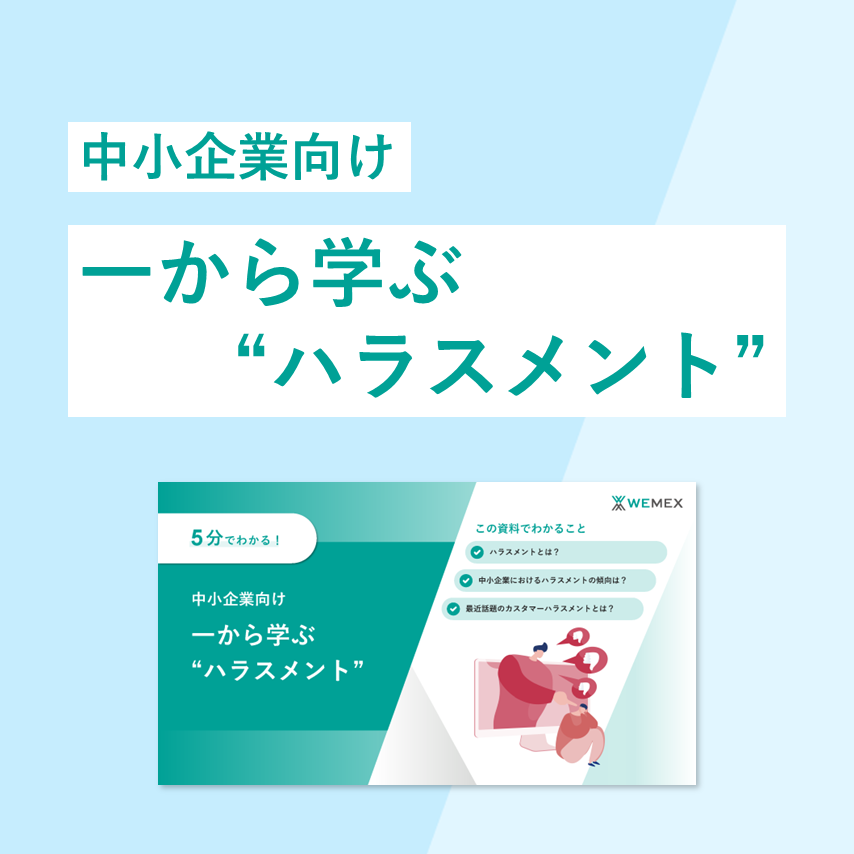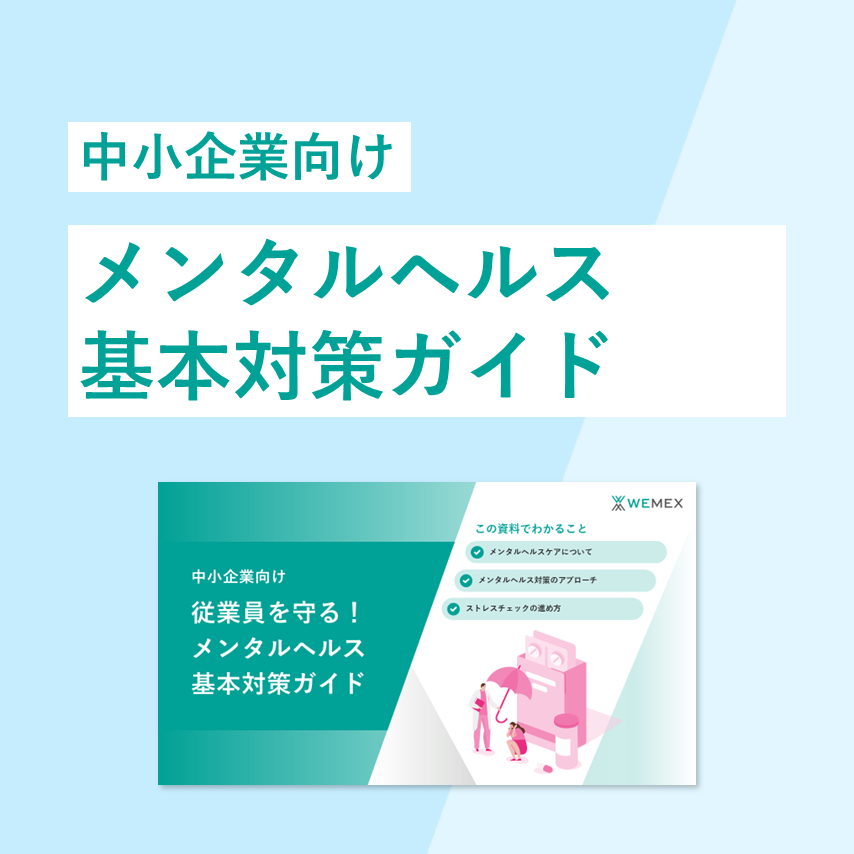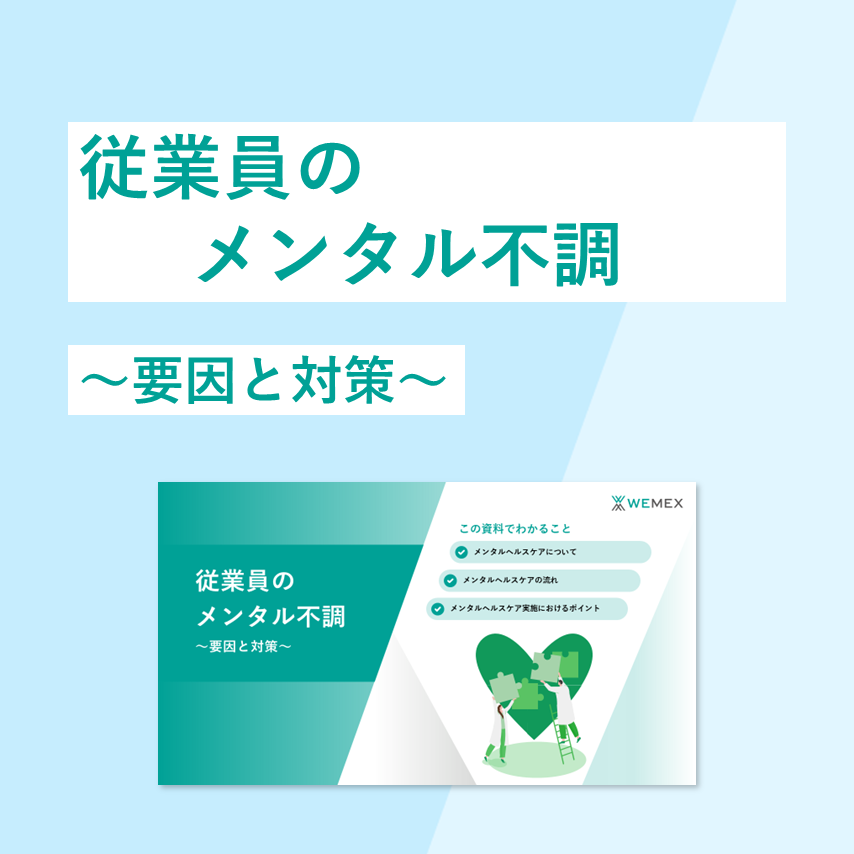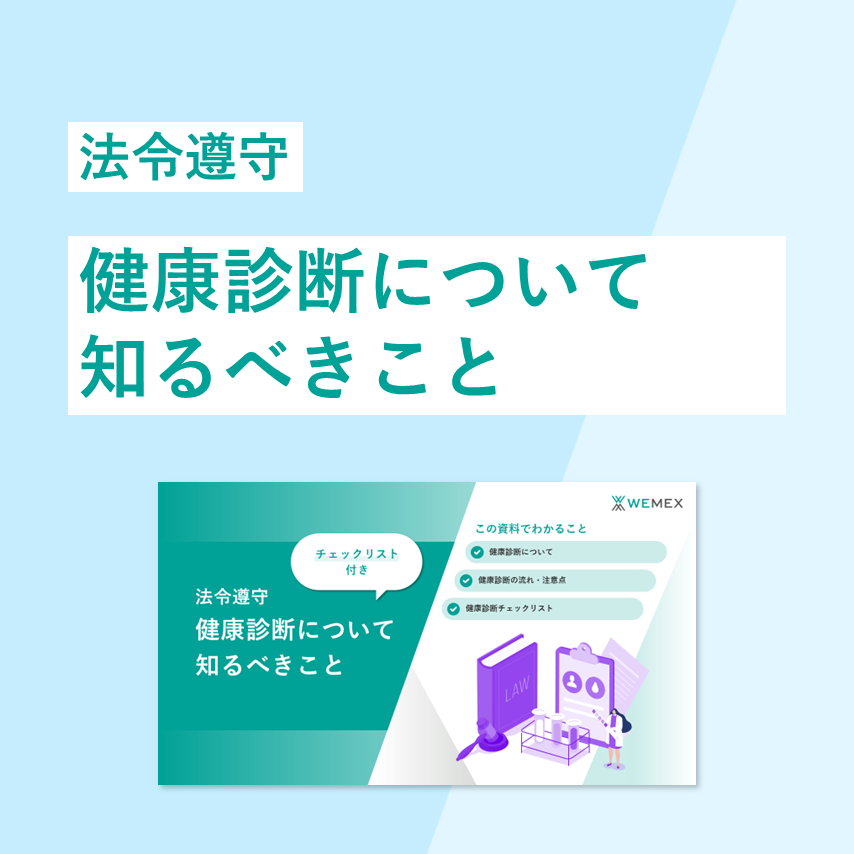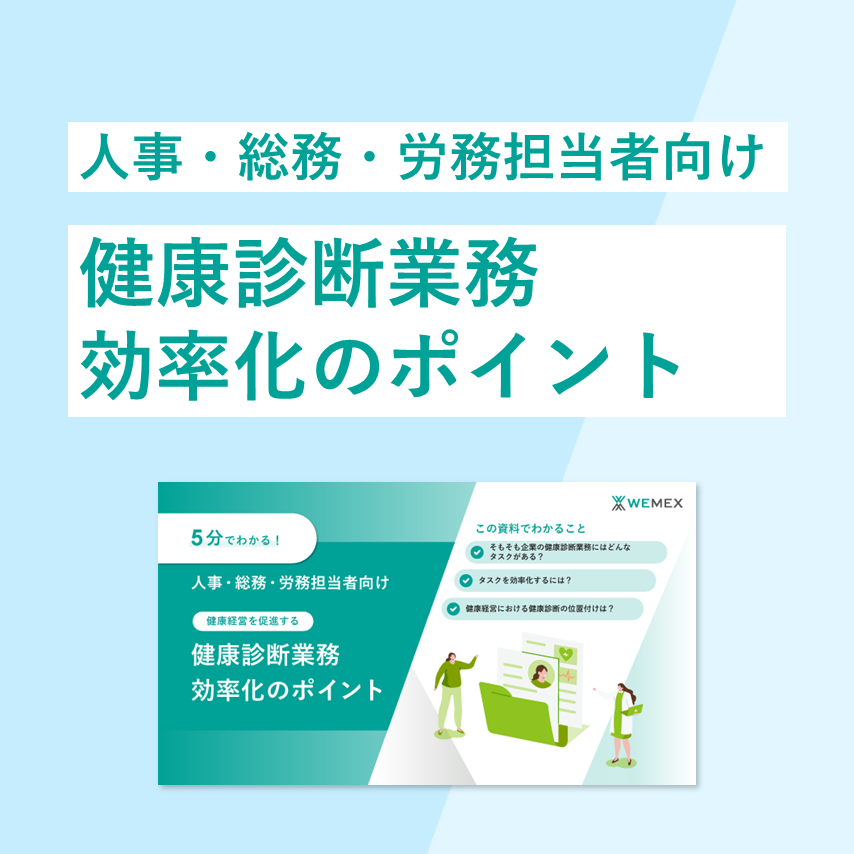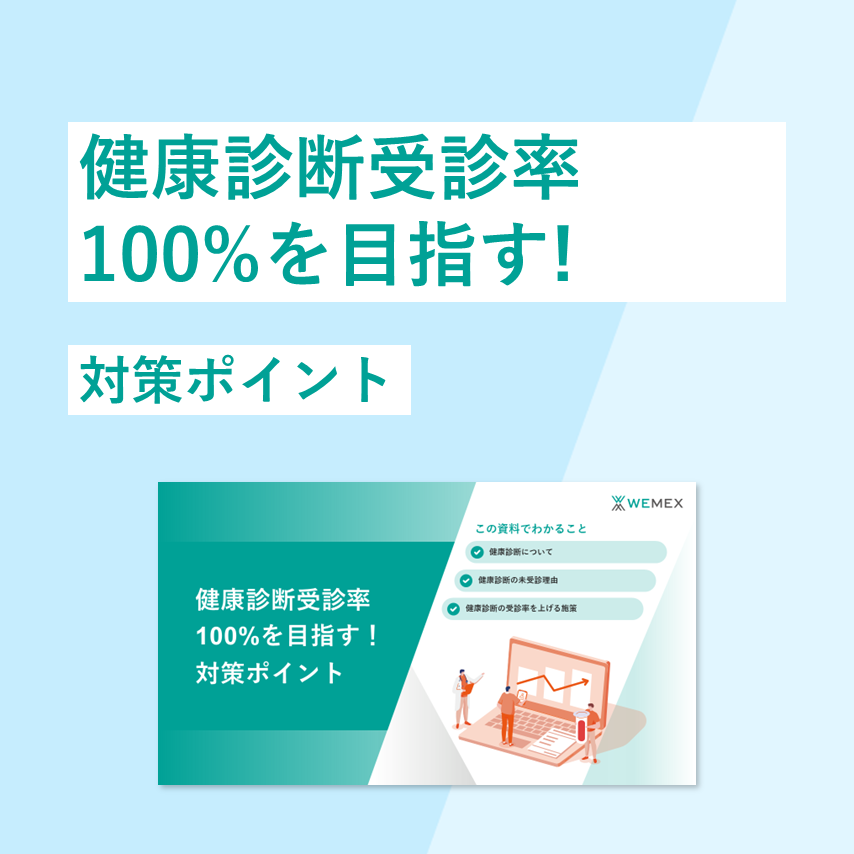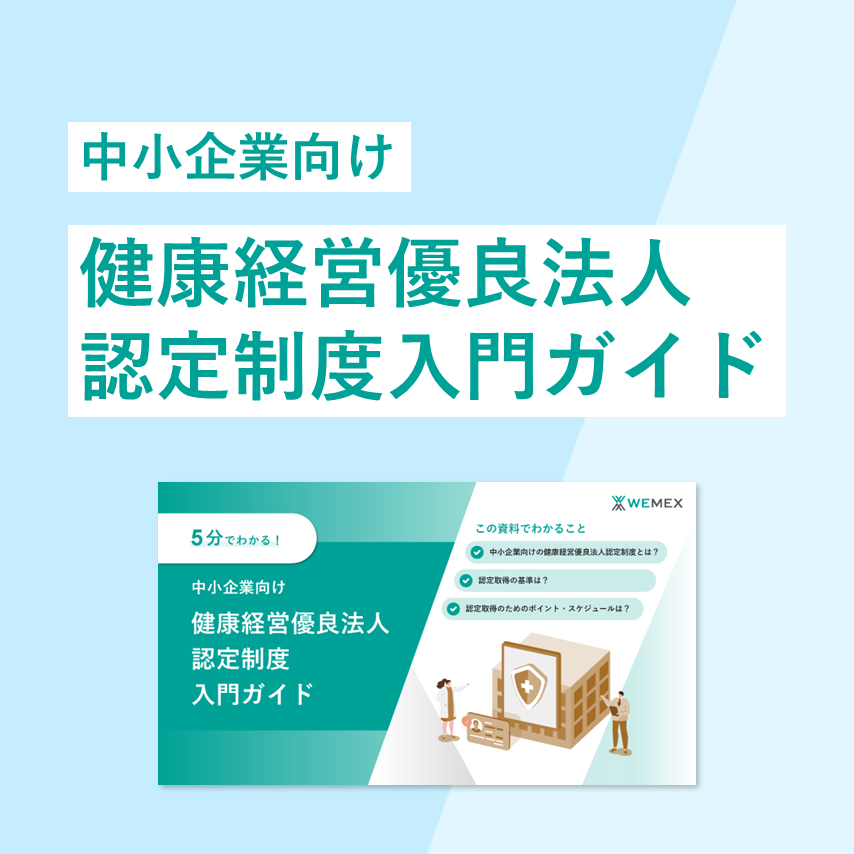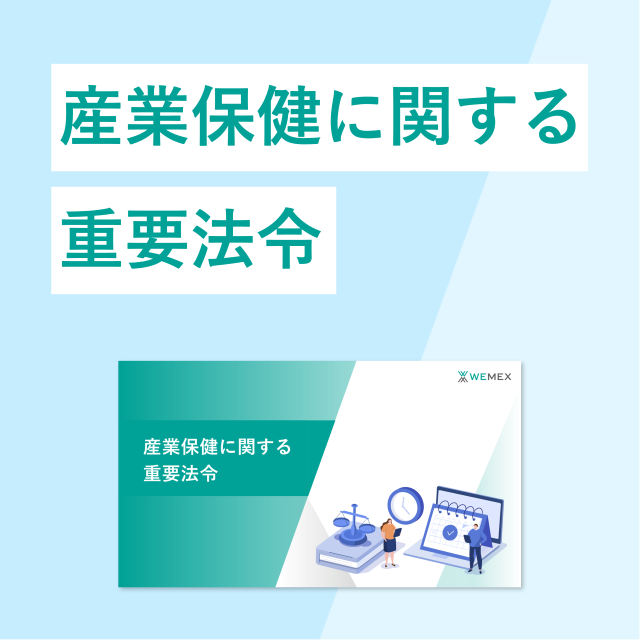目次
健康管理とは
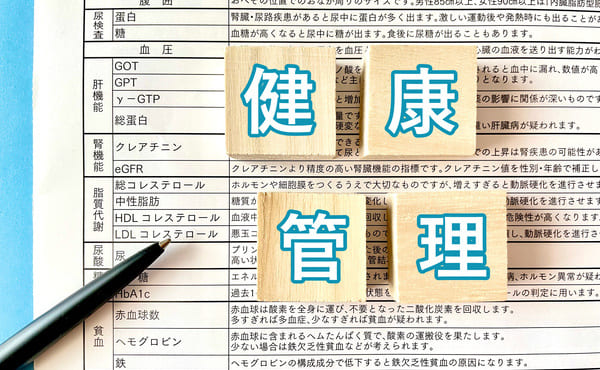
健康管理とは、労働衛生における「3管理」の一つです。労働衛生の3管理には、健康管理・作業環境管理・作業管理があり、これらは業務中の事故を防ぎ、従業員の健康や安全を確保するために行われます。
このうち健康管理は、従業員自身が健康状態を確認することではなく、企業が主体となって健康診断やその後の事後措置、保健指導などを実施し、従業員の健康を維持・増進するための幅広い取り組みを指します。
健康管理の目的は、従業員の健康増進と健康障害の未然防止にあります。健康診断などで従業員の健康状態を把握し、必要に応じて作業環境の改善を検討することで、健康障害の発生を防ぎます。
なお、近年は身体的な健康だけでなく、メンタルヘルスケアの重要性も高まっています。
作業環境管理
作業環境管理とは、有機溶剤や粉塵などの有害物質や危険要因を把握し、必要な対策を講じて職場環境を良好な状態に保つための取り組みです。特に2025年6月からは熱中症対策の強化が求められており、厚生労働省は遮へい物の設置や冷房・休憩場所の確保、水分補給の徹底などを推奨しています。今後、これらの対策はますます重要となっていきます。
デスクワーク中心の職場では、以下のような作業環境管理が考えられます。
- 換気状況の確認
- パソコン作業に適した照明の明るさの維持
- 職場の整理整頓による転倒事故の防止
作業管理
作業管理とは、「作業そのもの」を改善する取り組みです。作業の時間や量、方法を見直し、従業員の負担を軽減します。
例えば、以下のような取り組みが作業管理に該当します。
- 保護手袋の着用を義務付ける
- 立ち作業と座り作業を交互に実施し、腰痛を防止する
- 作業マニュアルを整備し、安全な作業手順を明確にする
企業が健康管理に取り組む必要性
企業が従業員の健康管理に取り組むべき主な理由は、以下の3点です。
法令遵守
健康診断やストレスチェックの実施は、労働安全衛生法により企業に義務付けられています。また、労働契約法第5条では、企業が従業員の生命や健康を労働災害などの危険から守る「安全配慮義務」が定められています。従業員の健康管理は、こうした法的義務を果たすうえで欠かせません。
労働災害の防止
従業員の健康に問題があると、労働災害が起こりやすくなります。例えば、睡眠不足で集中力が低下している場合、機械の操作ミスや不注意による事故が発生する可能性があります。
また、長時間労働が原因で従業員がうつ病などを発症した場合、その事例が労働災害と認定される可能性もあります。労働災害の防止は、企業経営の安定化にも直結する重要なテーマです。
健康経営の推進
近年重視されている「健康経営®」とは、従業員の健康への投資が企業の業績や株価の向上につながるという考え方です。従業員の健康に時間やお金を投資することで、業務のパフォーマンスが向上し、組織が活性化されると考えられています。健康経営を推進するためにも、健康管理は必要です。
関連記事:健康経営とは?メリットや取り組み方を解説
従業員の健康管理を行うメリット
従業員の健康管理で得られる主なメリットは以下の4点です。順に詳しく解説します。
- 従業員の健康維持・増進
- 労働生産性の向上
- 企業イメージ・ブランディング強化
- 人材確保や離職防止
従業員の健康維持・増進
従業員の健康維持・増進は、健康管理の最も直接的なメリットです。
充実した生活を送るためには、健康が欠かせません。心身ともに健康な状態で働ける従業員が増えれば、職場全体の雰囲気も明るくなり、従業員満足度の向上にもつながるでしょう。
企業が健康管理に力を入れれば、従業員一人ひとりの健康への意識が高まることも期待できます。
労働生産性の向上
従業員の健康状態は、企業の労働生産性にも大きく影響します。例えば、企業の健康管理が不十分で従業員の健康が維持できない場合、体調不良による急な欠勤や休職で業務が停滞する恐れがあります。
休んだ従業員の業務を他の人が補わなければならず、労働時間や負担の増加によって健康状態が悪化する従業員が増える可能性もあります。
また、出勤できたとしても体調が悪い状態では高いパフォーマンスは望めません。反対に、健康管理によって従業員の健康を維持できれば、業務のスピードや質の改善につながり、生産性の向上が見込めます。
企業イメージ・ブランディング強化
健康経営やウェルビーイングへの関心が高まる現代では、健康経営への取り組みはステークホルダーや社会への強力なアピールになります。客観的な評価を得るためには、以下のような認定制度の取得を目指すのも有効です。
| 認定制度 | 概要 |
|---|---|
| 健康経営優良法人 | 優れた健康経営を実践する法人を認定 |
| 健康経営銘柄 | 健康経営優良法人に認定された東京証券取引所上場企業のうち、特に優れた健康経営を実践している法人を原則33業種から1社ずつ選定 |
| ホワイト500 | 大企業の健康経営優良法人のうち、上位500法人を認定 |
| ブライト500 | 中小企業の健康経営優良法人のうち、上位500法人を認定 |
人材確保や離職防止
健康管理は、企業の採用活動や人材の定着に良い影響を与えます。就活生や転職希望者は、企業が健康経営に取り組んでいるかどうかを就職先選びの重要なポイントとしています。
健康管理を積極的に推進することで、外部から優秀な人材を採用しやすくなり、人材確保の強化につながります。
さらに、健康管理の推進によって、病気やけがによる休職や離職のリスクが減り、従業員満足度も高まります。これにより退職者が減少し、長く働く従業員が増える効果も期待できます。
従業員の健康管理における課題

健康管理の課題は、社会のトレンドや働き方の変化によって変化します。ここでは、近年の状況や特に課題とされている内容を確認しましょう。
健康診断の実施・受診
健康診断は従業員の健康状態を把握するために不可欠です。十分な健康管理を実現するには、受診率を高めることが求められます。
定期健康診断は労働安全衛生法により企業に実施が義務付けられていますが、実施率が100%に達していないことが課題です。厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、定期健康診断の実施率は90.1%にとどまっています。
さらに、「平成24年労働者健康状況調査報告」では、労働者の健康管理対策の重要課題として「定期健康診断の完全実施」が54.7%で最も多く、次いで「定期健康診断の事後措置」が40.0%となっています。また、「がん検診の実施・充実」は15.7%、「人間ドックの実施・充実」は18.6%と、これらも重要な課題とされています。
従業員の健康状態を正確に把握するためにも、健康診断の受診率向上が不可欠です。
関連記事:健康診断は会社の義務!目的や内容・罰則について解説
職場環境の整備
職場環境の整備とは、労働災害が発生しにくい作業環境を整備することです。以下のような取り組みが該当します。
- 整理整頓や滑り止め設置による転倒防止
- 機械設備の定期的なメンテナンスや防止カバーの設置によるはさまれ・巻き込まれの防止
- 危険な化学物質に対するラベル表記
大きな事故による労働災害が発生した場合、命の危険につながる可能性もあります。従業員の安全を確保するためにも職場環境の整備は重要な課題です。
メンタルヘルスケア
メンタルヘルスケアの重要性は近年高まっています。「令和5年労働安全衛生調査」によると、メンタルヘルス不調が原因で1か月以上休業した従業員がいた事業所の割合は10.4%、退職した従業員がいた事業所の割合は6.4%です。
個人調査では、働く人の82.7%が仕事に強い不安や悩み、ストレスを感じている結果となり、原因の上位には「仕事の失敗や責任の発生」「仕事の量」「対人関係」などが挙げられます。
メンタルヘルス不調は人によって原因が異なります。適切に対応するには、従業員一人ひとりに合わせた業務の量や内容の把握、相談しやすい環境づくりなど、周囲のサポートが欠かせません。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
健康管理に取り組む方法とポイント
従業員の健康管理は、企業が主体となって計画的に進める必要があります。健康管理を推進するための取り組みとポイントを6つご紹介します。
健康診断の実施と受診促進
労働安全衛生法で定められている定期健康診断の実施は企業の義務です。特別休暇を設けたり、「健康診断は受診するのが当たり前」という企業風土を醸成したりするなど、従業員が健康診断を受診しやすい制度や環境を整備しましょう。
福利厚生として人間ドックやがん検診の費用を補助する制度があれば、受診勧奨もしやすくなります。生活習慣病やメンタルヘルス不調の従業員には、産業医などの専門家のサポートも有効でしょう。
健康診断の準備に向けた人事労務担当者様の事務負担を軽減できるよう、ウィーメックスでは健診代行サービスを提供しております。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
勤怠管理と長時間労働の是正
長時間労働が続くと過労やメンタル不調など、健康不調につながりやすくなります。長時間労働を是正するには、労働時間の管理や柔軟な勤務制度が有効と考えられます。以下の取り組みを検討しましょう。
- 勤怠管理システムの導入
- フレックスタイム制の導入
- 計画的な有給休暇の取得促進
労働時間を正確に把握し、休暇の取得により従業員が心身を休める時間を確保できれば、健康リスクを減らす効果が期待できます。
快適な労働環境の整備
快適な労働環境は従業員の業務効率を高めるだけでなく、労働災害の防止や従業員の健康維持にも重要です。過ごしやすい室温や湿度、作業に適した明るさの照明を維持し、十分な作業スペースを確保するなど、働きやすい作業環境を整えましょう。
従業員アンケートなどで、現場の意見を集めるのも有効です。従業員の意見を踏まえて休憩スペースを充実させると、業務時間中のリフレッシュにも役立つでしょう。
ストレスチェックの実施と活用
ストレスチェックを実施すれば、従業員のメンタルヘルス不調を早期に見つけやすくなります。労働安全衛生法では、常時50人以上の従業員を使用する事業場にストレスチェックを義務付けていますが、従業員50人未満の事業場においても、ストレスチェック制度の義務を拡大する方針が示されています。
ストレスチェックは実施して終わりではありません。メンタル不調者を洗い出すだけでなく、メンタルヘルスに問題がない従業員の健康維持にも、ストレスチェックの結果を踏まえて職場環境の改善に活かしましょう。
ウィーメックスでは従業員の人数にかかわらず、企業のストレスチェック実施をサポートするサービスを提供しております。
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
相談窓口と産業医の設置
産業医やカウンセラーを設置し、健康やメンタルの悩みを気軽に相談できる体制を整備しましょう。
従業員が相談窓口を利用しやすくするには、相談での個人情報保護や秘密保持の徹底が重要です。相談した内容は外部に漏れず、相談したことで不利益な扱いは受けないことを社内周知しましょう。
産業医の設置義務がない企業の場合、地域の産業保健総合支援センターが活用できます。産業保健総合支援センターでは、産業医や保健師などの専門家に相談が可能です。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
健康に関する福利厚生の導入
福利厚生として、従業員の健康維持に役立つ取り組みを導入するのも有効です。以下のような制度が考えられます。
- 社員食堂の設置
- スポーツジムの利用補助
- リフレッシュ休暇制度の新設
健康維持に関連する福利厚生は、従業員のワークライフバランス向上や健康増進の効果が見込みやすくなるでしょう。
まとめ
健康管理とは、従業員の健康を維持・向上させるための取り組み全体を指します。健康管理を実施することで、従業員のワークライフバランスの確保だけでなく、労働生産性の向上や企業イメージのアップなど、さまざまなメリットがあります。
健康管理の課題は多岐にわたるため、効率的に進めるにはポイントを押さえた取り組みが大切です。まずは現在抱えている健康課題を明確にし、できることから始めてみることをおすすめします。
健康診断後のフォローアップや、従業員一人ひとりの健康状態に合わせたサポートが難しい場合は、各種ソリューションやシステムの活用が有効です。
ウィーメックスが提供する総合健康管理ソリューションでは、健康診断の業務効率化と受診率向上をサポートする健診代行をはじめ、診断後のフォローをスムーズに行う健診レポートや特定保健指導、保健指導の事務処理効率化を実現する保健指導システムなど、従業員の健康管理を支援する多様なサービスを提供しています。この機会にぜひご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo01.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo02.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_01.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo01.pdf)
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。