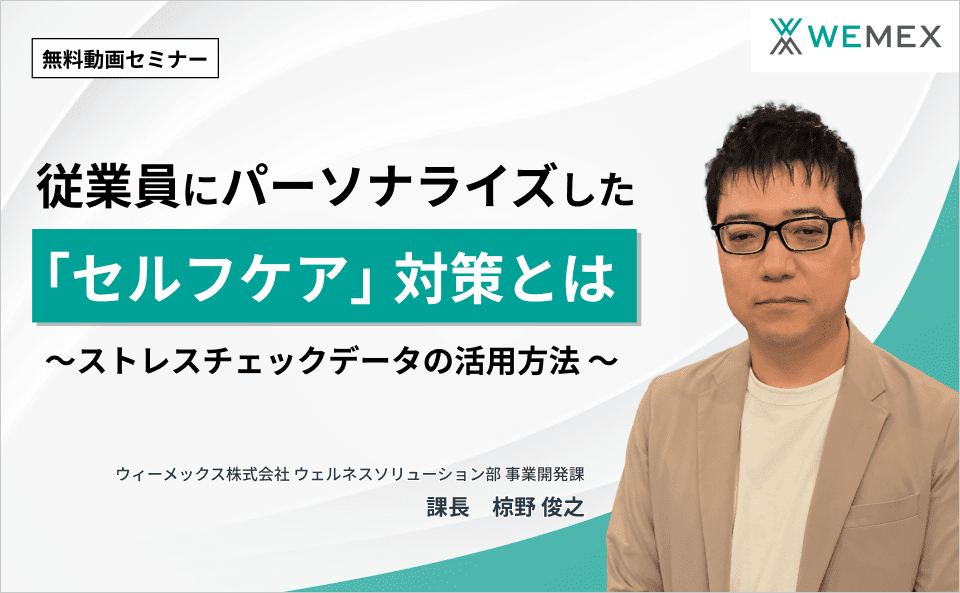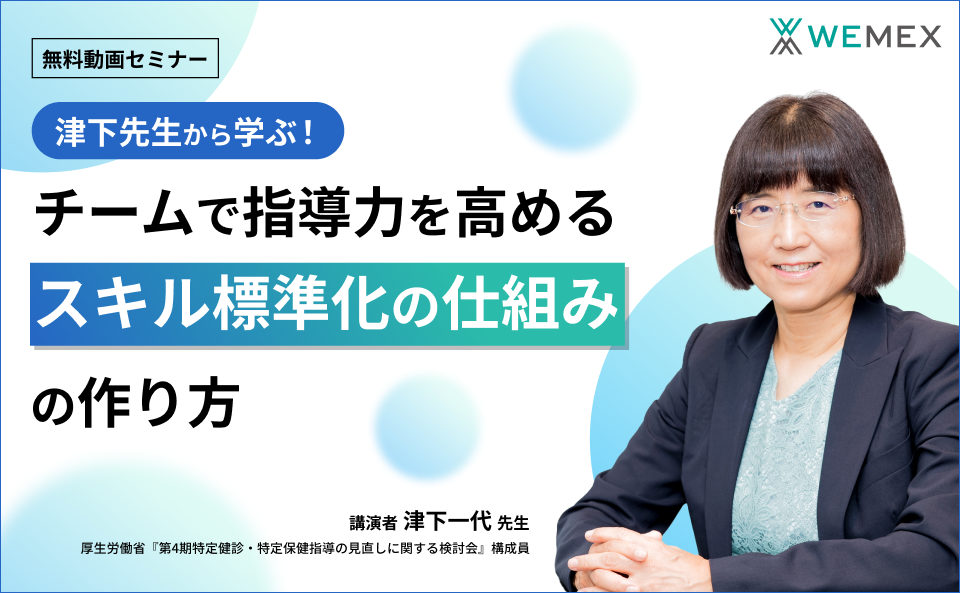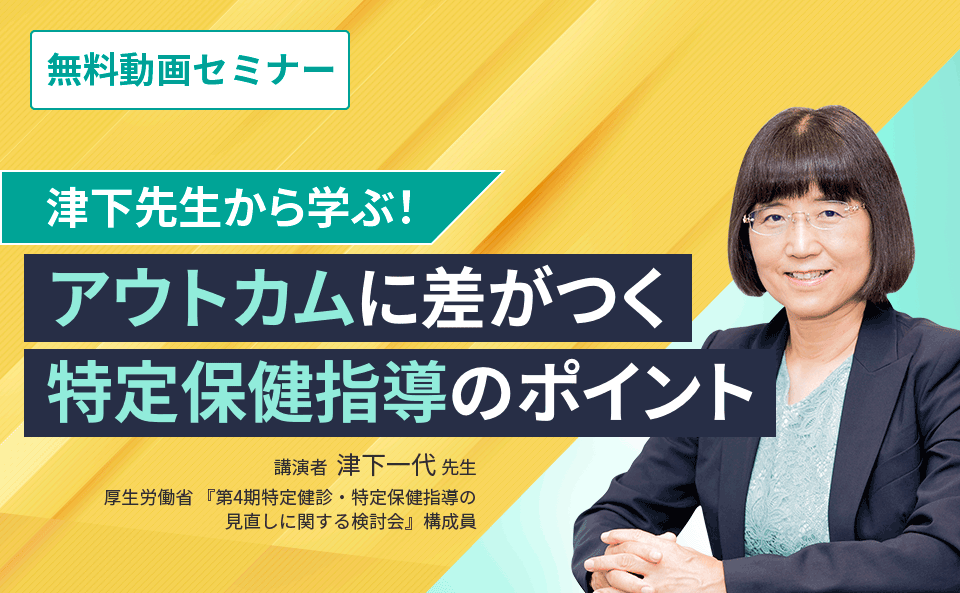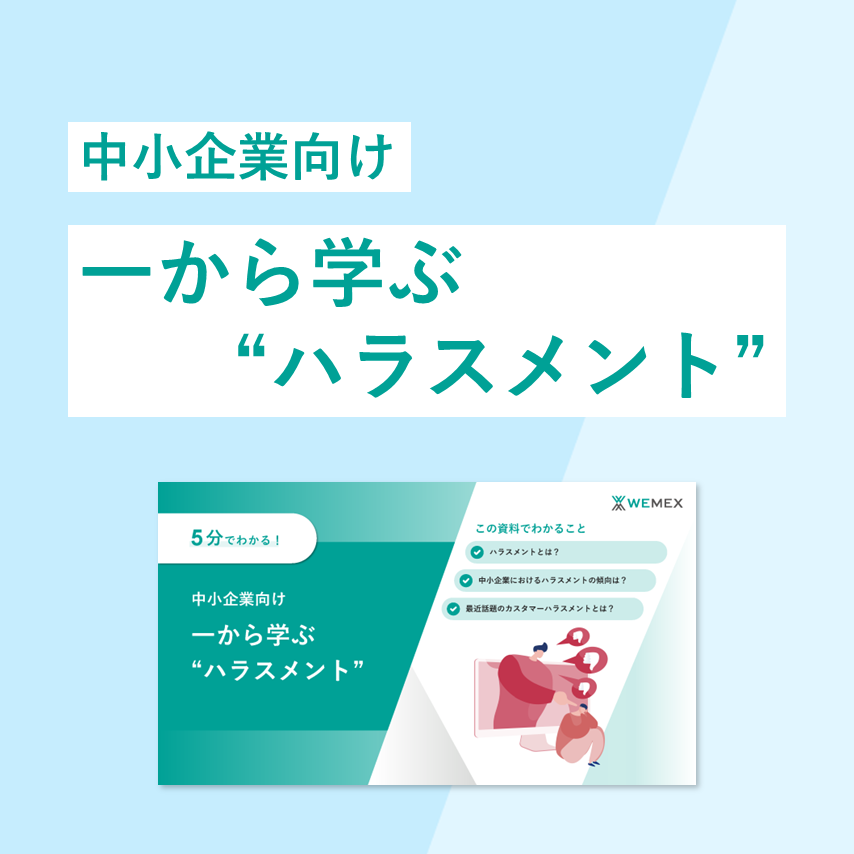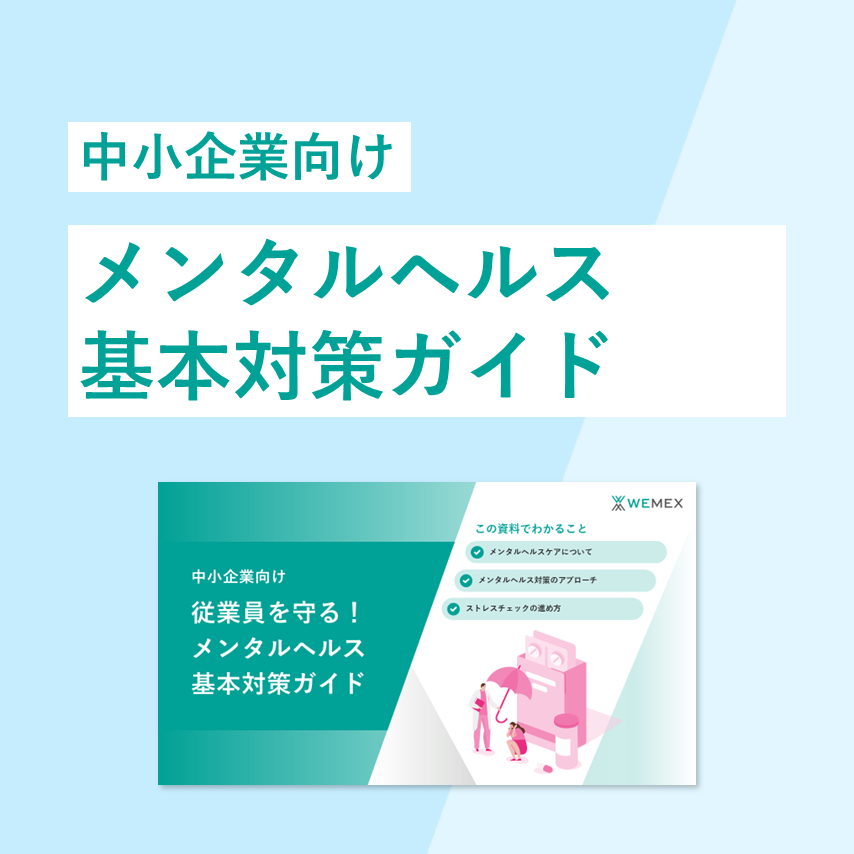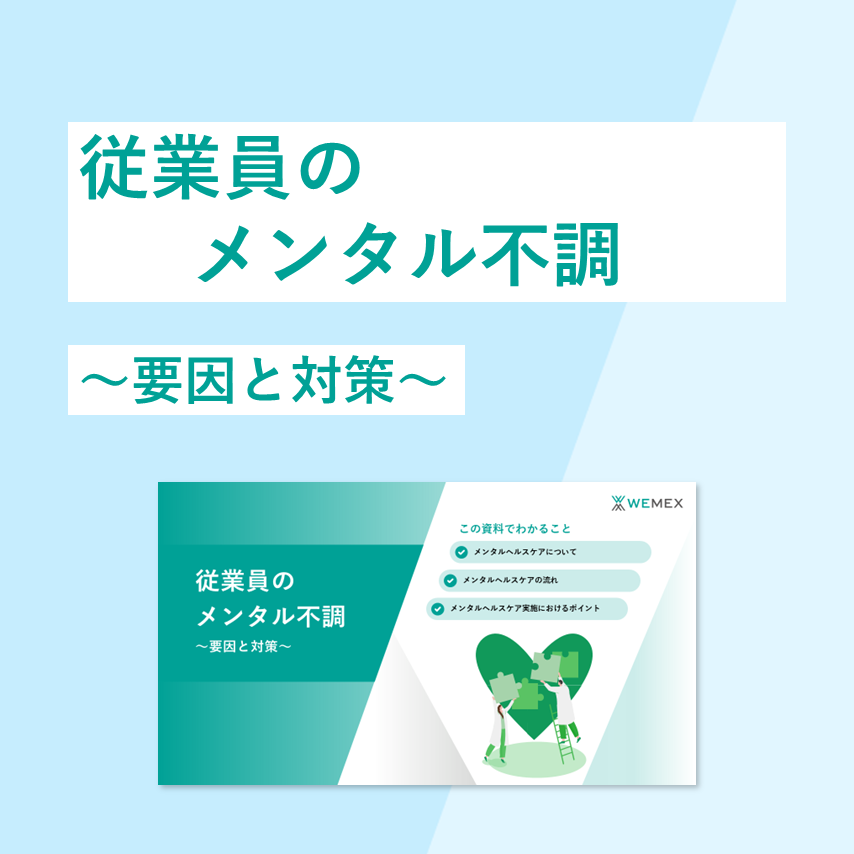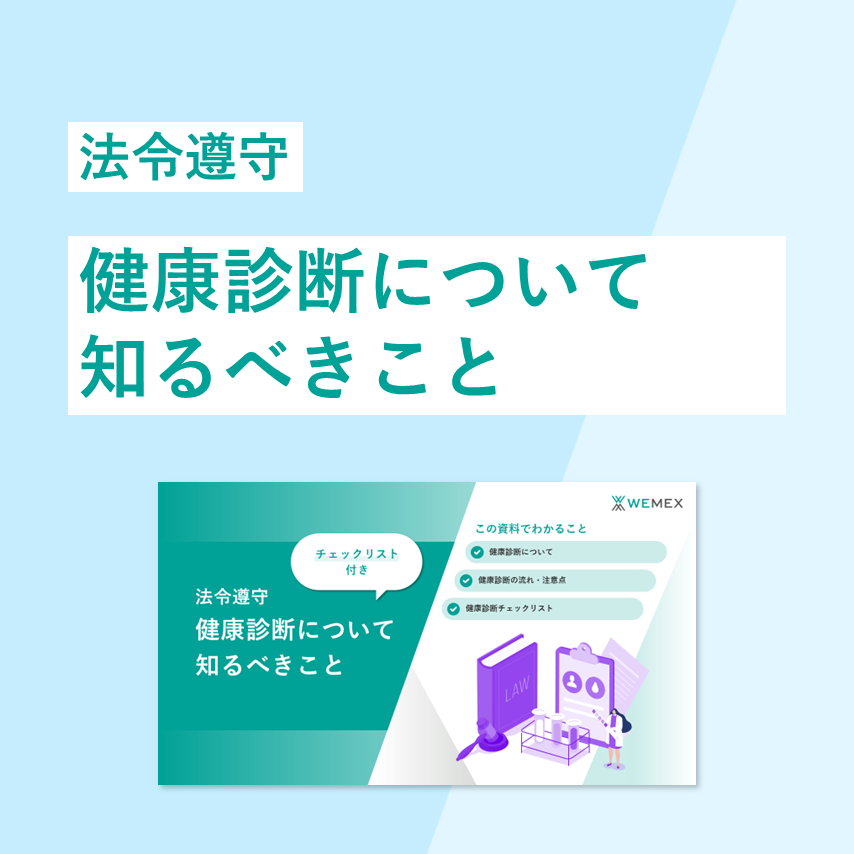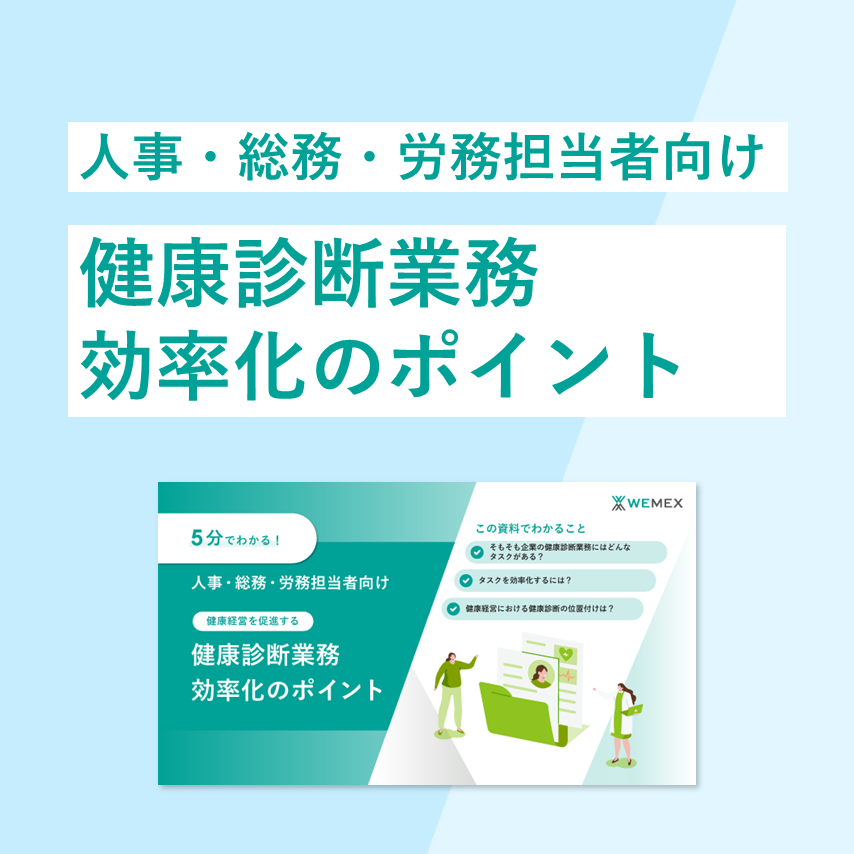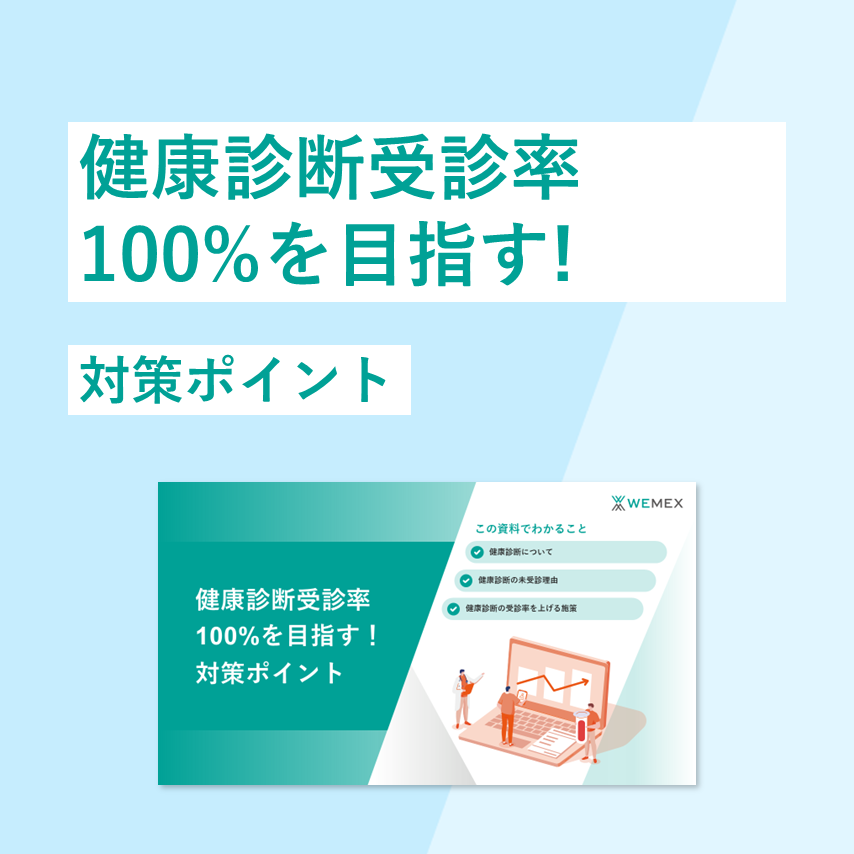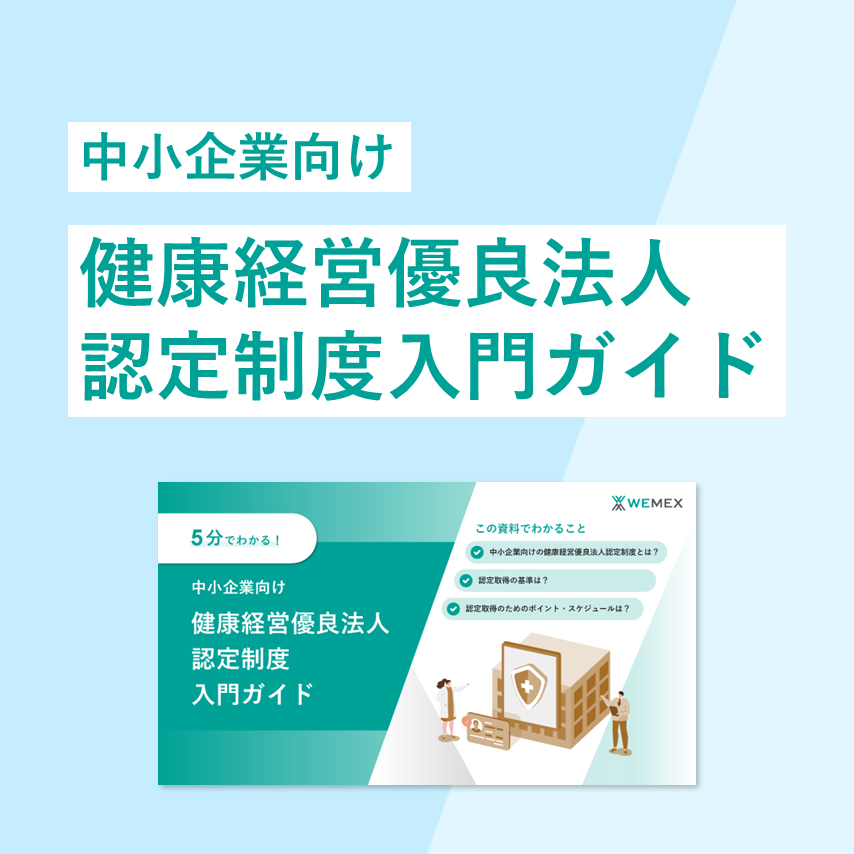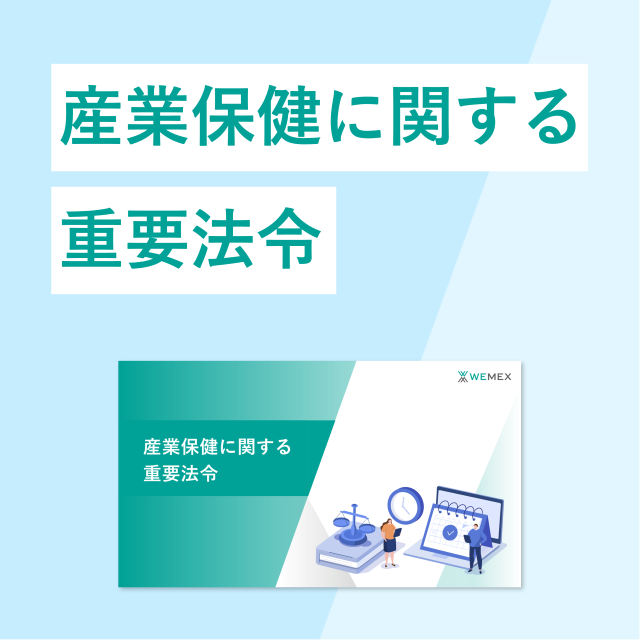目次
ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、従業員がストレスに関する選択式の質問票に回答し、その結果をもとに自身のストレス状態を把握するための簡易的な検査です。
この制度の目的は、従業員が自分のストレス状況を認識し、適切に対処できるよう支援することです。たとえば、高ストレスと判定された場合には、医師による面接指導を受けて助言を得たり、企業に業務負担の軽減や調整を依頼したりすることが可能です。
さらに、集団分析を通じて職場環境の改善に役立てることで、職場全体のストレス軽減を図り、「うつ」などメンタルヘルス不調の予防にもつなげられます。
ストレスチェックは義務の会社
ストレスチェックは、常時50人以上の従業員を雇用している事業場に義務付けられています。この「従業員」には、正社員だけでなく、パートタイム従業員や派遣先で働く派遣社員も含まれます。
一方、従業員数が常時50人未満の事業場については、現在のところ法的な義務はなく努力義務とされています。なお、最新の動向として、政府は2025年3月14日に労働安全衛生法改正案を閣議決定し、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付ける方針を示しました。改正法が成立した場合、公布から3年以内(2028年頃まで)に施行される見込みです。今後、50人未満の事業場もストレスチェックが義務化される予定であり、準備が求められます。
ストレスチェックが義務化された背景
ストレスチェック制度が義務化された背景には、社会全体で深刻化するメンタルヘルス問題があります。多くの人が日々の業務や職場の人間関係、将来への不安などから強いストレスを感じています。このような状況は、従業員の健康だけでなく、企業の生産性や組織運営にも悪影響を及ぼします。
政府は2006年に「従業員の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」を公表し、企業におけるメンタルヘルスケアを推進してきました。しかし、職場での強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災として認定されるケースは増加傾向にあります。
こうした背景から、ストレスの早期発見と予防の必要性が高まりました。そして2014年、労働安全衛生法が改正され、その中で創設されたのが現在のストレスチェック制度です。この制度は、従業員自身がストレスに気づき、職場環境改善にも活用できる仕組みとして導入されました。
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者は、正社員だけでなく、所定労働時間が正社員の4分の3以上で、かつ1年以上の雇用継続が見込まれるパートタイム従業員も含まれます。この基準は、一般的な定期健康診断の対象者と同じです。
さらに、契約期間が1年以上であれば、契約更新が予定されている場合も対象となります。また、労働時間が正社員の4分の3未満でも、2分の1以上であれば実施を推奨されています。
ストレスチェックの実施の流れ
ストレスチェックは、次の流れで進められます。
- 導入準備
- 質問表の配付・記入
- 面接指導を実施する
- 就業上の措置を行う
- 職場分析と職場環境の改善をする
各段階について詳しく見ていきましょう。
1.導入準備
ストレスチェック制度を円滑に進めるため、社内で運用ルールを整えることが必要です。関係者間で以下の点を十分に検討し、決定しておくことが重要です。
- ストレスチェックの実施者
- 実施のタイミング
- 使用する質問票
- 高ストレス者の選定方法
- 面接指導を希望する際の申し出先
- 面接指導を担当する医師
- 集団分析の方法
- ストレスチェックの結果の保管場所と責任者
また、制度運用には以下の役割の選定も欠かせません。
| 役割 | 詳細 |
|---|---|
| 制度全体の担当者 | 制度の設計や進捗管理を担う責任者 |
| ストレスチェック実施者 | 医師、保健師、または研修修了者(看護師・精神保健福祉士など)※外部委託も可能 |
| 実施事務従事者 | 質問票回収や入力、結果送付など個人情報を扱う実務担当者 ※外部委託も可能 |
| 面接指導担当医師 | ストレスチェック結果に基づき面接指導を行う医師 |
2.質問表の配付・記入
ストレスチェックを実施する際は、対象者に質問票を配布し、記入してもらいます。厚生労働省が提供する「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を利用すれば、パソコンを使った実施も可能です。
使用する質問票には決まった様式はありませんが、以下の3つの領域を必ず含める必要があります。
- ストレスの原因に関する質問項目
- ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 従業員に対する周囲のサポートに関する質問項目
これらを満たしていれば、企業が独自に作成した質問票を使用することも可能です。また、厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」を利用することもできます。
3.面接指導を実施する
ストレスチェックの結果に基づき、「医師による面接指導が必要」と判断された従業員から申し出があった場合、企業は1ヶ月以内に医師による面接指導を実施しなければなりません。申し出の期限は結果通知から1ヶ月以内と定められているため、従業員にその点を明確に伝えることが重要です。
面接指導では、医師が従業員のストレス状況や業務内容、勤務時間などを詳しく確認し、必要に応じて就業上の措置について意見を述べます。この意見は、従業員の健康を守るための具体的な改善策につながります。
さらに、面接指導の結果については、企業が5年間保存する義務があります。保存する記録には、面接指導の実施日や医師の意見などが含まれます。これらの記録は法定期間中、安全かつ適切に管理される必要があります。
4.就業上の措置を行う
面接指導を実施した後、医師から就業上の措置に関する意見を面接指導から1ヶ月以内に聴取し、その内容に基づいて必要な対応を講じなければなりません。
たとえば、以下のような措置が挙げられます。
- 労働時間の短縮、出張や時間外労働の制限
- 労働負荷の軽減、作業内容や就業場所の変更
- 深夜業務の回数削減、または日中勤務への転換
- 療養のため一定期間の休暇や休職
これらの措置は、従業員の健康状態や業務内容を考慮しながら実施されます。また、措置を講じる際には、本人の意向を尊重し、不利益な取り扱いがないよう配慮することが求められます。
5.職場分析と職場環境の改善をする
ストレスチェック実施後は、一定の単位で集団ごとのデータを集計・分析し、職場のストレス状況を可視化します。たとえば、部門や課、チームなどのグループごとに質問項目の平均値を算出し、集団間で比較することで、どの職場にどのようなストレス要因が存在しているかを把握できます。
ただし、対象者が10人未満の場合、個人が特定されるリスクがあるため、集計結果を提供するには全員の同意が必要です。そのため、原則として10人以上のグループを対象にします。
得られた集団分析結果をもとに、該当職場に対して環境改善の方針を検討します。改善策としては、業務の進め方や人員配置の見直し、休憩スペースの整備、上司と部下のコミュニケーション機会を増やすなどが挙げられます。また「職場環境改善のためのヒント集」などのツールを活用することで、自社に適した改善方法を見つけることができます。
ストレスチェックを行う際の注意点
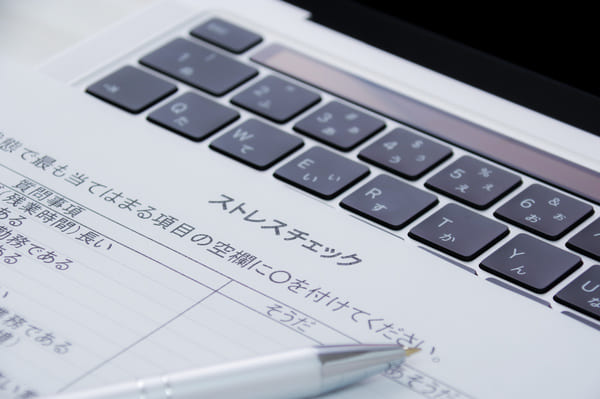
ストレスチェックを実施する際は、以下の注意点を押さえる必要があります。
- プライバシー保護を徹底する
- ストレスチェックに関して従業員に不利益な行為を行わない
それぞれ詳しく解説します。
プライバシー保護を徹底する
ストレスチェック制度の導入・運用にあたっては、従業員の個人情報を厳格に管理することが求められます。
ストレスチェックの実施者およびその補助業務を担う実施事務従事者には、法律で守秘義務が課されており、違反した場合には刑罰の対象となります。また、ストレスチェック結果や面接指導の所見などの個人情報は、企業に提供された場合でも、その取り扱いには十分注意が必要です。情報共有は業務上必要な範囲内に限定し、第三者への漏洩がないよう厳重に管理します。
さらに、データ管理をシステムで行う場合は、アクセス制限や暗号化などの措置を講じることで情報漏洩リスクを最小限に抑えることが重要です。
ストレスチェックに関して従業員に不利益な行為を行わない
ストレスチェック制度は、従業員の心の健康を守るための制度であり、本人の意思が尊重されることが前提です。そのため、以下のような理由で従業員に対して不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
- 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
- ストレスチェックを受けないこと
- ストレスチェック結果の企業への提供に同意しないこと
- 医師による面接指導の申出を行わないこと
また、面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機や目的による配置転換や職位の変更を行うことも禁止されています。
こうした不利益な取り扱いを避けることで、従業員が安心して制度を利用できる環境が整います。ストレスチェック制度の本来の目的は、職場全体のメンタルヘルス向上と早期の問題発見にあります。その目的を損なわないよう、公正かつ適切に制度を運用する責任が企業には求められます。
まとめ
ストレスチェック制度は、従業員の心の健康を守り、働きやすい職場環境を築くために欠かせない取り組みです。正しい方法で実施することで、個人が自分のストレスに気づくだけでなく、職場全体の改善にもつながります。一方で、制度の導入や運用には、プライバシー保護や適切な対応体制の整備など、慎重な配慮が求められます。
この制度を活用することで、従業員一人ひとりがいきいきと働ける職場を目指すことが可能です。ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の早期発見や予防だけでなく、職場環境改善の重要な手段として位置づけられています。従業員と企業双方にとって有益な制度として、その目的を理解し、公正かつ適切に運用していきましょう。
ストレスチェックをスムーズに実施するためには、ウィーメックスのストレスチェックサービスがおすすめです。英語受検や集団分析機能、課題抽出のサポートまで備えており、初めて導入する企業でも安心して活用できます。従業員がいきいきと働ける職場を目指して、ストレスチェック制度を見直してみてはいかがでしょうか。
【法人向け】Wemex ストレスチェック
出典:e-Govポータル(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000560416.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://stresscheck.mhlw.go.jp/)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://kokoro.mhlw.go.jp/manual/hint_shokuba_kaizen/)