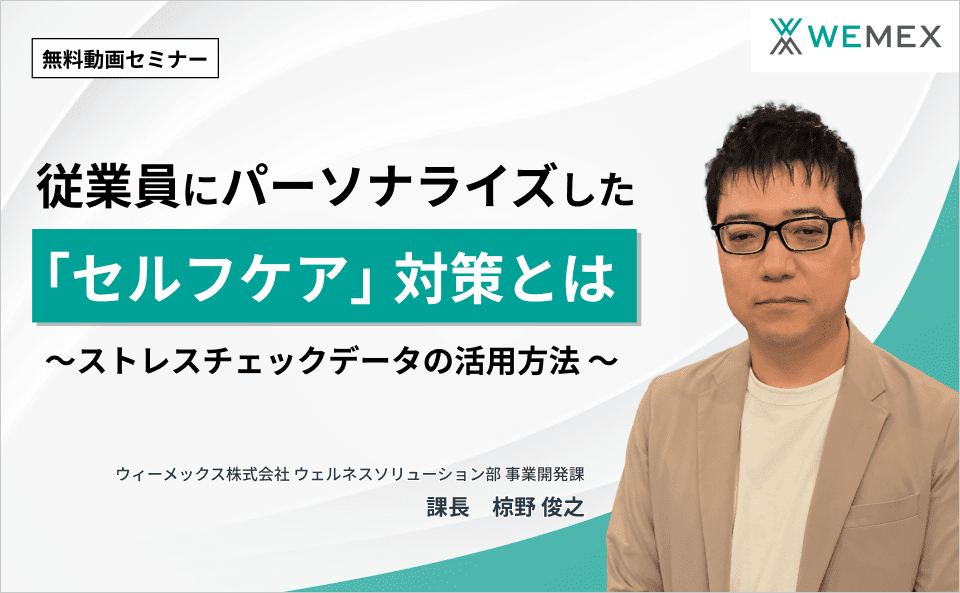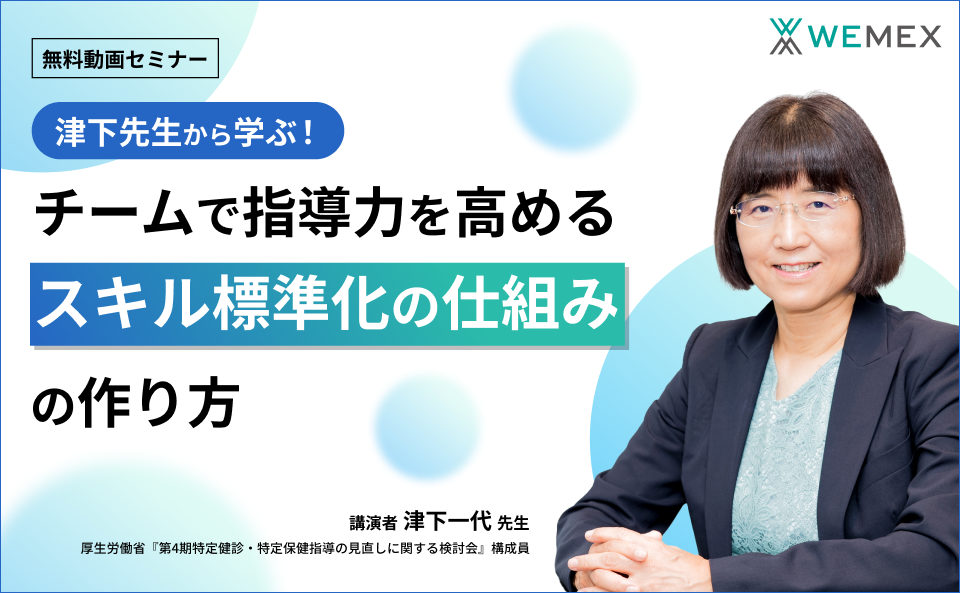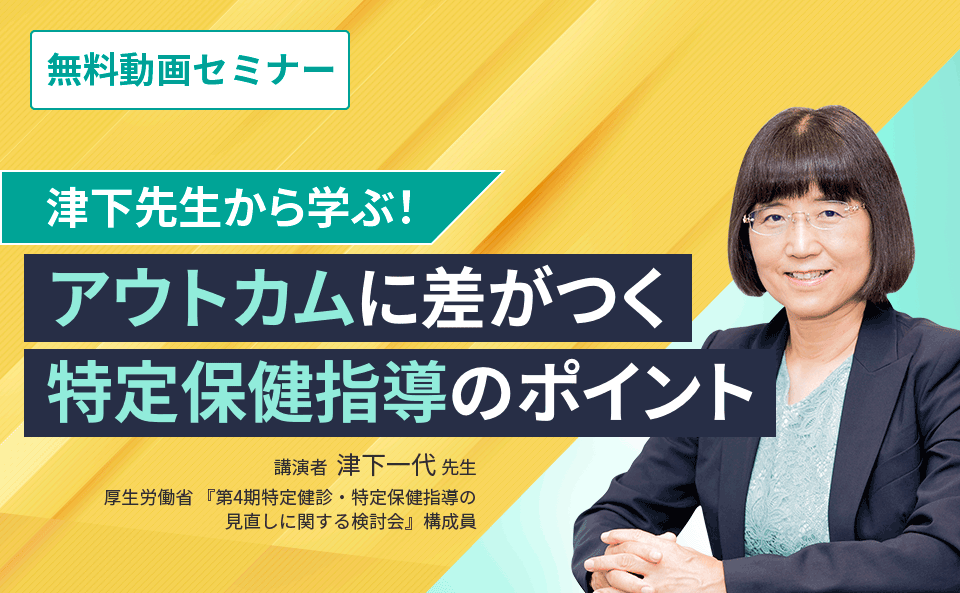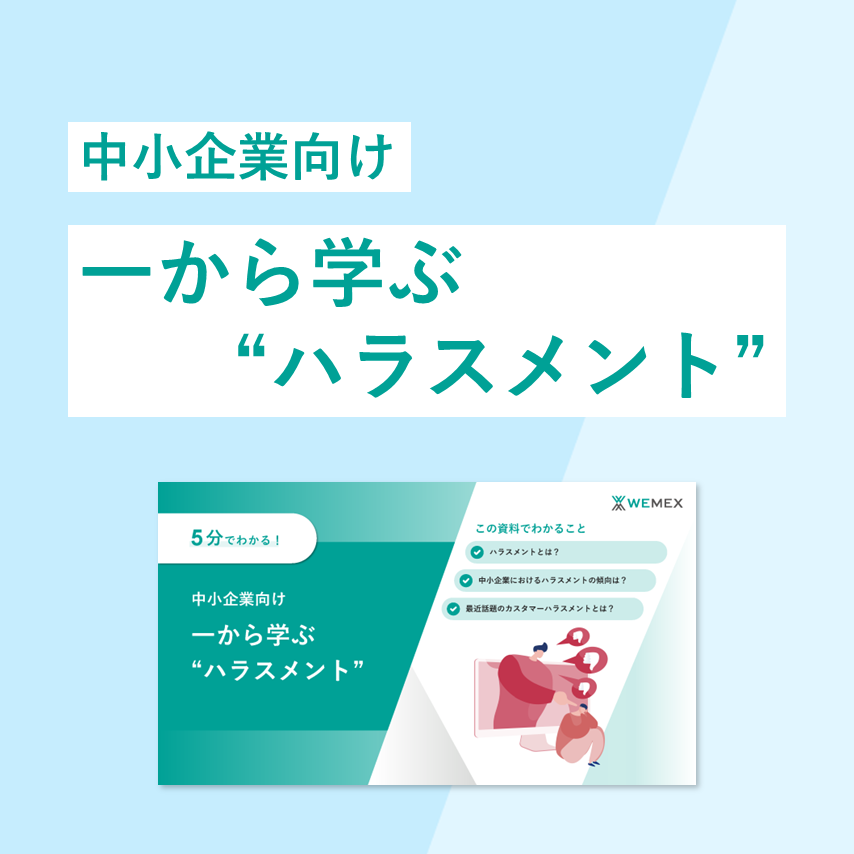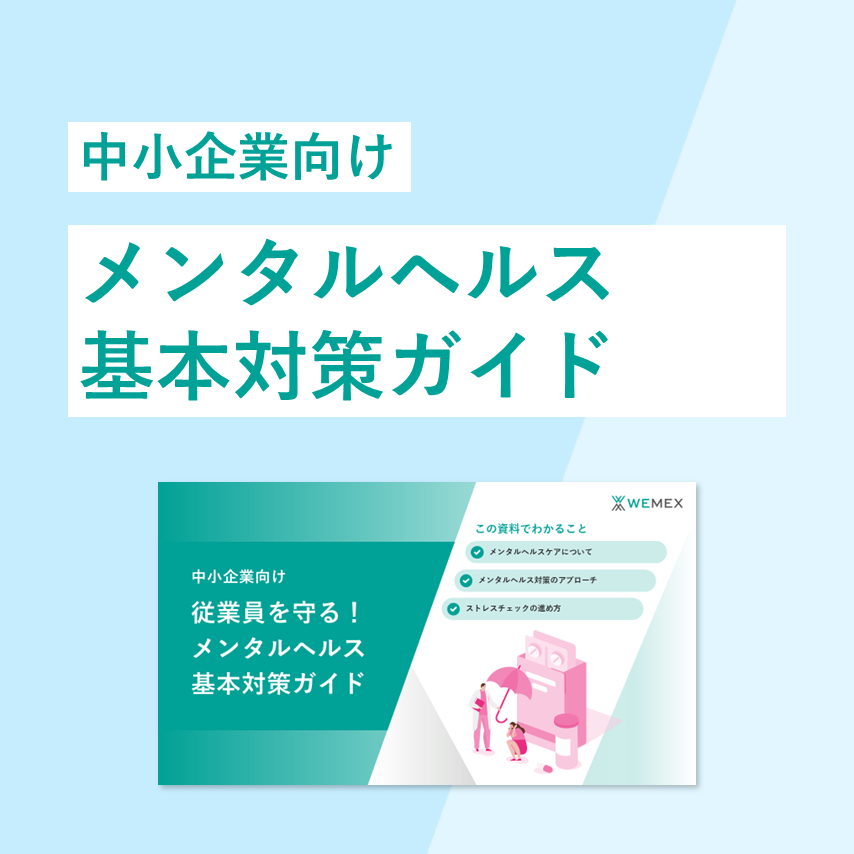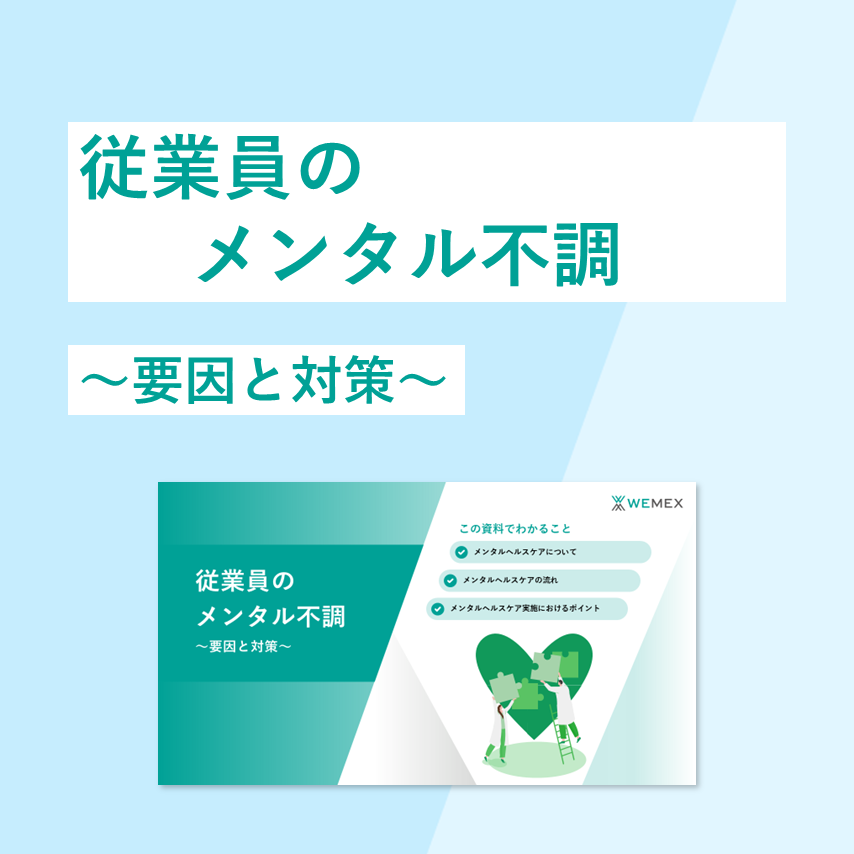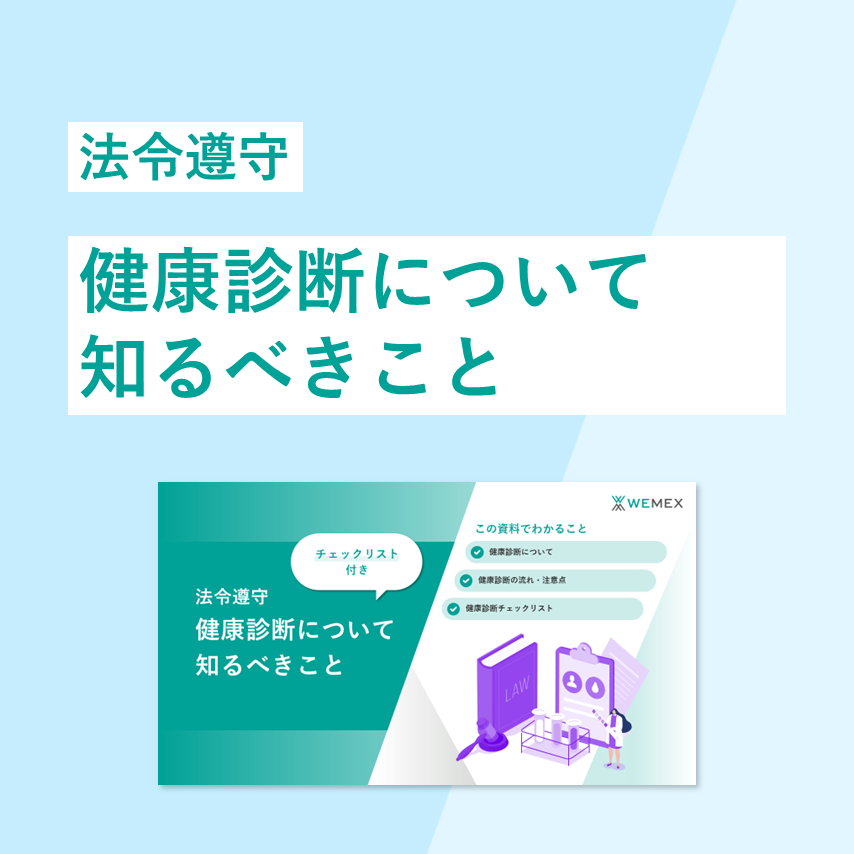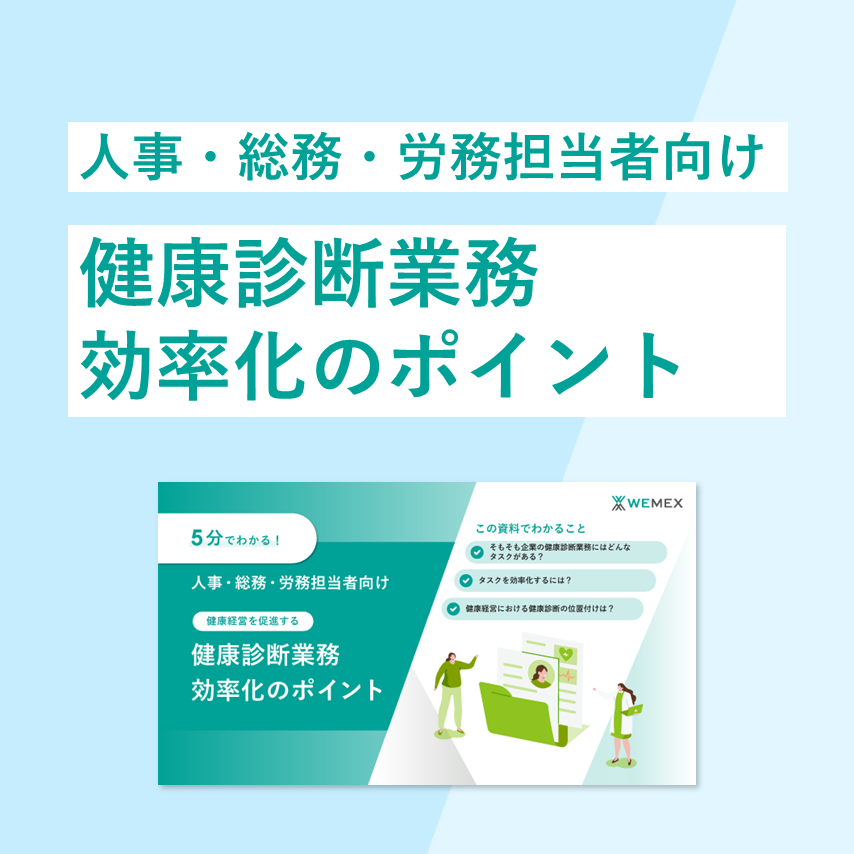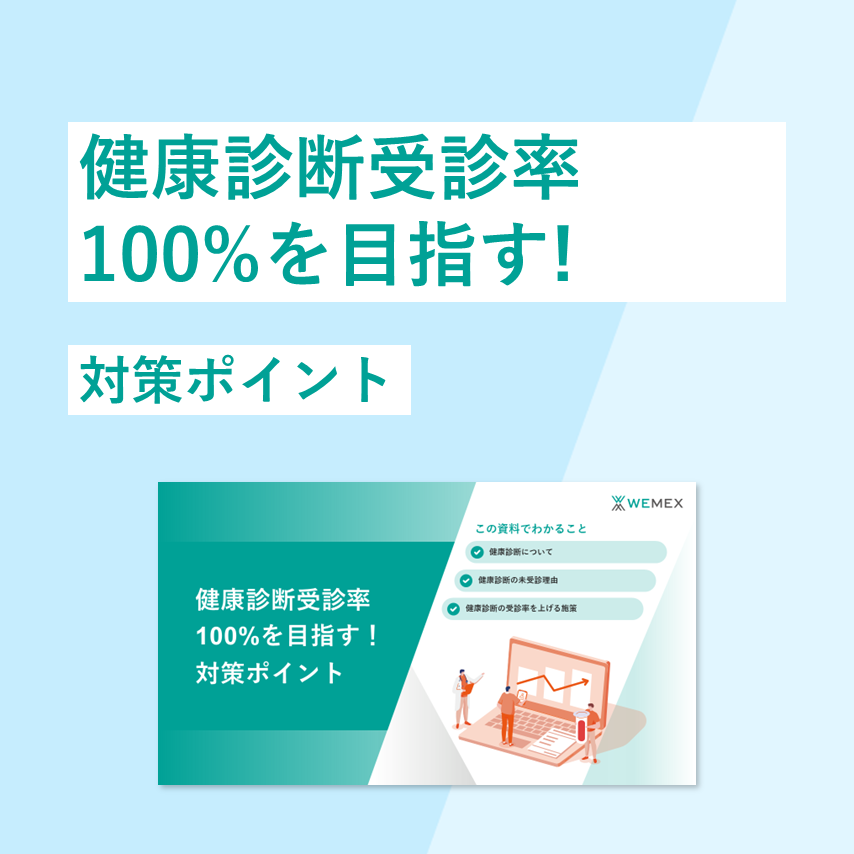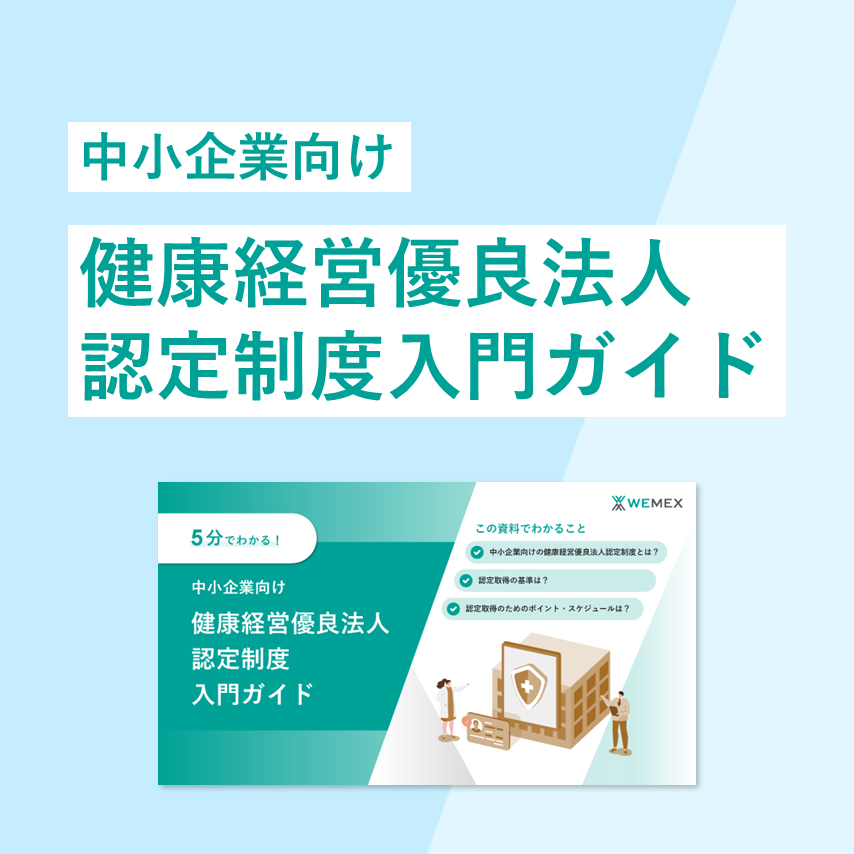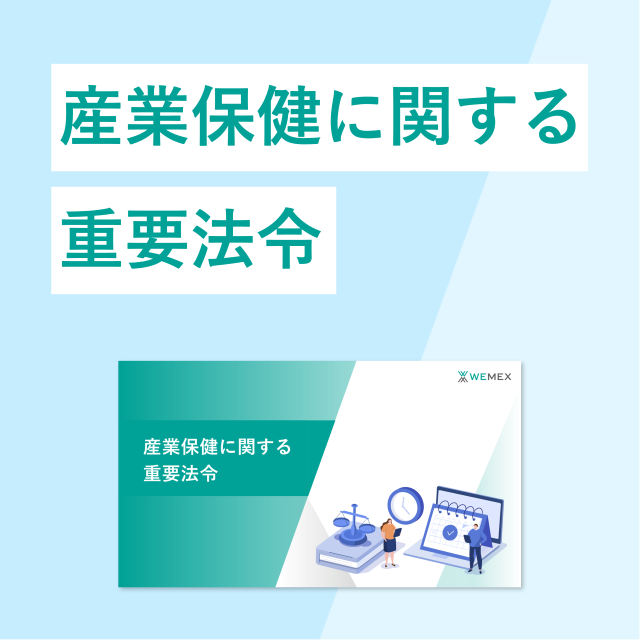目次
カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントは、近年社会問題化しており、政府もその対策を重視しています。2025年6月には、労働施策総合推進法の改正法が成立し、今後すべての事業主にカスタマーハラスメント対策を講じる義務が課されます(施行は2026年中の予定)。また、東京都や北海道など一部自治体では、カスタマーハラスメント防止の条例も施行され、各地で対策が進められています。
それでは、カスタマーハラスメントの概要についてみていきましょう。
顧客等による嫌がらせ
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先、施設利用者などが、社会通念上許容される範囲を超えた言動や不当な要求を行い、そのことで従業員の就業環境が害される行為を指します。
また、カスタマーハラスメントは、企業と契約関係のある顧客や取引先だけでなく、施設利用者やその他の利害関係者による場合も含まれます。
正当なクレームとの見分け方
顧客や取引先の要求が、事実に基づき、合理的かつ具体的な問題提起や補償・改善を求めるものであり、不必要に感情的・攻撃的な言動を伴わない場合は「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントには該当しません。
一方で、カスタマーハラスメントは、無理・理不尽・過激な要求や、感情的・攻撃的な言葉遣いなど、嫌がらせそのものを目的とした行為が特徴です。
よくあるカスタマーハラスメントの例
カスタマーハラスメントに該当する言動にはさまざまなものがあります。ここでは、特によくみられる代表的な例を取り上げます。
暴言・脅迫
従業員に対して「馬鹿」「無能」「クズ」など人格を否定する言葉を浴びせたり、大声で怒鳴りつけたりする行為は典型的なカスタマーハラスメントです。また、カウンターを強く叩いたり、「○○しないとどうなるかわからないぞ」などと脅す発言・威嚇行動も挙げられます。
これらの言動は、場合によっては脅迫罪や侮辱罪、威力業務妨害罪など刑法上の犯罪となる可能性もあります。
暴力
従業員に殴る・蹴るといった身体的暴力をふるう行為や、物を投げつける、首元を掴んで壁に押しつけるなどの行動も深刻なカスタマーハラスメントです。こうした行為は暴行罪や傷害罪に該当する可能性が高く、状況によっては速やかに警察への通報が必要です。
不当な要求
従業員が本来行う必要のないことを強要する行為も頻発しています。たとえば、「土下座をしろ」といった過剰な謝罪の強要や、営業時間外の対応、契約にないサービス提供、合理的理由のない金品や特別待遇の要求が代表的です。
拘束的な行動
長時間にわたり担当者を拘束し、業務に戻れないようにする言動もカスタマーハラスメントです。具体的には、何時間も説教したり、電話を長時間切らずに会話を続けさせたり、店舗やオフィスに居座り続けるなどの行為があります。業務に支障を与える程度の長時間対応の強要は、明確にハラスメントに該当します。
カスタマーハラスメントに上手く対応できない場合のリスク
企業にはカスタマーハラスメントへの対応が求められますが、実際には十分な対策が講じられていないケースもあります。その結果、どのようなリスクが生じうるか、主な例を紹介します。
従業員のメンタルヘルス不調
カスタマーハラスメントへの対応は、従業員に大きな精神的ストレスを与え、メンタルヘルス不調の原因になることがあります。重度の場合は身体的健康にも悪影響を及ぼし、非常に深刻な事態に発展しかねません。
厚生労働省の調査によれば、カスタマーハラスメントを繰り返し経験した従業員の21.2%が「眠れなくなった」と回答しています。また、「通院や服薬をした」と回答した従業員は8.8%です。
こうした被害に遭った従業員に対して、企業には適切なメンタルヘルスケアの実施が求められます。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)
安全配慮義務違反になる可能性
企業には、従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」が課せられています。対策を怠った場合、この義務違反と判断される可能性があります。
もし十分な対策がとられていないことで従業員が精神疾患などを発症した場合、企業側は損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
関連記事:安全配慮義務とは?根拠となる法律や事例、取り組み方を解説
離職率の増加
カスタマーハラスメントによるストレスや精神的苦痛は、従業員の離職を招く大きな要因となります。十分な対策がなければ、被害を受けた従業員が転職を検討するのは自然な流れです。
離職が発生すると、その補充や新入社員の教育に新たなコストがかかるだけでなく、経験者の流出によるサービス品質低下も懸念されます。
企業イメージへの悪影響
カスタマーハラスメント問題は、SNSや口コミなどを通じて広く拡散されることがあります。これにより企業イメージが大きく損なわれ、風評被害に発展する恐れも高まります。
また、事実に基づかない誹謗中傷が広がるリスクや、既存顧客の離脱、売上減少、採用活動への悪影響など、様々なマイナスの波及効果が懸念されます。
カスタマーハラスメントへの適切な対応方法

カスタマーハラスメントによるリスクを軽減するには、適切かつ組織的な対応が不可欠です。では、実際にどのように対応すべきかを解説します。
最初は通常のクレームと同じ対応をする
企業には日常的にさまざまなクレームが寄せられるため、はじめからカスタマーハラスメントだと決めつけるべきではありません。まずは冷静かつ丁寧に対応し、相手の要求内容や態度を正確に把握します。その上で、クレームの内容が社会通念上妥当か、不当または過剰なものかを慎重に見極めましょう。
複数人の従業員で対応する
カスタマーハラスメントへの対応を一人に任せるのは、過度な心理的負担やリスクの増大につながります。状況が深刻化した場合に備え、複数人または上司と連携して対応する体制を確立しましょう。他の従業員や管理職が同席することで、客観的な判断・安全確保もしやすくなります。従業員に他者への連絡・相談を促す仕組みを設けることも有効です。
記録や証拠を残しておく
対応時は「言った・言わない」のトラブル防止や、法的措置・社内処理のために、やり取りの記録・証拠を残すことが重要です。面談や電話応対ではメモや録音データ、発着信履歴などを保存し、証拠として活用できるよう管理しましょう。これらの記録により、正当な対応を証明し、迅速かつ適切な社内共有・判断につなげます。
不当な要求には応じない
不当または過剰な要求については、安易に応じると要求がエスカレートする可能性があります。要求内容が契約内容や社会通念に照らして適切かどうかを確認し、不当と判断される場合は毅然とした態度で対応・拒否することが大切です。その場しのぎの妥協では問題の長期化を招くため、組織全体として一貫した方針で対応しましょう。
従業員のメンタルを守るために実施すべきこと
カスタマーハラスメントに遭遇した従業員は、強い心理的ストレスにさらされることがあります。企業には、従業員の心身の健康を守るための対策が求められます。では、具体的にどのような対策が必要かみていきましょう。
対応マニュアルの作成
カスタマーハラスメントの対応マニュアルがあれば、従業員は落ち着いて状況に対処でき、心理的負担を軽減できます。自社で実際に発生した事例や具体的な対応手順・フローをまとめておきましょう。
マニュアルには、カスタマーハラスメントの定義や代表的な例、初動対応から報告・相談までの流れを記載します。また、不適切な対応例や注意点なども盛り込むと実効性が高まります。
被害者の相談窓口の設置
カスタマーハラスメントを受けた従業員が、速やかに相談・報告できる窓口を社内に設置しましょう。相談窓口では、被害状況のヒアリングやメンタルヘルスサポートの案内を行うことが重要です。社内対応だけで十分でない場合は、外部のカウンセラーや専門機関と連携し、必要に応じて産業医との面談を調整することで、従業員のメンタルヘルス不調の防止につなげましょう。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
まとめ
カスタマーハラスメントへの適切な対応には、複数名での対応体制を構築し、不当な要求には毅然と対応することが重要です。また、記録や証拠を残すことでトラブル防止につながります。企業としては、対応マニュアルの作成や相談窓口の設置を進め、被害に遭った従業員のメンタルヘルスも継続して守ることが必要です。
ウィーメックスでは、企業向けのストレスチェックサービスを提供しており、従業員が利用できる相談窓口の設置も標準機能(※プレミアムプランの場合)として含まれています。カスタマーハラスメント対策の一環として、ぜひご相談・お問い合わせください。