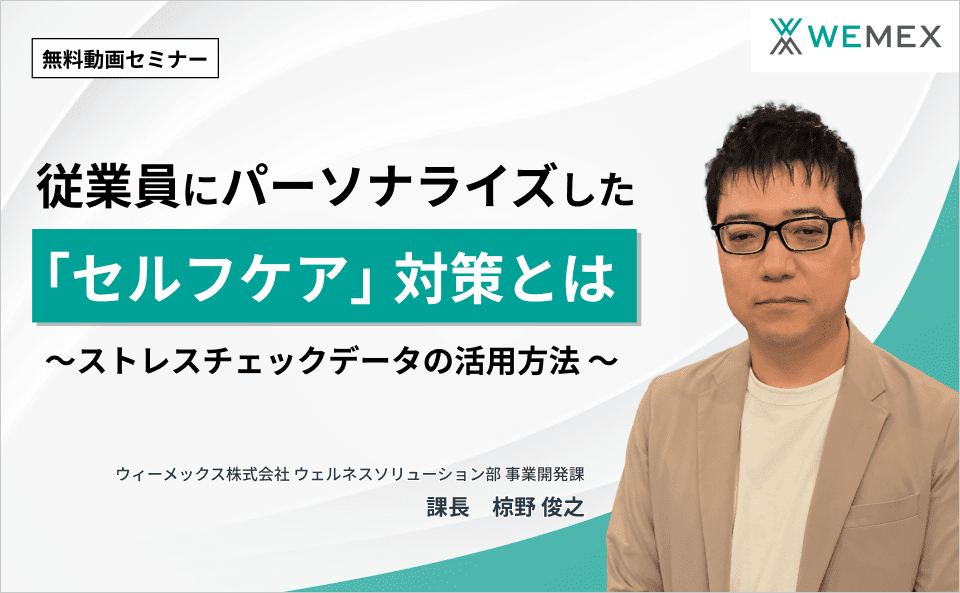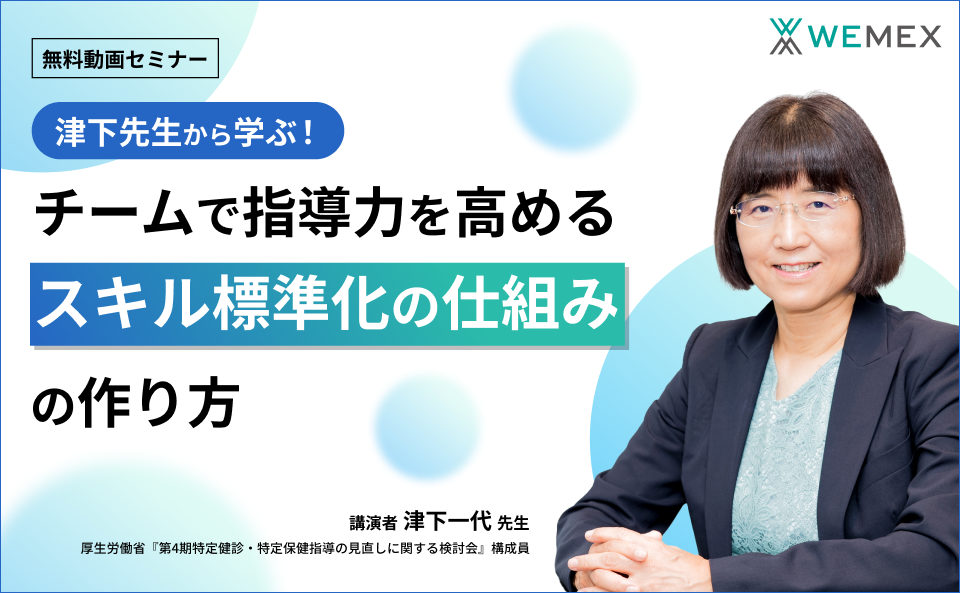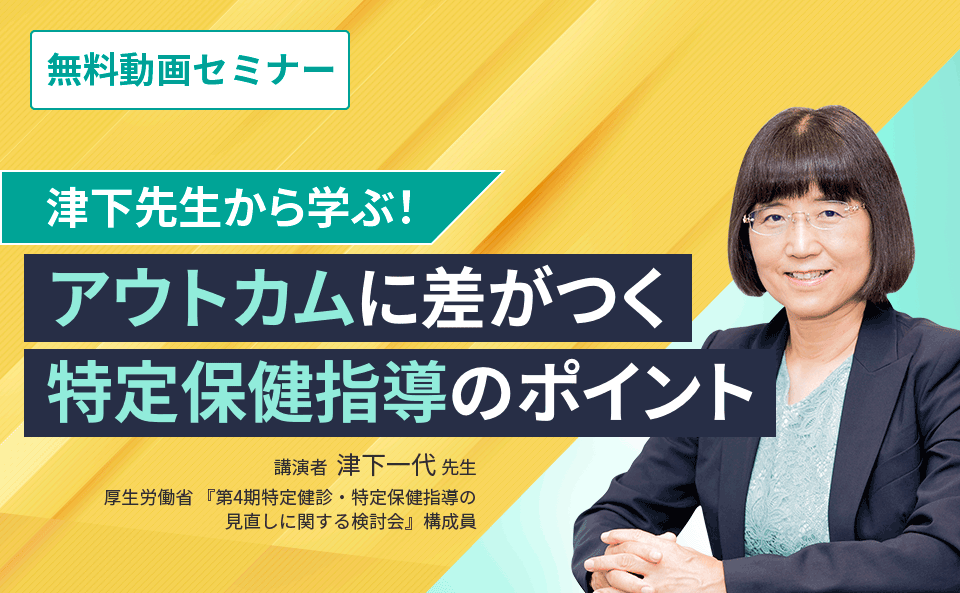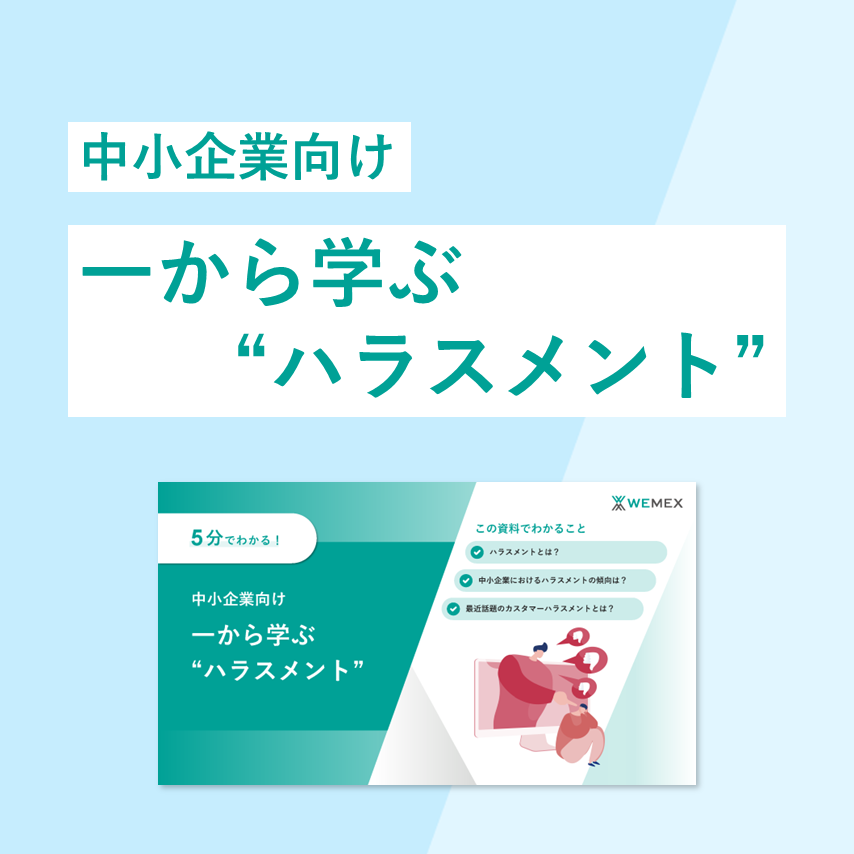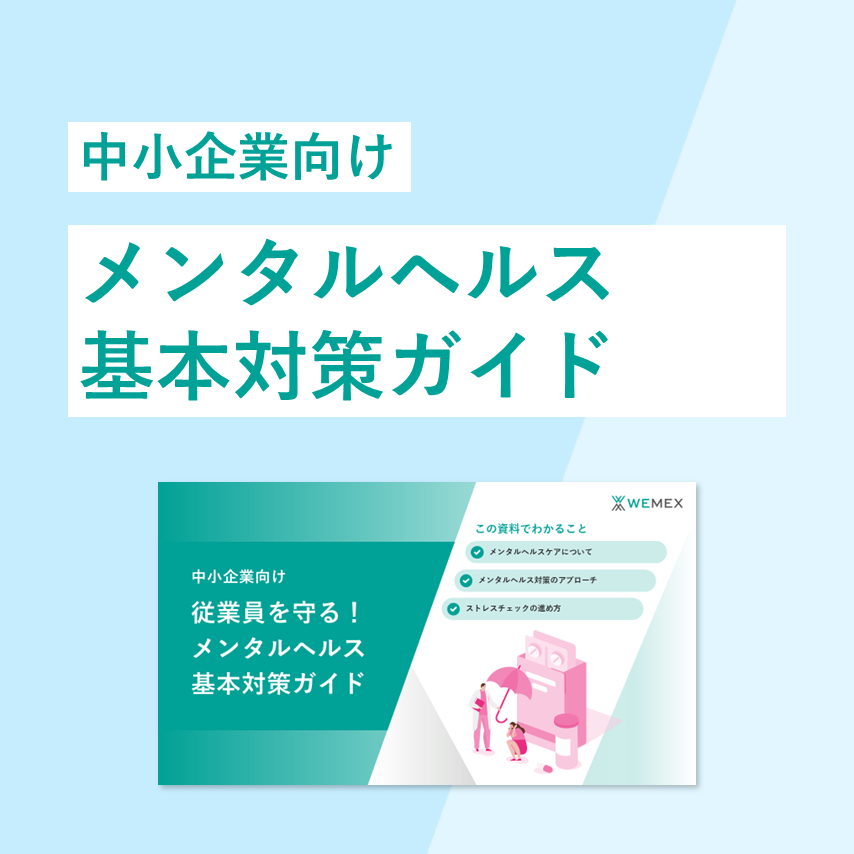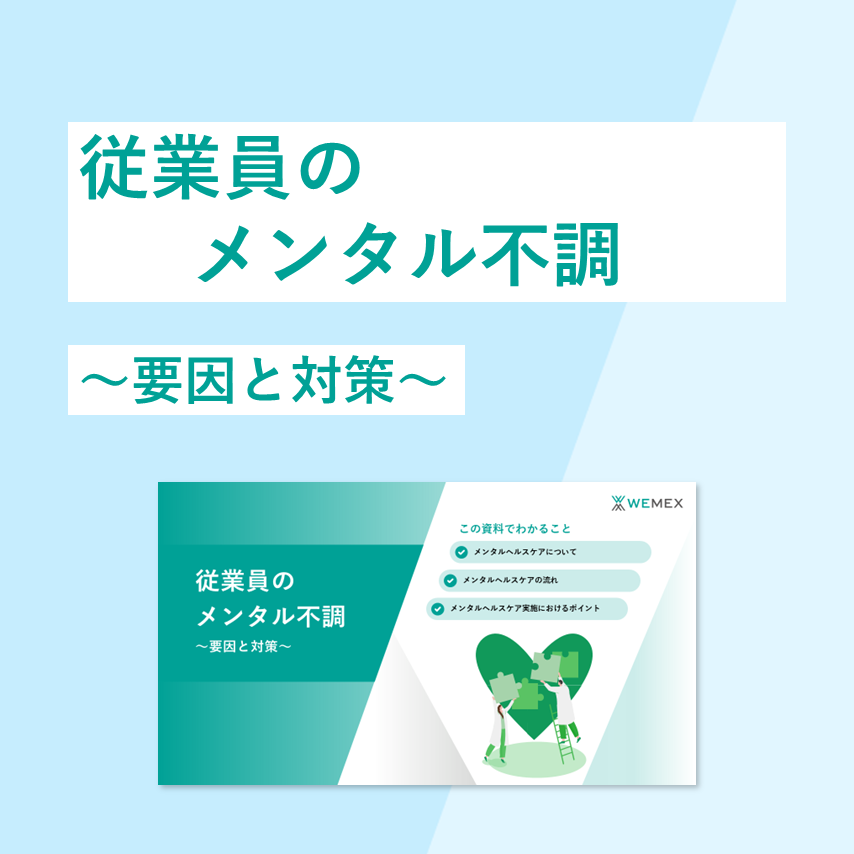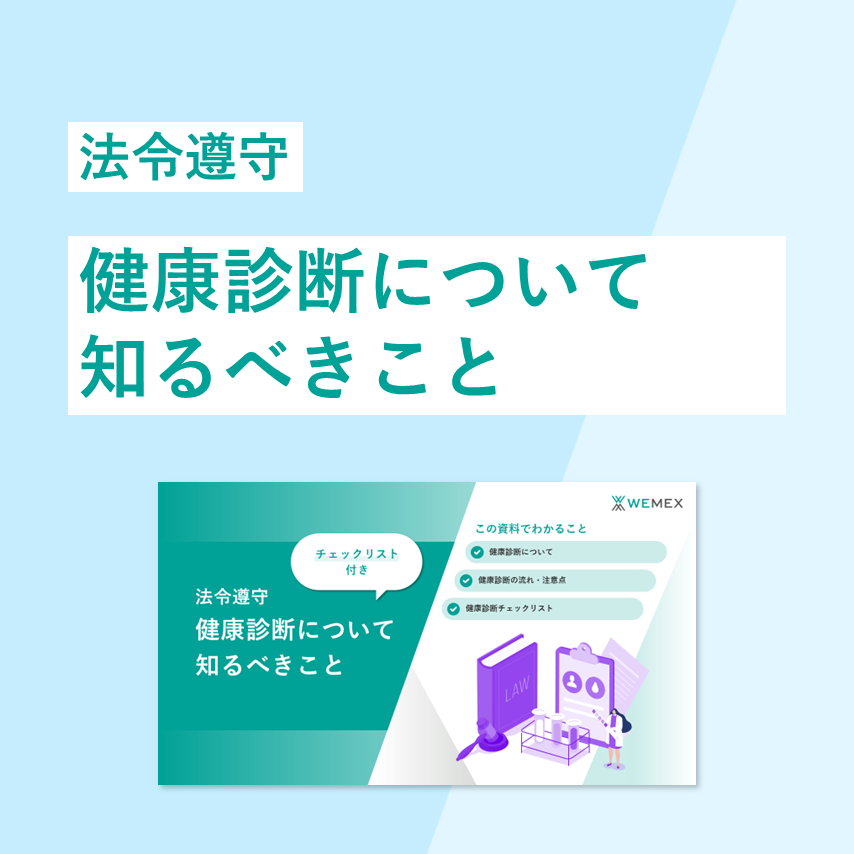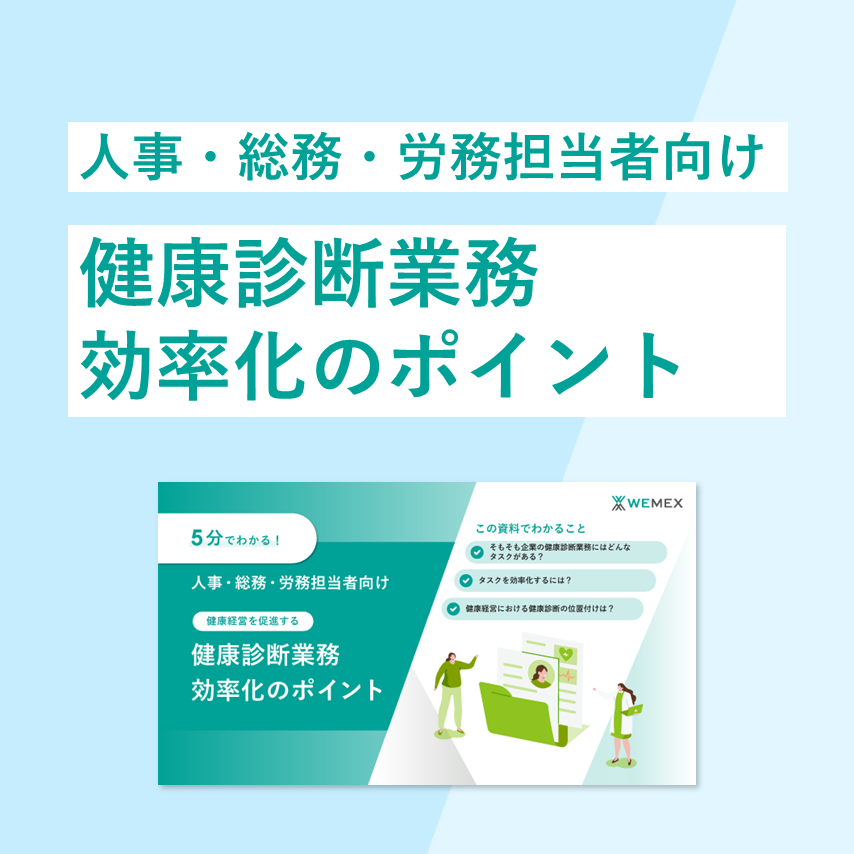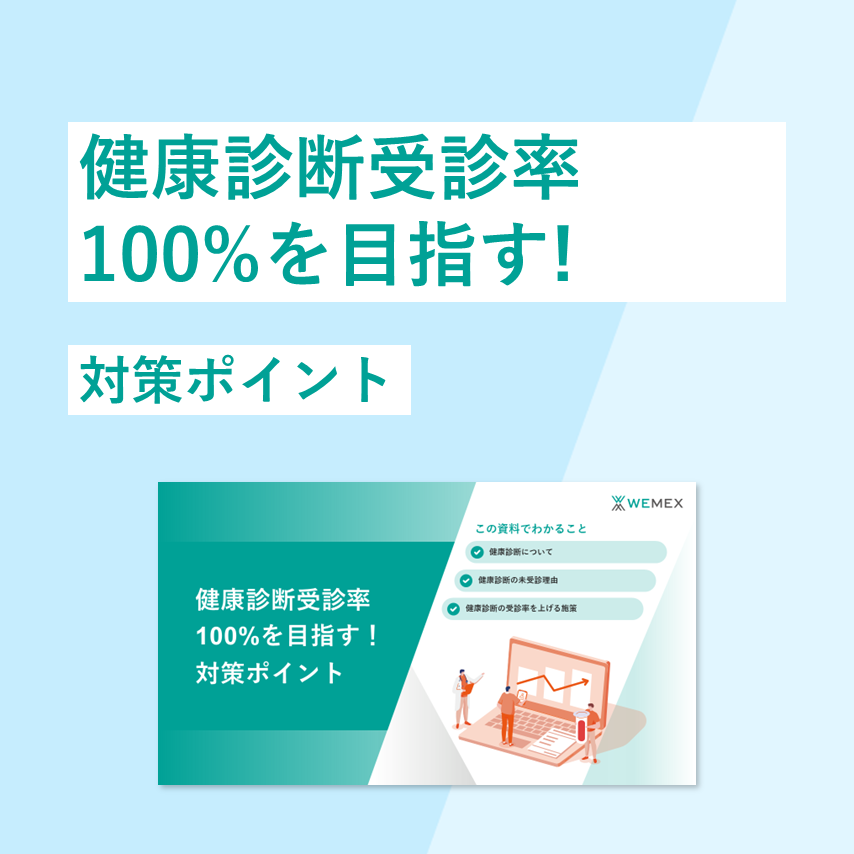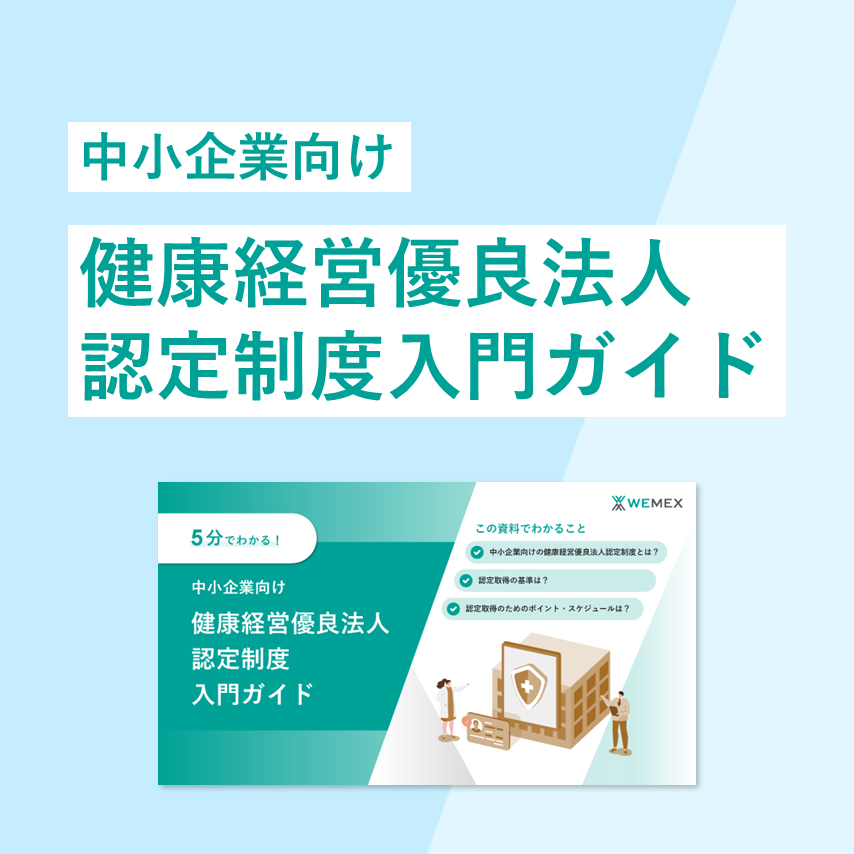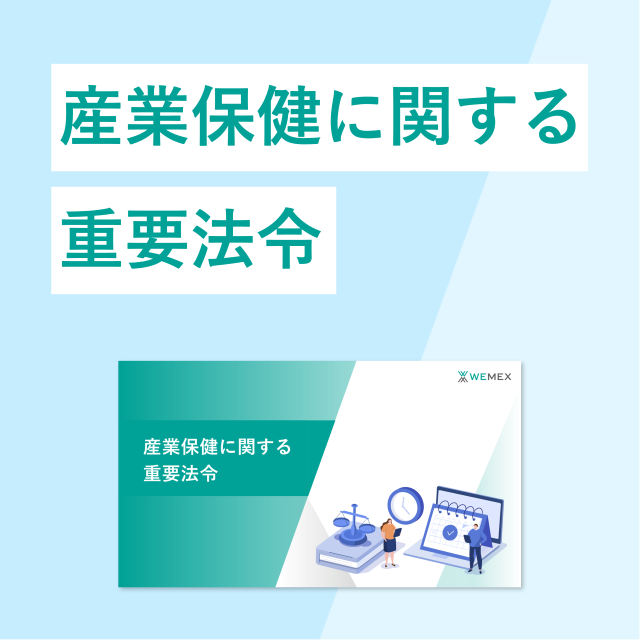目次
安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、従業員の心身の健康と安全を守るために企業が配慮すべき義務のことをいいます。これは労働契約書に明記されていなくても、企業に法律上課せられている義務です。
業務内容や職場環境によって危険の種類や程度は異なるため、どのような配慮が必要かは一概には決められません。そのため、安全配慮義務に違反しているかどうかも、個々の事案ごとに判断されます。
安全配慮義務に関わる法律
安全配慮義務に関係する法律は、以下の3つです。
- 労働契約法
- 労働安全衛生法
- 民法
それぞれの概要や関係する条文を解説します。
労働契約法
労働契約法は、従業員と企業の間で結ばれる労働契約に関する民事的なルールを定めた法律です。この法律は、従業員の保護や労使間のトラブル防止を目的としています。特に安全配慮義務については、第5条が重要な規定となっています。
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
「生命、身体等の安全」には物理的な損傷のほか、過重労働によるうつ病やハラスメントによる精神疾患の防止など、心身の健康も含まれます。「必要な配慮」の内容は、労働契約法には定められていません。企業は従業員の職種や業務内容、職場環境などに合わせて、適切な安全確保措置に取り組む必要があります。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成を目的とした法律です。第3条では、事業者が労働者の安全と健康を確保する責務(事業者等の責務)について定めており、これがいわゆる「安全配慮義務」の法的根拠の一つとなっています。
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
ポイントとなる法律の用語を確認しましょう。
労働災害
業務に関連した出来事により、従業員が負傷し、疾病にかかり、または死亡することを指します。
快適な職場環境の実現
適切な温度・湿度管理や清潔な作業スペース、休憩設備の整備など衛生面の快適さのほか、ハラスメントのない人間関係など、心理的な負担を軽減できる職場環境も含まれます。
労働条件の改善
長時間労働の是正や休憩時間の確保、有給休暇の取得促進などにより、従業員の負担を減らす取り組みのことです。
民法
民法は、契約についてのルールを定めた一般法です。企業が安全配慮義務に違反し、従業員にけがや病気などの損害が発生した場合、民法にもとづき損害賠償責任を問われる可能性があります。
たとえば従業員のパワハラ・セクハラを放置し、他の従業員がメンタル不調に陥った場合、民法第415条にもとづき「債務不履行による損害賠償」の責任を負う可能性があります。
このほか、安全配慮義務違反では、民法第709条の不法行為による損害賠償や民法第715条の使用者責任が論点となる場合もあります。
安全配慮義務違反の罰則
労働契約法には、安全配慮義務違反に対する罰則は定められていません。一方、労働安全衛生法は、違反すると罰則が課される場合もあります。
たとえば、従業員が危険な業務に就く際に求められる安全衛生教育を実施しなかったり、健康診断を受けさせなかったりした場合は、50万円以下の罰金が課される場合があります。
ただし、労働契約法に罰則の定めがないからといって、労働安全衛生法のみを守れば良いというわけではありません。労働契約法に違反した場合も損害賠償や慰謝料など、民事上の責任が問われる可能性があります。
安全配慮義務の対象者
安全配慮義務は、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートタイマーも労働契約を結んでいれば対象となります。
加えて、企業と直接労働契約がなくても、安全配慮義務が及ぶ場合があります。派遣社員については、労働派遣法により派遣元だけでなく派遣先企業にも安全配慮義務が課せられています。
また、下請け企業の従業員についても、元請企業と「使用者と労働者と同視できる特別な社会的接触関係」が認められる場合には、判例上、元請企業が安全配慮義務を負うとされています。
たとえば、元請企業が作業内容を具体的に指示・管理したり、元請企業の設備を使わせていた場合など、実質的に労働者の安全確保に関与していると判断されるケースが該当します。
安全配慮義務違反となる基準

安全配慮義務違反を判断する際は、「予見可能性」と「結果回避可能性」が重要です。これらは、企業が従業員の健康被害をどこまで予測し、かつそれを防ぐためにどのような対応をとることができたかという観点から判断されます。
予見可能性
予見可能性とは、従業員の心身の健康が害される出来事の発生を、企業が事前に予測できたかどうかという点です。企業が通常の注意を払っていれば、労働者に危険が及ぶことを認識できたかが問われます。
たとえば、過重労働や危険な作業環境など、過去の事例や現場の状況から危険を察知できたかが重視されます。企業が健康被害の発生を予測できていれば、適切な対策を講じる責任が生じ、安全配慮義務を果たす上でも重要な要素となります。
結果回避可能性
結果回避可能性は、従業員の健康を害する事象の発生を、企業が適切な対応を取ることで避けられたかどうかという点です。たとえば、労働者の異変に気づいた時点で業務内容を調整したり、医師の診断を受けさせるなどの措置を講じていれば被害を防げたかが問題となります。
企業が予見できた危険に対して、合理的な防止策を講じていなかった場合、安全配慮義務違反が認定される可能性が高くなります。反対に、十分な対応をしていた場合は、違反とされないこともあります。
安全配慮義務違反の事例
安全配慮義務違反が問題となる事例はさまざまです。人事担当者が特に注意すべき代表的な5つの事例を確認しましょう。
労災事故
企業は、業務により従業員がけがや健康障害を負うおそれのある危険を、予見可能な範囲で事前に把握し、合理的な回避措置を講じる義務があります。これらの義務を怠り、労災事故が発生した場合には、安全配慮義務違反が認定される可能性があります。
また、労災事故が発生した場合には、労働安全衛生法違反による刑事罰や、業務停止などの行政処分が科されることがあります。さらに、企業の社会的信用が失墜するなど、社会的責任を問われる場合もあります。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)
上司によるパワハラで従業員がうつ病を発症した場合や、他の従業員によるセクハラ行為により従業員が休職に追い込まれた場合、企業が被害の発生を認識しながら適切な対応を怠ったと認定されれば、安全配慮義務違反とされる可能性があります。
長時間労働・過重労働
長時間労働や過重労働は、安全配慮義務違反の代表例です。「脳・心臓疾患の労災認定基準」では、従業員が業務と疾患発症の関連性が強いと評価する時間外労働の目安として、以下を挙げています。
- 発症前1か月間に100時間以上
- 発症前2〜6か月間平均で月およそ80時間以上
平日の時間外労働のほか、休日労働や深夜労働が続いたり、終業してから翌日の始業までの時間(勤務間インターバル)が短い場合も、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
メンタル不調
上司からの理不尽な業務命令や職場の人間関係などが原因で、従業員がうつ病や適応障害などを発症した場合、企業が適切な対応を怠っていたと認定されれば、安全配慮義務違反とされる可能性があります。
厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害等による労災の認定(支給決定)件数は令和5年度に883件、うち自殺(未遂を含む)は79件でした。
企業は物理的なけがや損傷だけでなく、従業員に精神的な負担がかからないよう、働きやすい環境を整備することも求められます。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
自然災害
自然災害においても、企業には従業員の生命や身体の安全を確保するための安全配慮義務が課されています。特に発生が予測できる自然災害については、企業は事前に必要な対策を講じる責任があります。
自然災害はいつ発生するか予測が難しいため、万が一の際に従業員の安全を守るための備えが重要です。具体的な防止策については後述します。
安全配慮義務違反の防止策
安全配慮義務に違反しないためには、企業は日ごろから意識して対策する必要があります。代表的な5つの防止策を見ていきましょう。
労災事故の予防
令和5年の労働災害発生状況によると、労災によって亡くなった方は755人です。事故別では「墜落・転落」が204人で最多となっています。
労災事故を予防するには、墜落防止設備の設置や機械設備の作動チェック、従業員に対する安全装置装着の義務付けなど、安全な作業環境の整備が欠かせません。
そのうえで、安全衛生教育の実施や作業マニュアルの整備により、従業員が安全に作業できるよう教育指導することも重要になります。
ハラスメントの防止
ハラスメントを防止するには、以下の措置が有効です。
- 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制整備
- ハラスメントが発生した場合の迅速・適切な対応
- 相談者のプライバシー保護や不利益取扱いの禁止
加害者となる従業員自身が、ハラスメント行為を自覚していないケースも少なくありません。そのため、定期的な社内研修を実施し、ハラスメントに該当する言動や、その影響について従業員に認識させることが重要です。こうした取り組みを通じて、ハラスメントの未然防止に努めましょう。
労働時間の適切な管理
長時間労働を防止するためには、従業員の労働時間や休暇を適切に管理することが不可欠です。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、企業は従業員ごとに、労働日ごとの始業時刻と終業時刻を正確に確認し、その記録を適切に保存することが求められています。
また、安全配慮義務は管理監督者にも及びます。たとえ労働基準法上の労働時間規制の適用除外となる管理監督者であっても、部下の健康に配慮するだけでなく、自身の健康管理にも十分注意し、過重労働を避けることが重要です。
従業員の健康管理
安全配慮義務に違反しないためには、従業員の健康状態を把握することが重要です。定期健康診断やストレスチェックなどを通じて、定期的に従業員の健康状態を確認しましょう。
定期健康診断はすべての事業者に義務付けられており、ストレスチェックも今後は50人未満の事業場を含めて義務化される予定です。
健康状態に問題がある従業員が見つかった場合は、業務内容の見直しや医療機関の受診勧奨など、適切な対策を講じましょう。また、従業員への配慮が必要となった場合に、速やかに対応できる体制をあらかじめ整えておくことも重要です。
関連記事:健康診断は会社の義務!目的や内容・罰則について解説
ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
産業医やカウンセリンググ窓口の設置
従業員のメンタル不調による安全配慮義務違反を防止するためには、専門家の協力が欠かせません。産業医やカウンセラーを配置し、従業員が健康相談を気軽に受けられる体制を整えましょう。
常時50人以上の従業員が勤務する事業場では、産業医の選任や衛生委員会の設置が労働安全衛生法で義務付けられています。50人未満の事業場で産業医を配置できない場合は、地域産業保健センターなど、外部の産業保健サービスを活用することも有効です。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
まとめ
安全配慮義務は、従業員の安全確保と健康維持のために企業が必ず守るべき重要な義務です。安全配慮義務に違反した場合、従業員が危険にさらされるだけでなく、損害賠償請求や労災認定、行政処分、企業イメージの失墜など、企業経営にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
こうしたリスクを回避し、安全配慮義務に違反しないためには、人事部門だけでなく企業全体で対策に取り組むことが重要です。企業全体で取り組むことで、安全衛生担当者の負担を軽減し、より効果的な対策を実施できます。必要に応じて外部サービスの活用も検討しましょう。
ウィーメックスでは、健診代行や保健指導システム、ストレスチェックなど、企業の安全衛生の取り組みをサポートする多様なサービスを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。
Wemex 健診代行
Wemex ストレスチェック
出典:e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128)
e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_1)
e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/001309213.pdf)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf)