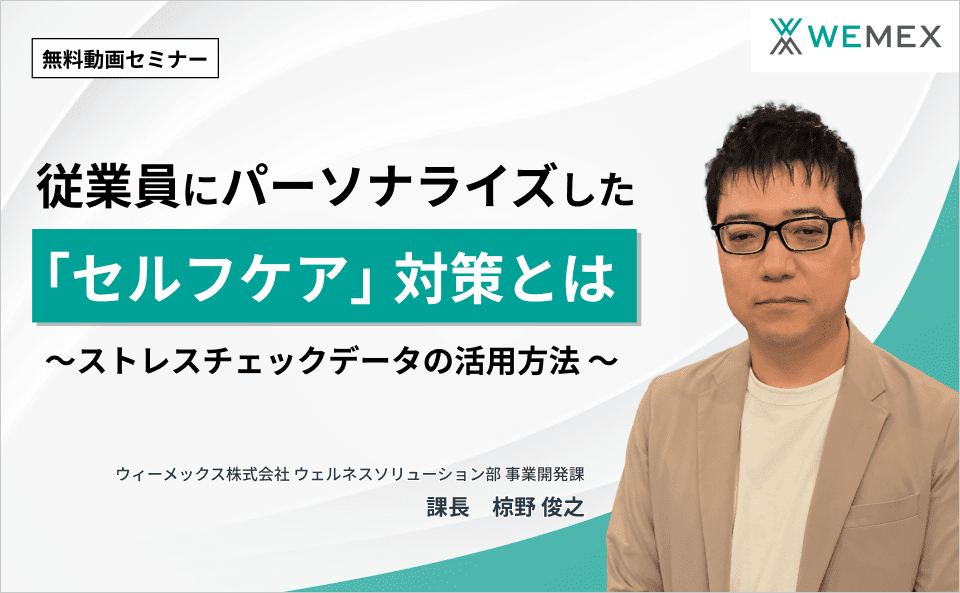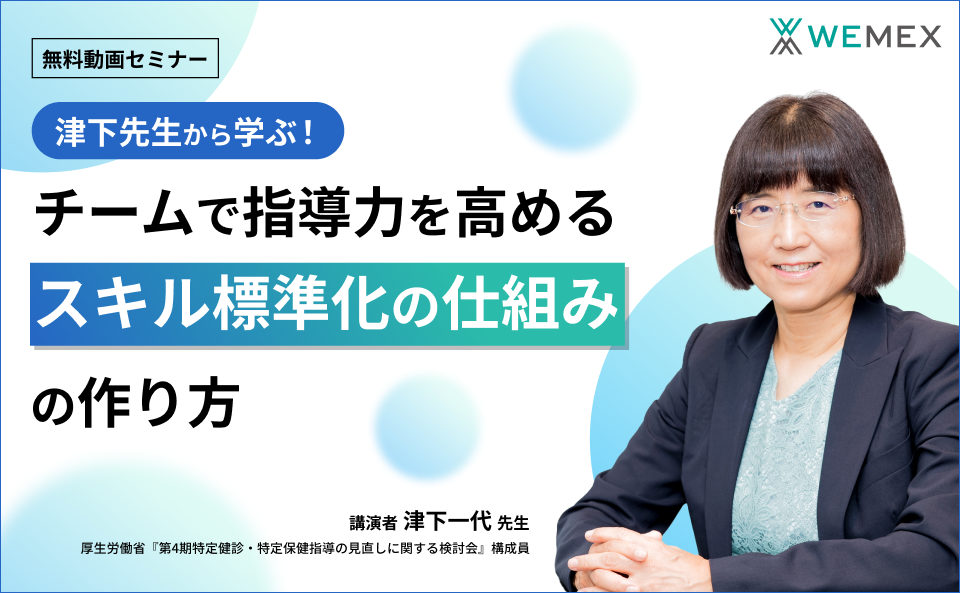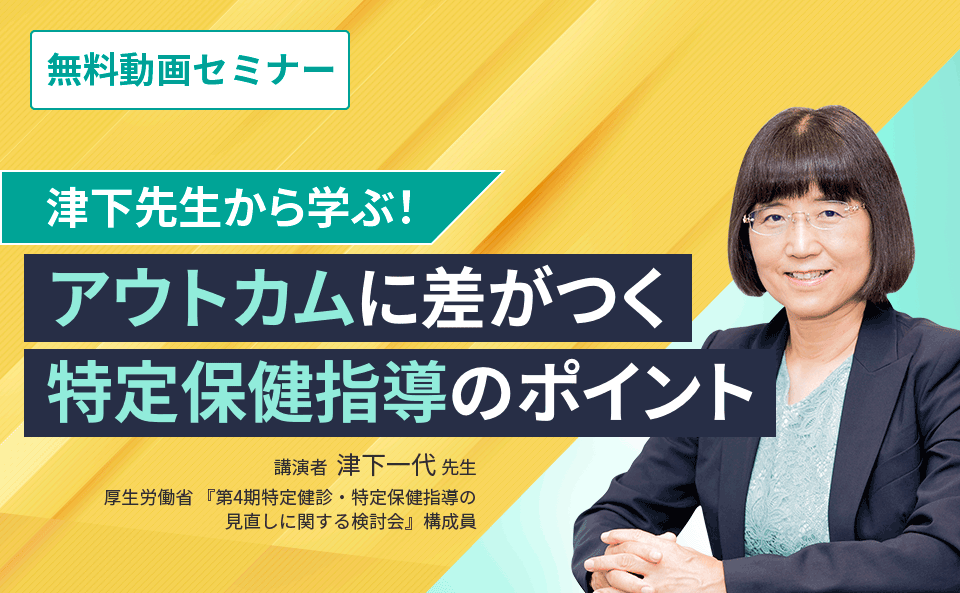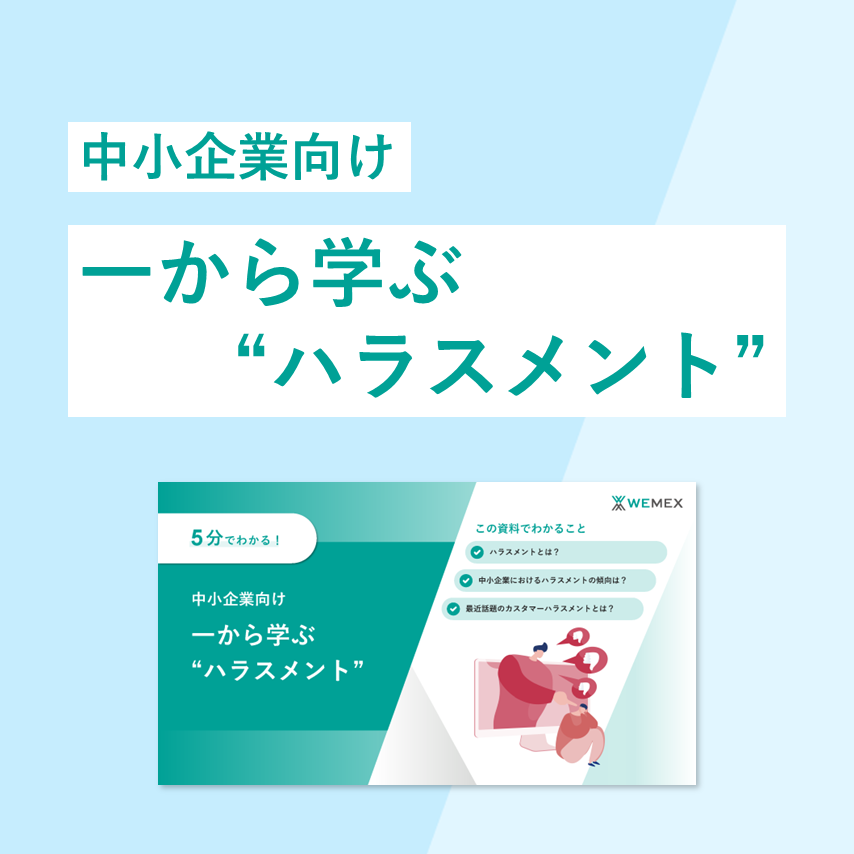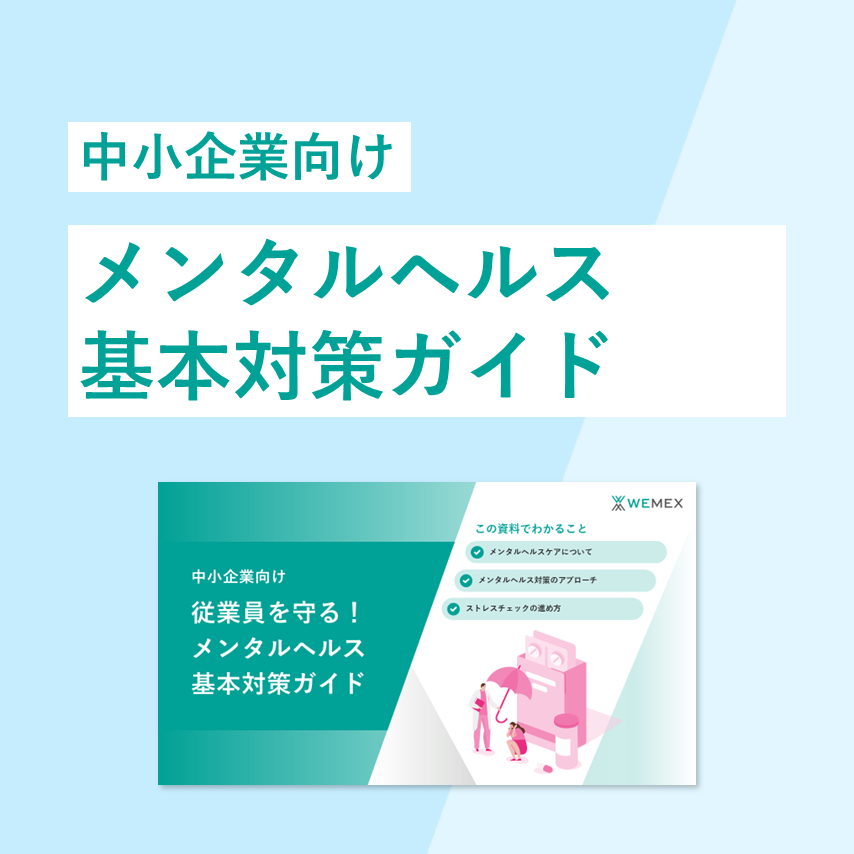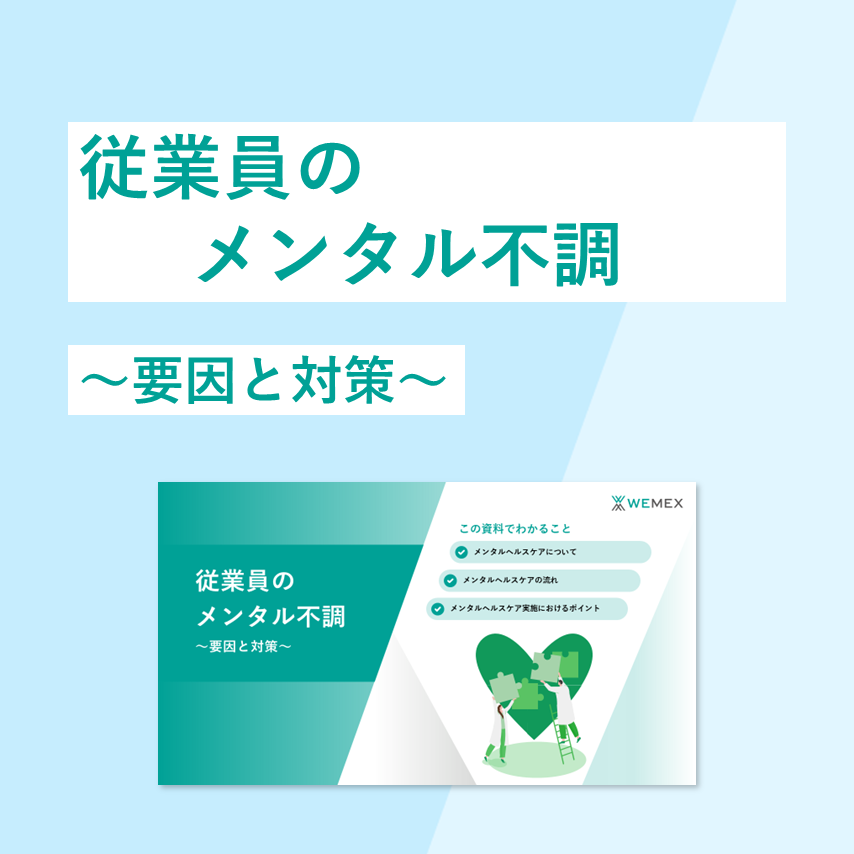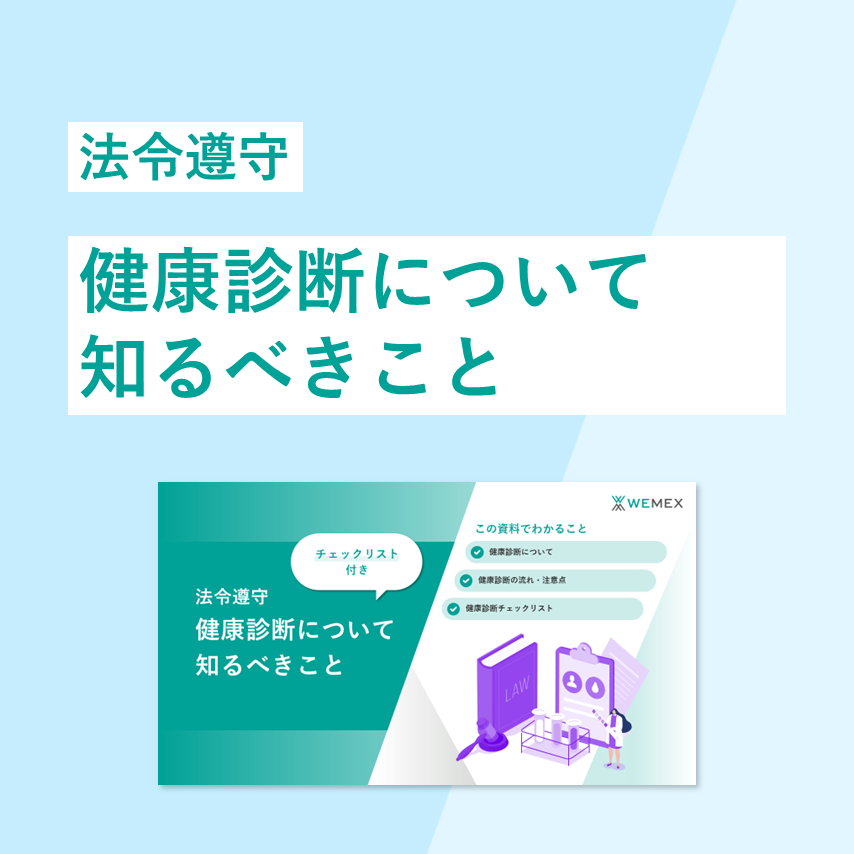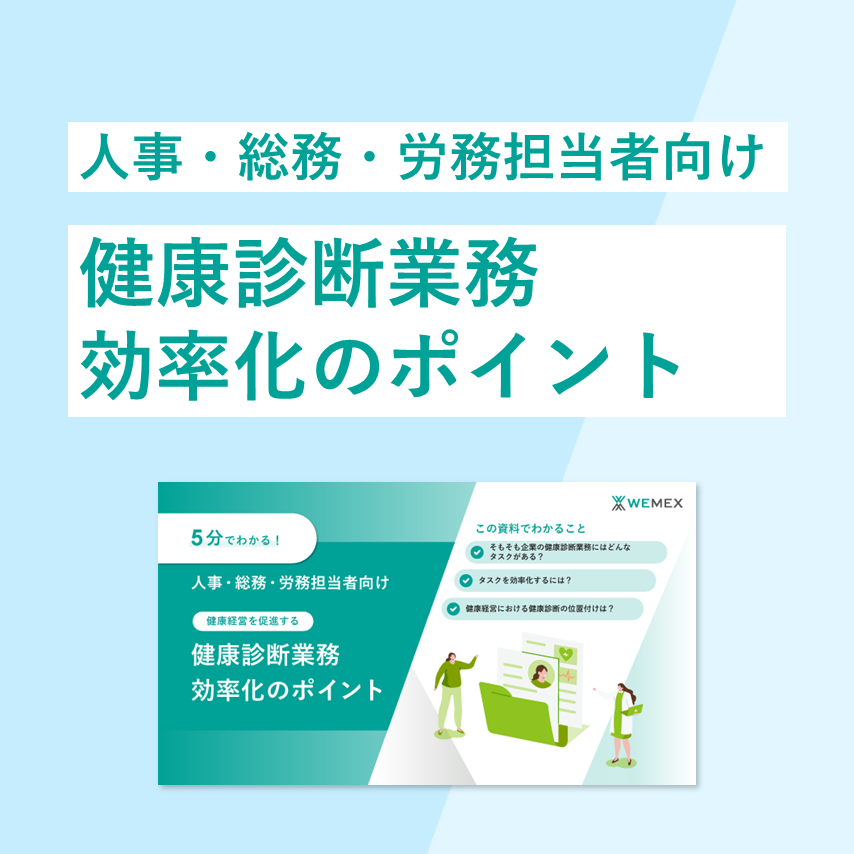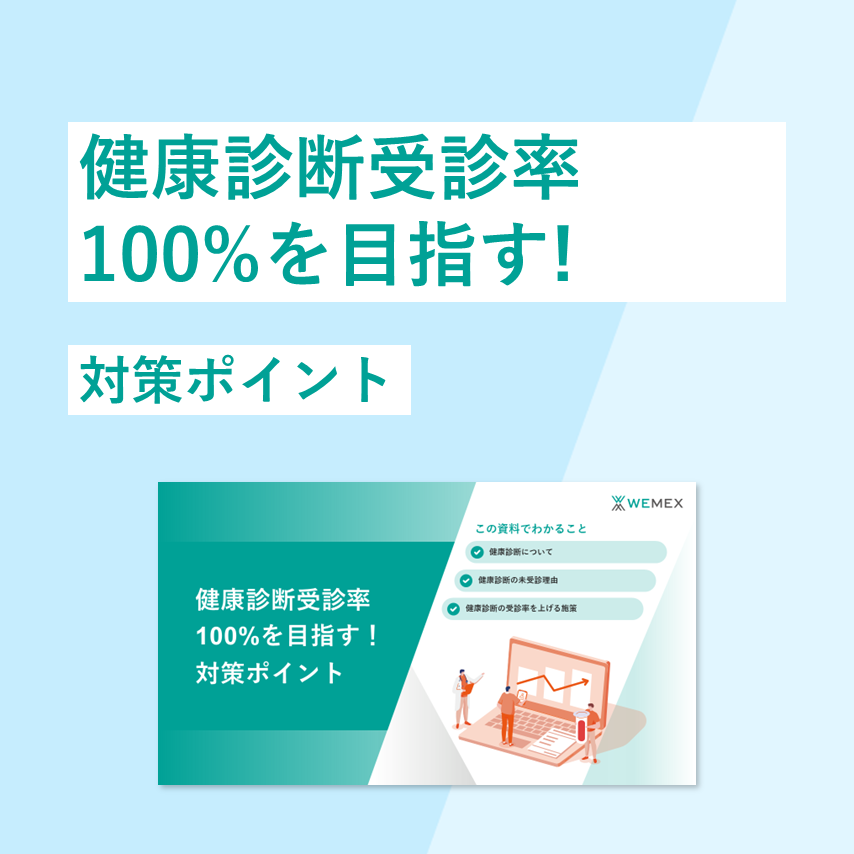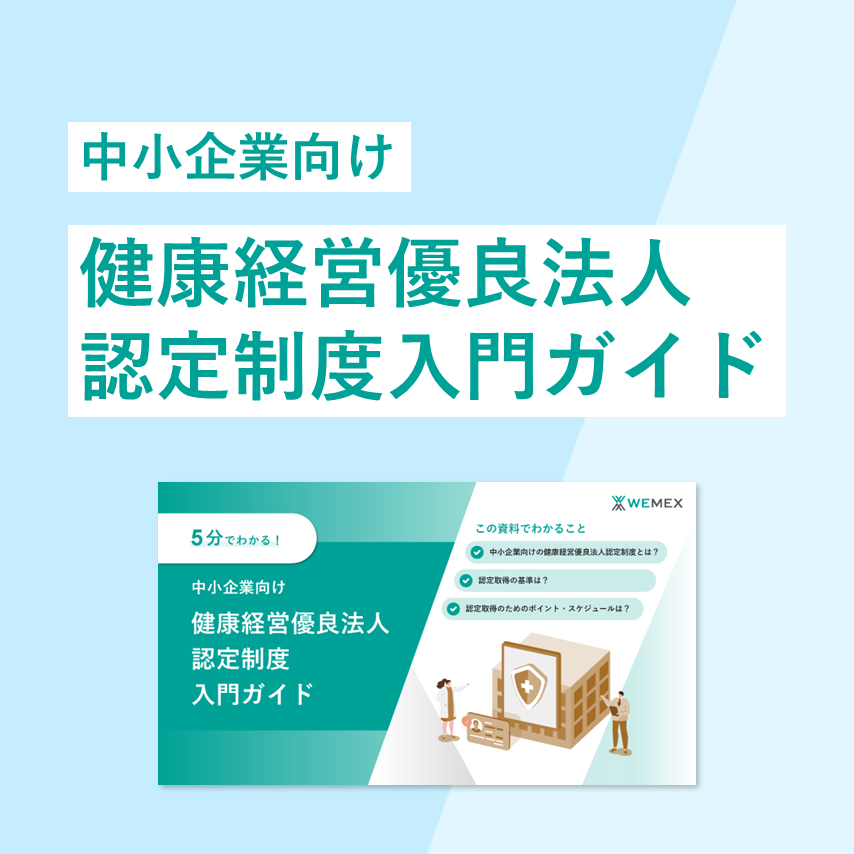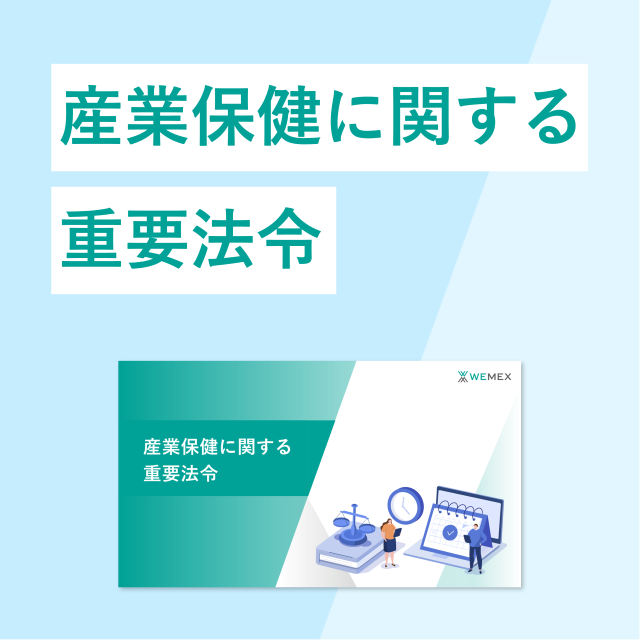目次
うつ病とは

うつ病は、脳のエネルギーが欠乏することで心身の働きに大きな不調をもたらす病気です。一時的な気分の落ち込みとは異なり、自然に回復することが難しく、放置すれば日常生活に深刻な影響を及ぼします。
症状の現れ方や重症度、病型は多様であり、個別の判断と専門的な治療が必要とされます。
うつ病の主な症状
うつ病の代表的な症状には、憂うつな気分や意欲の低下、強い疲労感などの心理的変化があります。さらに、睡眠障害(不眠または過眠)、食欲不振や過食、性欲の低下、頭痛や肩こり、めまい、胃腸の不調などの身体症状を伴うことも少なくありません。
これらの症状は日常生活全般に影響を及ぼし、仕事や学業、家庭生活、人間関係にも深刻な支障をきたします。
うつ病の発症要因と背景
うつ病の原因は完全には解明されていませんが、感情や意欲をつかさどる脳の機能に異常が生じていると考えられています。精神的・身体的ストレスや生活環境の変化が引き金となることが多いですが、結婚や昇進といったポジティブな出来事をきっかけに発症する場合もあります。
また、身体の病気や一部の内科治療薬の副作用が原因となるケースもあります。実際には、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いとされています。
うつ病による休職は就業規則の定めが必要
うつ病など私傷病による休職制度を適切に運用するためには、就業規則に明確なルールを定めておくことが不可欠です。
休職制度は法律で義務付けられているものではなく、企業が自由に設計できる仕組みです。ただし、休職制度がない場合でも、病気やケガで働けなくなった従業員をすぐに解雇することは認められていません。治癒の可能性や必要な療養期間を十分に考慮する必要があり、規定がなければ解雇に関するトラブルが発生するリスクが高まります。このため、多くの企業では就業規則に休職のルールを明記し、制度を整備しています。
発令要件や手続き、休職期間、復職の可否判断の基準などをあらかじめ定めておくことで、労使間のトラブルを未然に防ぎやすくなります。さらに、休職中や復職後の処遇や、リハビリ勤務制度など段階的な支援体制を導入することも重要です。
加えて、診断書の提出や医療情報の取り扱い、費用負担の有無などについても規定を整備することで、透明性の高い運用が可能となります。
従業員がうつ病で休職する場合の対応方法

従業員からうつ病を理由に休職の申し出があった場合は、医師の診断書の提出を必ず求めましょう。
診断書には「病名」「就業不能の理由」「就業できない期間」などが明記されているかを確認し、この内容をもとに対応方針を決定します。精神疾患は外見からは就業可否の判断が難しいため、診断書は休職判断の重要な根拠となります。
なお、診断書の具体的な記載内容は原則として企業側から指示できませんが、必要な情報がある場合は従業員を通じて医師に伝えてもらうと、配慮してもらえることがあります。
その後、診断書をもとに面談を実施し、休職期間や手当、社会保険料、給付金、連絡方法などについて従業員と丁寧に話し合います。休職期間については就業規則や診断書の内容を踏まえて最長期間を説明し、安心して休養できるよう配慮しましょう。連絡手段や頻度については負担を軽減するためメールや書面を基本とし、双方が合意したルールに基づいて進めます。
関連記事:適応障害による従業員の休職―企業が取るべき対応・フォローと再発防止策を解説
休職に入る従業員に面談で説明すること
従業員がうつ病で休職する際は、事前に面談を行い、休職期間や給与・手当、社会保険、連絡体制、退職に関する規定などを丁寧に説明することが重要です。ここでは、面談で伝えるべき主なポイントを解説します。
休職期間
休職期間は、就業規則および医師の診断書に基づき決定し、その内容を従業員に明確に伝える必要があります。一般的に、軽度のうつ病では約1か月、中等度で3〜6か月、重度の場合は1年以上の休養が目安とされます。状況に応じて柔軟に期間を設定すること、また無理なく回復できる環境づくりに配慮しましょう。
連絡手段・頻度・内容
休職中の連絡方法や頻度は従業員と相談の上、負担の少ない手段を選びましょう。メールや書面で月1回程度のやりとりを基本に、連絡内容は体調報告や必要手続きなど必要最小限とします。また、連絡窓口を担当者ひとりに限定するなど、従業員が安心して対応できる体制を整えることも大切です。
給与や手当
休職中は無給となる場合が多く、その点を丁寧に説明しましょう。なお、社会保険の被保険者であれば健康保険から傷病手当金が支給され得るため、その申請方法や制度の詳細についても詳しく案内し、従業員の不安を軽減できるようサポートします。
社会保険
休職期間中も社会保険の資格は原則として継続しますが、保険料の納付義務が発生します。多くの企業では、企業が一時的に保険料を立て替え、復職後に給与から精算する方法を採用しています。この仕組みを事前に十分に説明し、理解を得てください。
退職のリスク
休職期間満了後、復職できない場合は自然退職や解雇となることが就業規則に定められている場合があります。こうした規定についても、休職の開始時に丁寧に説明し、従業員が将来の選択肢を理解できるように配慮しましょう。
休業中に支給される傷病手当金
傷病手当金は、仕事を業務外の病気やケガで休業し、給与が支給されない場合に、生活を保障するために健康保険から支給される制度です。うつ病などの精神疾患による休職も対象となり、一定の条件を満たせば受給が可能です。以下に、傷病手当金の支給条件や支給期間、支給金額について解説します。
傷病手当金の支給条件
この制度は、業務外で発生した病気やケガのために療養し、医師から就業不能と診断された場合に利用できます。受給のためには、まず連続する3日間の待期期間が必要で、その後4日目以降も仕事を休んでいること、さらに休業期間中に給与が支払われていないことが条件となっています。
傷病手当金の支給期間
支給期間は、支給開始日から「通算して」最長1年6か月です。途中で出勤や給与支払いがあった場合、その期間は支給対象外となりますが、実際に傷病手当金が支給された日数の合計が1年6か月に達するまで受給できます。
傷病手当金の支給金額
支給額は「支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」で計算します。おおよそ月給の3分の2が支給額の目安です。標準報酬月額は健康保険の等級に基づくため、実際の金額は個人ごとに異なります。また、給与の一部が支給されている場合は、その差額分のみ支給されます。
休職に入る従業員への対応に関する注意点
休職に入る従業員への対応では、医師の許可や本人の体調を十分に考慮した上で、必要があれば業務の引き継ぎを依頼する場合があります。ただし、無理に出社を求めることは、症状を悪化させたり、法的リスクにつながったりする恐れがあるため、慎重に対応することが重要です。
また、うつ病などの病名や診断内容については、本人の同意なく他の従業員へ開示してはいけません。従業員のプライバシーに十分配慮し、情報管理を徹底することで、信頼関係の維持と職場環境の健全化につながります。
休職中の従業員が復帰を希望する場合の対応方法
休職中の従業員が復職を希望する場合は、まず主治医による「復職可能」の診断書を提出してもらいます。そのうえで、産業医や人事担当者が連携し、復職の可否や必要な支援内容を総合的に判断します。業務内容や勤務時間の調整、段階的な復職プラン(リハビリ勤務)などを検討し、従業員が無理なく職場復帰できる体制を整えることが重要です。
復職後も、業務への適応状況や症状の再発がないかを定期的に確認し、必要に応じて支援内容や職場環境の見直しを行いましょう。
関連記事:復職とは?タイミングと判断基準、注意点をわかりやすく解説
まとめ
従業員がうつ病で休職する際は、医師の診断書や就業規則に基づき、適切かつ柔軟な対応を行うことが重要です。給与や傷病手当金、社会保険料の扱いについても早めに説明し、従業員が安心して療養できる環境を整える必要があります。復職時には、産業医や人事担当者と連携し、段階的な復職計画を立てることで再発防止にもつながります。
従業員のメンタルヘルス不調を予防するには、日頃からストレス状況の把握と職場環境の改善が大切です。ウィーメックスのストレスチェックサービスは、診断結果の分析からフォロー体制の構築まで一括で提供し、企業の健康経営®をサポートします。職場環境の改善に、ぜひご活用ください。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。