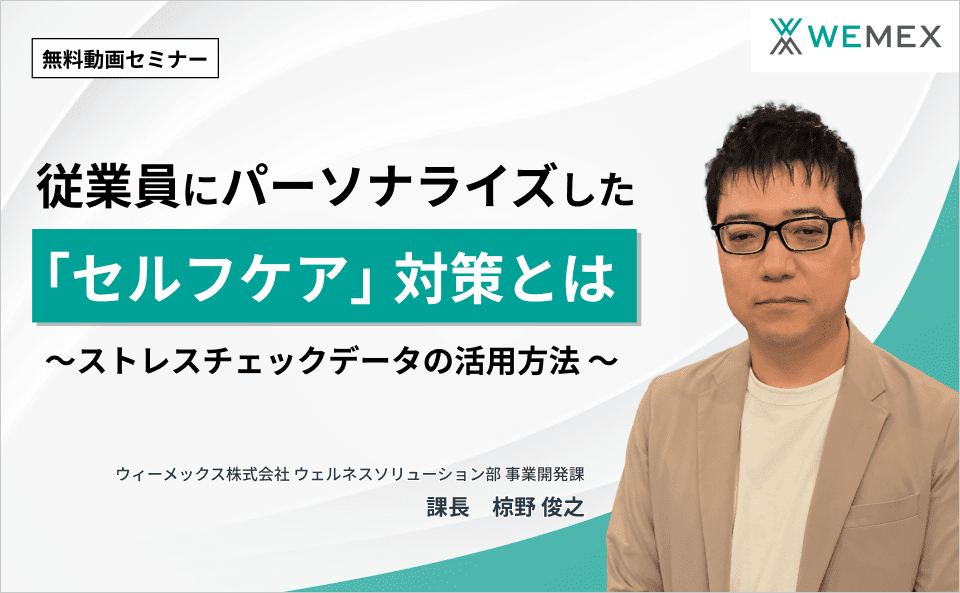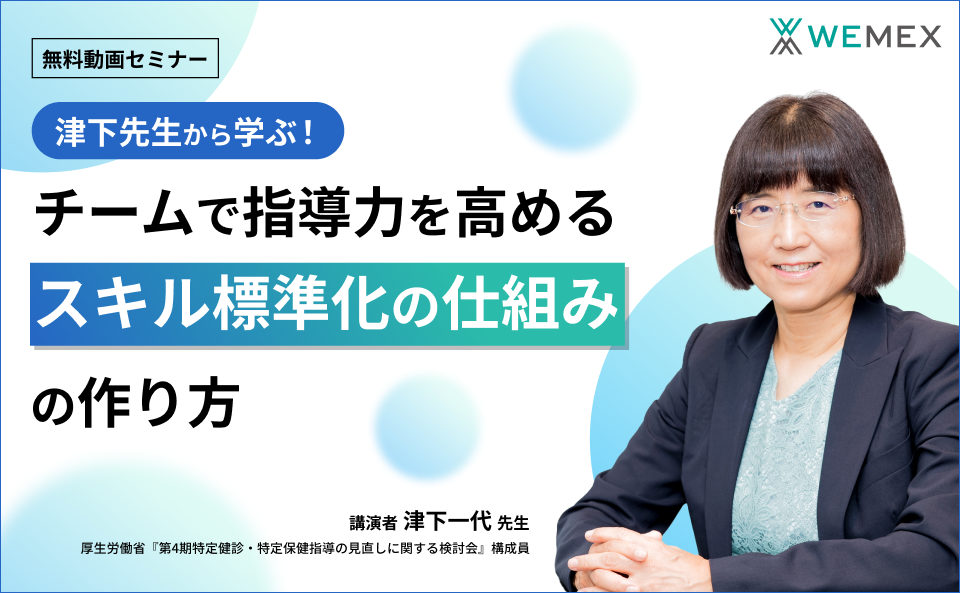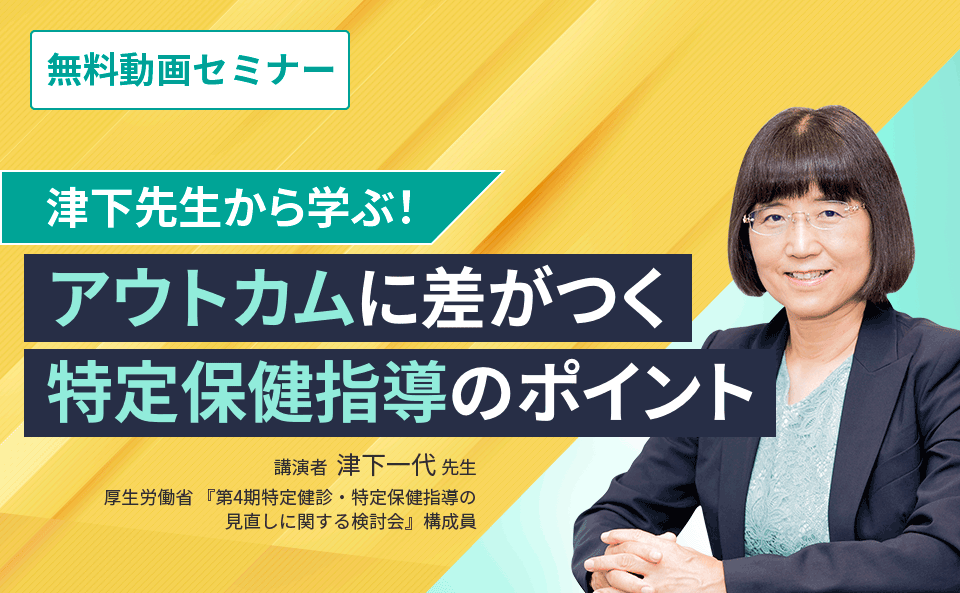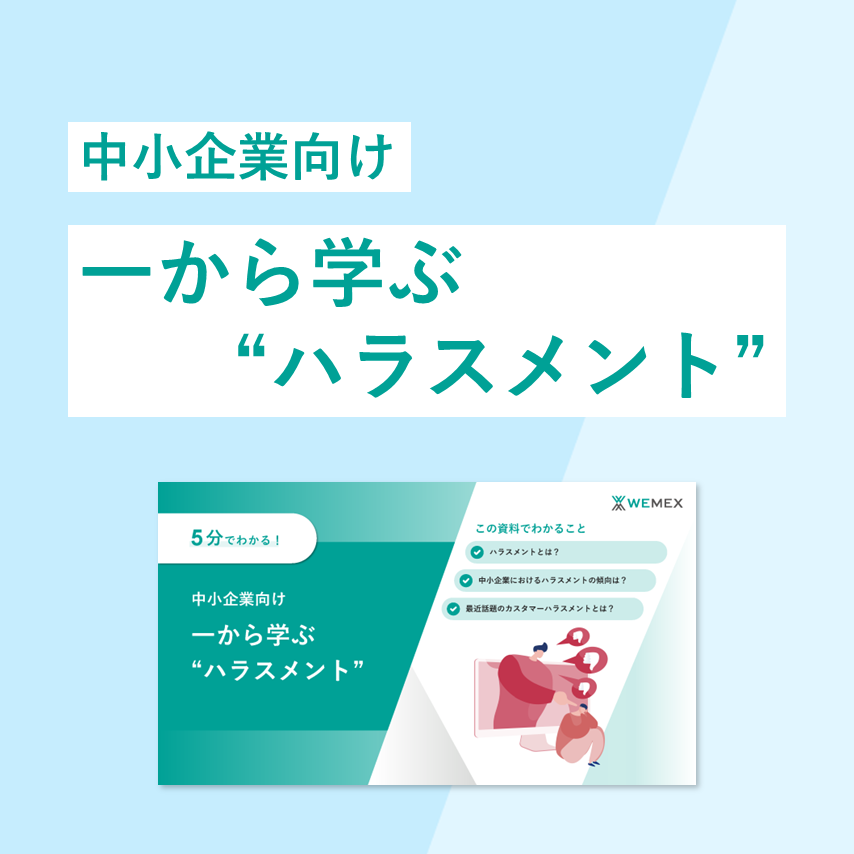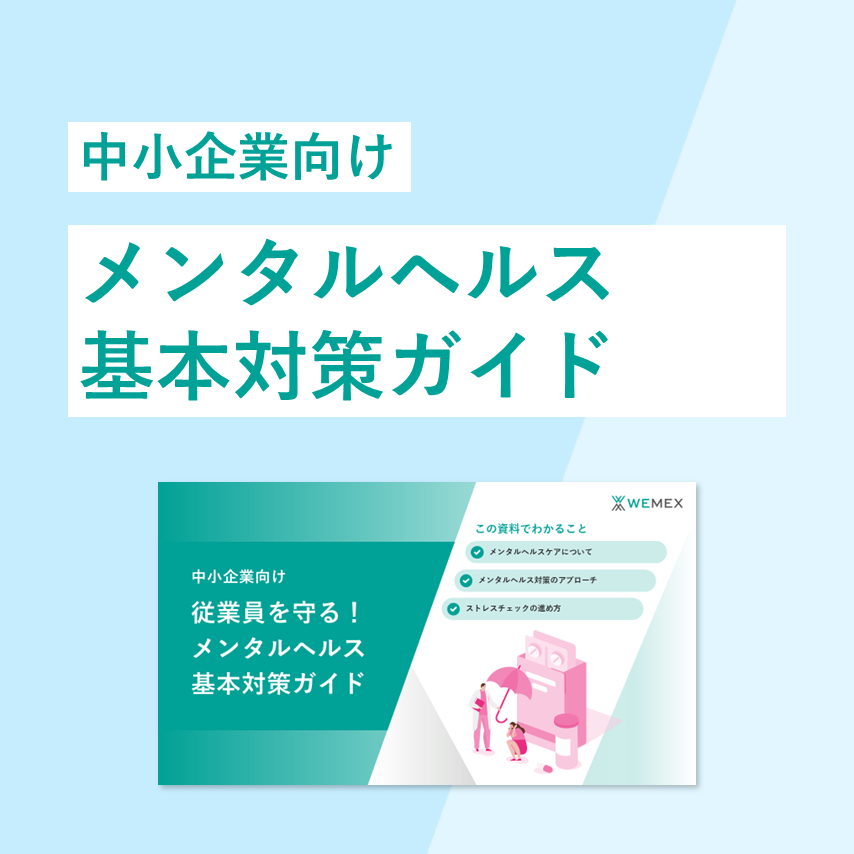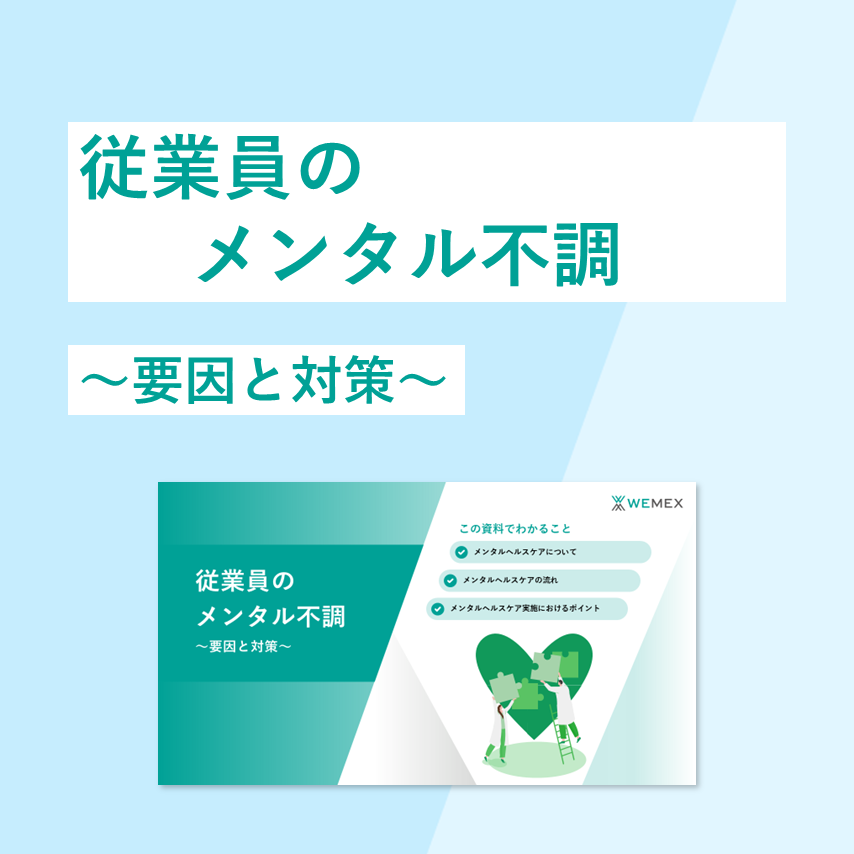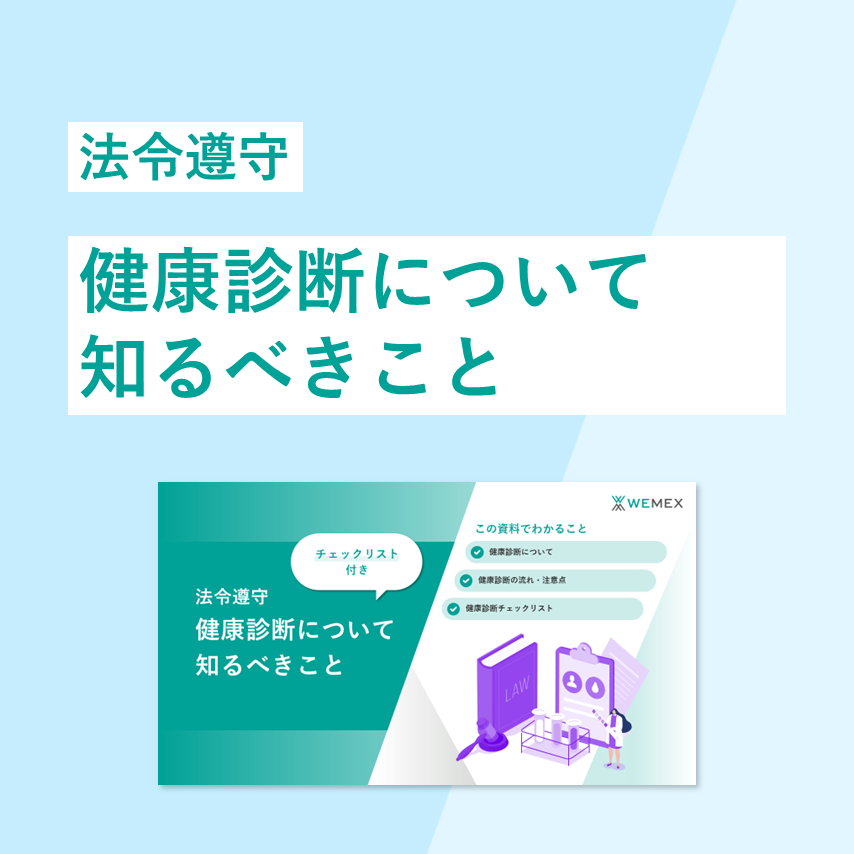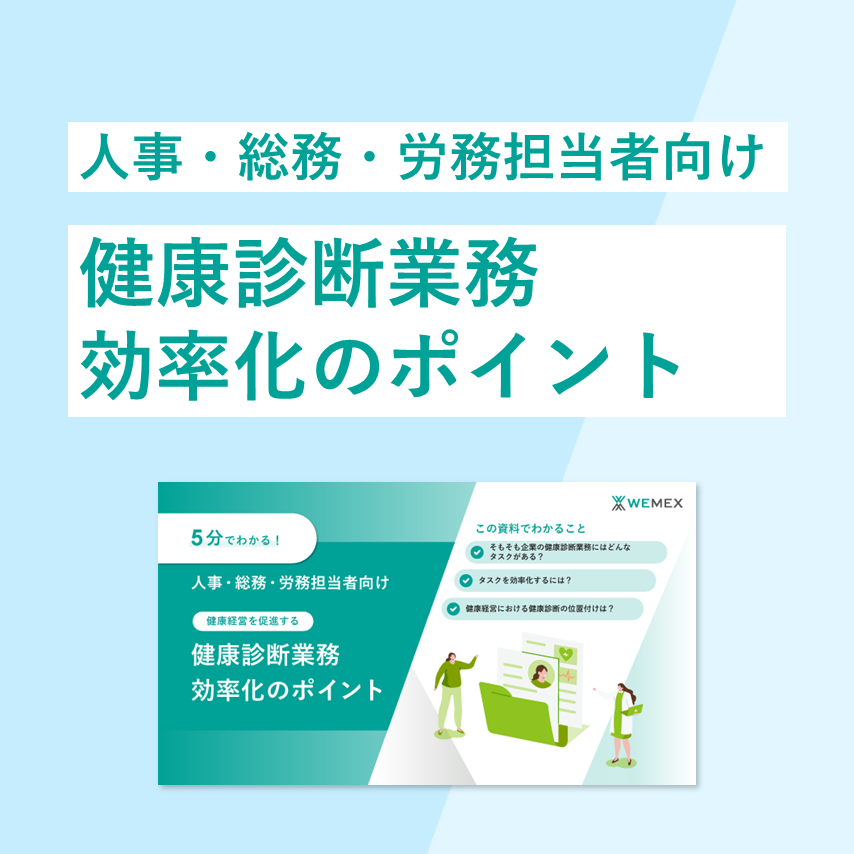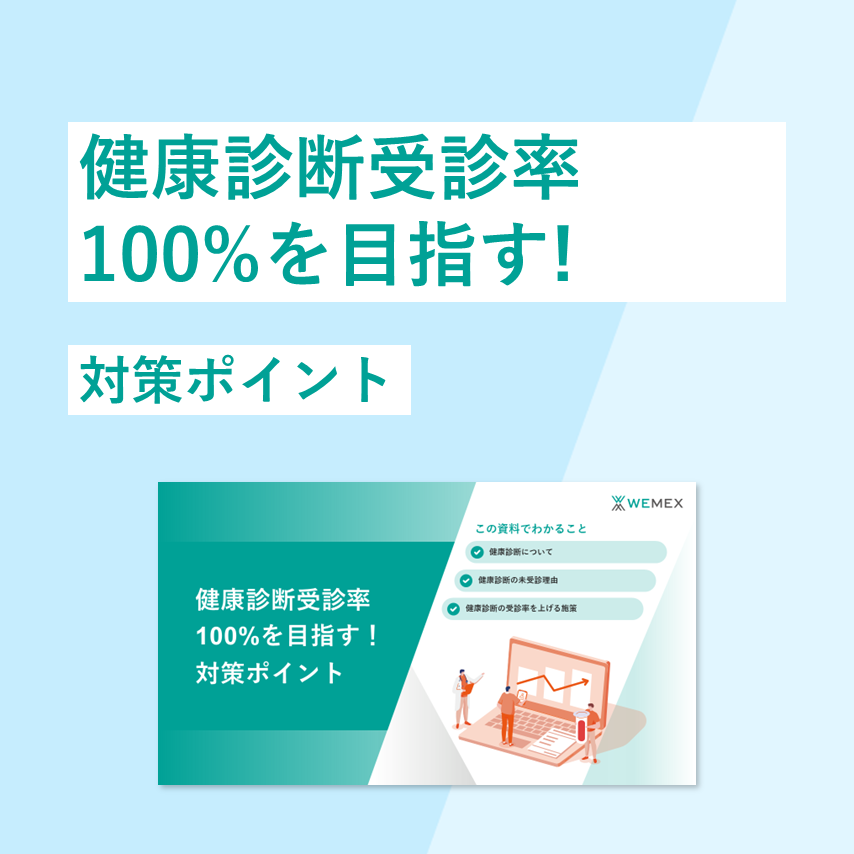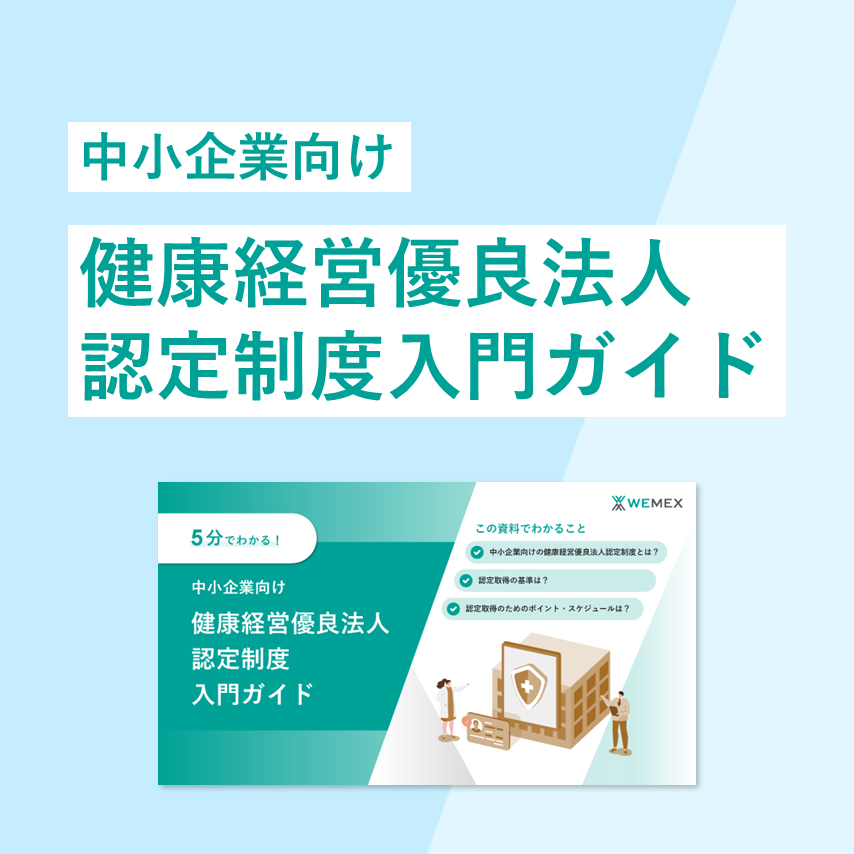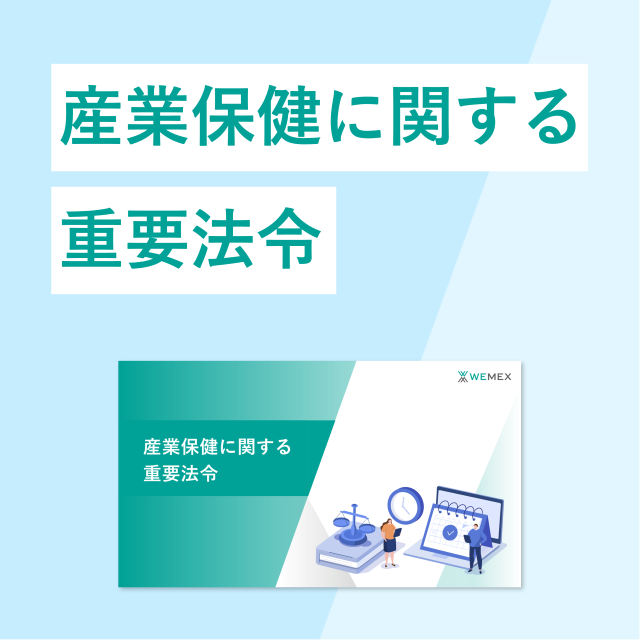復職とは?タイミングと判断基準、注意点をわかりやすく解説
メンタル不調などで休職していた従業員の復職対応は、人事労務担当者にとって非常に慎重な対応が求められる業務の一つです。復職支援に慣れていない担当者の場合、どこから着手すべきか悩むケースも少なくありません。休職からの復職はデリケートな課題であり、対応を誤ると休職期間の長期化や再休職につながるリスクがあります。そこで本記事では、復職の基本事項を整理し、復職のタイミングや判断基準、対応時のポイントを具体的に解説します。従業員が安心して職場復帰できるよう、復職直前から復職後までの適切な支援の流れや注意点を確認していきましょう。
※本内容は公開日時点の情報です
目次
復職とは

復職とは、休職や休業などで一時的に職場を離れていた従業員が、雇用関係を維持したまま再び職場に戻ることを指します。復職の対象となる休職・休業には、企業独自の制度によるものと、育児・介護休業法など法律で定められた制度によるものがあります。
復職を理解するうえで、「休職」と「休業」の違いも重要です。
| 区分 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 休職 | 従業員本人の事情(病気やけが、留学など)により、一定期間就労を免除されるが、雇用関係は継続される状態 | 病気やけがによる長期療養、留学など |
| 休業 | 会社都合や法律に基づき、従業員に労働の意思・能力があっても就労できない状態 | 設備故障による一時帰休、産前産後休業、育児休業、介護休業など |
復職制度とは
復職と似た言葉に「復職制度」があります。復職制度とは、一度退職した従業員を再び雇用する企業独自の制度を指します。休職や休業中の従業員が職場に復帰する「復職」とは異なります。職場に復帰する従業員へのサポートは「職場復帰支援」と呼ばれます。
なお、一度退職した従業員を再び雇用する制度として、以下のようなものがあります。
- カムバック制度:自己都合で退職した方が再雇用を希望した場合に、再度雇用する制度
- ジョブリターン制度:結婚や育児、介護などを理由に退職した方を再雇用する制度
職場復帰支援の重要性
職場復帰支援とは、病気やけが、特にメンタルヘルス不調などで休職している従業員が、円滑に職場へ復帰できるようサポートする取り組みです。
このうち、精神疾患などによる休職者を対象とした復職支援プログラムは「リワーク支援」とも呼ばれます。
職場復帰支援には、目的や提供主体に応じてさまざまな種類があり、従業員のスムーズな職場復帰に欠かせません。主な支援の種類は以下の通りです。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 医療リワーク | 医療機関(主に精神科や心療内科)で医師や看護師などによって行われる、医学的リハビリテーションを中心とした復職支援プログラム |
| 職リハリワーク | 地域障害者職業センターが実施する、職場への適応や就労継続を目的とした職業リハビリテーション |
| 職場リワーク | 企業内で実施される復職支援で、試し出勤や短時間勤務などを通じて、実際の職場環境に慣れながら復職を目指す取り組み |
| 福祉リワーク | 障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所などが提供する、社会復帰や就労を目指すための支援プログラム |
復職のタイミングと判断基準
復職のタイミングや期間は、休職した原因によって異なります。代表的な3つのケースについて、根拠や期間の目安を確認しましょう。
| 種類 | 概要 | 根拠 | 復職のタイミング | 休業期間 (上限) |
|---|---|---|---|---|
| メンタル不調による休職 | うつ病などにより就労できない場合の休業 | 就業規則 | 主治医や産業医の意見をふまえ、企業が就業可能と判断したとき ※1 | 企業が就業規則で定めた期間(例:3か月~3年)※3 |
| 育児休業 | 1歳未満の子を養育するための休業 | 育児・介護休業法 | 従業員が申し出た期間を過ぎたとき(通常は子が1歳に達する時)※2 | 子が1歳に達するまで(最大2歳まで延長可) |
| 介護休業 | 要介護状態の家族を介護するための休業 | 育児・介護休業法 | 従業員が申し出た期間を過ぎたとき | 通算93日間 |
※1 メンタル不調による休職の場合、復職の判断は主治医や産業医の意見が重視されますが、最終的には企業が職場環境や業務内容を考慮して決定します。
※2 育児・介護休業は法律で期間が定められており、原則として期間満了後に復職となります。
※3 傷病休職の期間上限は企業ごとに異なり、就業規則で規定されています。
休職から復職までの流れ
休職から復職までの流れは、休職の理由や根拠、就業規則の定めによって異なります。ここでは、うつ病などメンタル不調による休職から復職までの一般的な流れを解説します。
休職手続き
まず、休職前に必要な手続きを行います。主な流れは以下のとおりです。
- 従業員が、うつ病などにより休職が必要とする診断を主治医から受ける
- 従業員が会社へ休職を希望する旨を申し出る
- 主治医による診断書を会社へ提出する
- 従業員と人事担当者や管理監督者、必要に応じて産業医が面談を行う(就業規則に基づく)
- 休職届などの必要書類を従業員が提出する
- 会社が休職を正式に決定し、休職開始
関連記事:適応障害による従業員の休職―企業が取るべき対応・フォローと再発防止策を解説
復職診断書の提出・社内手続き
復職の手続きは、従業員から復職の意向連絡を受けてから始まります。主な流れは以下の通りです。
- 従業員から復職の意思表示がある
- 主治医が作成した復職診断書を会社へ提出する
- 会社は診断書の内容を確認し、必要に応じて産業医による面談・意見聴取を実施する
-
従業員・産業医・人事担当者・管理監督者などで面談を行い、以下の点を確認する
・ 本人の体調や生活状況
・ 復職希望日
・ 業務内容や勤務時間の希望・配慮事項 - 産業医・会社が総合的に復職の可否を判断する
産業医との面談
メンタル不調からの復職の場合、主治医の診断書や意見だけでなく、産業医との面談も不可欠です。産業医は、主治医の診断内容や従業員の体調・生活状況、職場環境や業務内容を総合的に評価し、「職場で安全かつ安定して働ける状態か」「復職時に必要な配慮は何か」を医学的・実務的観点から確認します。
産業医面談は、復職の可否を決めるだけでなく、復職後の働き方やサポート体制を検討するための重要なプロセスです。なお、産業医には従業員を復職させる権限はなく、主治医・産業医・本人の意見を総合し、最終的には企業が復職の可否を判断します。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
職場復帰支援プランの策定
産業医面談の後は、従業員や主治医・産業医の意見、人事担当者や管理監督者の見解などを総合し、職場復帰支援プランを作成します。このプランは、従業員が安心して復職し、再休職を防ぐために重要です。
作成時には、以下の点を検討しましょう。
- 復職日
- 復職後の業務内容や就業上の配慮(時短勤務、フレックス勤務、業務量の制限、段階的な復職=慣らし勤務等)
- 人事労務管理上の対応(配置転換や異動の必要性など)
- 主治医・産業医からの意見
- 管理監督者や同僚によるフォローアップ体制
- その他(試し出勤制度の導入など)
プラン策定には、従業員本人、管理監督者、人事労務担当者、産業保健スタッフが連携して取り組むことが重要です。厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」も参考になります。
職場復帰の決定・フォローアップ
職場復帰支援プランができたら、主治医・産業医の意見をふまえ、企業が復職日や業務内容、必要な配慮を最終決定し、従業員に通知します。
復職後は、管理監督者や産業医・産業保健スタッフによる定期的な面談や経過観察を行い、従業員の体調や勤務状況を確認します。必要に応じて職場復帰支援プランを見直し、再休職の防止や円滑な職場復帰を支援しましょう。
フォローアップ期間を設け、段階的に通常業務へ戻れるよう目標を立てることも有効です。
復職時の注意点

メンタルヘルス不調による休職の場合、復職日が決定しただけで終わりではありません。従業員が再び体調を崩し休職に入ることがないよう、復職時の注意点を確認しましょう。
復帰時の面談
復帰時の面談では、主治医や産業医の意見に加え、本人の意思や職場の受け入れ体制もふまえて、従業員の状態を総合的に確認します。以下の点をヒアリングし、復職後の業務に耐えられるか客観的に判断しましょう。
- 健康状態・疾病の回復状況
- 生活リズムの安定性
- 業務への意欲や職場適応の見通し
- 通勤の可否
復職後の業務内容や勤務条件、必要な配慮についても丁寧に話し合い、本人の不安や希望を聞き取って安心して職場に復帰できるよう支援します。必要に応じて職場環境の整備も検討しましょう。
復職時の仕事内容や配置
復職後は原則として元の職場や職務への復帰を目指しますが、休職の原因が業務内容や人間関係にある場合は、配置転換や業務内容の変更も検討します。
心身への負担を考慮し、短時間勤務や軽作業、試し出勤制度など、段階的な復職も有効です。業務量や労働時間は、本人の状態に合わせて徐々に増やすなど柔軟に対応しましょう。
復帰時の給与や待遇
復職後の給与や待遇は、原則として休職前と同じですが、時短勤務や職務内容の変更がある場合は、就業規則や賃金規程に基づき見直しが必要な場合もあります。給与や待遇が変更になる場合は、必ず事前に内容や理由を説明し、従業員の同意を得てトラブルを防ぎましょう。
社会保険や雇用保険、福利厚生は労働条件が変わらない限り復職前と同様に継続されます。
年次有給休暇は、休職期間中の出勤率が8割に満たない場合は付与されないことがありますが、継続勤務年数には休職期間も含まれます。有給休暇が付与されない場合は、事前に従業員へ説明しましょう。
復職後のフォロー
復職しても、従業員がすぐに万全な状態で働けるとは限りません。復職者の健康状態を継続的に確認し、職場全体で理解と協力を促すなど、フォローが重要です。ここでは、復職後のフォローのポイントを解説します。
復職後の健康状態
復職後も、主治医や産業医と連携し、下記の取り組みを行いながら従業員の健康状態を継続的に確認しましょう。
- 管理監督者・人事担当者・産業医による定期的な面談
- 産業保健サービスの活用
- 必要に応じた業務内容や勤務条件の見直し
特にメンタルヘルス不調の場合、再発や症状悪化のリスクが高いため、復職直後は1週間~1か月に1回程度、その後も1~数か月ごとに定期的な面談や健康チェックを行うことが推奨されます。
復職者の業務負担や治療継続状況も客観的に評価し、不調が見られる場合は職場復帰支援プランの見直しや勤務条件の調整など、柔軟にサポートしましょう。
復職後の周囲への理解
復職した従業員がストレスを感じず安心して働けるよう、職場全体の協力が欠かせません。周囲には過度な配慮は控えつつ、自然な態度で受け入れることを促しましょう。
また、復職者のプライバシーに配慮しつつ、必要に応じて管理監督者や同僚に復職者の状況や配慮事項を説明し、オープンなコミュニケーションが取れる環境を整えます。
一方で、復職者のケアを重視しすぎて周囲に過度な負担がかからないよう、管理監督者や人事担当者が連携し、職場全体のバランスにも配慮しましょう。
復職が難しい場合の企業に求められる対応
メンタルヘルス不調からの復職が難しい場合、まずは医師や産業医の意見をもとに、本当に復職が不可能か慎重に判断する必要があります。
従業員本人が退職を希望する場合は、その意思を尊重し、通常の退職手続きを進めます。ただし、状況によっては本人の意思や今後の働き方について丁寧に確認し、必要に応じて引き留めや相談の機会を設けることも検討しましょう。
また、就業規則に定められた休職期間が満了しても復職が難しい場合には、就業規則の規定に従い「休職期間満了による退職」または「解雇」といった対応を取ることになります。この際、退職や解雇の根拠や手続きを明確にし、従業員に通知することが重要です。
なお、就業規則にこれらの対応を明記し、適切に運用することで、不当解雇などの労働トラブルを防ぐことができます。
まとめ
メンタルヘルス不調で休職していた従業員の復職対応は、人事担当者にとって配慮が必要な業務のひとつです。
復職までの手続きでは、主治医の診断書や産業医の意見、本人の意思、就業規則などを総合的にふまえて復職可否を判断し、産業医や管理監督者との連携、復職後の体制整備が重要となります。
復職後も、定期的な面談やフォローアップ、業務内容や職場環境の見直しなど、継続的なサポートを行うことで、従業員が安心して職場に戻れるよう支援しましょう。
また、従業員のメンタルヘルス不調による休職を未然に防ぐには、職場全体のストレス状況の把握や、早期発見・早期対応が欠かせません。
ウィーメックスでは、メンタルヘルス不調の予防に有効なストレスチェックサービスを提供しています。人事担当者の事務処理の軽減や、従業員一人ひとりに合わせたフォローアップコンテンツの提供も可能です。ご興味のある方は、ぜひご相談ください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf)