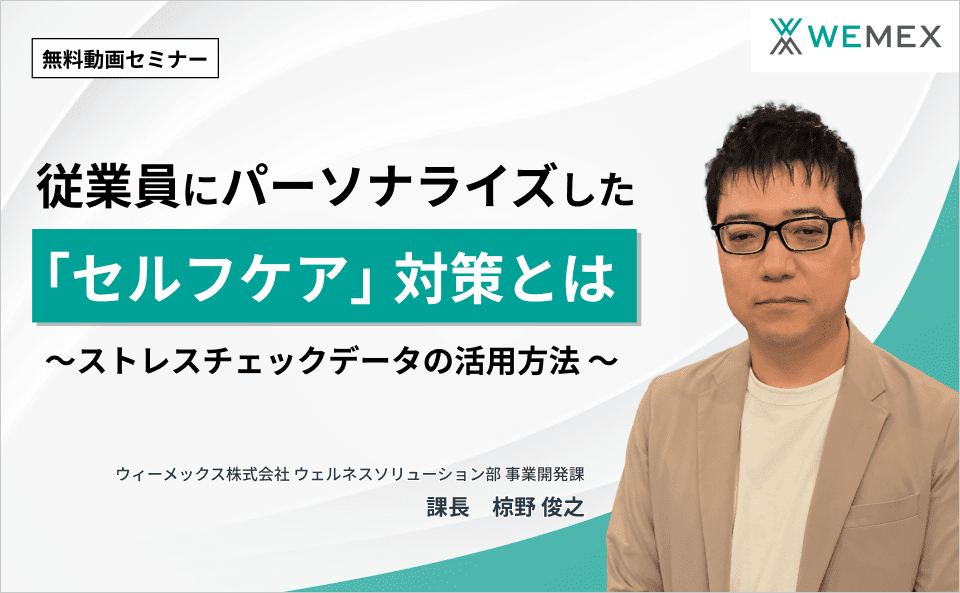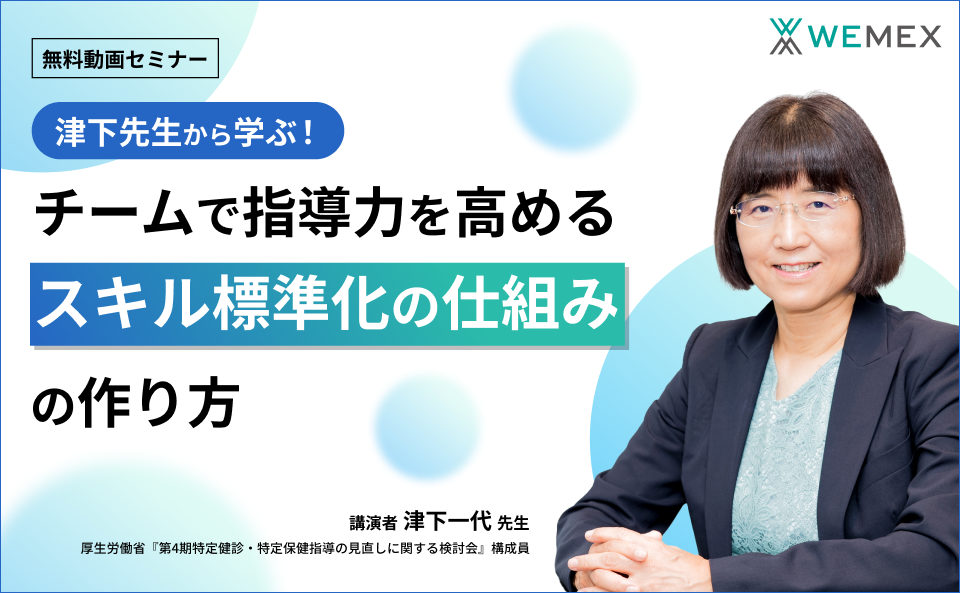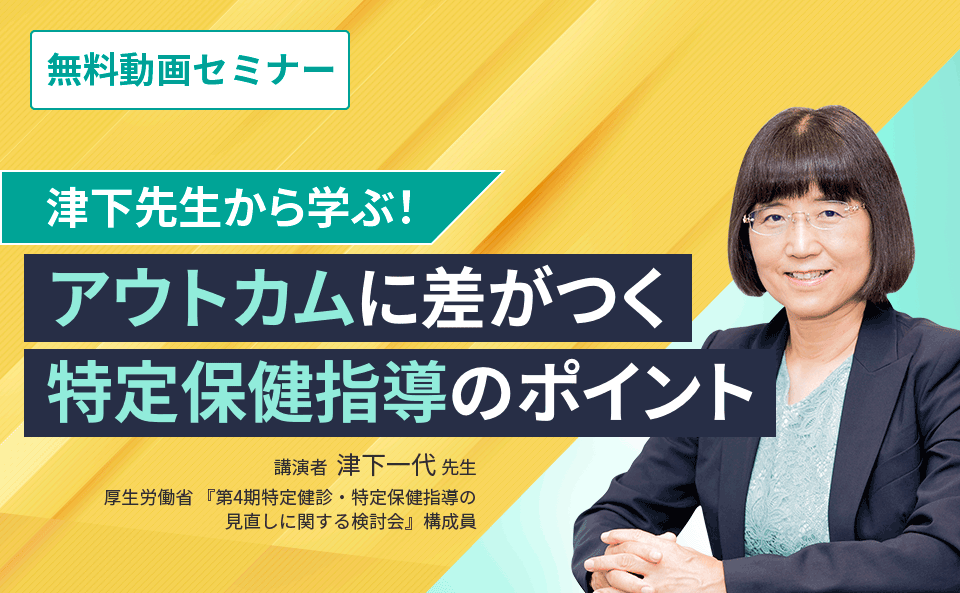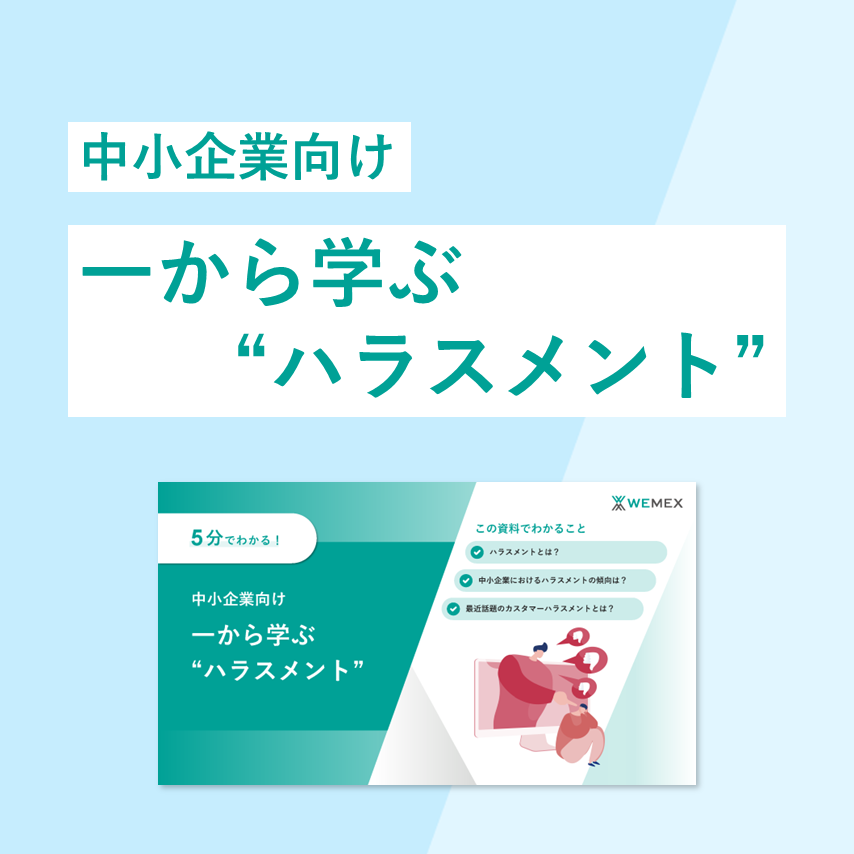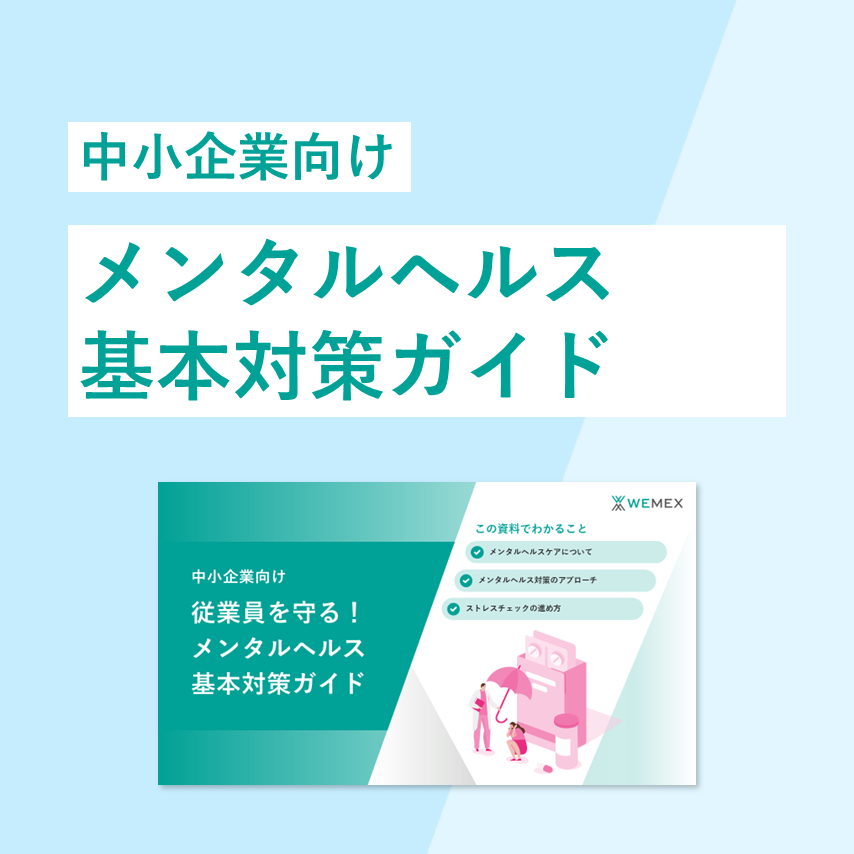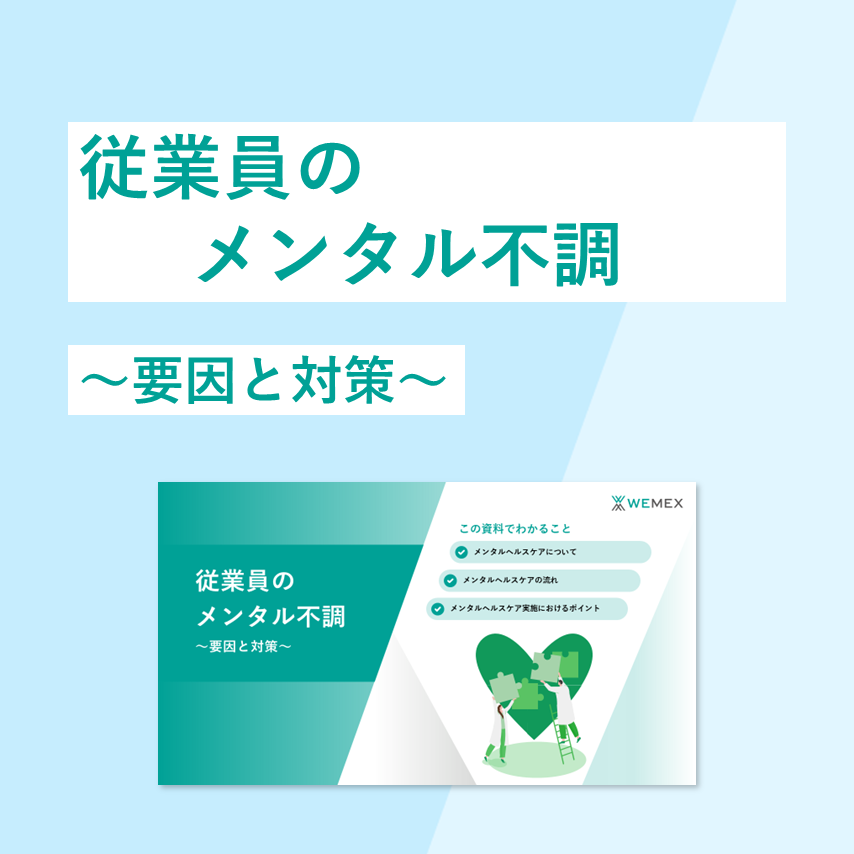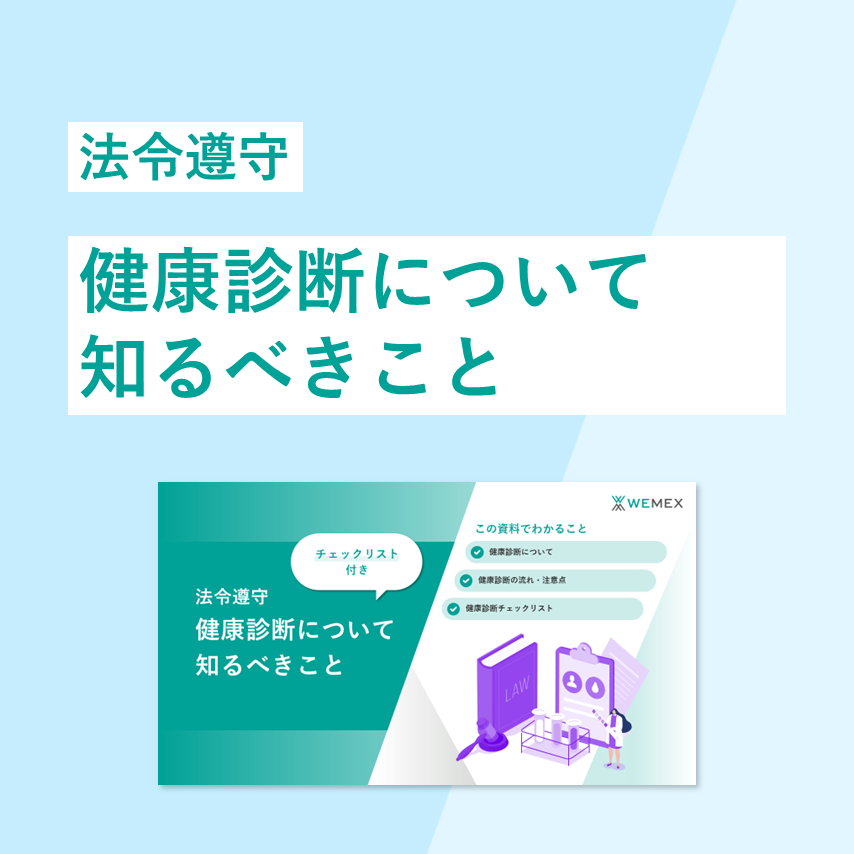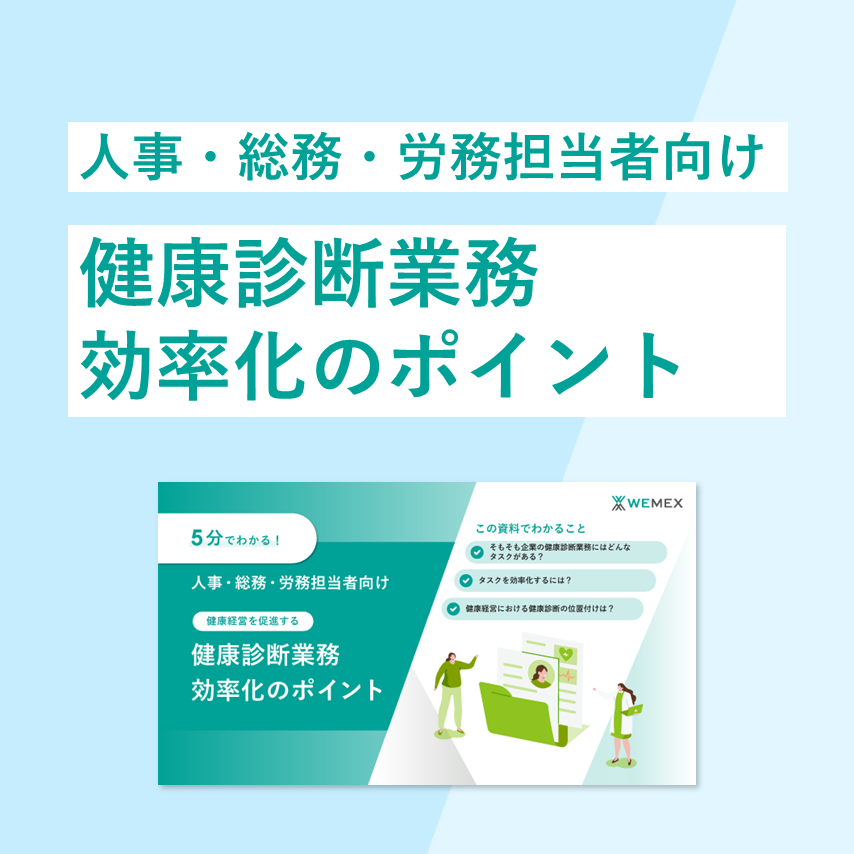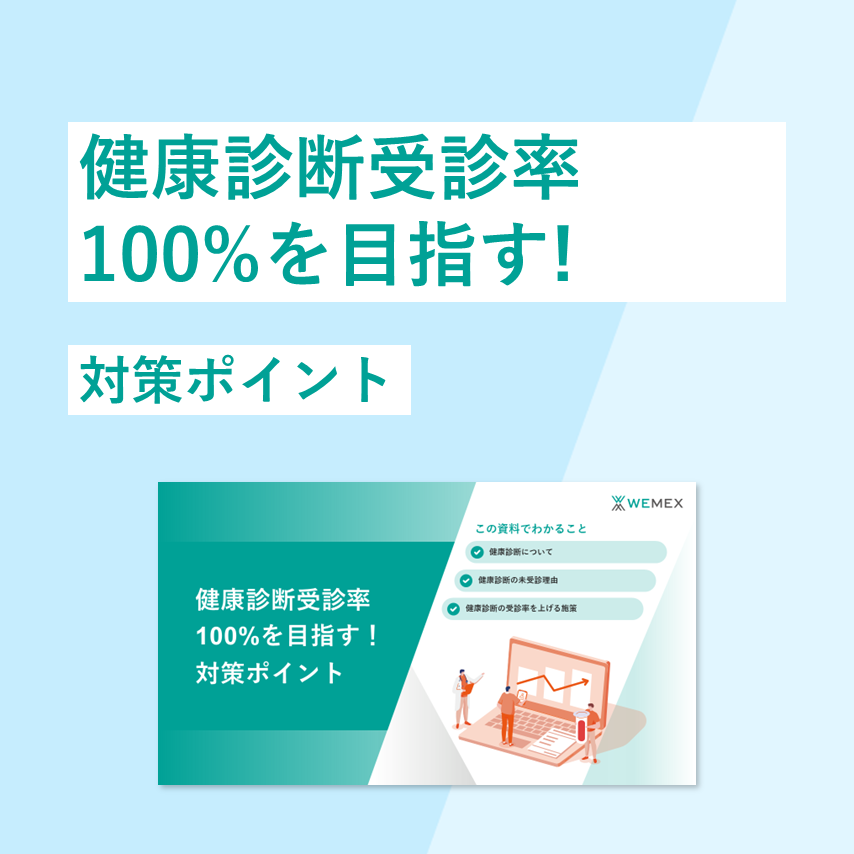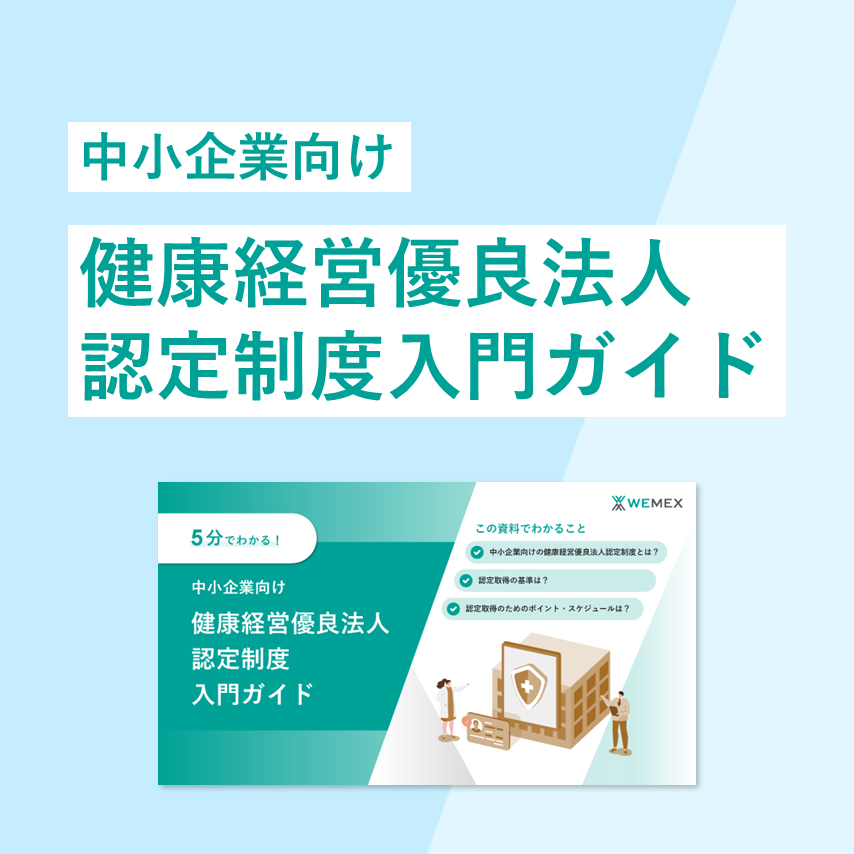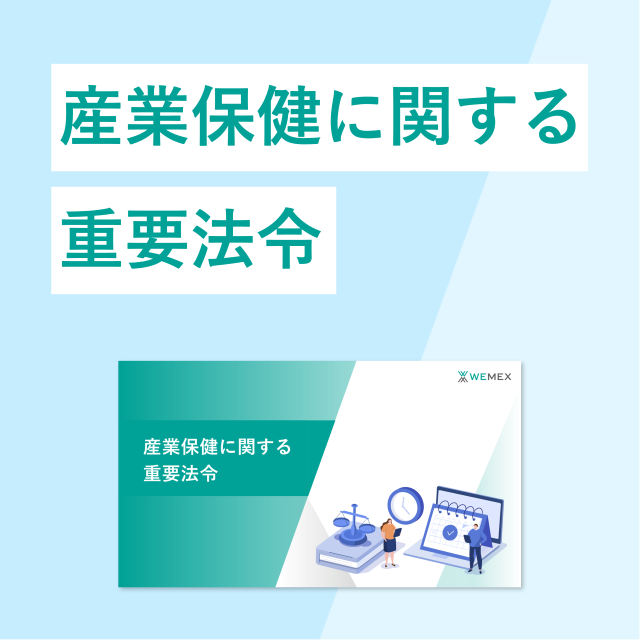目次
ストレッサーとは

ストレッサーとは、ストレスの原因となる外部からの刺激や要因のことを指します。多くの人は「ストレス」と聞くとネガティブな印象を持ちがちですが、ストレッサーには「ユーストレス(良性のストレス)」と「ディストレス(悪性のストレス)」があり、前者はパフォーマンス向上や成長機会に繋がることもあります。ストレッサーが与える影響は必ずしも悪いものだけではありません。強さや持続時間によって、心身への影響は大きく異なります。
例えば、強いストレスが長期間続くと心身に悪影響を及ぼす可能性があり、特に慢性的なストレスの継続は問題視されやすいです。一方、適度な強さで短時間のストレスであれば、成長の糧となるなど、良い影響をもたらすこともあります。
主なストレッサーの種類
ストレッサーにはさまざまな種類があり、それぞれ性質や影響する場面が異なります。主なストレッサーの種類ごとに、生じやすい場面やその影響について紹介します。
物理的ストレッサー
物理的ストレッサーは、室温、照明、騒音など、物理的な環境要因によって引き起こされるストレスです。例えば、暑すぎる・寒すぎる室内や、明るすぎる・暗すぎる照明、騒音のある環境では、集中力や作業効率が低下しやすくなります。
化学的ストレッサー
化学的ストレッサーは、さまざまな化学物質による影響で生じるストレス要因です。例としては以下が挙げられます。
- タバコの煙
- 有機溶剤
- 香水(閉鎖空間での使用など)
- 食事のにおい
- 酸素不足
環境に不快な化学物質が存在する場合だけでなく、酸素が不足している状態なども該当します。有害物質を扱う職場では、特殊健康診断の実施が法的に義務付けられています。
生物的ストレッサー
生物的ストレッサーは、花粉やホコリなどによるアレルギー反応など、生物由来の要因によって生じるストレスです。例えば、花粉症の人にとっては花粉が大きなストレッサーとなります。企業によっては花粉症対策を行っている場合もあります。
心理的ストレッサー
心理的ストレッサーは、時間的制約やノルマ、プレッシャーなど、精神的プレッシャーによって生じるストレスです。例えば、納期や成果の要求、過重な業務量などが該当し、多くの職場で主要なストレッサーとなっています。不安や焦りを感じやすい状況で強まります。
社会的ストレッサー
社会的ストレッサーは、家庭環境や政治・経済情勢、職場の人間関係など、社会的な環境要因によって生じるストレスです。例えば、同僚との対立や上司からのハラスメント、社会環境の急激な変化などが挙げられます。これらも心理的ストレッサーと同じく、職場で大きな割合を占めています。
ストレッサーに対する反応
人はストレッサーに長期間さらされると、さまざまな望ましくない反応が現れることがあります。具体的には、どのような反応が生じるのかみていきましょう。
心理的反応
ストレッサーによって、不安やイライラ、怒り、悲しみなどのネガティブな感情が生じやすくなります。短期間であれば大きな問題にならない場合がほとんどですが、長期間続くと徐々に無気力になり、うつ状態へと進行することもあります。
行動的反応
行動面では、集中力の低下がよくみられます。また、ストレスへの対処として、飲酒や喫煙の量が増える人もいます。引きこもりがちになる、不眠や意欲の低下がみられるといった変化も行動的反応の一つです。さらに、状態が悪化すると出社できなくなったり、アルコール依存症に陥ったりすることもあります。
身体的反応
身体的な反応としては、血圧の上昇や心拍数の増加、筋肉の緊張などが挙げられます。これらの状態が長く続くと、頭痛やめまい、胃痛、下痢などの症状が現れることもあります。心理的・行動的反応とあわせて身体的症状が現れることも少なくありません。
仕事でストレッサーになりやすいものの例
仕事においてストレッサーとなりやすい要素について、いくつか例を挙げて解説します。
業務範囲の曖昧さ

業務範囲が明確でないと、自分がどこまで担当すればよいのかわからず、結果として実際の業務量が増えてしまうことがあります。場合によっては、他の同僚が担当すべき業務まで引き受けてしまうこともあるでしょう。
一方で、自分の業務量が適切かどうか疑問や不満を感じる人も少なくありません。義務感と中途半端な責任感が入り混じり、ストレスの原因になりやすい状態です。
裁量権の低さ
裁量権が低いと、自分の判断で業務を進めることができません。効率的な方法や自分に合ったやり方を思いついても実行できないため、ストレスを感じやすくなります。上司の指示を頻繁に仰ぐ必要があると、「やらされている」と感じてモチベーションも下がりがちです。このような状態が続くと、仕事自体がストレッサーとなってしまうことがあります。
人間関係
上司や同僚、顧客などとの人間関係がうまくいかない場合、大きなストレッサーとなり得ます。特に、パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合は、深刻なストレスにつながります。また、毎日顔を合わせて仕事をする相手との関係が悪いと、長期間にわたってストレスが蓄積されやすくなります。
雇用の不安定さ
派遣社員などの非正規雇用では、雇用やキャリアに対する不安がストレッサーとなりやすく、雇用が継続できなければ収入が途絶え、キャリア形成にも支障をきたします。また、非正規雇用の場合、短期間で仕事内容が変わることも多く、これまでの経験を活かせないことがストレス要因となることもあります。
人事異動
人事異動で所属する部署や支店などが変わると、仕事内容や人間関係も一新されます。新しく覚えることが多く、人間関係の再構築も必要となるため、ストレッサーとなります。
もちろん、変化を前向きに捉え、新たな出会いや仕事内容を楽しめる人もいますが、変化への適応が苦手な人にとっては強いストレスとなる傾向があります。
職場のストレッサーを把握する方法
職場にはさまざまなストレッサーが存在していますが、管理職や人事担当者が必ずしもそれらを十分に把握できているとは限りません。ここでは、職場のストレッサーを把握する主な方法について解説します。
ストレスチェック
ストレスチェックは、従業員に対してアンケートなどを実施し、ストレスの状況を把握する手法です。個々の従業員がどの程度ストレスを抱えているかを数値で評価でき、メンタルヘルス不調の早期発見につながります。
また、従業員が50人以上いる事業場では、年1回のストレスチェック実施が法律で義務付けられています。2025年の法改正により、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化される予定です。
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
集団分析
集団分析は、ストレスチェックの結果を部署や事業場などの単位で集計・分析し、組織全体や部署ごとの傾向を把握するものです。これにより、どの部署にストレッサーが多いか、どのような要因が影響しているかを明らかにできます。
例えば、企業全体でストレスが高い傾向がある場合は企業風土や職場環境が要因となっている可能性があります。一方、特定の部署のみでストレスが高い場合には、その部署の人間関係や業務内容に課題がある場合が考えられます。
職場で行うべきストレッサーへの対処法
職場のストレッサーを把握したら、適切な対処が必要です。では、どのような方法があるのか、具体的にみていきましょう。
定期的な面談の実施
1on1ミーティングなどを通じて、従業員が上司と気軽に対話できる機会を設けましょう。1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行う面談のことで、主な目的は目標の共有や悩みごとの相談、信頼関係の構築などです。
このような面談の中でストレッサーについても相談できれば、早期の問題解決につながる可能性があります。上司は、部下が話しやすい雰囲気づくりや傾聴姿勢を意識することが大切です。
人員配置や業務量の見直し
少人数で業務を回さなければならない場合、従業員に慢性的なストレスがかかることがあります。特定の従業員に負担が集中している場合には、業務分担や内容自体を見直し、必要に応じて人員配置を調整しましょう。
さらに、健康経営®の観点では、各従業員の能力や適性を考慮して業務配分を見直すだけでなく、「ワークエンゲージメント」を高める取り組み(例:職務満足度を向上させる施策等)もストレスの軽減につながります。
まとめ
ストレッサーとは、ストレスの原因となる刺激のことです。職場では、業務範囲の曖昧さや裁量権の低さ、人間関係などがストレッサーとなることがあります。過度なストレスが長期間続くと、メンタルヘルスの悪化につながるため十分な注意が必要です。人事担当者には、職場のストレッサーを適切に把握し、迅速に対処することが求められます。
職場のストレッサーを把握するには、ストレスチェックの実施が重要です。ウィーメックスでは、企業向けにストレスチェックサービスを提供しております。集団分析にも対応しておりますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。