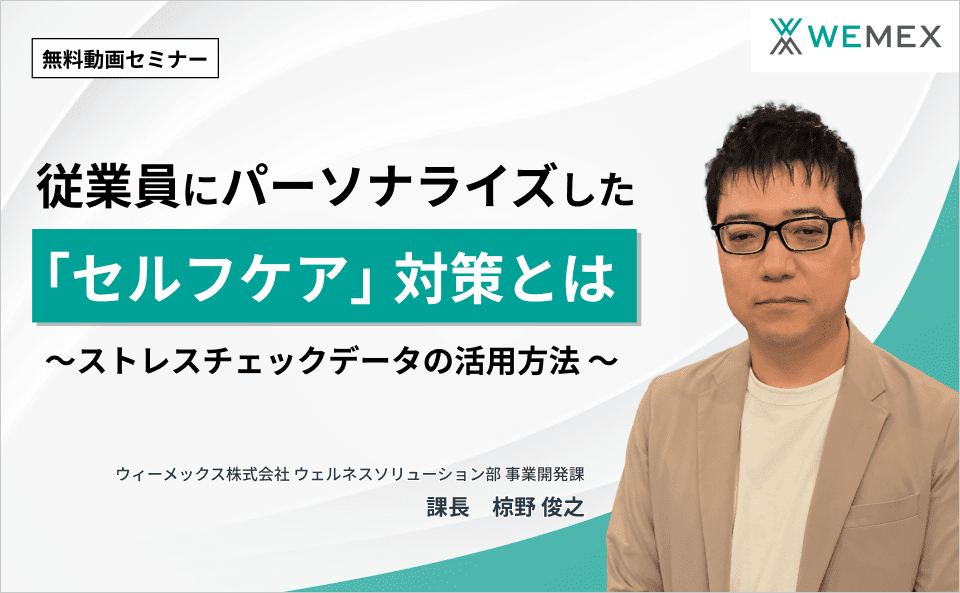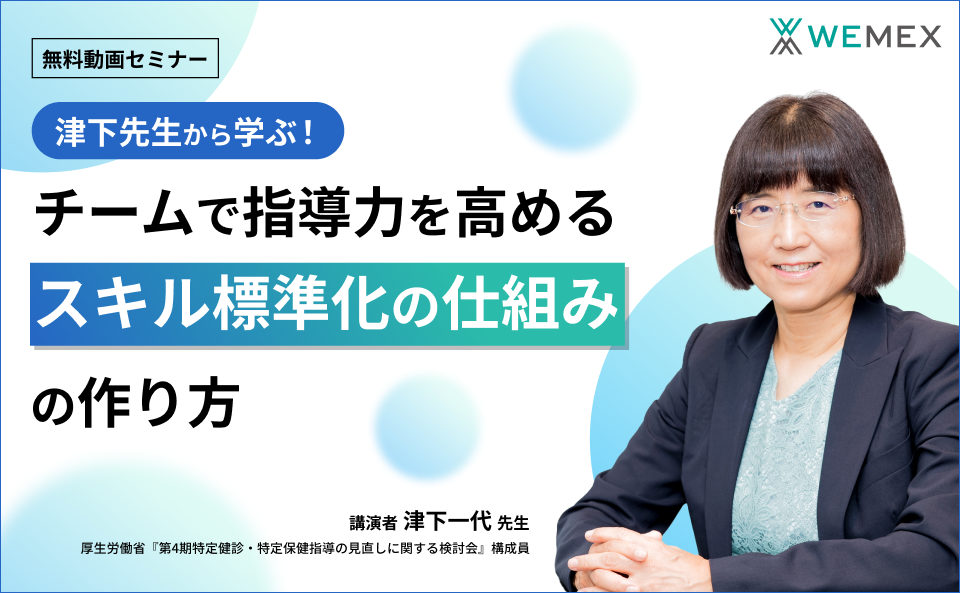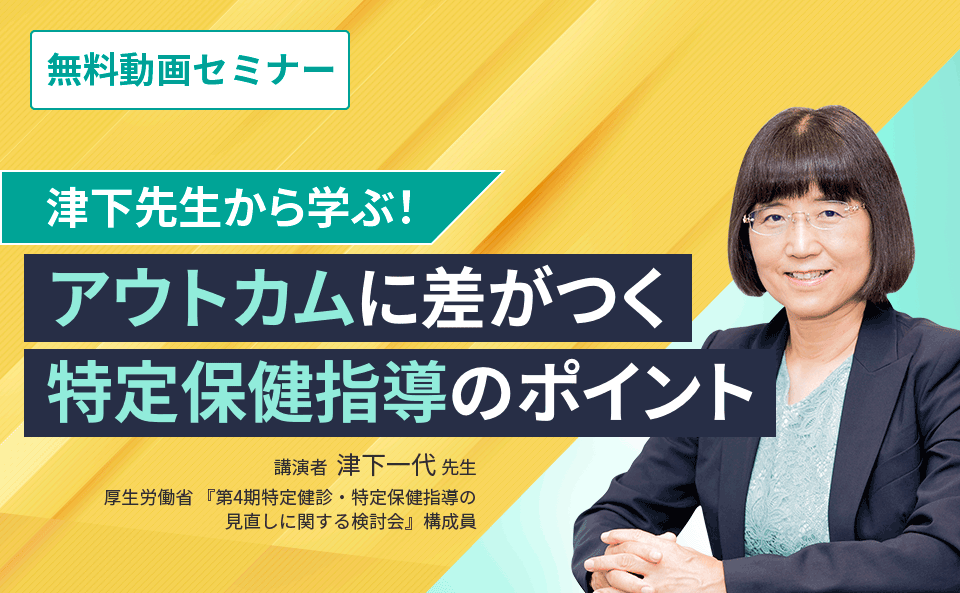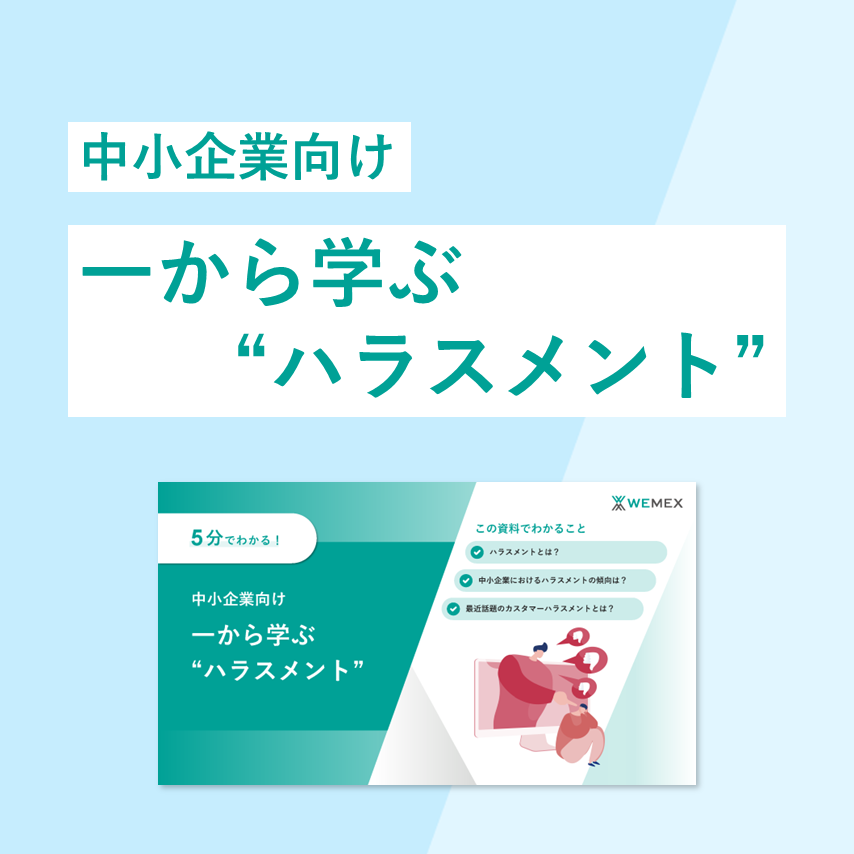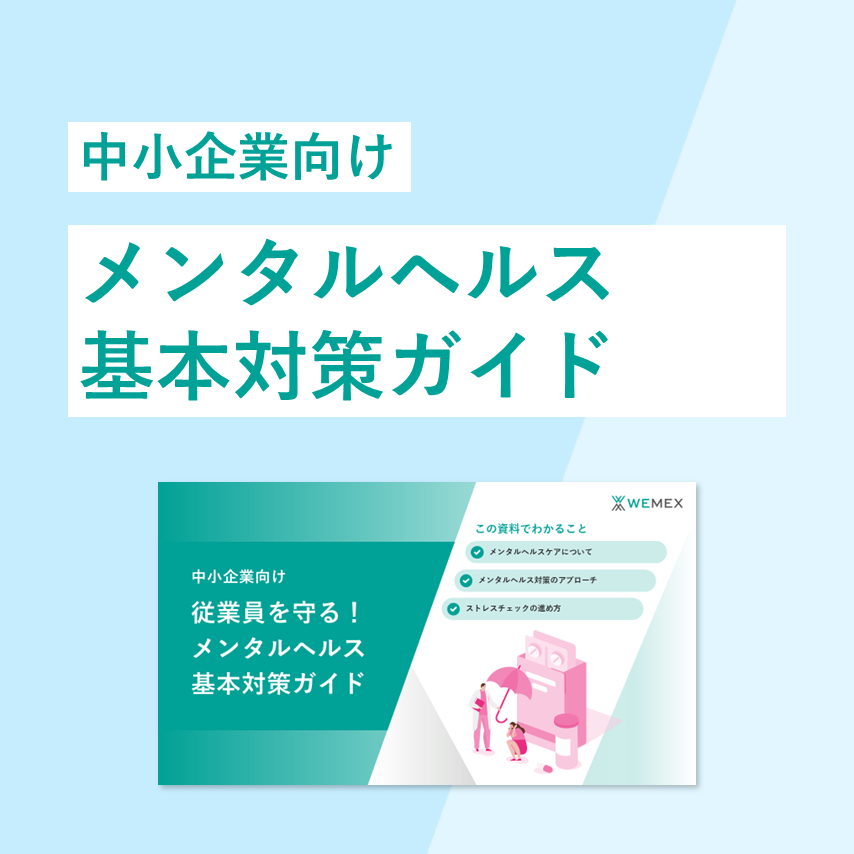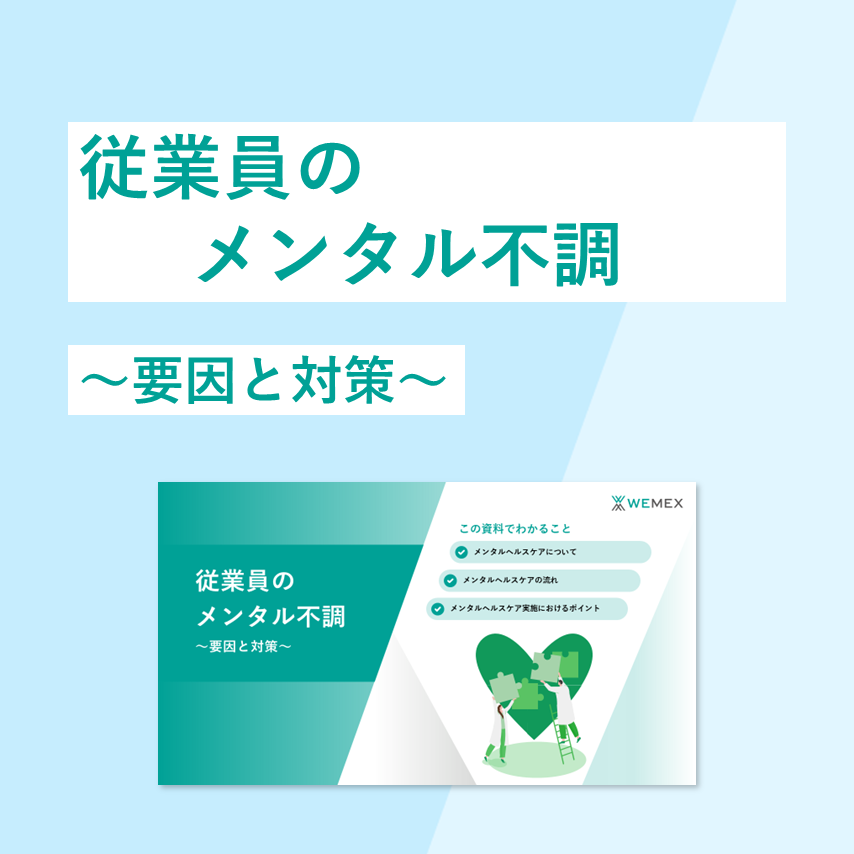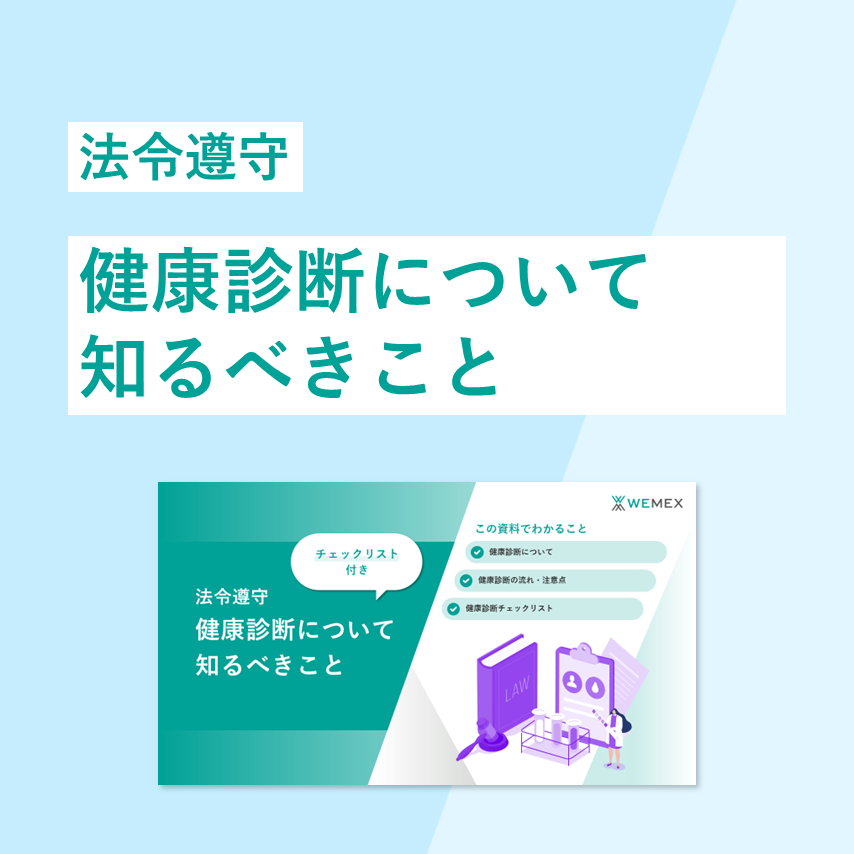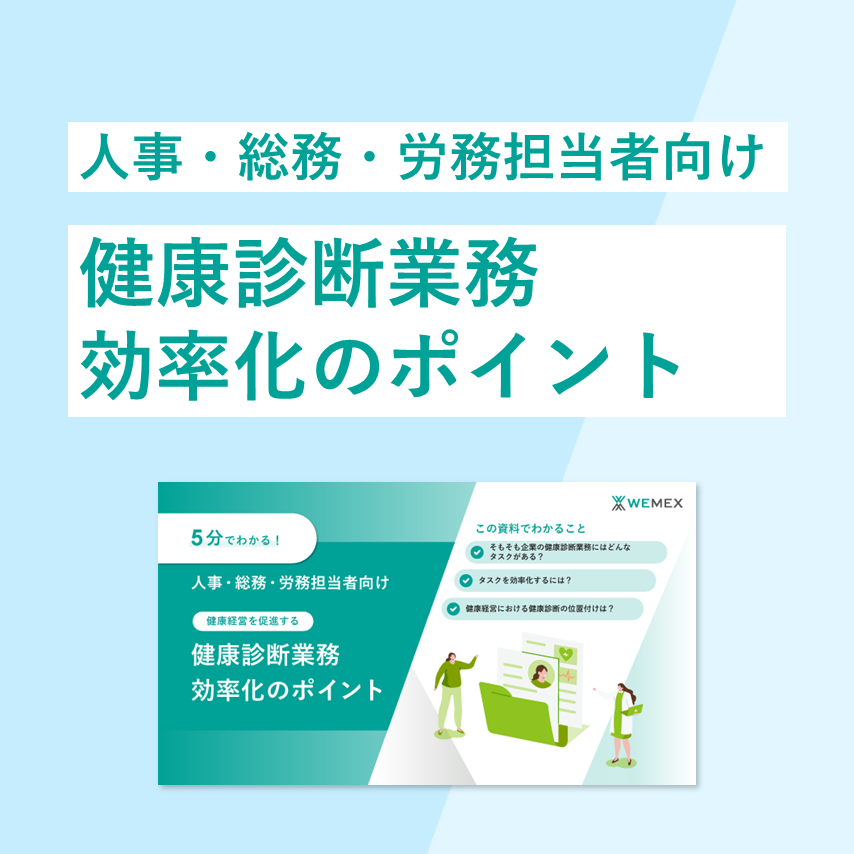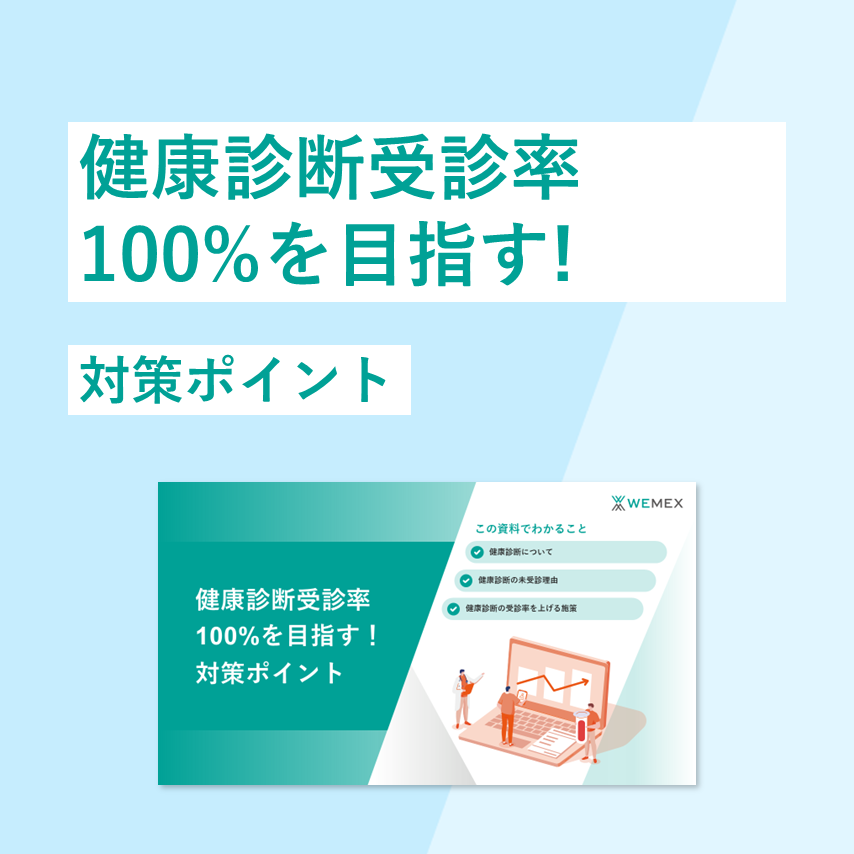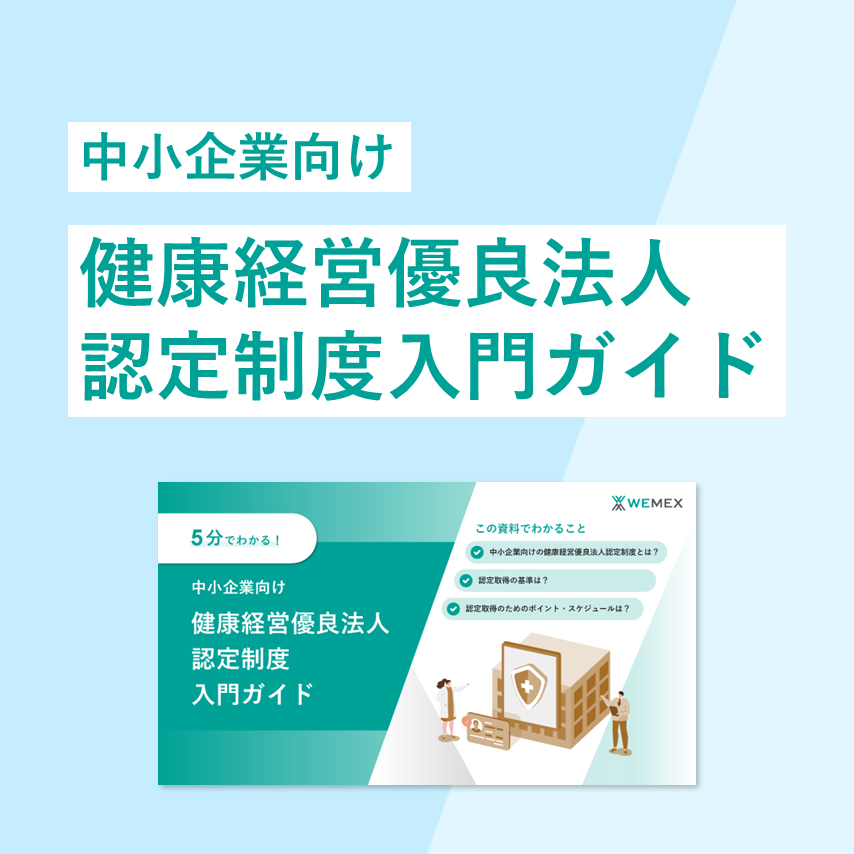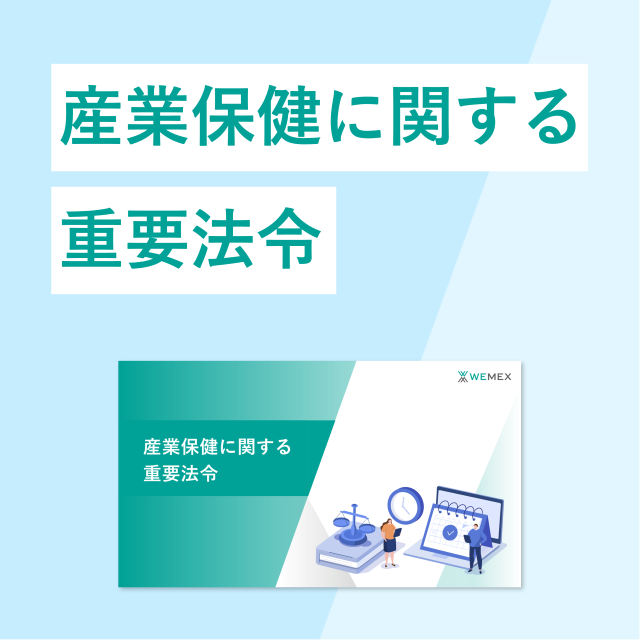目次
適応障害とは

適応障害とは、ある特定のストレス要因に直面したことで、情緒面や行動面にさまざまな反応が現れ、日常生活や社会的な機能に大きな支障をきたす状態を指します。
ここでいう「ストレス」とは、「重大な生活上の変化」や「ストレスに満ちた出来事」などを指します。何がストレスとなるかは人それぞれ異なり、ある人にとって深刻な出来事でも、他の人にはさほど影響を及ぼさない場合もあります。
適応障害の特徴は、このような出来事によって強い抑うつ気分や不安、心配が続き、自分ではコントロールできなくなることです。その結果、職場や学校、家庭などでの生活に適応することが困難になります。
次に、適応障害の症状や要因について詳しく見ていきましょう。
適応障害の症状
適応障害の症状は、「精神面」「身体面」「行動面」の3つに分類されます。代表的な症状は以下のとおりです。
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| 精神面 |
・やる気の低下 ・気分の落ち込み ・感情の起伏が激しくなる ・不安や焦りが強まる |
| 身体面 |
・慢性的な疲労感 ・不眠 ・食欲不振 ・頭痛や腹痛 ・めまい、動悸など |
| 行動面 |
・飲酒・喫煙・過食の増加 ・集中力の低下 ・ぼんやりする ・物忘れが増える |
ストレス要因が解消されることで、通常は6か月以内に症状が改善します。ただし、ストレスが長期間続く場合は、症状が持続するリスクが高まります。
適応障害の要因
適応障害の主な要因には、転職や異動、結婚・離婚、身近な人の死、病気の発覚、災害の被災など、生活の中で生じる大きな環境変化や出来事が挙げられます。こうした出来事に直面した際、うまく対応できず心理的な圧迫を受けることで、適応障害を発症するリスクが高まります。また、個人の性格やこれまでの経験、周囲からのサポート体制の有無なども発症に影響します。
適応障害による従業員の休職
従業員が適応障害を発症した場合、企業には適切な対応が求められます。無理に業務を継続させると、症状の悪化や長期離脱につながるリスクがあるため、状況に応じた休職対応が重要です。ここでは、メンタル不調による休職の実態や、休職制度の基本的な運用について解説します。
メンタル不調による休職者の割合と休職期間
近年、メンタルヘルス不調により休職する従業員は増加傾向にあります。厚生労働省の「労働安全衛生調査(令和5年)」によると、適応障害を含むメンタル不調により、1か月以上休職した従業員がいる事業所の割合は10.4%となっています。
また、「主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究」によれば、メンタル不調による平均的な休職期間は107日(約3.5か月)とされており、短期間での復帰が難しいケースも少なくありません。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
就業規則で定められた休職制度を適用
休職制度は労働基準法などの法律で一律に定められているものではなく、各企業の就業規則に基づいて運用されるのが原則です。そのため、制度の内容を明文化しておくことが、トラブル回避の観点からも重要です。
たとえば、傷病による休職の対象範囲、休職期間の上限、通算規定(繰り返しの休職への対応)、復職の判断基準などについて、事前に規定しておく必要があります。
また、休職期間の設定は、企業の規模や代替要員の確保状況、業務への影響などを踏まえて、実態に即した内容にすることが望ましいでしょう。
適応障害の休職期間の決め方
適応障害による休職期間を決定する際は、主治医の診断書に記載された意見と、自社の就業規則に定められた休職制度の両方を照らし合わせることが基本です。
また、精神疾患の場合には、企業の安全配慮義務の観点からも、産業医の意見を取り入れることが重要です。産業医は、主治医の診断内容や本人の状況、職場環境などを総合的に評価し、企業側に医学的な助言を行います。
従業員から提出された診断内容を正確に把握した上で、休職の可否や期間を慎重に判断します。本人が復職の意思を示していても、症状が十分に回復していない場合も多いため、主治医と産業医の両方の意見を参考にしながら、最終的な判断を行うことが望ましいでしょう。
また、休職期間の判断にあたっては、主治医の意見だけでなく、産業医による面談や本人との面談を通じて治療の内容や生活状況なども確認することが重要です。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
従業員の適応障害による休職への対応

従業員が適応障害と診断され、休職の申し出があった場合、企業には冷静かつ迅速な対応が求められます。適切な手続きを踏まずに進めると、後々のトラブルや労務リスクにつながる可能性があるため、事前に定めた社内ルールや就業規則に則った対応が必要です。ここでは、休職対応の初期段階で企業が行うべき基本的な対応を解説します。
診断書および書類の受理
従業員から提出された診断書は、速やかに人事部門や上司に共有します。診断書は、休職の可否や期間、今後の対応方針を判断するための重要な書類です。書類の受理と情報共有はできる限り迅速に行い、適切な対応につなげましょう。
面談の実施
診断書を受理した後は、対象従業員との面談を行い、今後の手続きや制度について丁寧に説明します。休職中の連絡手段や頻度、やりとりの内容、社会保険料の取り扱い、復職時の連絡方法など、本人が安心して療養に専念できるよう、必要な情報を分かりやすく伝えることが大切です。また、面談では業務の引き継ぎについても確認しましょう。
傷病手当金・休業補償への対応
休職理由が業務外の疾病である場合、健康保険による傷病手当金の対象となります。一方、業務中の負傷や職場環境が原因で発症した場合は、労災保険による休業補償給付の対象となる可能性があります。
いずれの場合も、従業員が適切な給付を受けられるよう、人事・労務部門が必要な手続きをサポートしましょう。
従業員の休職後のフォロー
休職からの円滑な復職や再発防止のためには、企業による継続的なフォローが不可欠です。ここでは、休職後の従業員への基本的なフォロー方法について解説します。
定期的な連絡
休職中の従業員には、月に1回程度を目安に定期的な連絡を行い、病状や生活の様子を確認することが大切です。連絡の目的は、業務復帰を促すことではなく、不安の軽減や必要な支援の継続にあります。過度な連絡は逆効果となるため、事前に頻度や方法を取り決めておくと良いでしょう。
無理のない範囲で情報交換を行い、従業員との信頼関係を保つことが、スムーズな復職につながります。
復職に向けた調整
休職期間が終わりに近づいた段階では、本人の意思を確認し、復職準備を進めます。主治医や産業医の意見を取り入れながら、復職が適切かどうか企業として客観的に判断する必要があります。
無理な復帰は再発リスクを高めるため、段階的な業務復帰(リワークプログラムや短時間勤務など)や業務内容の調整も検討しましょう。復職支援プランを作成し、本人・主治医・産業医・人事担当者が内容を共有・合意することが重要です。
退職・解雇時の適切な対応
適応障害が長期化し、治癒が難しい場合には退職を検討せざるを得ないこともあります。その際は、就業規則に明確な退職ルールを定めておくことが前提です。
「自然退職」として扱う場合でも、実質的に企業都合となる場合は解雇予告や予告手当の支払いが必要となることがあります。また、発症原因が業務にある場合や、主治医が復職可能と判断している場合は、解雇制限が適用されるため、法的リスクを十分に検討し、慎重な対応が求められます。
関連記事:復職とは?タイミングと判断基準、注意点をわかりやすく解説
適応障害による従業員の休職を防ぐポイント
適応障害による休職を未然に防ぐためには、日頃から従業員のストレス状況や心身の変化に注意を払い、早期に対処することが重要です。企業としては、メンタルヘルス対策を制度として整備するだけでなく、現場レベルで実効性のある取り組みを行うことが求められます。
ここでは、適応障害による従業員の休職を防ぐための主なポイントを紹介します。
ストレスチェックの実施・活用
定期的にストレスチェックを実施し、従業員が自身のストレス状況を客観的に把握できるようにします。ストレスチェックの結果は、個人へのフィードバックだけでなく、集団分析を行うことで職場全体のリスク要因や傾向を把握し、組織的な環境改善に役立てることができます。
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
セルフチェック・セルフケアの促進
従業員自身が心身の不調に早期に気づけるよう、「心身の疲労に関するチェックシート」などのツールを活用したセルフチェックを推奨します。また、ストレスやメンタルヘルスに関する基礎的な研修を実施し、セルフケアの知識や習慣を身につける機会を設けることも効果的です。
関連記事:メンタルヘルス研修はなぜ必要?実施するメリットや効果を高める方法も解説
ラインケアの強化
現場の上司や管理監督者が中心となる「ラインケア」は、メンタルヘルス対策の要です。日常的に部下の勤務態度や表情、業務効率、体調の変化などに注意を払い、異変に気づいた場合は早期に声をかけることが大切です。
【「いつもと違う」変化の例】
・ 遅刻、早退、欠勤が目立つ
・ 無断欠勤が発生する
・ 残業や休日出勤が増える
・ 業務効率が低下し、成果に悪影響が出る
・ 報告・相談・会話が極端に減る、または増える
・ 表情や動作に元気がない、または異常に高揚している
・ 判断力や思考力が低下し、ミスや事故が増える
・ 身だしなみに乱れが見られる
こうした兆候を見逃さないためには、日頃から部下の勤務状況や性格の傾向を把握しておくことが不可欠です。
関連記事:ラインケアでは何を行うべき?実施するメリットや注意点も解説
相談窓口の設置
メンタルヘルス不調の予防には、ストレス要因の早期発見と軽減が重要です。従業員が不調を感じた際に、気軽に相談できる窓口を設置し、社内外の専門家(産業医、カウンセラー等)と連携できる体制を整えましょう。
また、全従業員への周知や、相談しやすい雰囲気づくりも欠かせません。メンタルヘルス担当者が定期的に面談を行い、悩みや不安、人間関係の問題などを丁寧に聞き取ることで、ストレスの蓄積や深刻化を防ぐことができます。
従業員の適応障害への再発防止に向けて
復職後も適応障害の再発を防ぐためには、企業による継続的かつ多面的な配慮が欠かせません。まずは、業務量や業務内容について、主治医や産業医、本人と十分に相談し、無理のない形で段階的な業務復帰ができるよう調整しましょう。
復職直後だけでなく、慣れてきた後も定期的な面談やフォローを実施し、本人の状態や職場環境を継続的に確認・見直すことが大切です。業務の過重や人間関係によるストレスが再び蓄積しないよう、上司や産業保健スタッフとも連携し、サポート体制を整えましょう。
また、ストレスチェックや相談窓口の運用、職場環境の改善など、組織全体でメンタルヘルス対策を継続的に実施することが、再発防止と従業員の安心感につながります。必要に応じて、職場復帰支援プランの見直しやカウンセリングの活用も有効です。
まとめ
適応障害は誰にでも起こりうる心の不調であり、企業には従業員の変化に早期に気づき、適切に対応する姿勢が求められます。制度に沿った休職・復職対応はもちろん、日常的なストレスチェックの活用や相談体制の整備など、予防と再発防止の取り組みが重要です。
ウィーメックスでは、健康経営に欠かせないストレスチェックの実施から分析・従業員ケアまでを一貫して支援し、企業様の運用負担を大幅に軽減します。
従業員の心の健康を守る仕組みづくりに、ぜひWemex ストレスチェックをご活用ください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo01.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/hojokin/dl/28_14010101-02.pdf)