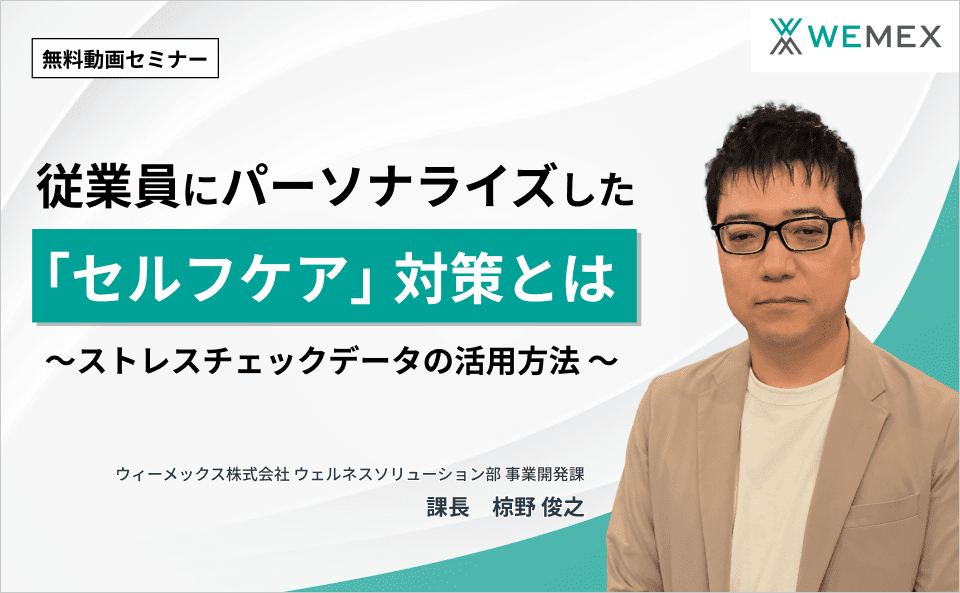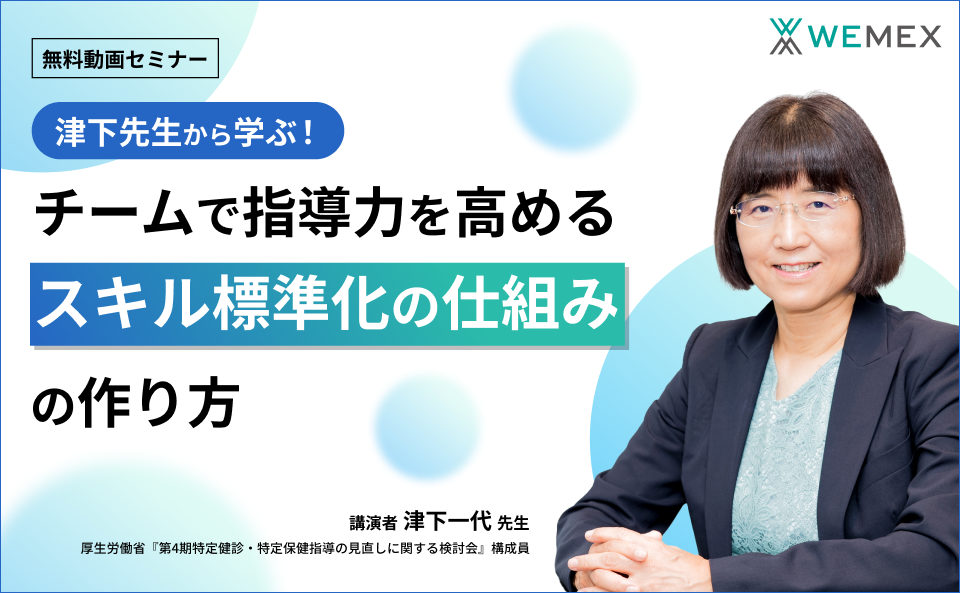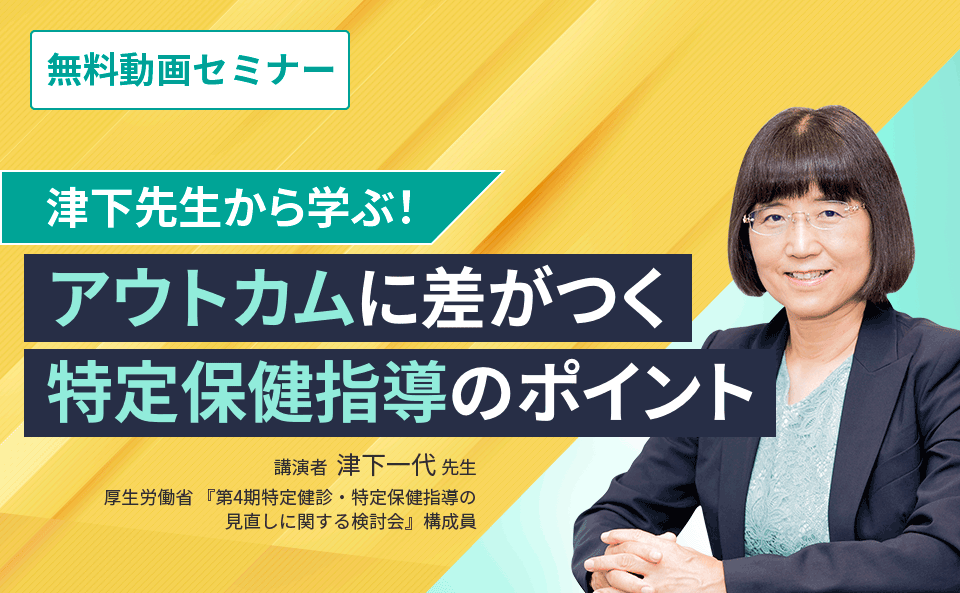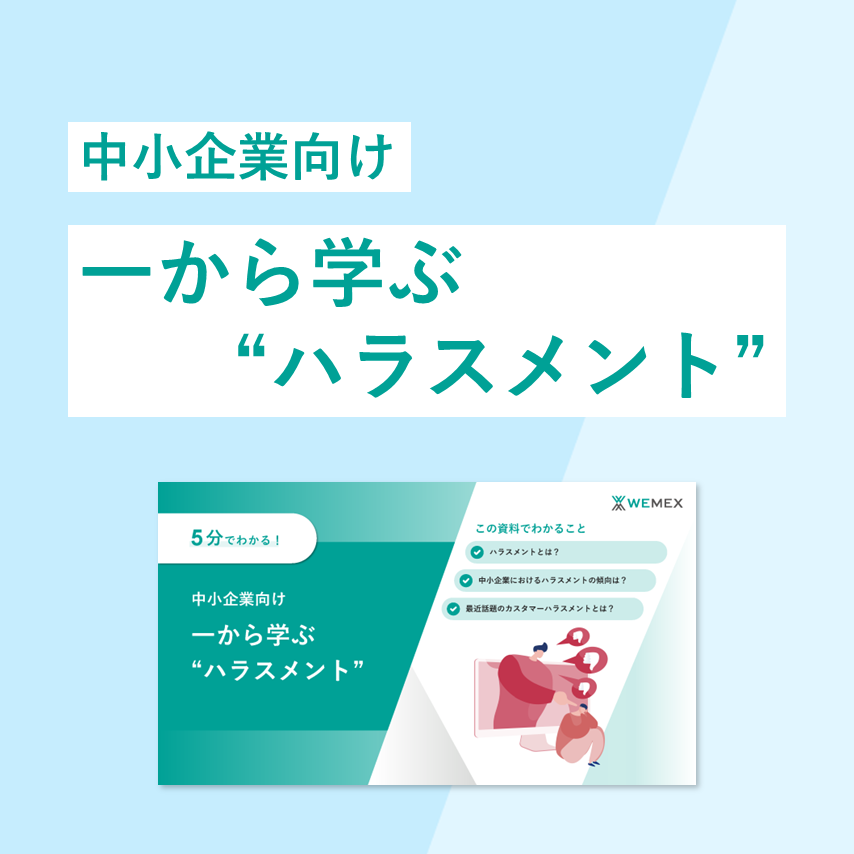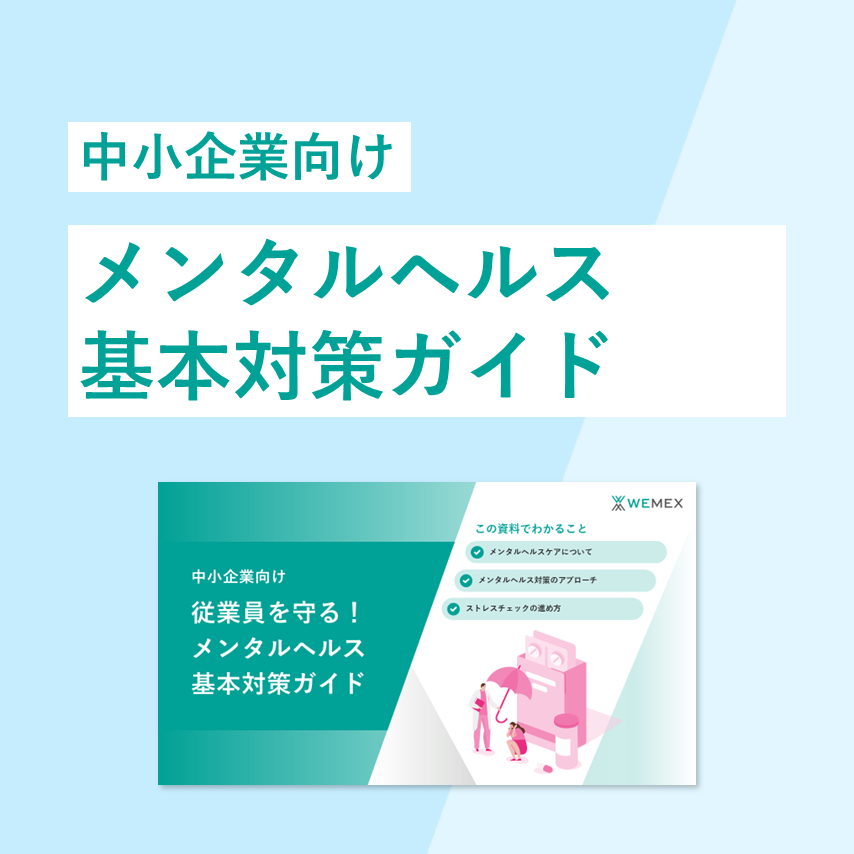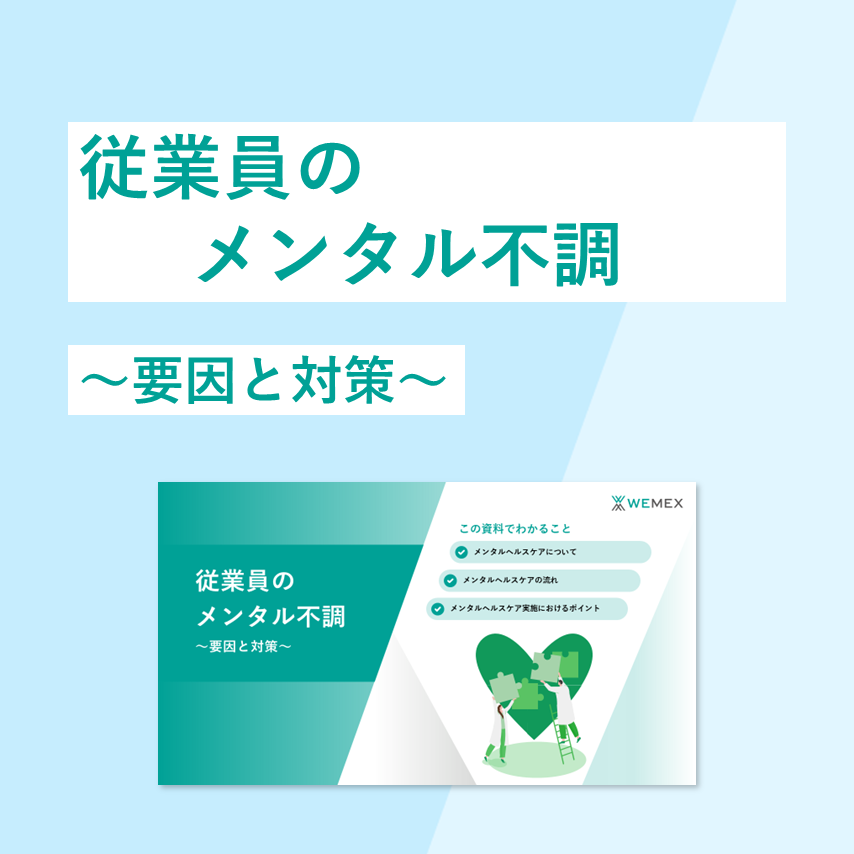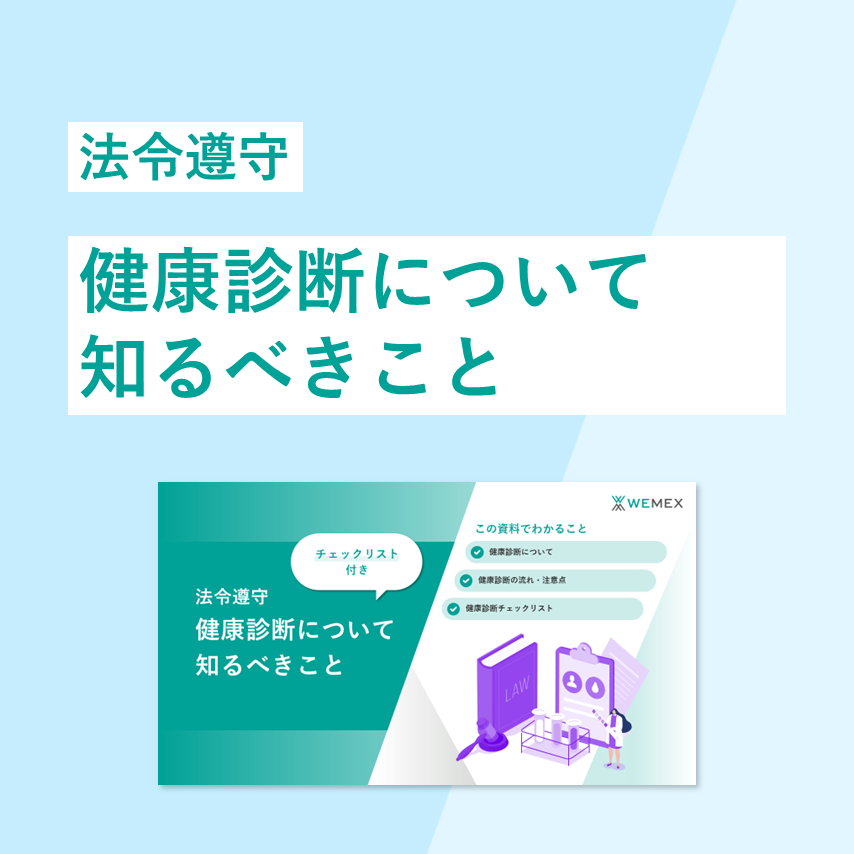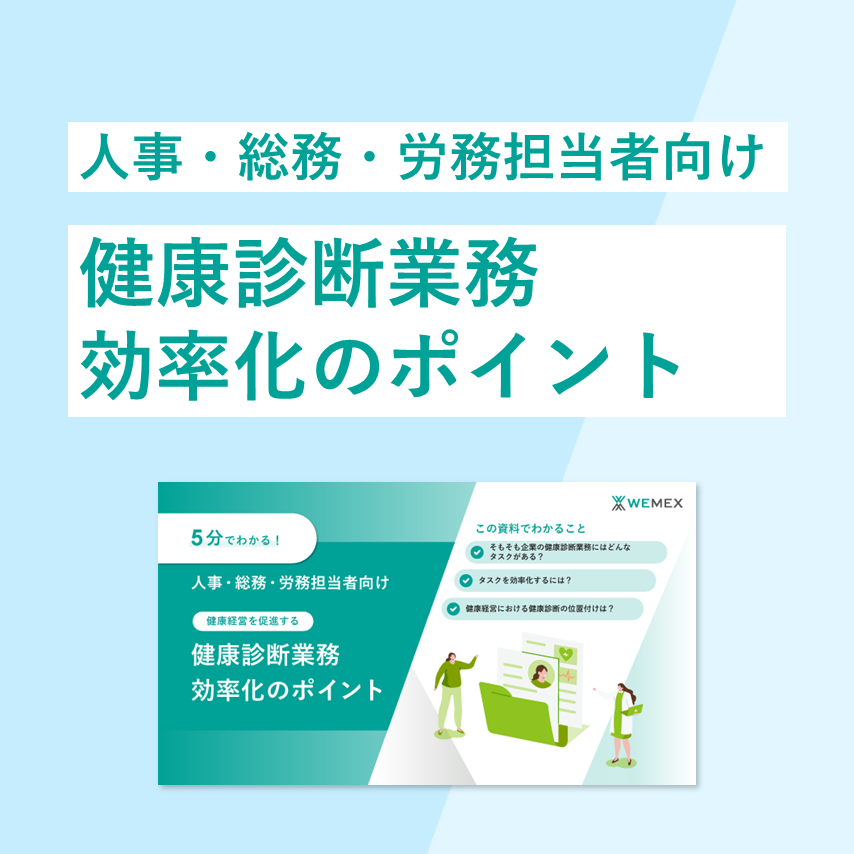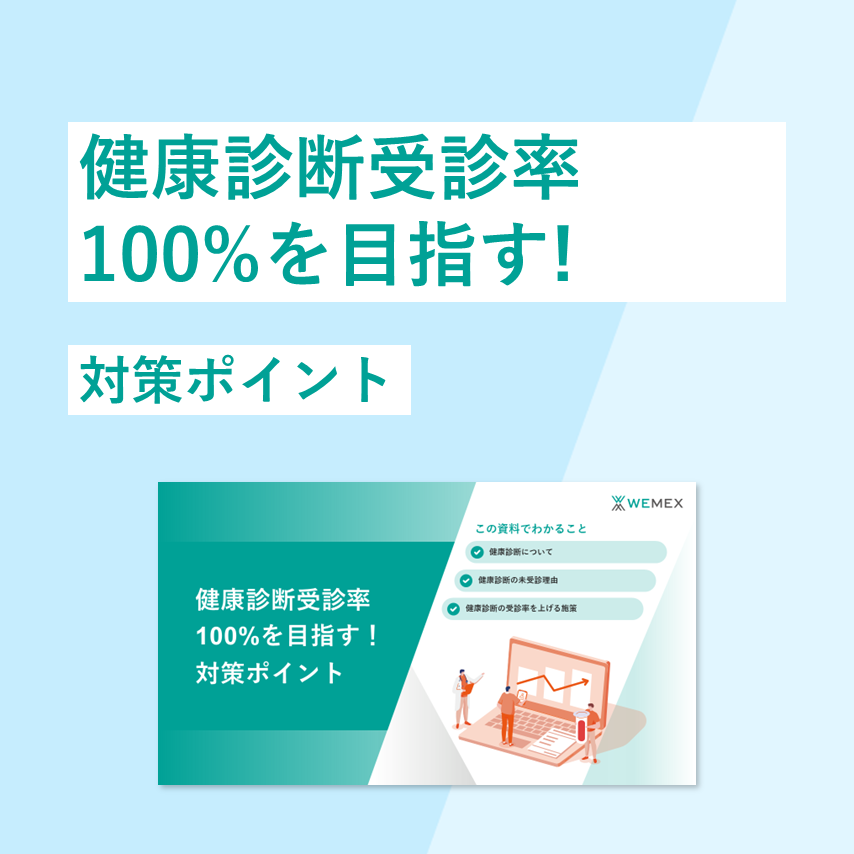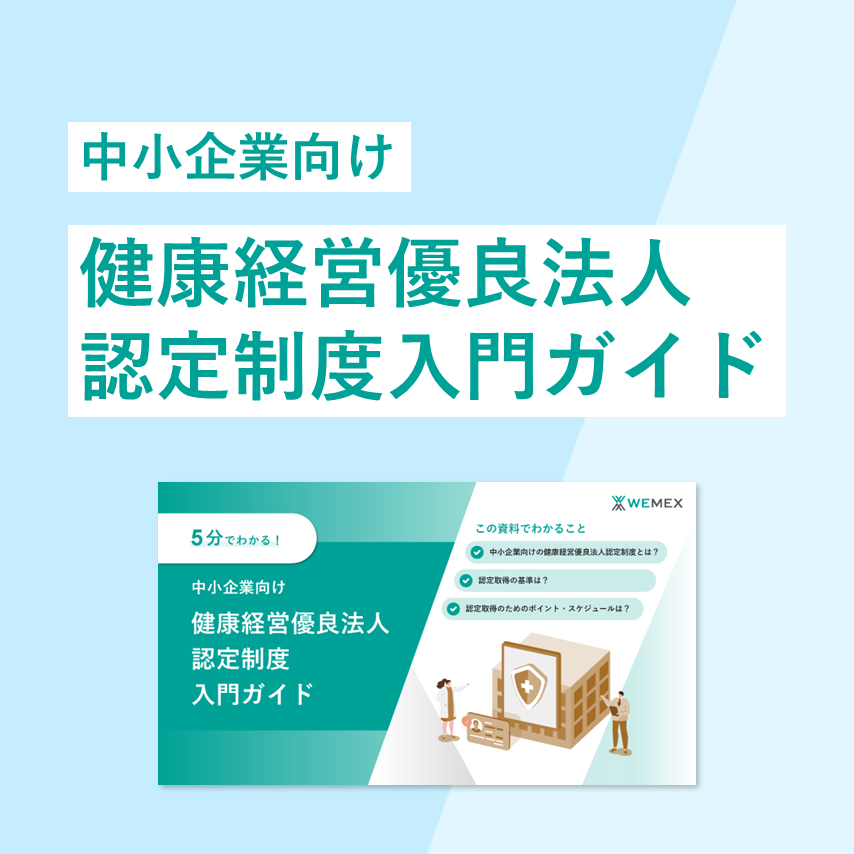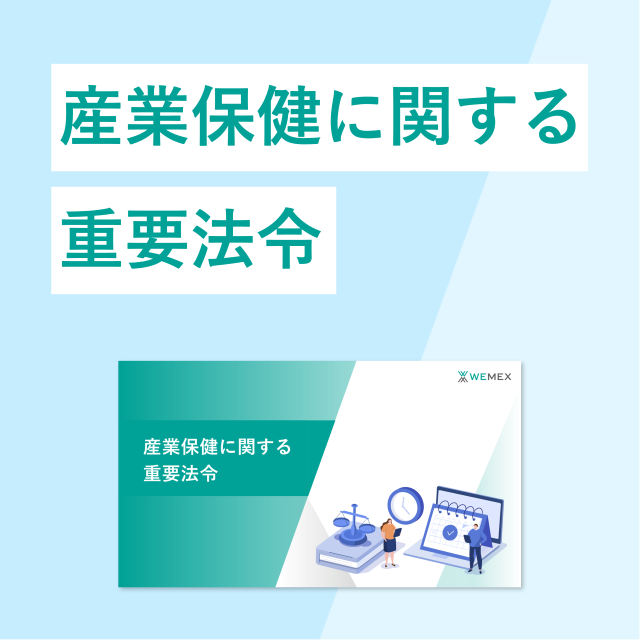受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
健康診断で「要再検査」や「要精密検査」と判定されても、すべての従業員が必ずしも二次健診を受けるとは限りません。二次健診の受診率を高めるためには、受診勧奨が重要です。二次健診によって心身の異常を早期に発見し、適切に対応することで、従業員の健康状態の向上が期待できます。本記事では、受診勧奨の流れやその重要性、実施時のポイントについて詳しく解説します。
なお、本記事では、自治体が実施するがん検診の受診勧奨ではなく、企業に実施義務がある定期健診の結果に基づく二次健診について説明します。
※本内容は公開日時点の情報です
目次
受診勧奨とは

受診勧奨とは、健康診断の結果で「要治療」や「要精密検査」と判定された従業員に対し、企業が医療機関での受診を促す取り組みを指します。声かけやメール、産業医との面談、受診報告書の提出などの方法を用いて、対象となる従業員に受診を働きかけます。
厚生労働省が毎年実施している「定期健康診断結果報告」の集計によれば、令和5年には健康診断で異常所見があった人の割合は58.9%に達しています。従業員の健康を守るためにも、企業による受診勧奨が重要です。
受診勧奨の流れ
受診勧奨は、以下の流れで行います。
1.健康診断の実施
労働安全衛生法に基づき、企業は従業員に医師による健康診断(一般健康診断)を受診させる義務があります。
2.健診結果の診断区分を確認
健診結果が届いたら、従業員ごとの結果を確認します。ただし、健診結果は個人情報に該当するため、慎重に取り扱う必要があります。
厚生労働省が示す「従業員の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために企業が講ずべき措置に関する指針」では、心身の状態の情報について、目的の達成に必要な範囲で取り扱うことが適切とされています。
受診勧奨における「目標の達成に必要な範囲」とは、従業員の健康状態に関する情報を人事担当者や受診勧奨を行う上司など必要最小限に限定し、不必要な検査項目は共有しないことを指します。
3.対象となる従業員に受診勧奨を実施
「要検査」や「要精密検査」と判定された従業員には、声かけ、メール、産業医との面談、受診報告書などを通じて受診を促します。
4.受診勧奨後の経過観察の実施
受診勧奨後、従業員が二次健診を受けたかどうかを確認します。受診済みの場合は、結果の報告を依頼しましょう。
なお、従業員には二次健診結果を提出する義務はありませんが、健康管理の観点から企業として提出を求めることが推奨されます。「健康診断結果に基づき企業が講ずべき措置に関する指針」においても、二次健診結果の提出を従業員へ働きかけることが望ましいとされています。
受診勧奨の基準
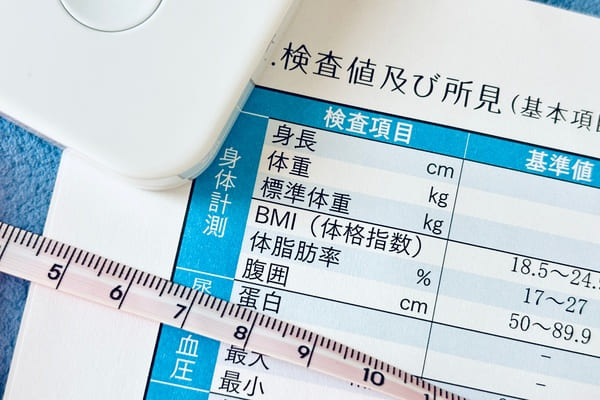
受診勧奨は、健康診断で「要検査」や「要精密検査」などと判定された従業員が対象です。これらの判定の表現は医療機関によって異なり、統一された基準はありません。異常がない場合や、異常が軽度で検査の必要がない場合には対象外となります。
一例として、日本人間ドック・予防医療学会が定める判定結果の区分では、「要再検査」は一時的な異常を確認するための検査、「要精密検査」は異常の原因を特定し治療の必要性を判断する検査とされています。
受診勧奨の重要性
受診勧奨が重要な理由は、従業員の健康を維持するためです。一般健康診断の受診後、二次健診を受けない従業員は少なくありません。しかし、健診結果の異常値を放置すると、重篤な病気につながる可能性があります。
受診勧奨を行うことで、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費の適正化やQOL(生活の質)の向上が期待できます。また、安全配慮義務の観点からも受診勧奨は重要です。
労働契約法では、企業には従業員の安全に配慮する義務が定められており、心身の健康もその対象に含まれます。健診結果で健康上の問題を把握しながら受診勧奨を行わない場合、安全配慮義務に違反しているとみなされる恐れがあります。
従業員へ受診勧奨が必要な理由
受診勧奨を十分に行わない場合、多くの従業員が二次健診を受診しない可能性があります。二次健診を受けない主な理由は以下の3点です。
- 受診の必要性を感じていない
- 受診するきっかけがない
- 受診への足かせがある
それぞれの理由について詳しく解説します。
受診の必要性を感じていない
健診結果で「要検査」や「要精密検査」と判定されても、自覚症状がなく日常生活に支障がない場合、健診結果を信用していないケースがあります。健康を意識している従業員でも、自分の健康状態を過信していることがあります。その結果、二次健診を受ける必要がないと従業員自身が判断してしまうことがあります。
症状が現れていない間は健康への危機感が薄れがちですが、異常が症状として表れる頃には手遅れになる場合もあります。そのため、企業は二次健診の必要性を従業員へ具体的に説明し、理解を促すことが重要です。
受診するきっかけがない
二次健診を受けたほうが良いことは理解していても、具体的なきっかけがないことで受診に至らない場合があります。今の生活習慣を変えたくない、健診で病気が見つかることへの恐怖など、心理的なハードルも原因の一つです。
労働安全衛生法では、二次健診の受診は従業員の義務ではなく、企業が受診を強制することはできません。また、「健康診断結果に基づき企業が講ずべき措置に関する指針」においても、二次健診の受診勧奨が適切とされるのみです。
しかし、法律上では受診を義務付けできないからといって、二次健診を本人任せにするのは適切ではありません。企業側から積極的に働きかけ、従業員が受診するきっかけをつくることが重要です。
受診への足かせがある
受診したくても、時間的制約や心理的な障壁などによって受診できない場合があります。主な原因は以下の通りです。
- 受診費用が自己負担となる
- 仕事の調整が必要になる
- 休暇を取得しなければならない
- 受診可能な医療機関がわからない
検査項目によっては数万円の費用負担や1日中拘束されるケースもあります。企業としては、こうした足かせを取り除き、従業員が二次健診を受けやすい環境を整えることが求められます。
受診勧奨の実施ポイント

受診勧奨を機械的におこなうだけでは、従業員の受診率は向上しません。効果的な受診勧奨を行うためには、重要なポイントを押さえる必要があります。二次健診を受ける従業員が増え、健康状態の改善につながるよう、適切な方法を確認しましょう。
受診勧奨のオペレーションを見直す
効果的な受診勧奨には、社内ルールとオペレーションの明確化が欠かせません。誰が、どのタイミングで、どのような方法で受診を促すかを明確に設定しましょう。
受診勧奨は法的義務ではないため、ルールが不明確だと後回しになりがちです。他の業務に追われて対応が疎かにならないよう、体系的な仕組みづくりが求められます。
対象者一人ひとりへの個別対応と職場全体への情報発信を組み合わせることも有効です。健康診断結果が出た後に職場全体へ通知を行い、対象者に個別フォローをすることで、受診率向上が期待できます。
産業医・産業保健師と連携する
産業医や産業保健師の専門知識を活用した受診勧奨は効果的です。以下の連携方法が考えられます。
- 従業員へ交付する書面を産業医に作成してもらう
- 産業保健師による個別フォロー
労働安全衛生法第66条の4では、健康診断で異常所見があった従業員に対し、健康診断実施日から3か月以内に医師の意見聴取を行うことが義務付けられています。この意見聴取で二次健診の受診勧奨を行う方法も有効です。
なお、従業員50人未満の事業所では産業医設置義務がないため、地域産業保健センターを活用するとよいでしょう。同センターでは、一般健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、個別訪問による保健指導などのサービスを提供しています。
上司・経営層と連携する
人事部門だけでなく、上司や経営層が受診勧奨に関わることも効果的です。特に、普段から従業員の状況を把握している直属の上司の協力は重要です。まずは管理職や役員に受診勧奨の意義を理解してもらいましょう。
例えば、上司には1on1やミーティングなどで対象従業員に声かけをお願いする方法があります。また、経営層から健康経営®(※)の観点で受診勧奨の重要性を発信してもらうことで、メッセージの浸透が期待できます。
※健康経営とは、従業員の健康管理を経営戦略として考え、実践する考え方です。健康への投資は従業員の活力向上や生産性向上につながり、組織全体の活性化や業績向上が期待されます。
関連記事:健康経営とは?メリットや取り組み方を解説
通知方法を見直す
受診勧奨の通知方法も工夫が必要です。以下のように段階的な通知を行うと効果的です。
- 一次勧奨:文書による通知
- 二次勧奨:電話や文書による通知
段階的な受診勧奨は各自治体のがん健診でも導入されており、二次勧奨によって受診率が大きく向上することが確認されています。
また、受診勧奨用の資料も見直しましょう。協会けんぽ各支部では受診勧奨用リーフレットを作成しており、参考にすることができます。検査項目に応じて通知内容を調整すると効果的です。
さらに、異常所見を放置するリスクをわかりやすく伝えることで従業員の理解が深まり、受診につながる可能性が高まります。
研修を実施する
二次健診に対する従業員の意識を向上させるには、研修が効果的です。新入社員研修や管理職研修を通じて、健康管理の重要性への理解を深めましょう。
新入社員研修で健康について学ぶ機会を設けることで、若いうちから健康を意識する従業員を増やせます。また、管理職研修ではメンバーの健康管理を含めたマネジメントの理解を促すことで、職場全体の健康意識向上に寄与します。
二次健診の受診が当たり前という風土が形成されると、受診勧奨もスムーズに進められます。健診を受ける側と受診勧奨する側、それぞれの視点で研修内容を設計しましょう。
従業員の自己負担を軽減する
二次健診にかかる費用負担を軽減することで、金銭的ハードルが原因で受診できなかった従業員の背中を押すことができます。
従業員には二次健診を受ける法律上の義務がなく、二次健診に掛かる費用も自己負担となるため、受診を躊躇する従業員も少なくありません。そのため、企業が二次健診費用や交通費を負担し、受診を妨げる要因を取り除くことが有効です。
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ」でも、一般健康診断の検査値確定のための再検査は企業負担とすることが望ましいとされています。
さらに、労災保険には「労災保険二次健康診断等給付」という制度があり、特定の条件のもと無料で二次健診と特定保健指導を1年度内に1回受けられます。この制度は以下の4項目すべてで異常所見がある場合に適用されます。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
制度概要を確認し、有効活用できるよう準備しておきましょう。
就業時間で受診できる環境を整備する
法律上、勤務時間中に二次健診を受診することを認めなくても問題はありません。しかし、安全配慮義務や従業員が受診しやすい環境を考慮すると、勤務時間中の受診を認めることが望ましいでしょう。勤務時間中に受診しても賃金が減額されず、年次有給休暇の取得も不要であれば、二次健診の受診率向上を期待できます。
さらに、職場で受診しやすい雰囲気をつくることも重要です。職場全体の理解があることで、二次健診のために職場を離れることへの抵抗感が軽減され、従業員が安心して受診できる環境が整います。
まとめ
受診勧奨は従業員の健康維持に欠かせない取り組みであり、企業には従業員の健康状態を適切に把握する責任があります。受診勧奨を怠ると、従業員本人の健康だけでなく、事業運営にも悪影響を及ぼす可能性があります。
単に受診を促すだけでは、二次健診を受ける従業員を増やすことは困難です。職場全体で仕組みや風土を整え、産業医や保健師、直属の上司、経営層などと連携しながら受診勧奨に取り組むことが重要です。
効果的な受診勧奨には外部サービスの活用も有効です。「Wemex 健診代行」では、健診の契約から結果の回収までを一括で代行し、はがきや電話による受診勧奨にも対応しています。このサービスを利用することで、安全衛生担当者は受診勧奨にかかる時間を削減し、従業員の健康管理や他の業務に専念できます。
まずはお気軽に問い合わせくださいませ。
【法人向け】Wemex 健診代行 お問い合わせ
- 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/127-1.html)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000922318.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/28ke_shishin.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001145635.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html)
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。