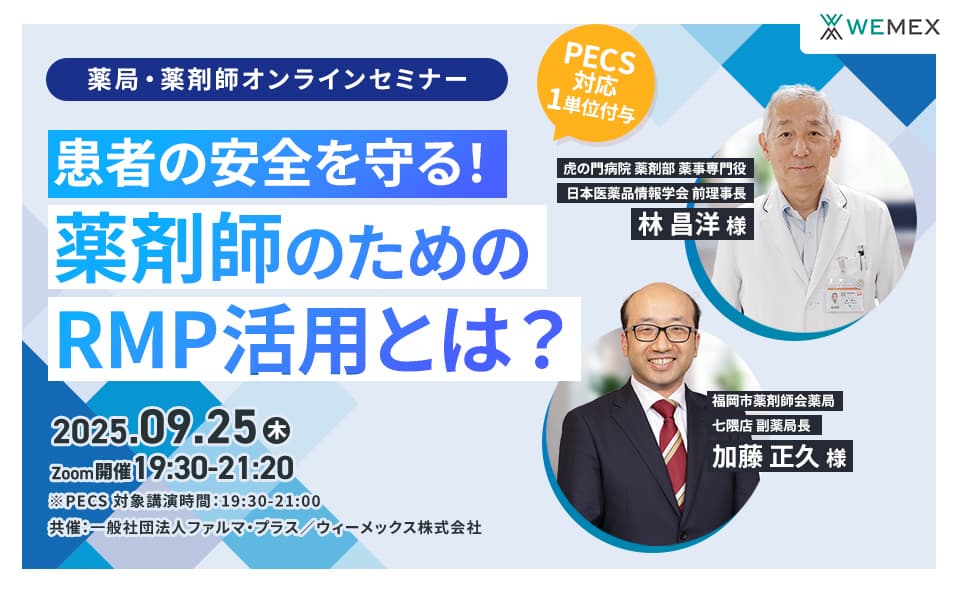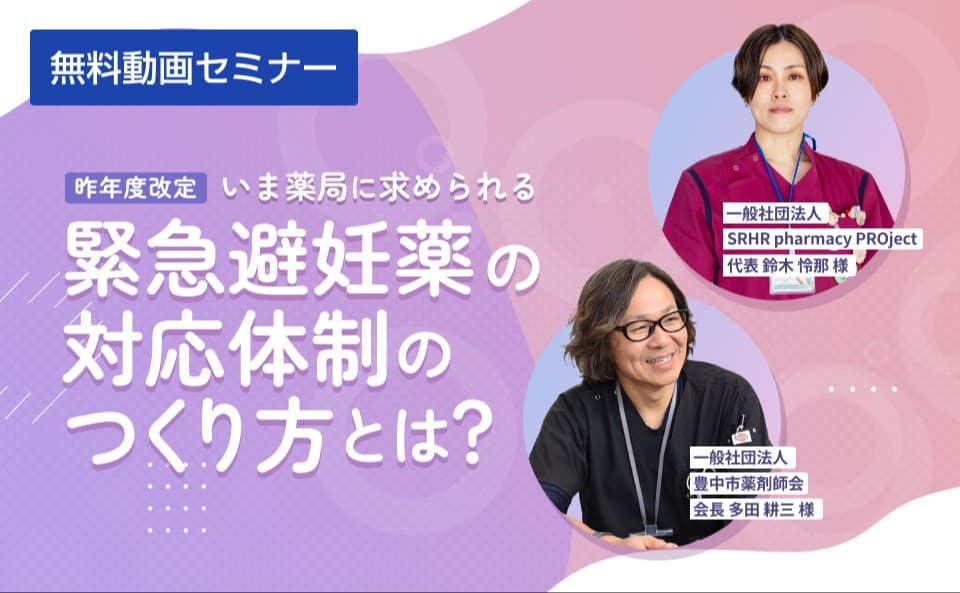目次
特定薬剤管理指導加算3とは何か?

特定薬剤管理指導加算とは、薬局において薬剤師が実施する医薬品の適正使用に関する安全管理および服薬指導等の結果として算定される点数を指します。2024年度改定では、特定薬剤管理指導の加算が3つに分類されました。
2024年度改定により新設された特定薬剤管理指導加算3は、従前の管理や指導に加え、薬剤師が患者さんに対して重点的な服薬指導を必要と認め、必要な説明および指導を行った場合に、患者1人あたり、最初に処方された1回分のみ算定することが可能です。
出典:調剤報酬点数表に関する事項(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293314.pdf#page=25)
2024年度改定におけるポイント
2024年度調剤報酬改定では、特定薬剤管理指導加算1の評価基準も見直されました。従来は複数のハイリスク薬が処方された場合、それぞれの医薬品の特徴を踏まえた服薬指導が要されていました。
しかし、本改定ではその記載が削除され、新たに特に安全管理が必要な医薬品の処方、用法・用量の変更、患者さんの副作用発現状況に基づいた薬剤師の指導時に加算が適用されるようになりました。
また、服薬指導を行う際、特に患者さんに対して重点的かつ丁寧な説明が求められる場合には、特定薬剤管理指導加算3が新設されました。
さらに、2024年10月1日以降に長期収載品の選定療養が施行されました。選定療養とは、患者さんが医療機関や治療方法を選択する際に、保険診療に加えて、患者さんが追加費用を負担することで、保険適用外のサービスや特別な待遇を受けることができる制度のことです。これに伴い、薬局ではジェネリックが存在する医薬品に対して、患者さんの意思で先発品を選択される際に発生するお薬代に加えて自己負担額が増加します。2025年には、この選定療養に関する説明をすることによる薬局の業務負担の増加を鑑みて、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の評価基準の見直しと点数の引き上げが行われました。
出典:令和6年診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf)
特定薬剤管理指導加算1および2との違い
特定薬剤管理指導加算には3種類あります。ここでは、特定薬剤管理指導加算3の内容について説明する前に、特定薬剤管理指導加算1および2の違いについても解説します。
特定薬剤管理指導加算1は、通常の服薬指導に加えて、ハイリスク薬と呼ばれる医薬品の薬効ごとに、医薬品の安全管理や服薬指導を患者さんまたはその家族などに行った場合に算定されます。
ここで挙げられているハイリスク薬は、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」(日本薬剤師会)に記載がある以下3つの分類のいずれかに含まれるものです。
以下の内容に当てはまる医薬品が初回で出された場合や、用法または用量の変更もしくは副作用等の状況に応じた薬剤師の判断で管理や指導などを行った場合に算定されます。
【厚生労働科学研究「『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル(平成19年3月)」において「ハイリスク薬」とされているもの】
- 投与量等に注意が必要な医薬品
- 休薬期間の設けられている医薬品や服薬期間の管理が必要な医薬品
- 併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- 特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- 重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- 心停止等に注意が必要な医薬品
- 呼吸抑制に注意が必要な注射薬
- 投与量が単位(Unit)で設定されている注射薬
- 漏出により皮膚障害を起こす注射薬
【投与時に特に注意が必要と考えられる以下の治療領域の薬剤】
- 抗悪性腫瘍剤
- 免疫抑制剤*
- 不整脈用剤*
- 抗てんかん剤*
- 血液凝固阻止剤
- ジギタリス製剤*
- テオフィリン製剤*
- 精神神経用剤(SSRI、SNRI、抗パーキンソン薬を含む)*
- 糖尿病用剤
- 膵臓ホルモン剤
- 抗HIV剤
*:特定薬剤治療管理料対象薬剤(TDM対象薬剤)を含む
【投与時に特に注意が必要と考えられる以下の性質をもつ薬剤】
- 治療有効域の狭い薬剤
- 中毒域と有効域が接近し、投与方法・投与量の管理が難しい薬剤
- 体内動態に個人差が大きい薬剤
- 生理的要因(肝障害、腎障害、高齢者、小児等)で個人差が大きい薬剤
- 不適切な使用によって患者に重大な害をもたらす可能性がある薬剤
- 医療事故やインシデントが多数報告されている薬剤
- その他、適正使用が強く求められる薬剤(発売直後の薬剤など)
特定薬剤管理指導加算2は、連携充実加算を届け出ている医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者さんに対して、抗悪性腫瘍剤などを調剤する薬局の薬剤師が以下の内容をすべて実施した場合に算定することができます。
- 当該患者のレジメン(治療内容)などを確認して、必要な薬学的管理および指導を行った
- 当該患者が注射または投薬されている抗悪性腫瘍剤および制吐剤などの支持療法に係る薬に関して、電話などで服用状況、体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などについて患者またはその家族などに確認した
- 患者の状況確認の結果を踏まえて、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供した
特定薬剤管理指導加算1および2の内容を解説しました。少し複雑になってしまう内容でもあるため、簡易的な表でもまとめましたので、参考にしてみてください。
| 特定薬剤管理指導 | 点数 | 算定要件 | 算定回数 | 施設基準 | 保険医療機関へ文書による情報提供 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算1 | 10点 | 新規のハイリスク薬 | 処方箋受付回数につき1回 | なし | なし |
| 5点 | 用法用量の変更、副作用の発現状況など必要と判断したとき | ||||
| 加算2 | 100点 | 抗癌剤治療に関連した業務を行った場合 | 患者1人につき月1回 | あり | あり |
出典:薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)(日本薬剤師会)(https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/high_risk_guideline_2nd.pdf)
「医薬品の安全使用のための 業務手順書」作成マニュアル(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001025572.pdf)
特定薬剤管理指導加算3の点数と算定要件
点数
特定薬剤管理指導加算3
(イ) 5点 / 回
(ロ) 10点 / 回
特定薬剤管理指導加算3は「イ」と「ロ」の2区分があります。2025年3月以前は算定要件を満たせば、どちらも5点を算定していました。しかし2025年4月以降は、選定療養に関わる業務の負担が増えたことでロの点数が10点に変更されています。
算定要件
特定薬剤管理指導加算3の算定できる要件は2つに分かれております。
1つ目の「イ」は、患者さん向けの医薬品リスク管理計画(RMP)の策定が義務付けられている医薬品が初めて処方されたとき、または既にある医薬品に緊急安全性情報(イエローレター)や安全性速報(ブルーレター)が新たに発出されたときに限り、適正使用や安全性に関する指導を薬剤師が行うことで算定されます。
2つ目の「ロ」は、調剤前に医薬品の選択に関する情報が特に必要な患者さんに説明および指導を行った場合です。具体的には、後発医薬品が存在する先発医薬品を選択するような選定療養の対象となる場合や、医薬品の供給状況が不安定であるため、調剤時に前回調剤された医薬品を変更した薬の交付が必要となる患者さんに対して説明を行った場合が含まれます。
また、処方箋に記載された薬の調剤に必要な数量が確保できない場合、その薬剤名をレセプト摘要欄や調剤報酬明細書の摘要欄に記載してはじめて算定できます。
| 特定薬剤管理指導 | 点数 | 算定要件 | 算定回数 | 施設基準 | 保険医療機関へ文書による情報提供 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算3 イ | 5点 |
医薬品リスク管理計画(RMP) 緊急安全性情報(イエローレター) 安全性速報(ブルーレター) これらに基づいて十分な指導を行った場合 |
患者1人につき当該医薬品が最初に処方されたとき1回のみ | なし | なし |
| 加算3 ロ | 10点 | 調剤前に医薬品の選択に関わる情報提供について説明や指導した場合 | なし | なし |
出典:調剤報酬点数表に関する事項(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293314.pdf)
疑義解釈資料の送付について(その1)(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)
算定上の注意点
特定薬剤管理指導加算3を算定する際には、注意が必要な事項があります。患者さんが薬局に処方箋を持ってきた際に、服薬指導を行う薬剤師が特定薬剤管理指導加算3のイ(ハイリスク薬)とロ(選定療養に該当する医薬品)を、同時に加算できるのかについてです。
以下の3つのケースに分けて解説していきます。
ケース①
同じ処方箋内で医薬品Aがハイリスク薬、医薬品Bが選定療養に該当する医薬品の記載がある場合
この場合には、医薬品Aに対して特定薬剤管理指導加算3のイを算定できます。医薬品Bに対しては、患者さんの意思で医薬品を選択することで、特定薬剤管理指導加算3のロを算定することができます。つまり、処方箋内で別々の薬に対してであれば同時に加算を取ることが可能です。
ケース②
同じ処方箋内で医薬品Cがハイリスク薬であり、選定療養に該当する医薬品にも該当する場合
この場合には、ハイリスク薬の説明をし、選定療養に関する説明をしたうえで患者さんの意思で変更があった場合には、特定薬剤管理指導加算3のイとロの両方を算定することができます。
ケース③
処方箋内に記載されている医薬品Dに対して、医師からの先発品指定がなく、薬剤師が患者さんの意思によって後発品から先発品に変更して調剤を行いました。
その後、服薬指導中に選定療養の説明をしたことで、先発品希望を取り消して、患者さんの意思で後発医薬品を選択して再調剤を行った場合
この場合は、中身が複雑ですが、ポイントとなるのが選定療養の説明を行ったことで、先発品希望から後発品へ変更することになったことです。先発品から後発品、後発品から先発品どちらであっても、薬剤師が説明をして患者さんの意思で変更があったとき、特定薬剤管理指導加算3のロを算定することができます。
以上3つの考えられるケースについてお伝えしました。実際に目の前の患者さんに説明する前に処方箋を見て、どのケースに当てはまるのか確認してみましょう。また、ケース③のような事例もあることも知っておくことが大切です。
出典:疑義解釈資料の送付について(その1)(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)
RMPとは
ここでは、特定薬剤管理指導加算3の算定要件に含まれる患者さん向けの医薬品リスク管理計画(RMP)について説明します。
RMPは、新薬が作られてから市場に出回った後までに起こり得るリスクに対して適切に管理するための文書です。
薬局で薬剤師がRMP文書を用いて行うことは、患者さんに対して医薬品の副作用リスクを下げること、医薬品の適正使用による効果を把握することになります。
そのため、RMP文書で説明するような医薬品が出されたからといって、危険な薬を処方されたという意味ではありません。患者さんが安全に使用していただくための薬剤師の情報提供を行うこと、効果がしっかり出ているのかを患者さん側からも薬剤師に教えてほしい薬になります。
特に高齢者や小児など、医薬品が開発された時点では得られていない対象者の情報がある場合もRMP文書の説明が必要なものがあります。
薬剤師と患者さんの間で報告をし合う薬が、RMP文書を必要とする医薬品というイメージです。薬剤師もその都度聞き取り調査をするので、何か気になることがあれば薬剤師に伝えてほしいということです。
出典:医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)(PMDA)(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html)
RMP資材の確認方法について
そんなRMPですが、どこで確認することができるのでしょうか。
作成されたRMPはPMDAのウェブサイトに掲載されています。
【方法1】
PMDAのホームページにて「RMP提出品目一覧」にアクセスし、一覧から見たいRMPを探す方法
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html
【方法2】
PMDAのホームページの添付文書検索から個別に医薬品を検索して該当医薬品のRMPを閲覧する方法
まとめ
特定薬剤管理指導加算3の内容について解説しました。薬剤師は、患者さんに対して適切な服薬管理および指導を行う責務があります。理由が不明確な状態で加算を取得する行為は、倫理的にも問題があります。
「PharnesX-MX」は、幅広い処方監査チェックシステムを標準装備しており、選定療養に関する指導やRMP指導実績の記録メモを追加することが可能です。これにより、多忙な薬剤師の業務をサポートし、適切な服薬指導を実現します。処方監査チェックや薬歴記録の手間を削減し、適切な加算取得をするために、「PharnesX-MX」による業務効率化をご検討ください。
著者情報
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-
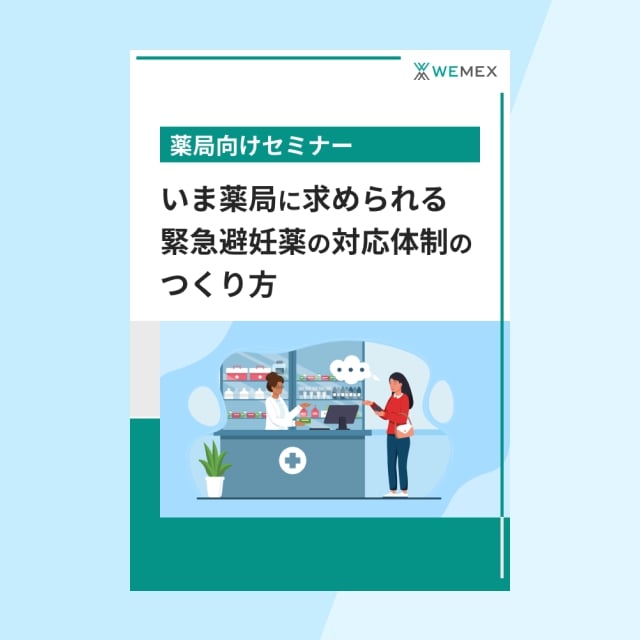
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
いま薬局に求められる緊急避妊薬の対応体制のつくり方
-
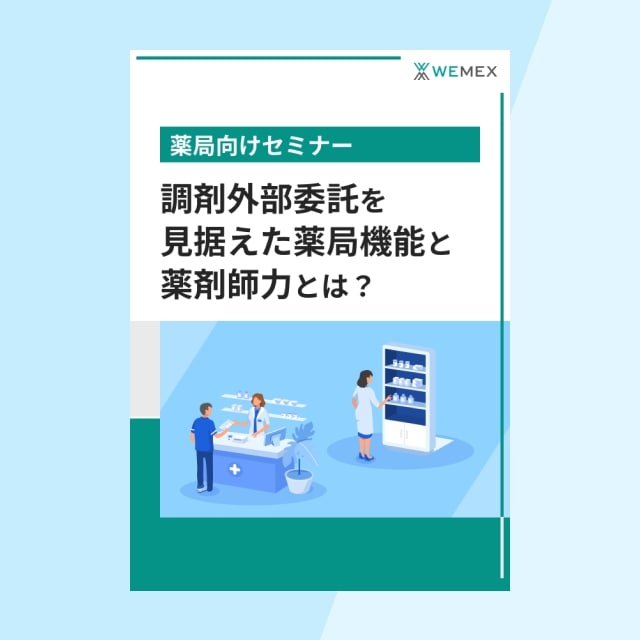
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
調剤外部委託を見据えた薬局機能と薬剤師力とは
-
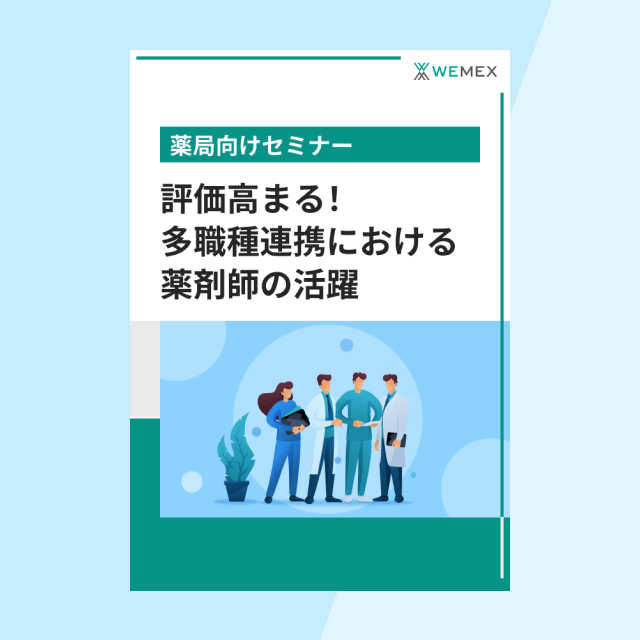
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
評価高まる!多職種連携における薬剤師の活躍
-
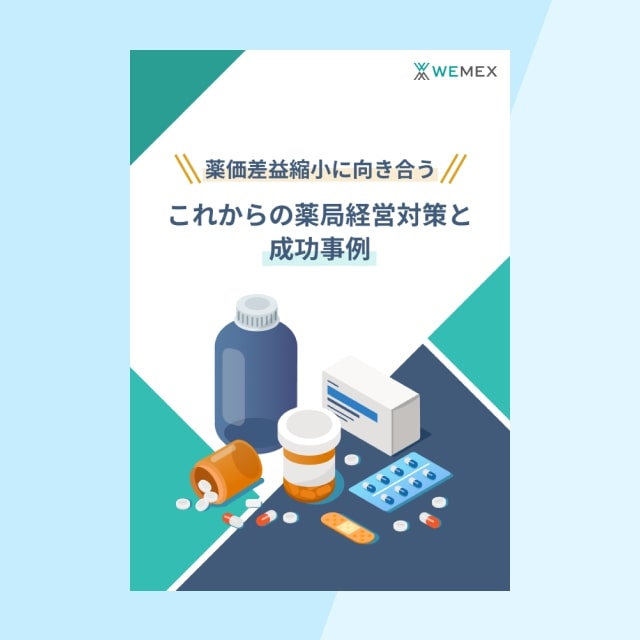
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
薬価差益縮小に向き合うこれからの薬局経営対策と成功事例
-
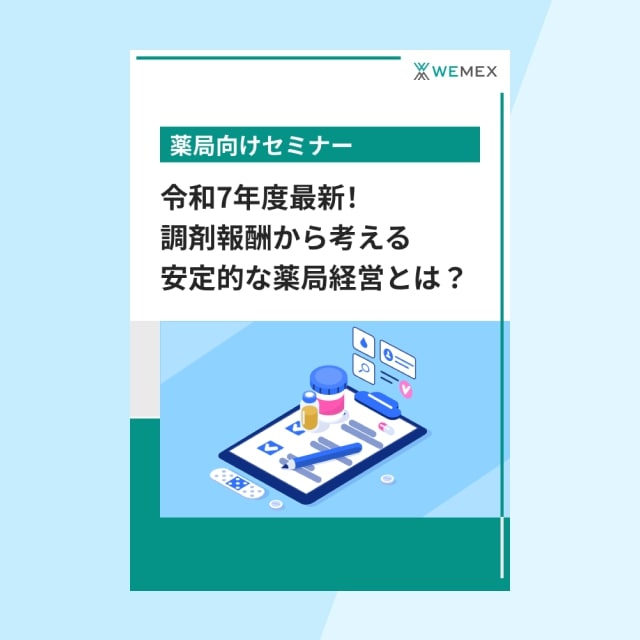
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
令和7年度最新!調剤報酬から考える安定的な薬局経営とは?
-

薬局経営 薬局経営者 薬剤師
地域医療を支える かかりつけ薬局・薬剤師のかかりつけ化実現とその効果
-
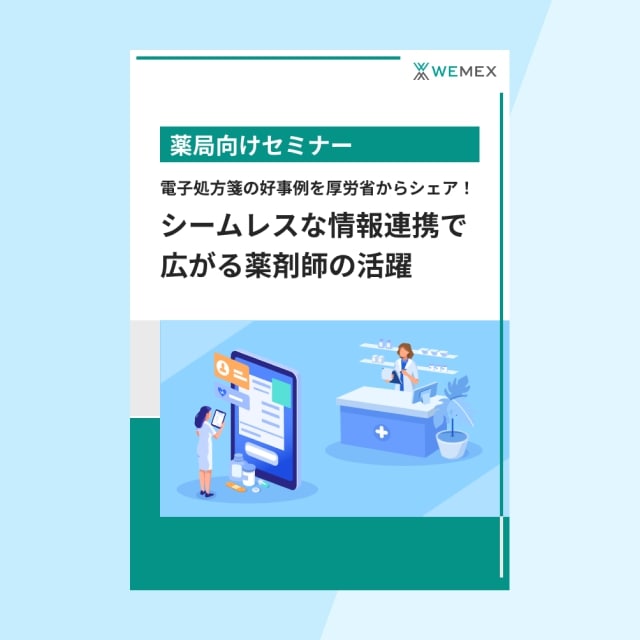
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
電子処方箋の好事例を厚労省からシェア!シームレスな情報連携で広がる薬剤師の活躍
-
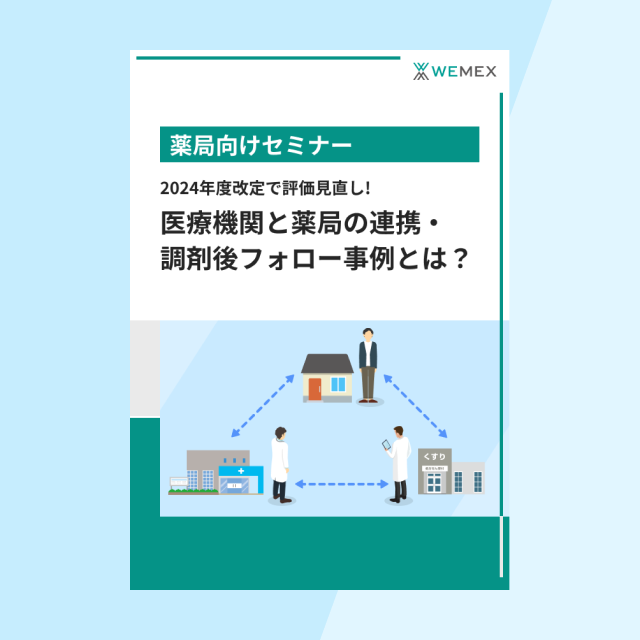
薬局経営 薬局経営者 薬剤師
2024年度改定で評価見直し!医療機関と薬局の連携・調剤後フォロー事例とは?