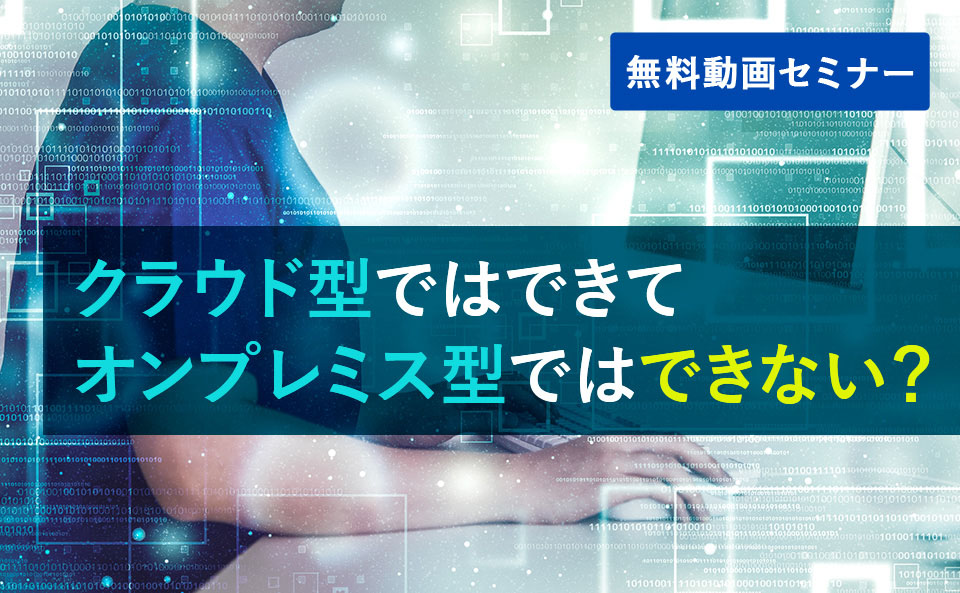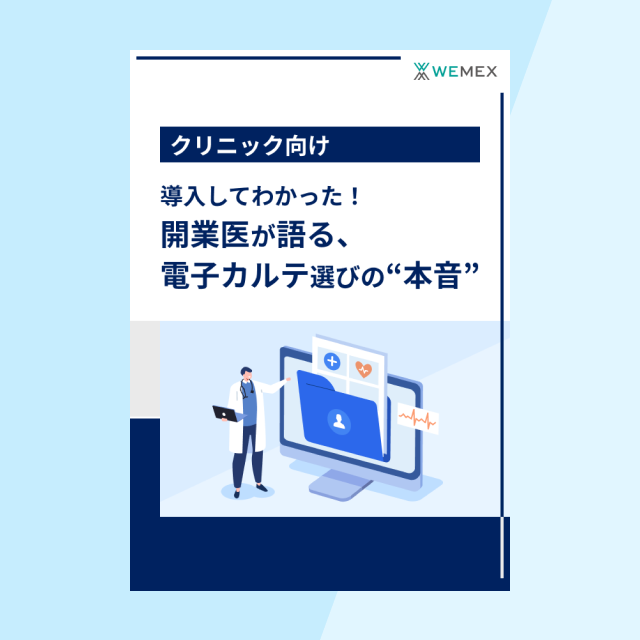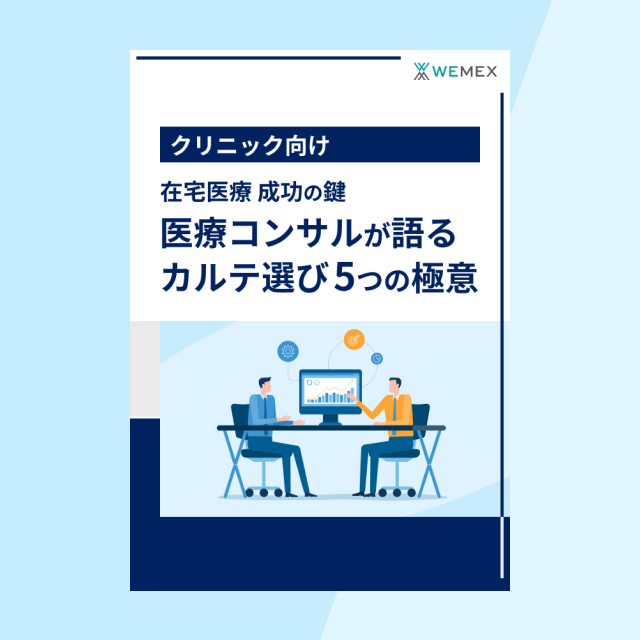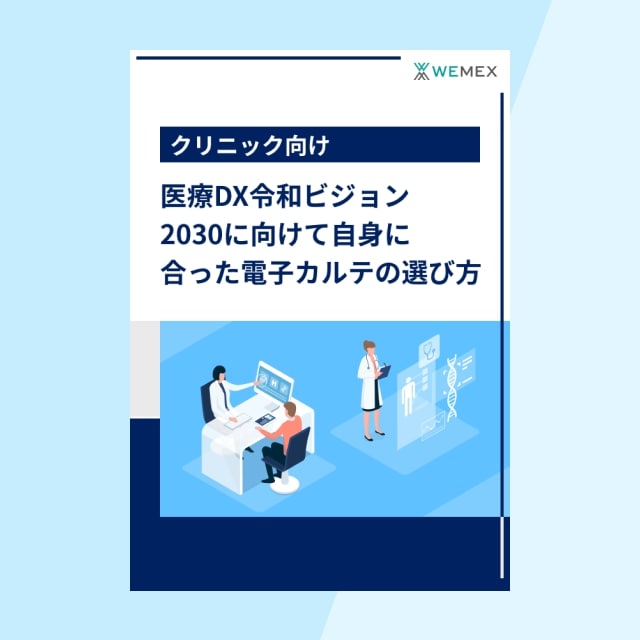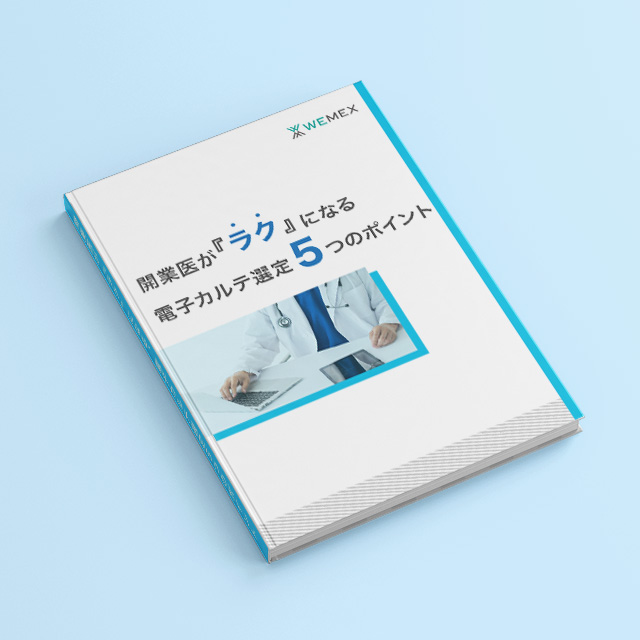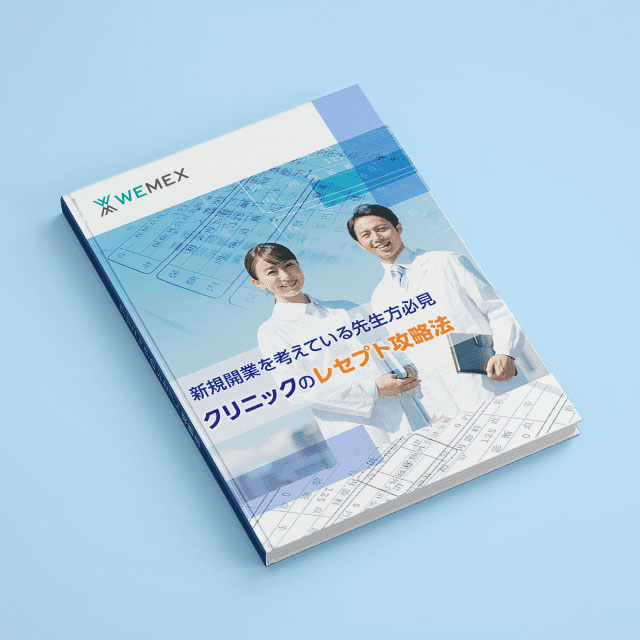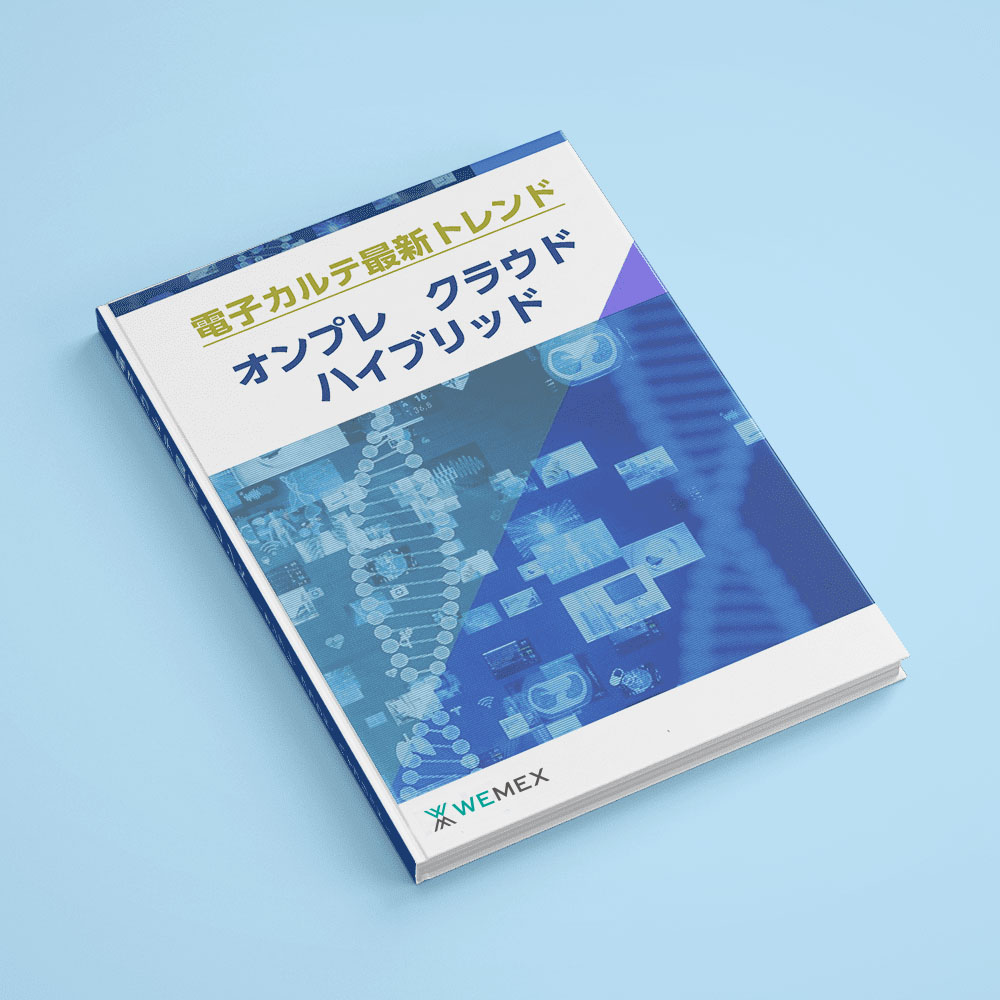電子カルテの費用まとめ2025|導入・運用コストの相場と選び方
電子カルテの費用相場は、導入形態や施設規模により大きく異なります。診療所の場合、クラウド型なら初期費用数十万円程度、オンプレミス型は200万円〜が一般的な価格帯といわれていますが、実際には無料から1,000万円超まで幅広い選択肢があります。「思ったより高額で導入を断念した」「運用開始後に想定外のコストが発生した」といった失敗を避けるには、導入前に総額を把握することが不可欠です。本記事では、2025年最新の費用相場から、見落としがちな隠れコスト、賢く費用を抑える方法まで、電子カルテの"お金"に関する重要なポイントを解説します。
※本内容は公開日時点の情報です
#開業検討 #機器選定ポイント #業務効率化 #紙カルテの電子化 #システム入替
目次
電子カルテの導入・運用費用相場

電子カルテの導入費用は、無料から数百万円単位と大きな幅があります。金額差が生じる理由は、電子カルテの種類と規模によって価格が異なるためです。
電子カルテは、大きくオンプレミス型とクラウド型に分類されます。それぞれの費用相場をまとめたものが下表です。
| 項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |
|---|---|---|
| 導入費用 | 200万円~500万円程度 | 無料~数十万円程度 |
| 費用に含まれるもの |
・ システム構築費 ・ サーバー設置費など |
・ サーバーレンタル料 ・ システム使用料 ・ メンテナンス費用など |
また、オンプレミス同士・クラウド同士でも、導入する医療機関の規模によって費用は上下します。「自院で実現したい環境に適した電子カルテとは何か」という観点から絞り込んでいくと、費用面での比較もしやすくなるでしょう。
導入費用が変動する5つの要素
電子カルテの導入費用は、複数の要素が絡みます。時代の流れから、電子カルテの標準化対応で追加費用がかかるのか心配される方もいらっしゃいますが、標準化に対応した製品であれば、大きな費用負担を避けられます。適切な製品選択のためにも、費用変動の要素を理解しておきましょう。
1. 導入形態による違い(オンプレミス型 vs クラウド型)
オンプレミス型は、サーバーやソフトウェアなどの情報システムを院内に設置する分、初期費用は高額になる傾向にあります。また、カスタマイズにも柔軟に対応できる分、システム更新の費用もかさむケースは珍しくありません。
クラウド型は、サーバーやソフトウェアの設置が不要で、インターネットを介して利用する分、初期費用はオンプレミス型よりも抑えられます。カスタマイズは限定的ながら、月額費用だけで利用できるシステムも増えています。
そのほか、オンプレミス型の安心感とクラウド型の利便性を備えたハイブリッド型も登場しており、導入形態の選択肢は豊富です。
メディコムでは、クラウド型とハイブリッド型をラインナップしています。
2. レセコン一体型 vs 電子カルテ単体
多くの医療機関では、電子カルテと一緒にレセコンも導入し効率化を進めています。電子カルテとレセコンを別々に導入するよりも、設定面や互換性の面でレセコン一体型を導入したほうが安心できるためです。
また、データ連携の手間やシステム間の不整合リスクを考慮すると、長期的には一体型のほうが効率的に運用できるメリットもあります。
初期費用だけではなく、長い目で安心して使い続けられる環境を選ぶようにしましょう。
3. 導入サポートの内容
電子カルテは導入した後のシステム設定に手間取ったり、使い方を把握するまで時間がかかったりするケースが散見されます。一方、ご自身で対応を進めたほうが早い先生もいるでしょう。
そこで、電子カルテの設定や操作に関して、どのようなサポート体制がとられているかの比較はしておきたいものです。
サポート内容には、システム設定代行・操作研修・運用コンサルティングなどが含まれます。
費用はかかりますが、操作に不安を感じる場合や、1日でも早く電子カルテを使った運用の軌道に乗せるためには、検討の余地があるといえます。
反対に設定を自身で進められる場合は、レスオプションで費用を抑えられる選択肢があるかが検討の土台に上がるでしょう。
4. 利用者数や端末数
利用者数や端末数は医療機関の規模が大きくなるほど増えるため、数が多いほど導入費用は高くなります。診察室の数や受付端末の数によっても、必要な端末数が変わるため、施設の規模に応じた試算が重要です。将来的なスタッフ増加も考慮して、適切なライセンス数を検討しましょう。
なお、導入時の注意点や手順などは以下の記事で詳しく解説しています。
運用コスト
電子カルテ導入後は、月々の運用費用がかかります。導入時の初期費用だけでなく、継続的な運用費用も含めて総合的に判断しましょう。
運用コストは大きく固定費用と変動費用に分かれ、導入形態や利用状況によって金額が変わります。下記の表を参考に、運用に必要な内容を確認しておくと対応漏れが防げます。
| 費用項目 | 種類 | 費用感 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハードウェア費用 | 変動費 | 数万円~ |
・ パソコン ・ プリンター ・ スキャナーなど |
・ 既存機器が使える場合は不要 ・ 電子カルテの種類により利用可能機種が限定される場合あり ・ 運用上問題ないかスペックの確認は必須 |
| 周辺システムとの連携費用 | 固定費 | 環境とシステムによる | 検査機器や会計システムとの連携設定費用 | 電子カルテと機器の双方で設定が必要 |
| サポート・メンテナンス費用 | 固定費 | 数万円~ | システムの保守・不具合対応費用 |
・ 月額運用費用に含まれている場合が多い ・ 内容はベンダーによって異なるため事前の確認を推奨 |
| システム更新費用 | 変動費/固定費 | 環境とシステムによる | システムを使い続けるために必要なアップデート費用 |
・ オンプレミス型:5年に1度更新が必要(導入時と同程度の費用) ・ クラウド型:月額費用に包含 |
重要な確認ポイント:
- 導入前に将来的な費用発生について確認
- 年間あたりのコストを算出して検討
- 作業効率とコストのバランスを考慮
見落としがちな隠れコスト
ここまでお伝えした費用のほかに、見積で見落としてしまう可能性があるコストについて確認しておきましょう。思ったより高額になってしまい、予算をオーバーしないよう、事前に確認しておくと安心です。
考えられるコストの例は以下のとおりです。
- スタッフ研修費用:電子カルテの操作習得のために必要な費用
- データ移行費用:既存の紙カルテや他システムからのデータ移行時に発生
- ネットワーク環境の強化費用:回線増強やWi-Fi整備が必要になる場合がある
- セキュリティ対策費用:ウイルス対策ソフトやVPN(専用の通信環境)構築時に発生
- バックアップシステムの構築・運用費用:外付けHDDや世代管理(さかのぼって復元できる仕組み)導入時に発生
- 停電対策のUPS設置費用:停電時に電飾供給できる無停電電源装置導入時に発生
電子カルテの費用を抑える3つのポイント
電子カルテの導入費用は高額になりがちですが、適切な計画と選択によって費用を抑えられます。予算の設定から補助金の活用、段階的な導入まで、具体的な方法を確認しておきましょう。
1. 予算を決め、総コストと突き合わせる
電子カルテの導入を検討する際は、まず予算を明確に決めましょう。初期費用だけでなく「月額の運用費用」「システム更新費用」「隠れコスト」も含めた総コストを正確に算出します。
具体的には、5年10年といった中長期の視点で、利用人数や規模の拡大などを加味した総運用コストを計算すれば、費用対効果を判断しやすくなります。そのうえで、予算内に収まる選択肢を絞り込んでいくとよいでしょう。
2. 補助金・助成金を最大限活用する
電子カルテの導入には、複数の補助金や助成金を活用できる可能性があります。IT導入補助金をはじめ各自治体が展開している補助金など、候補は1つではありません。補助金を活用すれば、導入費用を大幅に削減できる可能性があります。申請には条件や締め切りがあるため、早めの情報収集と準備が功を奏します。
以下の記事で詳しく解説しているため、ご活用ください。
3. 必要最小限の機能から始める
電子カルテの導入は、必要最小限の機能から始めれば費用を抑えられます。診療記録の電子化という基本機能から開始し、運用に慣れてから段階的に機能を追加していくとスタッフへの負担という観点でも効果的です。
予約管理などの機能は、後からでも追加できます。ただし、データ連携を個別に進めると高額になったり情報の統合がしづらくなったりする可能性があります。将来的な機能拡張を見据えて、柔軟に対応できる電子カルテを選択しましょう。
よくある質問と回答
電子カルテの費用に関して、よくある質問をまとめました。導入検討時の参考になさってください。
Q1. 電子カルテの費用が5年間で2倍になると聞きましたが、本当ですか?
A. 費用が2倍になるケースは限定的です。400床以上の大規模病院でオンプレミス型の電子カルテを導入している場合、昨今の物価高による影響もあり、システム更新費用が大きくなってしまうケースが考えられます。
機能追加や利用者数の増加により費用が上昇する場合もありますが、事前に将来の費用見通しを確認・準備しておけば、予期しない費用増加を避けられます。
Q2. レセコンも一緒に導入すべきですか?
A. 既存のレセコンがない場合は、一体型の導入をおすすめします。既存のレセコンを使用中の場合は、連携可能な電子カルテを選択すれば、段階的な導入も可能です。
電子カルテとレセコンが連携すれば、診療情報から請求業務まで一貫した業務効率化が図れます。
Q3. 診療所でも電子カルテを導入する価値はありますか?
A. 診療所でも十分に価値があります。
診療記録の検索性向上や処方箋発行の効率化、データバックアップによる安全性確保など、規模に関わらずメリットを享受できます。
最近では、月額費用だけで利用できるクラウド型電子カルテも登場しており、診療所でも導入しやすいでしょう。無料トライアルやデモ体験を提供している製品もあるため、まずは操作感を確認してから判断できます。
メディコムでは、デモ体験の環境をご用意しております。以下より詳細をご覧いただけるためご検討ください。
詳細ページはこちらから:Medicom 電子カルテ ご導入検討/開業相談キャンペーン
費用対効果を考慮して検討を
電子カルテの導入費用だけを見ると、高額だと感じる場合があるかもしれません。しかし電子カルテを使うと、紙のカルテにはない利便性を感じられるはずで、さまざまな院内の作業の効率が大幅にアップすると期待できます。導入費用に各種の運用費用を加え、さらに利用できる補助金を考慮して、費用対効果を考えて導入を検討してはいかがでしょうか。