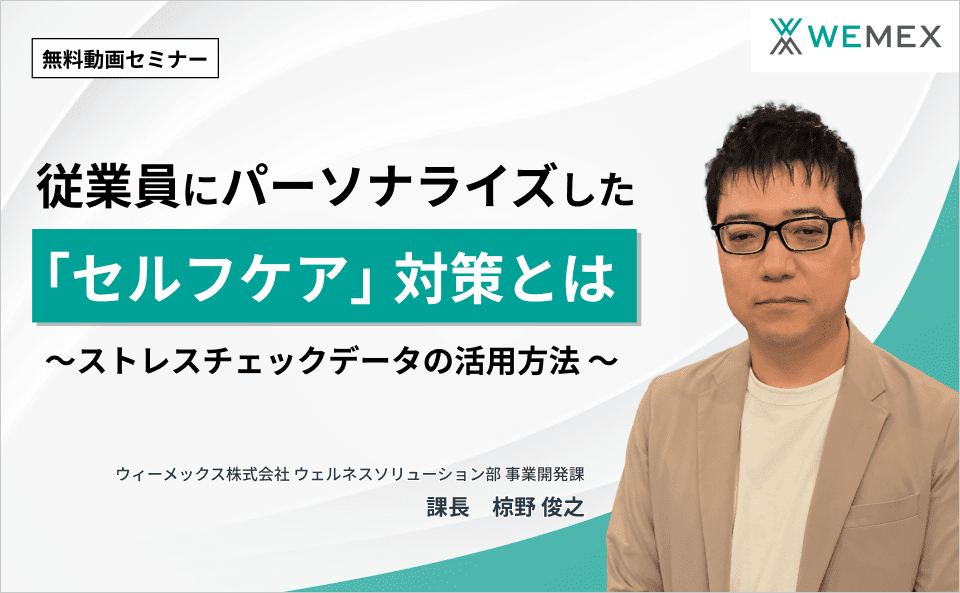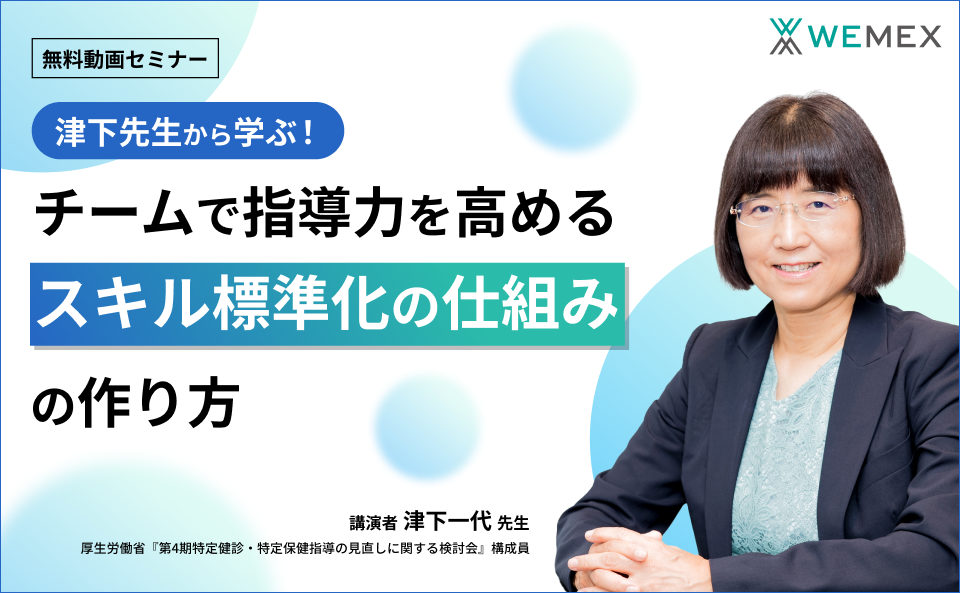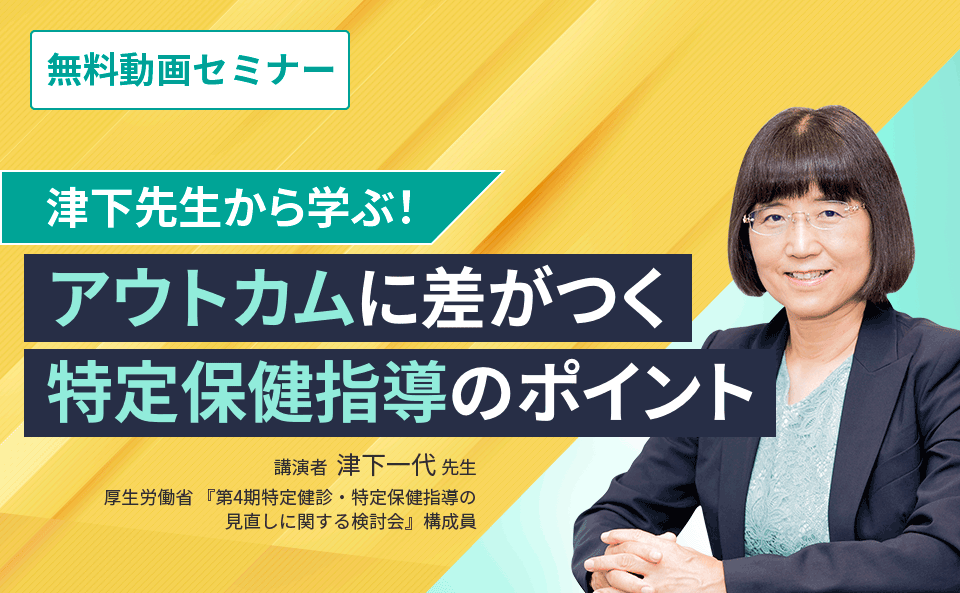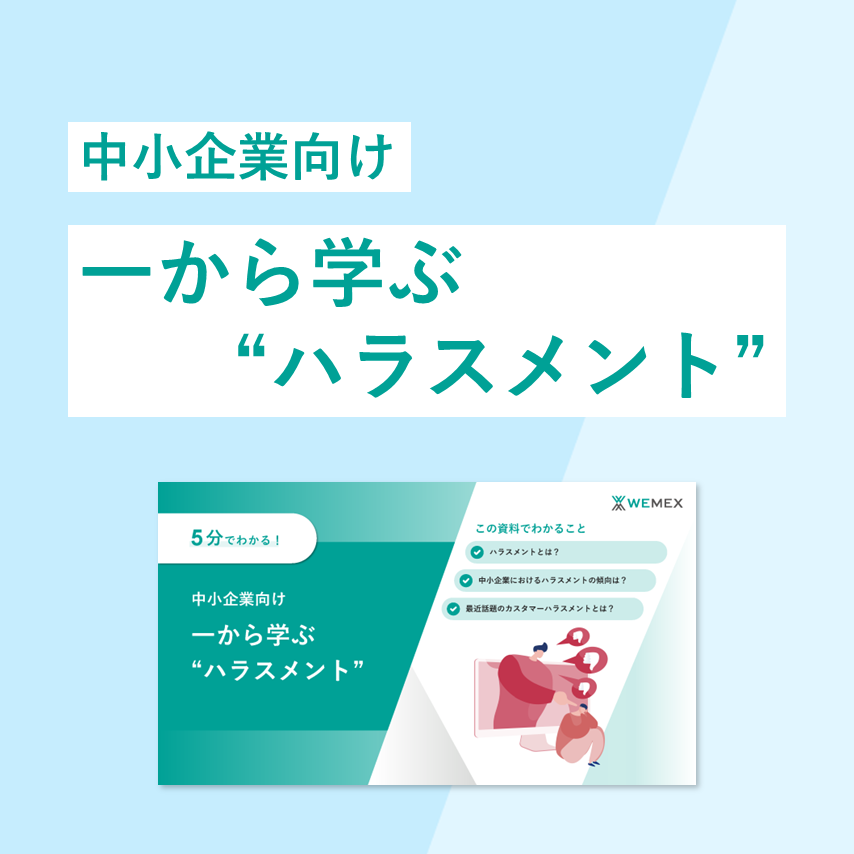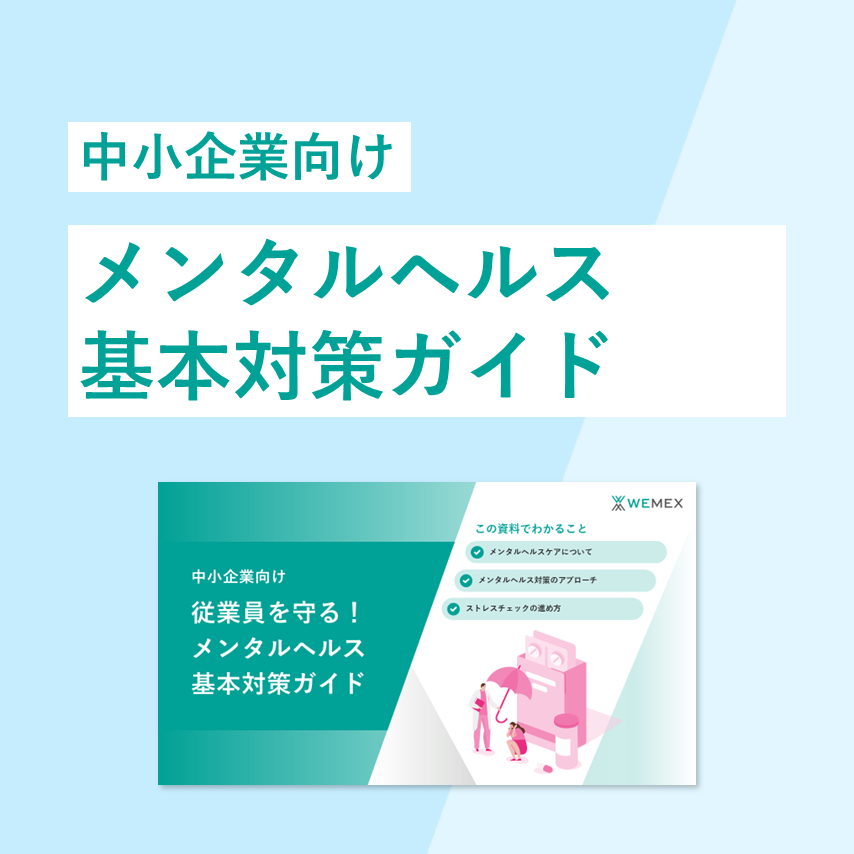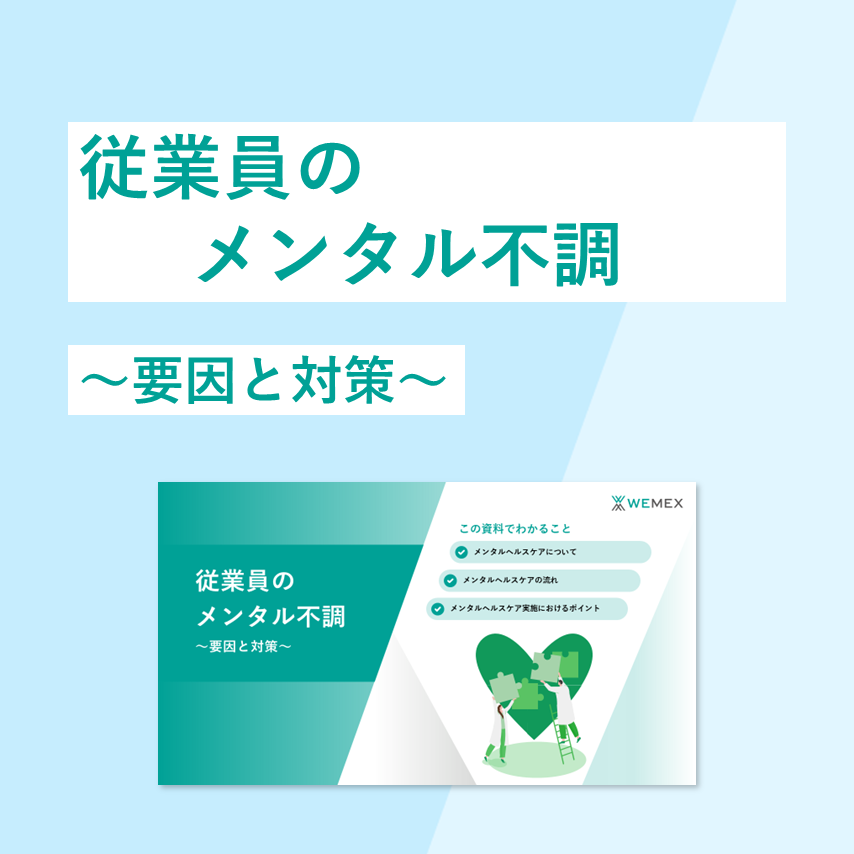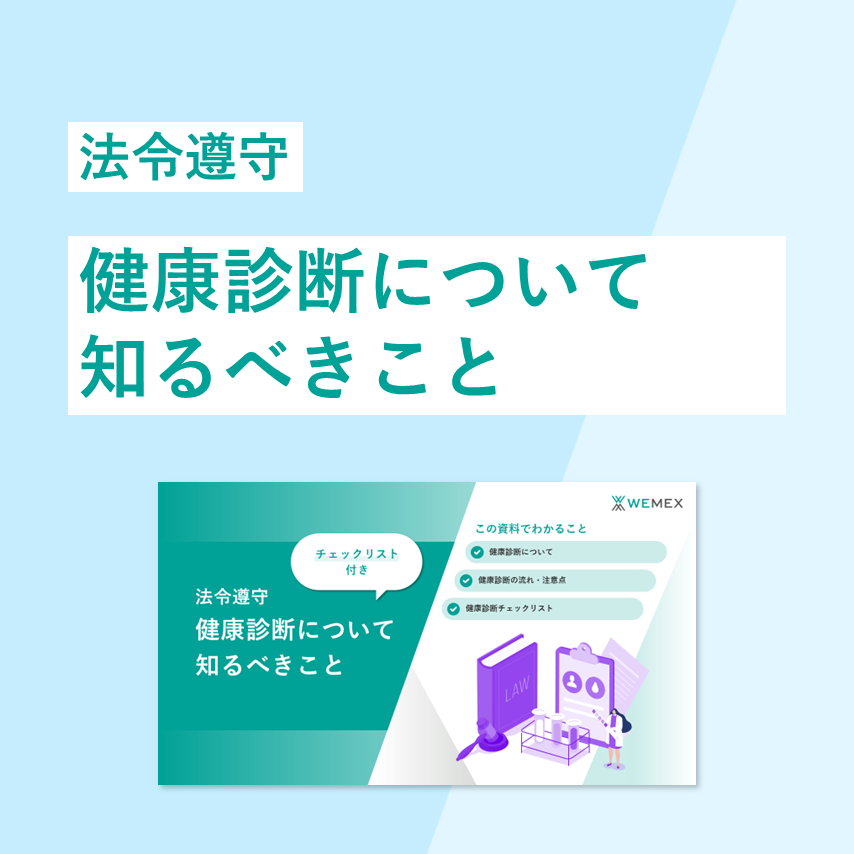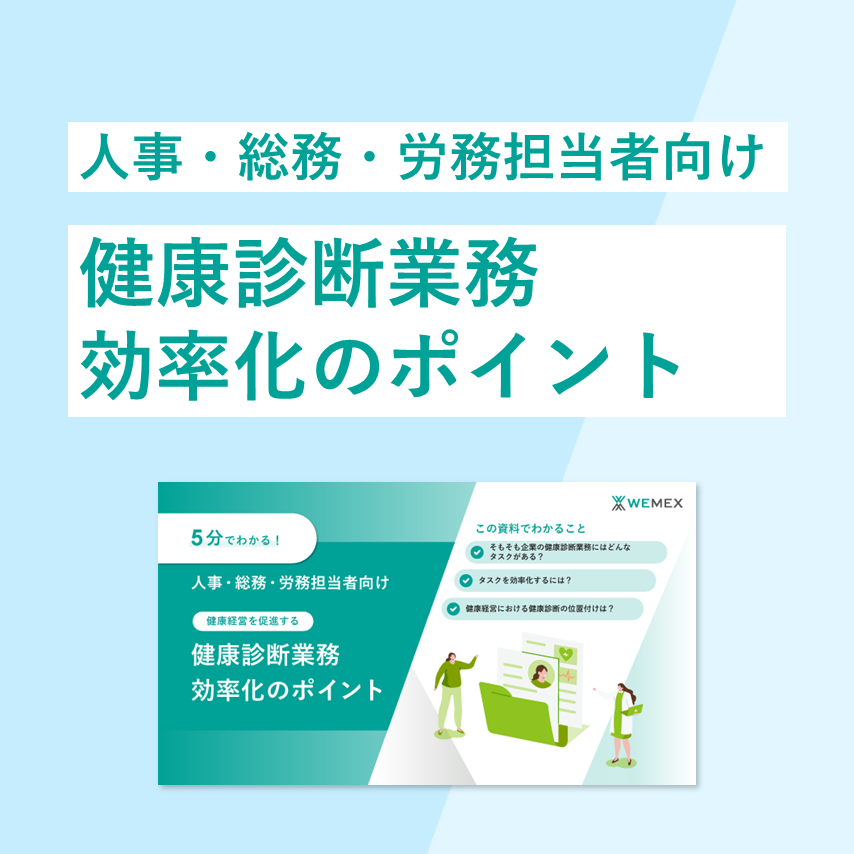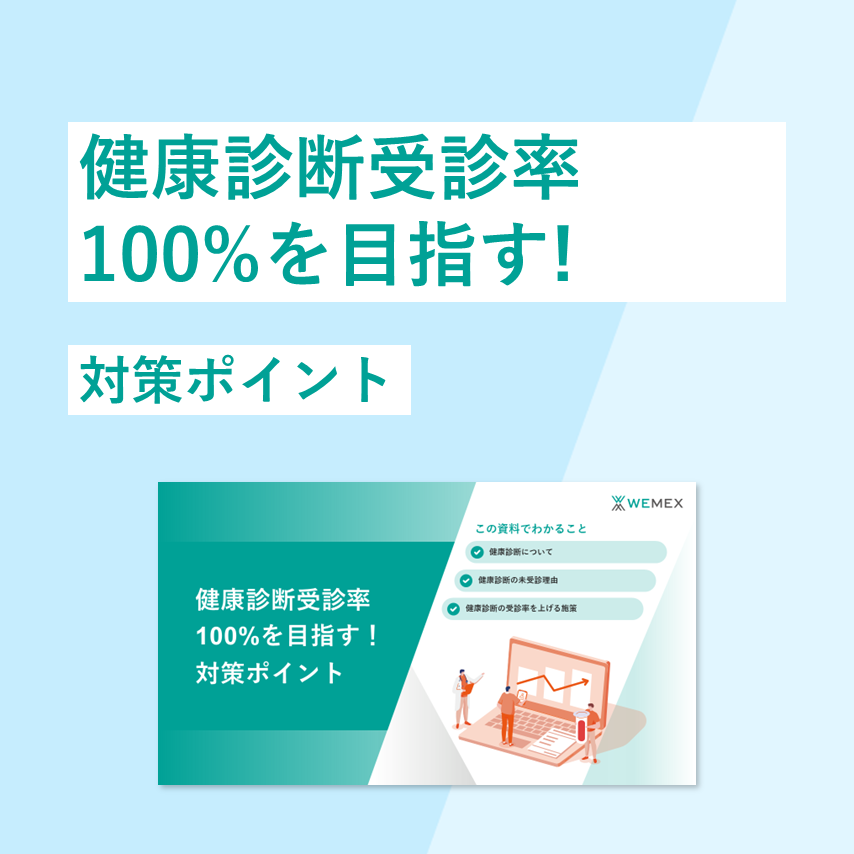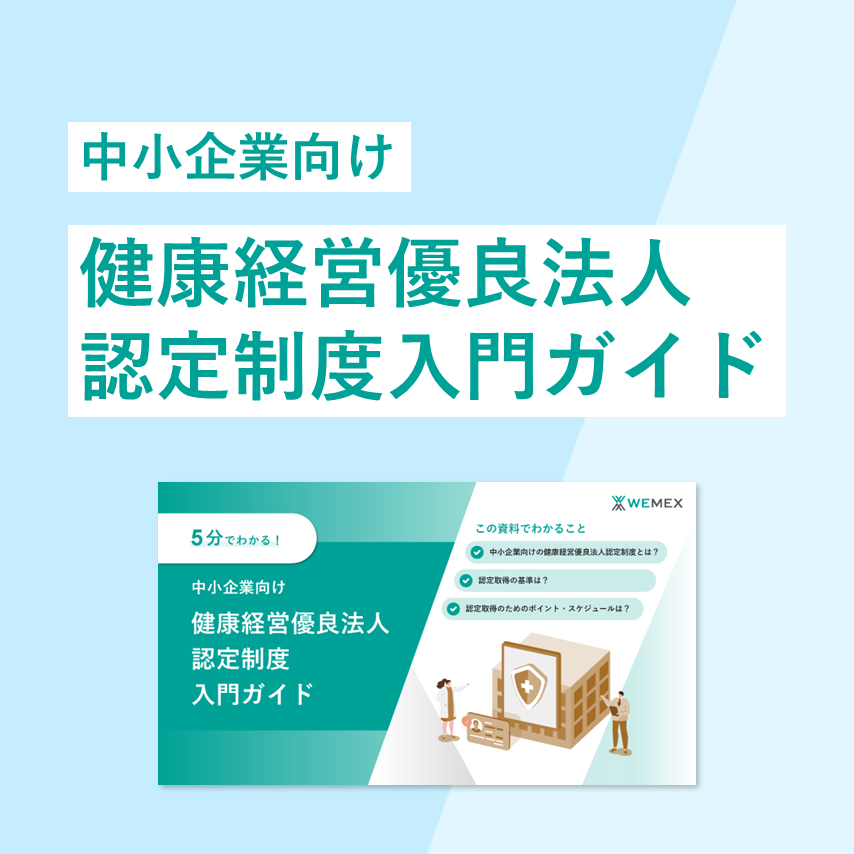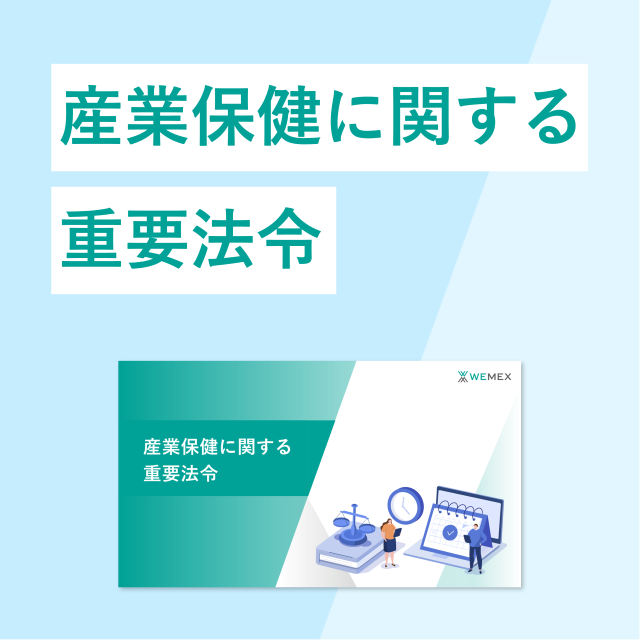目次
セルフケアとは

セルフケアとは、企業におけるメンタルヘルス対策のひとつであり、従業員自身がストレスに気づき、その予防や軽減、メンタルヘルス不調に対して自ら行う取り組みを指します。
ストレスに気づくためには、従業員自身がストレスや心の健康について理解し、自分の心の状態を正しく把握することが重要です。セルフケアでは、従業員がメンタルヘルスに関する知識を身につけ、自ら心の状態をチェックすることが推奨されています。
4つのメンタルヘルスケア
「職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜」によると、メンタルヘルスケアにはセルフケア以外に、以下の3つの方法が定められています。
- ラインケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
詳細は以下の関連記事をご参照ください。
関連記事:メンタルヘルスケアの基礎知識|4つのケアと3つの予防策
ラインケア
ラインケアは管理監督者から部下に対するケアです。直属の上司などの管理監督者が、以下の取り組みを行います。
- 従業員の健康状態や職場環境の把握と改善
- 部下からの相談対応
- 休職者の職場復帰の支援
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医や保健師、衛生管理者などが行うケアです。従業員一人ひとりの健康情報の管理や休職者の職場復帰の支援、産業医による長時間労働者面談などで従業員のセルフケアや管理監督者のラインケアを支援します。
事業場外資源との連絡調整やメンタルヘルスケアの企画・立案の対応なども、事業場内産業保健スタッフ等の役割です。
事業場外資源によるケア
事業場外資源とは、医療機関や外部の専門機関のことです。都道府県産業保健総合支援センター(さんぽセンター)などが挙げられます。
事業場外資源を活用すれば、事業場内では準備できない専門的な知見からの支援を得られます。メンタルヘルスに問題を抱える従業員が、職場内で相談をしたくない場合の相談先としても有効です。
メンタルヘルス不調初期に現れるストレスサイン
メンタルヘルス不調の初期には、以下のような症状が見られます。
【身体面】
- 食欲が低下する
- なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める
- 頭痛や肩こり、倦怠感が続く
【精神面】
- 気分が沈み、元気が出ない
- 理由もなくイライラしたり、不安な気持ちになる
【行動面】
- 遅刻や欠勤が増える
- ミスや物忘れが増える
- 表情が暗くなる
従業員自身がメンタル不調に気づいていない場合、セルフケアを行うことができません。また、不調に気づいていても、メンタルヘルスの問題だと認識していないこともあるため、状況によっては周囲からの働きかけも必要です。
従業員ができるセルフケア
従業員ができるセルフケアにはさまざまな方法があります。ここでは厚生労働省のサイトを参考に、6つの例をご紹介します。
| セルフケアの方法 | 効果 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身体を動かす |
ネガティブな気分を発散できる リラックスできる 睡眠リズムを整える |
軽いランニング サイクリング ダンス |
| 今の気持ちを書き出してみる |
悩みを客観視できる 新しい気づきが得られる |
文章 イラストや漫画 落書き |
| 腹式呼吸をゆっくり繰り返す | 不安や緊張が和らぐ |
ゆっくりと口から息を吐く 鼻から息を吸い込む |
| 「なりたい自分」に目を向ける | 自信がつく |
理想を思い浮かべる 小さくても目標を立てて、実行する |
| 音楽を聴いたり歌ったりする |
エネルギーや活力が生まれる 不安や緊張が和らぐ |
音楽を聞くことに集中する カラオケボックスで歌う |
| 失敗したときは笑ってみる | 気持ちが軽くなる |
見方を変える 笑い飛ばす |
従業員がセルフケアを行う重要性
従業員がセルフケアを行うことで、メンタル不調を正しく認識し、早期に悪化防止ができます。職場の同僚や家族に相談したり、専門の医療機関を受診したりするなど、適切な対処が可能になります。
日ごろからセルフケアに取り組むことで心身の健康が保たれ、仕事の生産性向上や離職防止にもつながります。
企業が従業員のセルフケアを促進するメリット
企業が従業員のセルフケアを促進する主なメリットは、以下の3点です。
- 従業員の健康維持・増進
- 企業の生産性向上
- 人材確保(採用・リテンション)
従業員の健康維持・増進
従業員の健康維持や増進は、セルフケア促進の直接的なメリットです。メンタル不調を放置すると、うつ病などの精神疾患に発展し、働けなくなるだけでなく、日常生活にも支障をきたす可能性があります。
従業員自身がメンタルヘルスの重要性を理解し、セルフケアを実践することで、メンタル不調の早期発見と悪化防止につながります。その結果、メンタルヘルス不調に悩む従業員を減らすことが期待できます。
企業の生産性向上
従業員のメンタルヘルスケアを推進することは、企業の生産性向上にもつながります。メンタル不調の状態では、集中力や判断力が低下し、従業員は本来の業務遂行能力を十分に発揮できません。
ストレスや精神的な負担が少ない状態で働けることで、仕事の質や効率が向上します。セルフケアを通じて従業員が業務に集中できるようになれば、企業の生産性が高まり、組織全体の活性化にもつながります。
人材確保(採用・リテンション)
従業員のセルフケアを推進し、働きやすい環境を整えることは、人材の採用やリテンション(定着支援)にもプラスに働きます。
厚生労働省が行った「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス不調により1か月以上休職した、または退職した従業員がいた事業場の割合は13.5%に上ります。
メンタルヘルスケアを計画的に行い、従業員のメンタル不調が減少すれば、休職者や退職者も減らすことができます。こうした取り組みにより、働きやすい職場として認識され、優秀な人材の確保や継続雇用にもつながるでしょう。
従業員のセルフケアを推進するポイント

企業はどのように従業員のセルフケアを後押しすればよいのでしょうか。以下の4つのポイントを確認しましょう。
- セルフケアに対する正しい理解
- ストレスチェックの実施・活用
- メンタルヘルス研修の実施
- 専門家の協力
セルフケアに対する正しい理解
従業員自身がストレスに気づき、メンタル不調の早期発見と悪化防止につなげるには、セルフケアが重要です。従業員のストレスの原因は職場に限らず、家庭環境や地域社会との関わりなど、職場外の出来事による場合もあります。
従業員が積極的にセルフケアに取り組めるよう、企業はセルフケアの重要性を認識し、推進する必要があります。メンタルヘルスケア計画を策定する際は、セルフケアを含む「4つのケア」が継続的かつ計画的に実施されるよう配慮しましょう。
セルフケアの対象は一般の従業員だけでなく、管理監督者も含まれます。管理監督者にもセルフケアの必要性を理解してもらい、取り組みを促すことが大切です。
ストレスチェックの実施・活用
ストレスチェックを定期的に行い、結果を上手に活用しましょう。従業員50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施が労働安全衛生法で定められた法的義務です。法定義務のない50人未満の事業場でも、ストレスチェックはストレスを認識する機会として効果的です。
ストレスチェックは実施したら終わりではありません。
- 従業員が上司や同僚に相談しやすい雰囲気づくり
- 社内外の相談窓口の案内
など、ストレスチェックの結果を踏まえて従業員がセルフケアに取り組みやすい環境整備を行いましょう。ストレスチェックを定期的に行い、結果を上手に活用しましょう。従業員50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施は労働安全衛生法で定められた法的な義務でもあります。法定義務のない50人未満の事業場でも、ストレスチェックはストレスを認識する機会として効果的です。
ストレスチェックは実施したら終わりではありません。従業員が上司や同僚に相談しやすい雰囲気をつくる、社内外の相談窓口を案内するなど、ストレスチェックの結果を踏まえて、従業員がセルフケアに取り組みやすい環境整備を行いましょう。
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
メンタルヘルス研修の実施
従業員がセルフケアの必要性を認識し、積極的に取り組むためには、企業の支援も重要です。以下の内容を含んだ研修や情報提供を通じて、セルフケアの取り組みを促しましょう。
- メンタルヘルスケアに関する方針
- メンタルヘルスケアの基礎知識
- セルフケアの重要性
- ストレスへの気づき方と予防
- 自発的な相談の有用性
- 職場内外の相談先
厚生労働省が運営するポータルサイト「こころの耳」では、セルフケアの解説ページやストレスチェックツール、動画教材などが用意されています。こうしたツールを活用することも、従業員のセルフケアへの意識向上に有効です。
関連記事:メンタルヘルス研修はなぜ必要?実施するメリットや効果を高める方法も解説
専門家の協力
メンタルヘルスケア計画の策定や施策の実施にあたっては、産業医や保健師など産業保健分野の専門家の協力が欠かせません。産業保健スタッフは専門的な知見に基づき、以下の取り組みで企業のメンタルヘルスケア推進を支援します。
- セルフケアに関する教育研修の企画や実施
- 職場環境の評価と改善への助言
- 従業員や企業の相談対応
ストレスチェックの実施を委託する場合は、外部サービスの活用が効果的です。「Wemex ストレスチェック」は、ストレスチェック業務の代行だけでなく、従業員一人ひとりの状況に合わせた動画の提供など、セルフケアに役立つコンテンツも提供しています。
【法人向け】Wemex ストレスチェック
従業員にセルフケアを促す施策例
従業員自身に任せるだけでは、セルフケアに取り組む従業員はなかなか増えません。従業員がセルフケアに取り組みやすくなるよう、企業が後押しし、環境を整えることが重要です。参考となる施策例を見ていきましょう。
運動を促す施策
運動習慣は、意識的に取り組まないと身につきにくいものです。特に仕事が忙しい従業員の場合、運動の時間を確保するのはさらに難しくなります。以下のような取り組みで、従業員が身体を動かす機会をつくりましょう。
- 社内にジムスペースを設ける
- バランスボールを配置する
- ヨガや体操の時間を設ける
- 運動系の部活動・サークル活動を支援する
運動にはストレス反応を緩和し、心身をリラックスさせる効果があります。また、適度に身体を動かすことで、睡眠リズムも整いやすくなります。
休息を促す施策
繁忙期や突発的な業務対応などで、長時間労働や不規則な勤務が発生することに備えて、従業員が十分に休息を取れる環境を整えましょう。例えば、
- 静かに過ごせる休憩室
- 短時間でも身体を休められる仮眠スペース
- リフレッシュルーム(従業員同士のコミュニケーション活性化にも有効)
などの設置が効果的です。
休暇制度については、リフレッシュ休暇の導入や年次有給休暇を取得しやすい職場風土の醸成が重要です。休暇を取得しにくい理由としては、「周囲に迷惑がかかると感じる」「後で仕事が多忙になる」「職場の雰囲気で取得しづらい」などが挙げられます。
業務の相互フォロー体制を整えたり、上司が率先して休暇を取得したりすることで、従業員が休暇を取りやすい仕組みや環境を整備しましょう。
感情表出を促す施策
笑いにはストレスを軽減し、免疫力を高める効果があります。従業員が仕事から離れ、感情を表に出せる機会を提供しましょう。以下のような取り組みが効果的です。
- 社内サークル活動の支援
- 運動会やレクリエーションイベントの実施
- 舞台観劇やスポーツ観戦チケットの提供
- 社員旅行や懇親会など、従業員の交流機会の設定
また、ストレスを感じた場合は一人で抱え込まず、産業医などの専門家に相談することが効果的です。社内に専用の相談窓口を設置するほか、匿名性を確保するために外部委託による電話相談やオンライン面談を導入するのも良いでしょう。
まとめ
セルフケアは職場のメンタルヘルスケア対策に欠かせません。企業は、従業員がセルフケアの重要性を正しく認識し実践できるよう、環境や制度を整え支援する必要があります。
セルフケアやメンタルヘルス対策を効率的に推進するには、ストレスチェックの活用が有効です。ウィーメックスが提供するストレスチェックサービスは、法令に準拠したストレスチェックの実施だけでなく、集団分析や従業員ごとのセルフケア動画配信、カウンセリング、職場環境改善のサポートまで幅広く対応しています。
Web・紙両方に対応し、多言語受検やe-Learningコンテンツも利用可能なため、さまざまな働き方や事業場規模に合わせた運用が可能です。
ストレスチェックの運用負担軽減や、従業員のメンタルヘルスケア推進に課題を感じている場合は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【法人向け】Wemex ストレスチェック
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/000560416.pdf)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/index.html)
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_gaikyo.pdf)